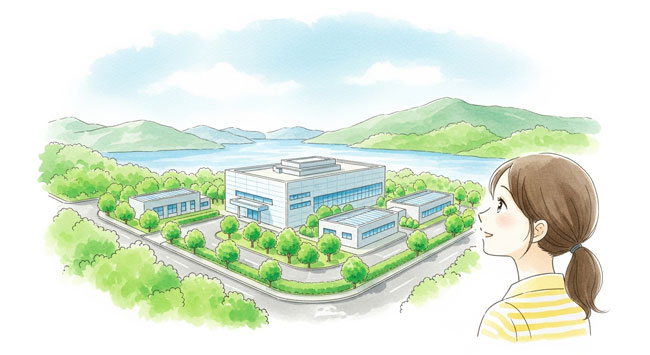こんにちは!食べること大好なCHIKOです。
皆さん、お寿司屋さんやスーパーで、ついついサーモンに手が伸びちゃうこと、ありませんか?あのとろけるような脂のりと、鮮やかなオレンジ色は、大人から子供までみんな大好きですよね。
でも、私たちが普段食べているサーモンのほとんどが、実はノルウェーやチリからの輸入品だってご存知でしたか?
「え、そうなの?」って思った方も多いかもしれません。
ところが最近、その常識が大きく変わろうとしているんです。今、日本のあちこちで「国産サーモン」の養殖が、ものすごい勢いで盛り上がっているんですよ!
「国産のサーモンって、なんだか新鮮で美味しそう!」
「でも、養殖って環境に悪いのかな…?」
「輸入ものと何が違うの?」
そんな皆さんの気になるギモンを、今日はとことん掘り下げていきたいと思います。この記事を読み終わる頃には、きっとあなたも国産サーモンを食べたくてたまらなくなっているはず!
それでは、日本のサーモン養殖が持つ、驚きのポテンシャルとその未来について、一緒に見ていきましょう。
1. 拡大の余地は十分!日本のサーモン養殖が持つポテンシャル

「日本のサーモン養殖って、そんなにすごいの?」って思いますよね。ええ、すごいんです。それにはちゃんとした理由があるんですよ。
国の後押し:政府も本気で応援中!
実は、国(水産庁)も「これからは養殖だ!」と、かなり力を入れているんです。
その名も「養殖業成長産業化総合戦略」。なんだか難しい名前ですけど、要は「日本の養…殖業を、もっと儲かるカッコイイ産業にしていこう!」という国のプロジェクトなんです。
特にサーモンは、ブリやマダイと並んで「戦略的養殖品目」に選ばれていて、国を挙げて生産量を増やそうとしています。
具体的な目標を見てみましょう。
| 品目 | 平成30年度の生産量 | 令和12年度の目標 |
| サケ・マス類(サーモン) | 約3.6万トン | 約7万トン |
(出典:水産庁「養殖業成長産業化総合戦略」)
なんと、生産量を約2倍にしようという計画なんです。国がここまで本気だなんて、期待しちゃいますよね!
マーケットの魅力:みんなが待っていた国産サーモン
もちろん、作るだけでは意味がありません。でも、心配ご無用!国産サーモンには、売れる理由がちゃんとあるんです。
- 安定した国内需要日本のサーモン消費量は、なんと世界トップクラス。回転寿司に行けば、サーモンは常に人気ネタの上位にランクインしています。これまでは輸入に頼っていましたが、「新鮮で安全な国産が食べたい」という声は、日に日に高まっています。
- インバウンド需要の取り込み日本にやってくる海外からの観光客にとって、「日本の美味しい魚」は旅の大きな楽しみの一つ。特にアジア圏ではサーモン人気が絶大です。「Made in Japan」の高品質なサーモンは、彼らにとっても非常に魅力的。観光地などで提供すれば、大きなビジネスチャンスになります。
技術革新の波:これまでの常識を覆す新しい養殖
「でも、養殖って魚がたくさん死んじゃったり、環境を汚したりするイメージが…」
そんな心配をされている方もいるかもしれませんね。
確かに、昔ながらの海面での養殖には、赤潮や台風による被害、病気のリスクなど、様々な課題がありました。
しかし、今、その常識を根底から覆すような、すごい技術が登場しているんです。
それが、次の章でお話しする「陸上養殖」なんですよ。
2. 【技術革新】サーモン養殖の未来を握る2大テクノロジー

さて、ここからは日本のサーモン養殖を語る上で欠かせない、最先端の技術について詳しく見ていきましょう!ちょっと専門的な話も出てきますが、できるだけ分かりやすく説明しますね。
「陸上養殖」がゲームチェンジャーに
「陸の上で魚を養殖するって、どういうこと?」って思いますよね。
まるでSF映画みたいですが、これがもう現実になっているんです。
具体的には、「閉鎖循環式陸上養殖(RAS)」というシステムを使います。
これは、水槽の水をろ過してキレイにしながら、何度も循環させて使う技術のこと。いわば、「超高性能なろ過装置がついた、巨大な水槽システム」を、建物の中で動かすイメージです。
この陸上養殖には、今までの海面養殖の悩みを解決する、たくさんのメリットがあるんですよ。
| 陸上養殖のメリット | 具体的な内容 |
| いつでもどこでも養殖可能 | 海から離れた内陸部でも、水さえ確保できれば養殖ができます。消費者のすぐ近くで育てて、新鮮なまま届けられるのが強みです。 |
| 天候に左右されない安定生産 | 台風や赤潮、水温の変化といった自然災害のリスクがありません。1年中、計画通りに安定して出荷できます。 |
| 寄生虫「アニサキス」のリスクが極めて低い | これ、すごく大事なポイントです!アニサキスは、通常、餌となる他の魚介類から感染します。陸上養殖では管理された人工の餌を与えるため、アニサキスの心配がほとんどないんです。だから、一度も冷凍せずに「生」で安心して食べられます。 |
| 環境にやさしい | 魚のフンや食べ残しが海に流れ出ることがありません。また、薬の使用も最小限に抑えられるので、環境負荷が低いサステナブルな養殖方法だと言えます。 |
もちろん、いいことばかりではありません。
一番の課題はコスト。特に、巨大なプラントを建設するための初期投資と、水を循環させるための電気代がかなりかかるんです。
それでも、このデメリットを上回る魅力があるからこそ、多くの企業が挑戦しているんですね。
最新事例:未来のサーモンは、ここで生まれる!
今、日本各地で、この陸上養殖の商業プラントが次々と稼働を始めています。代表的な事例をいくつかご紹介しますね。
FRDジャパン:「おかそだち」ブランドを首都圏へ
- 場所: 千葉県(木更津市、富津市)
- 特徴:
- 三井物産などが出資する、陸上養殖のパイオニア的存在。
- バクテリアの力を利用した高度な水処理技術で、海水をほとんど使わずにサーモンを育てています。
- 「おかそだち」というキャッチーなブランド名で、スーパーや飲食店向けに出荷しています。
- 口コミでは…「脂が上品で、身がプリプリしてる!」「養殖特有の臭みが全然なくて、本当に美味しい」といった声が見られます。
三菱商事・アトランド:富山の名水で育てるサーモン
- 場所: 富山県入善町
- 特徴:
- 大手商社の三菱商事が手がける大規模プロジェクト。
- 北アルプスの雪解け水である、清らかで冷たい伏流水を利用。さらに、水温管理には海洋深層水を活用することで、電力コストを抑える工夫も。
- まさに、日本の豊かな自然と最新技術のハイブリッドですね!
丸紅:日本初の陸上養殖アトランティックサーモン
- 場所: 静岡県小山町
- 特徴:
- ノルウェーのサーモン養殖会社の技術を導入。
- 「FUJI ATLANTIC SALMON」というブランドで、日本で最も人気のある「アトランティックサーモン」の陸上養殖を日本で初めて商業化しました。
- 富士山の雪解け水が豊富な場所で、高品質なサーモン生産を目指しています。
こうした大企業が何十億、何百億円という規模で投資していることからも、陸上養殖への本気度が伝わってきますよね。
「餌(えさ)」の進化が持続可能性を高める
もう一つの重要な技術革新が、「餌」です。
「魚の餌なんて、なんでもいいんじゃないの?」と思うかもしれませんが、実はこれが、養殖業の未来を左右する、とっても大きな問題なんです。
課題:天然資源である魚粉(フィッシュミール)への依存
これまで、養殖魚の餌の主原料は「魚粉(フィッシュミール)」でした。これは、イワシなどの天然の小魚を粉末にしたものです。栄養価が高く、魚の成長には欠かせません。
でも、ここに大きな矛盾があります。
「魚を育てるために、別の魚を大量に獲り続けなければならない」のです。
世界の人口が増え、養殖の需要が高まるにつれて、魚粉の価格は高騰し、資源の枯渇も心配されています。これでは、持続可能な産業とは言えませんよね。
解決策:未来の主食は「昆虫」や「藻類」!?
そこで今、魚粉に代わる新しい原料の開発が、世界中で進められています。
- 昆虫ミール「え、虫!?」と驚くかもしれませんね。でも、アメリカミズアブなどの昆虫は、タンパク質が豊富で、魚の餌として非常に有望視されているんです。食品廃棄物などを餌にして育てられるため、環境負荷も低いんですよ。
- 藻類DHAやEPAといった、魚の健康に良いとされる油分を豊富に含む微細な藻類を培養し、餌に加える研究も進んでいます。
こうした代替飼料を使うことで、海の資源に頼らない、本当にサステナブルな養殖が実現できるんです。
スマート給餌:AI・IoT活用でコスト削減
さらに、餌やりの方法も進化しています。
AIを搭載したカメラやセンサーが、水槽の中のサーモンの食欲を24時間監視。「お腹が空いていそうだな」というタイミングで、必要な分だけ自動で餌を与える「スマート給餌器」が開発されています。
これにより、餌の無駄をなくしてコストを削減できるだけでなく、魚にとって最適な環境を保ち、成長を早める効果も期待できるんです。
すごい時代になりましたよね!
3. 【ブランド化戦略】各地で花開く「ご当地サーモン」たち
最先端の陸上養殖が注目される一方で、日本各地の豊かな海の幸を活かした「ご当地サーモン」も、どんどん増えているんですよ。まるで戦国時代の武将のように、各地で個性豊かなブランドサーモンがしのぎを削っています。
旅行先で、その土地ならではのサーモンを味わう…なんていうのも、これからの新しい楽しみ方になるかもしれません。
ここでは、代表的なご当地サーモンをいくつかご紹介しますね!
海の恵みを活かしたブランド
| ブランド名 | 産地 | 魚の種類 | 特徴 |
| 海峡サーモン | 青森県 | ニジマス | 津軽海峡の速い潮の流れにもまれて育つため、身が引き締まっているのが特徴。脂のりも上品で、さっぱりとした後味。 |
| みやぎサーモン | 宮城県 | ギンザケ | 養殖ギンザケ生産量日本一を誇る宮城のブランド。生のまま出荷されるため、もっちりとした食感が楽しめる。 |
| 境港サーモン | 鳥取県 | ギンザケ | 大山の雪解け水が注ぎ込む美保湾で養殖。水揚げ後すぐに活け締め処理をするため、鮮度抜群。 |
地域の特性を活かした陸上養殖ブランド
| ブランド名 | 産地 | 魚の種類 | 特徴 |
| 信州サーモン | 長野県 | ニジマス×ブラウントラウト | 長野県水産試験場が10年かけて開発。きめ細かく、とろけるような舌触りが人気。卵を産まないため、産卵期の栄養ロスがなく、一年中美味しい。 |
| 甲斐サーモンレッド | 山梨県 | ニジマス | 名水百選にも選ばれた湧水で育てられる。赤ワインのポリフェノールを餌に加えることで、鮮やかな赤身とさっぱりした味わいを実現。 |
| 富士山サーモン | 静岡県 | ニジマス | 富士山の湧水で育ち、抗酸化作用を持つアスタキサンチンを豊富に含んだ餌で、美しいサーモンピンクの身と深い甘みを持つ。 |
いかがですか?
本当にたくさんの種類があって、どれも美味しそうですよね!
「ニジマス」や「ギンザケ」と聞くと、川魚のイメージが強いかもしれませんが、品種改良や育て方の工夫で、私たちが大好きなサーモンの味に見事に変身しているんです。
こうしたブランド化の動きは、単に美味しい魚を作るだけでなく、地域の活性化にも繋がる、とても素敵な取り組みだと思います。
4. 乗り越えるべき3つの課題
ここまで、日本のサーモン養殖の明るい未来についてお話ししてきましたが、もちろん、いいことばかりではありません。
この新しい産業が本当に大きく成長していくためには、いくつかの大きな壁を乗り越える必要があるんです。
コストの壁:やっぱりお金がかかる
これが一番の課題かもしれません。
- 莫大な初期投資特に陸上養殖は、ハイテクなプラントを建設するために、何十億、場合によっては100億円以上ものお金がかかります。これは、中小企業が簡単に参入できる金額ではありません。
- 高いランニングコストプラントを24時間稼働させるための電気代や、高品質な餌代など、日々の運営にもかなりのコストがかかります。FRDジャパンの十河社長もインタビューで「電気代が一番の悩み」と語っているほどです。
このコストを、最終的に商品の価格にどこまで転嫁できるのか。つまり、「高くても消費者が買ってくれるか」が、事業として成り立つかどうかの大きな分かれ道になります。
技術と人材:誰でもできるわけじゃない
陸上養殖は、ボタン一つで魚が育つような魔法の箱ではありません。
- 繊細な水質管理バクテリアの働きをコントロールして、魚にとって快適な水質を保ち続けるには、非常に高度なノウハウが必要です。ちょっとしたバランスの崩れが、大量死に繋がるリスクも。
- 専門知識を持つ人材の不足水産学の知識はもちろん、ITや機械工学、経営の知識まで、幅広いスキルを持った人材がまだまだ足りていません。この分野のプロフェッショナルをどう育てていくかが、今後の大きな課題です。
販売戦略:どうやって選んでもらうか
無事にサーモンが育っても、売れなければ意味がありません。
- 輸入サーモンとの価格競争スーパーに並ぶノルウェー産サーモンは、大量生産によって価格が抑えられています。コストの高い国産サーモンが、価格だけで勝負するのは難しいのが現実です。
- 価値を伝えるブランディング「なぜ高いのか?」「輸入ものと何が違うのか?」という価値を、消費者にしっかりと伝える必要があります。「アニサキスの心配がない安全性」「環境にやさしいサステナビリティ」「獲れたての鮮度」といった付加価値を、価格に見合う魅力として感じてもらえるかどうかが、成功のカギを握っています。
これらの課題を一つ一つクリアしていくのは、決して簡単なことではありません。しかし、多くの企業が知恵を絞り、挑戦を続けているのもまた事実なんです。
まとめ:日本のサーモン養殖は、課題を越えて世界に羽ばたけるか

さて、ここまで日本のサーモン養殖の可能性と課題について、じっくりと見てきましたが、いかがでしたか?
最初は「国産のサーモンって珍しいな」くらいの気持ちだったかもしれませんが、その裏側には、こんなにも壮大なストーリーと、多くの人々の情熱が隠されていたんですね。
もう一度、大切なポイントを整理しておきましょう。
- 背景: 世界的な需要の高まりと、輸入依存からの脱却を目指す国の後押しがある。
- 可能性: 「陸上養殖」という技術革新が、安全性と持続可能性を両立させる。
- 広がり: 大企業から地域に根差した「ご当地サーモン」まで、多様なプレイヤーが参入している。
- 課題: コスト、技術、販売戦略という大きな壁を乗り越える必要がある。
技術革新と企業の挑戦によって、日本のサーモン養殖は、今まさに大きな成長期を迎えています。
私たちがスーパーで「おかそだち」や「富士山サーモン」といった国産ブランドを見かける機会は、これからどんどん増えていくでしょう。
それは、単に「食卓の選択肢が増える」ということだけではありません。
私たちが国産サーモンを選ぶという、その小さな行動一つ一つが、日本の漁業の未来を応援し、環境を守り、地域を元気付けることに繋がっていくのかもしれません。
次にサーモンを食べる時は、ぜひその産地にも注目してみてください。
もしかしたら、あなたの選んだその一皿が、日本の食の未来を、ほんの少し変える力を持っているかもしれないのですから。