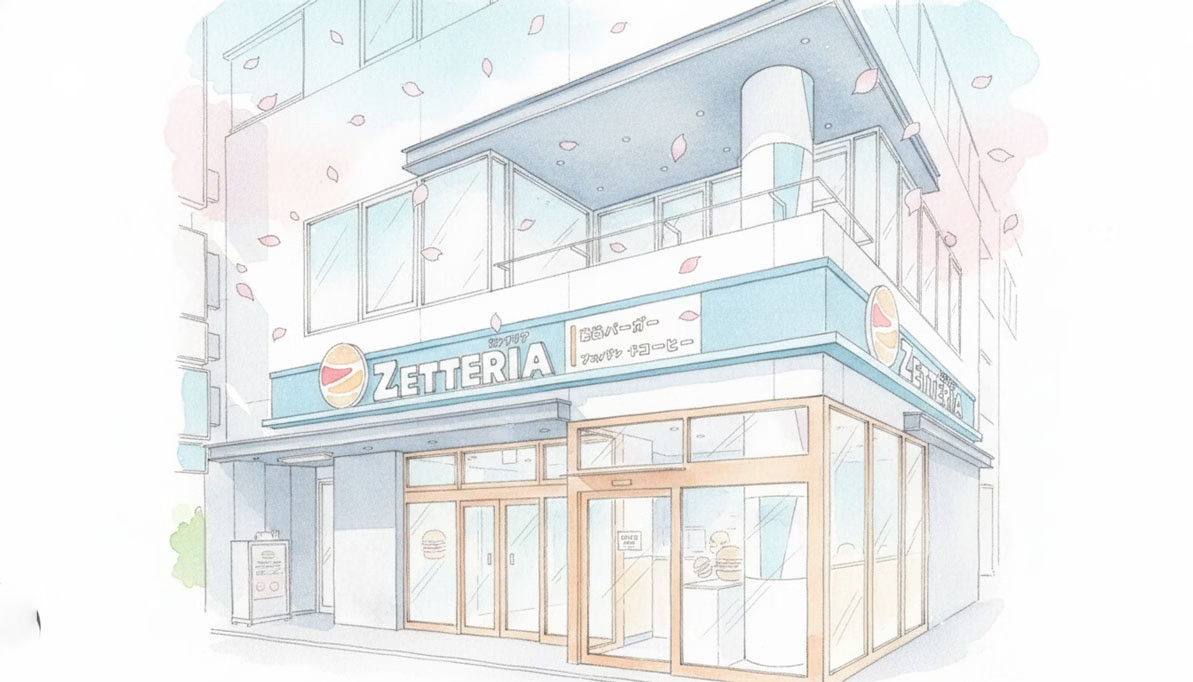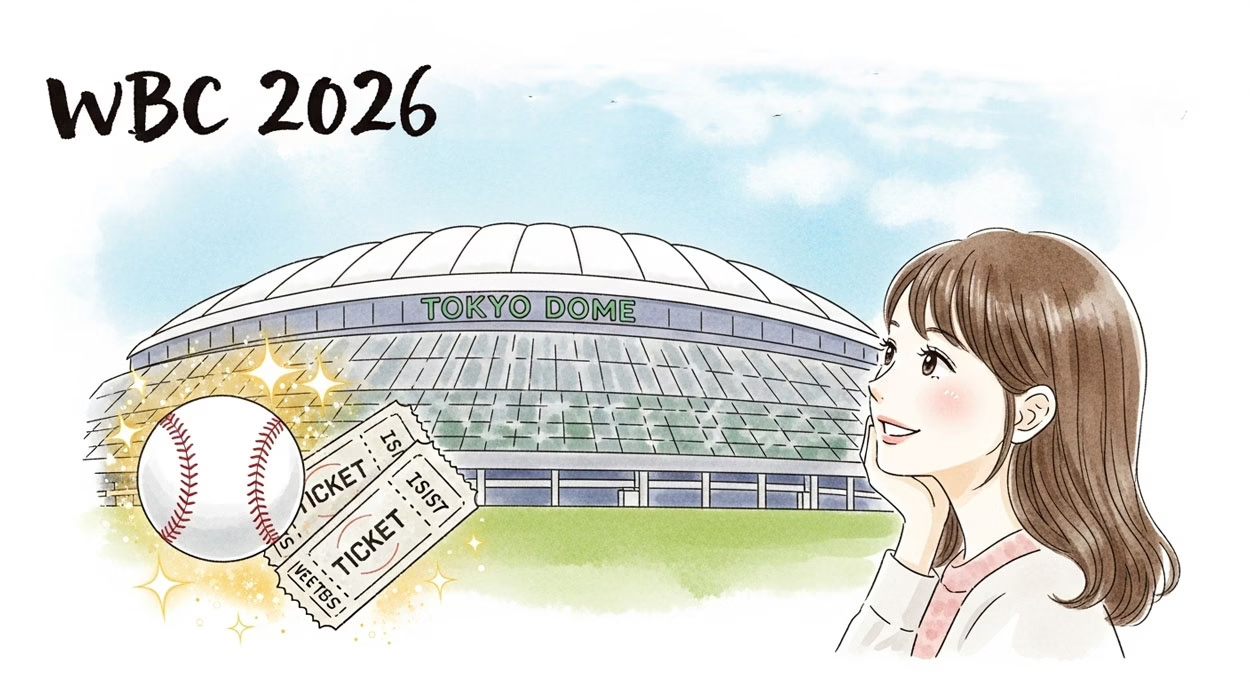こんにちは!
最近、テレビやネットで「食べられるフィルム」って言葉、耳にしたことありませんか?
「え、フィルムが食べられるの?どういうこと?」って、ちょっとびっくりしますよね。
実はそれ、私たちの食卓にもおなじみの「昆布」から作られた、すごい新素材なんです。その名も「アルフィル」。
このアルフィル、ただ食べられるだけじゃなくて、環境問題の切り札になるかもしれないって、今、ものすごく注目されているんですよ。
「でも、昆布でできたフィルムって、本当にラップの代わりになるの?」
「味とか匂いはどうなんだろう?」
「そもそも、どうしてそんなものが開発されたの?」
たくさんの「?」が浮かんできますよね。
この記事では、そんな未来の素材「アルフィル」の秘密について、開発の裏話から、私たちの暮らしをどう変えるのかまで、どこよりも分かりやすく、詳しく解説していきます。
この記事を読み終わる頃には、あなたもきっとアルフィルのファンになっているはず。ぜひ最後までお付き合いくださいね!
暮らしを変える新素材「アルフィル」とは?

食べられる、水に溶ける、環境に優しいフィルム
さっそく結論から言ってしまうと、アルフィルは「昆布の成分から作られた、食べられて、水に溶けて、土に還るフィルム」です。
なんだかすごい特徴がてんこ盛りですよね。一つずつ見ていきましょう。
まず、一番の驚きはやっぱり「食べられる」こと。
例えば、このアルフィルでおにぎりを包んだとします。そうしたら、フィルムを剥がさずに、そのままパクっと食べられちゃうんです。
これって、すごくないですか?
ラップを捨てる手間も省けるし、ゴミも出ない。忙しい朝には特に嬉しいかもしれませんね。
そして、「水に溶ける」というのも大きなポイント。
お湯を注ぐだけでサッと溶けるので、だしパックや粉末スープの袋に使えば、袋を破って中身を出す必要がなくなります。そのままお椀に入れてお湯を注げばOK。
最後に「土に還る」。
アルフィルは天然の海藻からできているので、もし捨てられても、微生物によって分解されて自然に還ります。これが「生分解性」という性質です。
今、世界中で問題になっているプラスチックごみ。特に、海に流出して海の生き物たちを苦しめているマイクロプラスチック問題は深刻ですよね。
アルフィルは、そんなプラスチックに代わる救世主として、大きな期待が寄せられているんです。
主な成分は昆布のネバネバ「アルギン酸」
「でも、昆布でできてるってことは、昆布の味がするんじゃないの?」って気になりますよね。
安心してください。アルフィルは、無味無臭。だから、包んだ食品の味や香りを邪魔することがありません。
その秘密は、主成分にあります。
アルフィルの主成分は、昆布やワカメといった海藻に含まれる、特有の「ネバネバ」成分。これを「アルギン酸」と言います。
「アルギン酸」って聞くと、何だか難しそうな化学物質みたいに聞こえるかもしれません。でも実は、これって私たちのすごく身近にあるものなんです。
例えば、食品添加物として、アイスクリームやドレッシングにとろみをつけたり、分離するのを防いだりするのに使われています。成分表示を見てみると「増粘多糖類」と書かれているのが、それにあたることが多いです。
他にも、シャンプーやリンス、化粧品などにも、保湿成分として利用されているんですよ。
つまりアルフィルは、何か特別な化学薬品からできているわけではなく、私たちが昔から口にしたり肌に触れたりしてきた、安全な天然成分100%のフィルムというわけなんです。
アルフィルの驚くべき特徴とメリット
アルフィルには、先ほどお伝えした「食べられる」「水に溶ける」「環境に優しい」以外にも、たくさんのすごい特徴があるんです。ここでは、その主なメリットを4つに分けて、詳しくご紹介しますね。
| 特徴 | 内容 |
| 可食性 | 無味無臭でカロリーはゼロ。食物繊維100%です。 |
| 水溶性 | お湯にサッと溶けるので、だしパックや粉末スープに最適。 |
| 環境性 | 天然由来で土に還る「生分解性」。プラスチックごみ削減に貢献します。 |
| その他 | 燃えにくく、熱くならず、印刷も可能という多様な性質を持っています。 |
【可食性】無味無臭でカロリーゼロ
アルフィルの最大の魅力は、やはり「食べられる」こと。
しかも、ただ食べられるだけではありません。
- 味がしない(無味)
- 匂いがしない(無臭)
- カロリーがゼロ
という、食品を包む素材としては理想的な特徴を持っています。
これなら、繊細な味の和菓子を包んでも、風味豊かなパンを包んでも、素材本来の美味しさを損なうことがありません。
さらに、主成分のアルギン酸は「水溶性食物繊維」の一種。
つまり、アルフィルは実質「食物繊維100%」のフィルムなんです。カロリーを気にせず、むしろ体によい成分を摂れるなんて、なんだか得した気分になりますよね。
【水溶性】お湯を注ぐだけで「だしパック」が溶ける
次に注目したいのが「水に溶ける」性質です。
特に、お湯をかけるとサッと溶けるのが大きなポイント。
想像してみてください。
いつも使っている粉末のコンソメスープや和風だし。アルフィルで個包装されていれば、袋をハサミで切って、中身をこぼさないように慎重にカップに入れる…なんて手間が一切なくなります。
フィルムごとカップに入れて、お湯を注ぐだけ。
あっという間にフィルムは溶けて、美味しいスープやだしが完成します。
この手軽さは、一度体験したらやみつきになりそう。
料理の時短にも繋がるし、ゴミも出ない。まさに一石二鳥ですよね。
【環境性】土に還る生分解性
そして、今この時代に最も重要視されるべき特徴が「環境性」です。
アルフィルは、海藻という天然素材からできているため、使用後に土や海に還っても、微生物の力で自然に分解されます。
今、私たちが日常的に使っている食品用ラップやプラスチック袋は、石油から作られています。これらは非常に便利ですが、自然界で分解されるのには数百年という途方もない時間がかかると言われています。
その結果、たくさんのプラスチックごみがゴミ処理場を圧迫し、一部は海や川に流れ出て、環境を汚染し続けています。ウミガメの鼻にストローが刺さっていたり、クジラのお腹から大量のビニール袋が出てきたり…そんなニュースに胸を痛めたことがある人も多いのではないでしょうか。
もし、このプラスチックの一部でもアルフィルに置き換わったら?
地球環境への負担を、大きく減らすことができるはずです。アルフィルは、サステナブルな社会を実現するための、大きな可能性を秘めた素材なんですね。
【その他】難燃性・非蓄熱性・印刷可能
アルフィルには、まだまだ隠れたすごい能力があります。
まず「難燃性(ねんねんせい)」。
これは「燃えにくい」性質のことです。アルフィルに直接火を近づけても、燃え上がらずに炭になるだけ。火を扱うキッチンの周りでも、安心して使えるのは嬉しいポイントです。
次に「非蓄熱性(ひちくねつせい)」。
これは「熱くなりにくい」性質です。加熱してもフィルム自体は熱をためにくいので、例えば電子レンジで温めた食品を取り出すときも、フィルムの部分は熱くなりにくいそう。うっかり「アチッ!」となるのを防げるかもしれません。
そして「印刷適性」。
アルフィルには、食用のインクで文字や絵を印刷することができます。
例えば、おにぎりを包むフィルムに「梅」「しゃけ」と印刷したり、お菓子のパッケージに可愛いイラストを入れたり。アレルギー情報を直接フィルムに記載する、なんていう使い方も考えられます。
食べられて、安全で、デザイン性も高められるなんて、本当に万能選手ですよね。
アルフィル誕生の背景

こんなに画期的なアルフィルですが、一体誰が、どうやって開発したのでしょうか?
実はその裏には、大阪の老舗昆布店による、長い研究と、ある偶然の発見の物語があったんです。
開発したのは大阪の老舗昆布店「舞昆のこうはら」
アルフィルを開発したのは、株式会社舞昆(まいこん)のこうはら。
大阪で塩昆布や発酵昆布「舞昆」の製造・販売を手掛ける、昆布のプロフェッショナルです。
「え、昆布屋さんがフィルムを?」って、ちょっと意外に思いますよね。
でも、昆布のことを知り尽くしているプロだからこそ、その秘められた可能性に気づき、形にすることができたんです。
アルフィルを開発した『舞昆のこうはら』さん、実はこんなに美味しい昆布製品を作っているんです!未来の素材を生み出した老舗の味、一度試してみませんか? →こちら
きっかけは偶然の産物
開発の物語は、数年前に遡ります。
当時、こうはらでは、日本の昆布の漁獲量が減っていることから、海外産の昆布を使った佃煮の開発に取り組んでいました。
しかし、海外産の昆布は日本のものほどうま味が強くなく、残念ながら製品化には至りませんでした。
ただ、研究のために抽出した昆布の成分(アルギン酸)が、実験で使ったシャーレ(ガラスの平たいお皿)の中に残っていました。
研究室のスタッフがそのシャーレを片付け忘れて、数ヶ月間放置してしまったそうです。
そして、ある日、そのシャーレを覗いてみると…
なんと、液体だったはずの昆布の成分が、カピカピに乾いて、薄いオブラートのような膜(フィルム)になっていたんです!
「これは何かに使えるかもしれない!」
ちょうどその頃、世界ではプラスチックごみ問題が大きく取り上げられ始めていました。
「このフィルムの強度を高めて、ロール状にできれば、ラップの代わりになるんじゃないか?」
この偶然の発見と、時代のニーズが結びついた瞬間でした。
一つの「うっかり」から、世界を変えるかもしれない大発明が生まれたなんて、なんだかドラマみたいですよね。
6年の歳月と100以上の試作品
しかし、製品化までの道のりは、決して平坦ではありませんでした。
最初にできたフィルムは、手で触るとすぐに破れてしまうほど、もろいものでした。
ラップのように使うには、もっと強度が必要です。
そこから、開発チームの試行錯誤の日々が始まりました。
- 昆布からアルギン酸を抽出する際の濃度
- フィルム状に乾燥させる時間や温度
- 強度を高めるための天然由来の添加剤の配合
など、考えられるあらゆる条件を変えて、何度も何度も実験を繰り返しました。
その数、実に100種類以上。
そして、開発開始から約6年。
ついに、実用に耐えうる強度と柔軟性を持ち、ロール状に加工できる「アルフィル」が完成したのです。
老舗昆布店の、昆布への深い知識と、諦めない探求心があったからこそ、この画期的な新素材は生まれたんですね。
アルフィルの活用方法と広がる可能性
さて、そんなすごい特徴と開発ストーリーを持つアルフィルですが、具体的にどんな風に使われるのでしょうか?
すでに食品分野だけでなく、全く違う分野からも熱い視線が注がれています。
食品分野での活用例
まずは、一番イメージしやすい食品分野から見ていきましょう。
- おにぎりの包装海苔のように、フィルムごと食べられます。手が汚れず、ごみも出ないので、コンビニやスーパーで採用されたら、一気に広まりそうですね。
- 溶けるだしパック・スープの素すでにご紹介したように、お湯を注ぐだけでOK。計量スプーンもいらず、洗い物も減ります。インスタントみそ汁の味噌も、アルフィルで包めば、手に付かずに絞り出せそうですよね。
- 飴やキャラメルの包装一個ずつ包装紙を剥がすのって、地味に面倒だったり、ゴミが散らかったりしませんか?アルフィルなら、そのまま口にポイっと入れられます。
他にも、チーズを一枚ずつ包むスライスチーズのフィルムや、お弁当の仕切りに使うバランの代わりなど、アイデア次第で無限の可能性が広がります。
食品以外の分野への応用
アルフィルの活躍の場は、食べ物だけにとどまりません。
- 水に溶けるフェイスパックなんと、2025年に開催される大阪・関西万博では、アルフィルを使ったフェイスパックが披露される予定だそうです。使用後は、洗面台で水に溶かして流せるので、ゴミが出ないエコな化粧品として注目を集めそうですね。
- シャンプーやリンスの個包装旅行やジムに持っていくのに便利な、一回使い切りタイプのシャンプーやリンス。これもアルフィルで包めば、濡れた手で袋を開けるストレスから解放されます。
- 農薬や肥料のカプセル農薬や肥料をアルフィルでカプセル化し、土に埋めるという使い方も研究されています。こうすることで、雨などによってゆっくりとカプセルが溶け、必要な成分が少しずつ土壌に浸透していくため、効果が長持ちし、環境への負荷も減らせると期待されています。
トヨタ紡織との共同開発
さらに驚くことに、自動車部品メーカーの「トヨタ紡織」も、アルフィルの可能性に注目しています。
現在は、アルフィルを原料の一部に使った、新しい素材の開発を共同で進めているとのこと。
もし実現すれば、自動車の内装などに使われているプラスチック部品の一部が、昆布由来の素材に置き換わるかもしれません。
「昆布でできた車」が走る未来。想像するだけでワクワクしますよね。
アルフィルの今後の展望と課題
夢のような新素材アルフィルですが、私たちの生活に広く普及するまでには、まだいくつか乗り越えるべきハードルがあります。
価格と安定供給
まず、気になるのが「価格」です。
現在、アルフィルはまだ本格的な量産体制が整っておらず、価格は「未定」となっています。
新しい技術なので、最初はどうしても製造コストが高くなりがちです。
スーパーで売っている食品用ラップと同じくらいの価格で手に入るようになるには、大量生産の技術を確立して、コストを下げていく必要があります。
また、原料となる昆布の安定的な確保も重要です。
天候不順などによって昆布が不作になると、原料が足りなくなってしまう可能性もあります。国内外から安定して原料を調達できるルートを確保することが、今後の大きな課題と言えるでしょう。
さらなる強度と機能性の追求
アルフィルは、開発当初に比べて格段に強度がアップしましたが、用途によっては、さらに高い機能性が求められます。
例えば、液体を包む場合。
水に溶ける性質はメリットですが、逆に言えば、現時点では液体を長期間保存するのには向いていません。水分に強いタイプのアルフィルなど、用途に合わせた改良が期待されます。
また、プラスチックのように、あらゆる形に加工できるかどうかも、普及の鍵となります。
より強く、より多機能なアルフィルを目指して、これからも研究開発は続いていきます。
世界の食料・環境問題への貢献
課題はありますが、アルフィルが持つ可能性は、それを補って余りあるほど大きいものです。
開発のきっかけとなった「海外産の昆天」。
これまでは、うま味が少ないという理由で、ほとんどが活用されずに廃棄されていました。
しかし、アルフィルの原料としてなら、これらの昆布も有効活用できます。
これは、世界的な「食品ロス」の削減に繋がります。
また、食料が不足している地域で、昆布を新たな資源として活用できる道が開けるかもしれません。
アルフィルは、単なるプラスチックの代替品ではありません。
日本の「もったいない」の精神から生まれた、世界の食料問題と環境問題の両方を解決しうる、まさに希望の素材なのです。
【まとめ】昆布が切り拓くサステナブルな未来

今回は、昆布由来の未来のフィルム「アルフィル」について、詳しくご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか?
この記事のポイントを、最後にもう一度おさらいしてみましょう。
- アルフィルは、昆布の「アルギン酸」からできた、食べられるフィルム
- 「無味無臭」「カロリーゼロ」「水溶性」「生分解性」など、すごい特徴がたくさん
- 大阪の老舗昆布店「舞昆のこうはら」が、偶然の発見から6年かけて開発
- 食品ラップだけでなく、化粧品や自動車部品など、幅広い分野での活用が期待されている
- 価格や供給などの課題はあるが、環境問題や食料問題を解決する大きな可能性を秘めている
研究室での小さな偶然から始まった物語が、今、私たちの暮らしや地球の未来を大きく変えようとしています。
おにぎりをフィルムごと食べたり、だしパックが勝手に溶けたりする。そんなSFのような日常が、もうすぐそこまで来ているのかもしれません。
次にスーパーで昆布を見かけたら、ぜひこのアルフィルの話を思い出してみてください。
小さなネバネバの一粒に、とてつもなく大きな未来が詰まっていることが感じられるはずです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
アルフィルを開発した『舞昆のこうはら』さん、実は改装由来の化粧水も販売しています。!未来の素材を生み出した老舗の商品、一度試してみませんか?→ こちら