日本経済新聞 2025年8月3日(日曜日)の要約と、暮らしと歴史の交差点
こんにちは。毎日暑い日が続きますが、いかがお過ごしでしょうか。
窓の外の景色はいつもと同じように見えても、実は暦の上では少し特別な時間が流れていることをご存知でしたか?
今日の日本経済新聞のコラム「春秋」は、そんな暦の話から始まります。
今年は旧暦で「閏月(うるうづき)」がある年。具体的には「閏水無月(うるうみなづき)」という、普段は聞かない月の名前が登場します。「水無月」というと、水が無い月?と心配になりますが、実は「無」は助詞の「の」を意味していて、「田んぼに水を張る月」という豊かなイメージの言葉なのだそうです。
でも、コラムはそこから、水がもたらす恵みだけでなく、津波や渇水といった怖さ、そして、戦場で兵士の命を脅かした「水」の問題へと話を進めます。安全な水を確保するために作られた部隊が、その裏で非道な人体実験を行った「731部隊」であったという、歴史の暗い側面。
さらに話は現代へ。この731部隊をテーマにした映画の公開が中国で直前に見送られたというニュースに触れ、その背景にある複雑な国際関係や、日本の政局、特に石破茂元首相の動向へと繋がっていきます。石破氏のかつての派閥「水月会」の名前の由来である「水に映る月」という言葉を引用しながら、暦の季節の移ろいと、これからの政治の季節の到来を重ね合わせ、静かに締めくくられていました。
なんだか、閏月という一つの言葉から、歴史や政治まで、壮大な話が繋がっていますよね。
「閏月ってそもそも何?」「731部隊って、名前は聞くけど詳しくは知らない…」「石破さんや今の政治って、これからどうなるの?」
コラムを読んで、そんな風に感じた方もいらっしゃるかもしれません。
そこでこの記事では、コラムをきっかけに浮かび上がった様々なキーワードを、一つひとつ丁寧に紐解いていきたいと思います。私たちの日常と、遠いようで実は繋がっている歴史や政治の世界。少しだけ、一緒に寄り道してみませんか?
なぜ今「閏月」が話題なの? 私たちの暮らしと暦の優しい関係
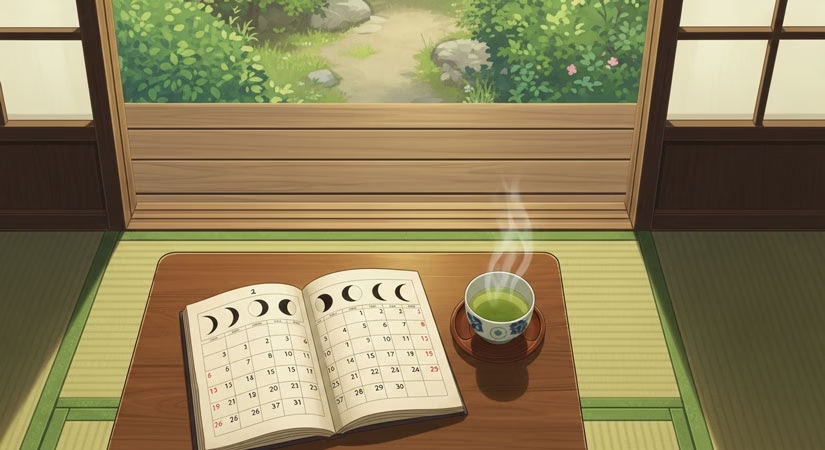
まずは、コラムの冒頭に出てきた「閏月(うるうづき)」から見ていきましょう。
「うるう年」なら4年に1度、2月29日がある年として馴染みがありますが、「閏月」は少し聞き慣れないかもしれませんね。
そもそも「閏月(うるうづき)」って何?
普段私たちが使っているカレンダーは「太陽暦(新暦)」といって、地球が太陽の周りを一周する時間(約365.24日)を基準にしています。
一方で「閏月」が登場するのは、「太陰太陽暦(旧暦)」という、月の満ち欠けを基準にした暦の世界です。
月の満ち欠けと季節のズレ
月の満ち欠けのサイクルは、約29.5日。これを12回繰り返すと、約354日になります。
太陽暦の1年(約365日)と比べると、1年で約11日も短いんですね。
このままでは、3年も経つと1ヶ月以上も季節がズレてしまいます。
お正月が春に来たり、七夕が真冬になったり…。それでは農作業の目安にもならず、生活が混乱してしまいますよね。
ズレを解消する知恵が「閏月」
そこで、昔の人たちが考え出したのが「閏月」という仕組みです。
数年に一度、1年を13ヶ月にする年を設けることで、この季節のズレをリセットしたのです。
なんだか、少し長くなってしまったズボンの裾を直すような、暮らしの知恵を感じませんか?
| 項目 | 太陽暦(新暦) | 太陰太陽暦(旧暦) |
| 基準 | 地球が太陽を回る周期 | 月の満ち欠けの周期 |
| 1年の日数 | 約365日 | 約354日 |
| 季節とのズレ | ほとんどない | そのままだと毎年約11日ズレる |
| ズレの調整法 | 4年に1度「閏日(2/29)」を入れる | 約3年に1度「閏月」を入れ1年を13ヶ月にする |
「水無月(みなづき)」の本当の意味って?
コラムにもあったように、6月を意味する「水無月」は、「水の無い月」ではありません。
この「無」は、昔の言葉で「~の」を意味する格助詞なんです。
つまり、「水無月」は「水の月」。
ちょうど田植えのために田んぼに水を引く季節であることから、この名前が付いたと言われています。
言葉のイメージが、がらりと変わりませんか?
ちなみに、他の月の名前にも素敵な意味が込められています。
弥生(やよい):木草弥や生ひ茂る月(草木がますます生い茂る月)皐月(さつき):早苗を植える月神無月(かんなづき):全国の神様が出雲大社に集まるため、神様が「居なくなる」月(逆に出雲では「神在月(かみありづき)」と呼ばれます)
スマホのスケジュール帳も便利ですが、たまにはこうした昔ながらの暦に目を向けてみると、季節の移ろいをより豊かに感じられるかもしれませんね。
<PR> 季節の移ろいを感じながら、静かにお香を嗅ぐ。そんな豊かな時間が、日々の思考をクリアにしてくれます。→ こちら
コラムが投げかける「水の記憶」- 恵みと歴史の影
コラムは、「水」というテーマを、単なる季節の言葉としてだけでなく、もっと深く、私たちの命や歴史に関わるものとして捉え直していました。
命をつなぐ水、命を奪う水
今年の夏も、局地的な大雨による川の氾濫や、反対にダムの貯水率が下がって渇水が心配されるニュースを目にします。
数年前にあった大きな津波の記憶も、まだ私たちの心に深く刻まれています。
水は、私たちの体を満たし、植物を育て、命を育む、なくてはならない恵みです。
その一方で、一度牙をむけば、全てを飲み込み、押し流す恐ろしい力も持っています。
コラムが言うように、「水のありがたさと怖さが身にしみる」というのは、災害の多い日本に暮らす私たちが、常に感じていることなのかもしれません。
近代日本の忘れられない教訓 – 戦争と防疫給水
この「水」が持つ二面性は、戦いの歴史においても、兵士たちの運命を大きく左右しました。
コラムでは日清戦争(1894年~1895年)の例が挙げられていましたね。
当時の日本兵の死因で、実は戦闘による死者よりも多かったのが、病気による死者でした。
特に、汚染された水や食べ物から感染するコレラや赤痢といった感染症は、軍隊にとって大きな脅威だったのです。
「お腹を壊す」なんてレベルではありません。コレラは激しい脱水症状を引き起こし、あっという間に命を奪う、恐ろしい病気です。
戦場で武器を持って敵と戦う以前に、飲む水一つで部隊が壊滅してしまう。
そんな事態を避けるため、軍は「防疫給水」、つまり病気を防ぐための安全な水を供給することに、必死で取り組むようになります。
高性能なろ過装置を開発し、安全な水を前線に届ける専門の部隊を作る。
それは、兵士の命を守るための、いわば「光」の側面でした。
しかし、その光が濃ければ濃いほど、深い影もまた生まれてしまったのです。
光と影 – 「関東軍防疫給水部」、いわゆる「731部隊」とは
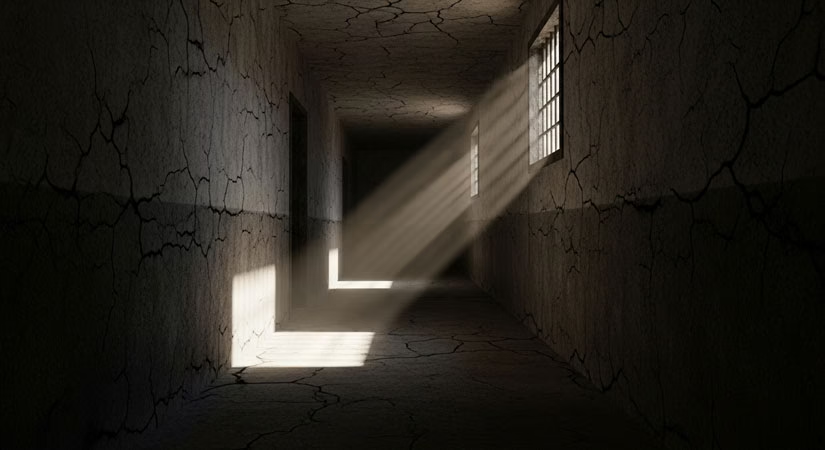
コラムで触れられていた「関東軍防疫給水部」。
この名前だけ聞くと、先ほどお話ししたように、兵士を病気から守るための大切な部隊のように聞こえますよね。
ですが、この部隊こそが、歴史に「731部隊」という名で知られる、暗い影の部分そのものでした。
ここで少し、731部隊について、私たちが知っておくべき情報を整理してみたいと思います。
目を背けたくなるような内容も含まれますが、コラムが現代の政治と結びつけている以上、その背景を知ることは、今のニュースを理解するためにも大切な一歩だと思うのです。
731部隊の概要
| 項目 | 内容 |
| 正式名称 | 関東軍防疫給水部本部 |
| 通称 | 731部隊、石井部隊 |
| 所在地 | 満州(現在の中国東北部)ハルビン近郊 |
| 活動期間 | 1930年代後半~1945年 |
| 目的(表向き) | 感染症予防の研究、安全な水の供給 |
| 目的(秘密裏) | 細菌(生物)兵器の研究・開発 |
| 主な活動 | ・ペスト、コレラ、炭疽菌などの細菌を研究・培養<br>・捕虜やスパイ容疑者など(中国人、ロシア人、朝鮮人など)を「マルタ」と呼び、生きたまま人体実験を行った<br>・細菌兵器の効力を試すため、中国の村落にペスト菌を散布するなどの実戦テストも行われたとされる |
なぜ、そんな非道なことが行われたのか
「人の命を救うはずの医学者が、なぜ?」
そう疑問に思うのは、当然のことです。
背景には、当時の世界的な軍拡競争と、戦争のためならどんな手段も許される、という歪んだ空気があったと言われています。
「敵国よりも強力な兵器を持たなければ、国が滅ぼされる」という恐怖が、科学者たちの倫理観を麻痺させてしまったのかもしれません。
また、実験対象とされた人々を、同じ人間としてではなく、研究のための「材料(マルタ)」と見なすことで、罪悪感を薄めていたという、恐ろしい心理も指摘されています。
これは、遠い昔の、どこか特別な人たちの話ではありません。
私たち人間が、特定の状況下では、いかにたやすく「非道」に手を染めてしまう可能性があるのか。
731部隊の歴史は、そんな重い問いを、現代に生きる私たちにも投げかけています。
戦後、この部隊の幹部たちは、研究データと引き換えにアメリカから戦争責任を追及されず、日本の医学界や製薬業界の要職に就いた者も少なくありませんでした。
この事実もまた、私たちが向き合わなければならない、歴史の複雑さを示しています。
歴史は現代にどう繋がる?- 映画と政治の裏事情
コラムは、この731部隊をテーマにした映画の公開が、中国で直前に見合わされたというニュースを取り上げていました。
歴史の問題が、現代の文化や政治に、どう影響を与えているのでしょうか。
なぜ今、731部隊の映画が?
近年、中国では歴史、特に抗日戦争(日中戦争)をテーマにした映画やドラマが数多く作られています。
これは、国民の愛国心を高めたいという政府の意向もあると言われています。
731部隊のような、日本の加害行為をテーマにした作品が作られるのも、その流れの一つと考えることができます。
歴史の事実を後世に伝え、忘れないようにしよう、というメッセージが込められているのでしょう。
映画公開見送りの背景にある複雑な思い
では、なぜその映画の公開が見送られたのでしょうか。
コラムでは、いくつかの可能性が示唆されていましたね。
- 残忍な場面への配慮人体実験などをリアルに描いた場面が、観客に強いショックを与えすぎるため、当局が公開をためらったのかもしれません。
- 興行上の理由似たようなテーマの別の映画と公開時期が重なってしまい、観客の奪い合いになるのを避けるため、戦略的に時期をずらした、というビジネス的な判断も考えられます。
- 日中関係への配慮これが、一番政治的な側面です。現在、日中関係は決して良好とは言えないまでも、対話を続け、これ以上悪化させないようにしようという動きもあります。そんな中で、日本を刺激するような映画を大々的に公開することが、両国関係に水を差しかねないと判断した可能性です。
コラムはさらに、この「配慮」が、日本の特定の政治家、つまり石破茂元首相に向けられたものではないか、と推測しています。
「かの国は石破さんの続投に期待しているらしい」という一文は、なかなか踏み込んだ見方ですよね。
エンタメと政治の微妙な関係 – 「贔屓の引き倒し」ってどういうこと?
ここで出てくるのが「贔屓(ひいき)の引き倒し」という言葉。
これは、「ある人を応援しすぎるあまり、かえってその人の立場を悪くしてしまう」という意味のことわざです。
もし、中国が「石破さん(あるいは、親中派と見なされる政治家)がトップになってくれれば、日中関係がうまくいくのに」と考えて、あからさまに応援するような態度を取ったとします。
例えば、石破氏が総理・総裁になるかもしれないこの時期に、日本への刺激を避けるために映画の公開を見送る、といった行動です。
すると、日本の国内ではどう受け取られるでしょうか。
「あの人は中国に甘い」「中国の言いなりになるのではないか」といった批判が、かえって高まってしまうかもしれません。
良かれと思ってした応援が、結果的に相手の足を引っ張ってしまう。これが「贔屓の引き倒し」です。
一つの映画の公開見送りの裏には、こんなにも複雑な、各国の思惑や駆け引きが隠されているかもしれないのですね。
政局の秋へ – 「水月会」に込められた意味と今の政治
物語は、いよいよ日本の政治の中心へと移ります。
コラムの最後を飾るのは、石破茂元首相と、彼がかつて率いた政策グループ「水月会(すいげつかい)」の話です。

石破茂さんってどんな政治家?
皆さんは、石破茂さんというと、どんなイメージをお持ちでしょうか?
- 防衛や安全保障にものすごく詳しい
- 地方創生に熱心
- テレビ番組などで、難しい政策を分かりやすく説明してくれる
- ちょっとマニアックな趣味(軍事、鉄道、アイドルなど)を持っている
こんなイメージが強いかもしれませんね。
長く自民党の重鎮として活躍し、何度も総理・総裁を目指してきた、日本の政治に欠かせない人物の一人です。
一方で、党の中心グループとは距離を置き、政権に対して厳しい意見を言うことも多かったため、「孤高の人」といった印象を持つ人もいるようです。
「水月会」に込められた理想 – 自然体で無私無欲な政治とは?
そんな石破さんが率いていたグループが「水月会」でした。
この「水月」という美しい名前には、禅の教えに基づいた、深い意味が込められています。
「水に映る月」
水面(みなも)に、静かに月が映っている光景を想像してみてください。
月は、水に映ろうと意識しているわけではありません。
水もまた、月を映そうと努力しているわけではありません。
ただ、そこにある月が、そこにある水に、自然のままに映っているだけ。
この情景から、「特定の地位や利益を求めるのではなく、無私無欲の心で、ただ国民のために為すべきことを為す」という、政治家としての理想の姿を表現したのが「水月会」という名前だったのです。
とても清らかで、素敵な理念ですよね。

理想と現実のギャップ?「水に映る月はすくいようがない」という皮肉
しかし、この美しい理念は、時に皮肉を込めて使われることもありました。
コラムにも「水に映る月はすくいようがない、とやゆされたこともある」と書かれていましたね。
これは、「理想は立派だけれど、しょせんは水に映った月と同じで、実体がない。手ですくおうとしても、掴むことはできない」という意味の、厳しい批判です。
政治の世界は、残念ながら清らかな理想だけでは勝ち抜けません。
総理・総裁になるためには、多くの議員の支持を集め、派閥の力を拡大していく、といった現実的な戦略も必要になります。
「水月会」は、理念を大切にするあまり、そうした勢力争いにはなかなか乗り切れず、石破さんを総理の座に押し上げるまでには至りませんでした。
結局、水月会は2021年に事実上の解散となっています。
2025年、政局の秋の行方は?
そして、コラムは「水の月もあと20日ほど。暦とともに、政局の秋が訪れるのだろうか」と締めくくられています。
「水の月」である閏水無月が終わる頃、永田町では次の自民党総裁選に向けた動きが本格化し、「政局の秋」がやってくる、という見立てです。
現在、自民党内では、様々なリーダー候補の名前が挙がっています。
現職の総理への支持、世代交代を求める声、政策の違いなど、色々な要素が絡み合い、誰が次のリーダーになるのか、先行きはまだ不透明です。
その中で、かつて「水月会」を率いた石破さんは、どのような動きを見せるのでしょうか。
コラムは「続投意欲は別のようだ」と、石破氏が再びリーダーを目指す意欲を持っていることを示唆しています。
「無私無欲」を掲げた「水月」の理念と、トップを目指すという強い「意欲」。
その間で、石破氏はどのような政治判断を下していくのか。
そして、国民は、彼の姿に何を期待するのでしょうか。
まとめ – 暦から歴史、そして未来へ
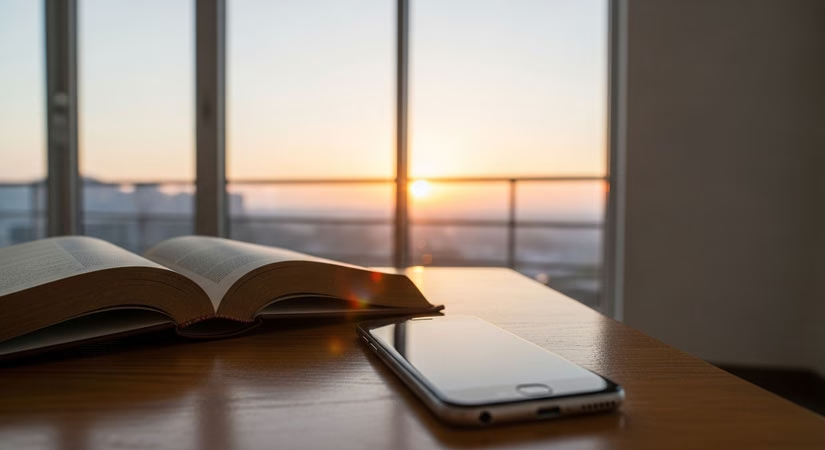
いかがでしたでしょうか。
日本経済新聞の短いコラムを入り口に、暦、歴史、国際関係、そして日本の政治まで、壮大な旅をしてきました。
日常の中にある「歴史のヒント」
「閏月」という、私たちの生活に身近な暦の話題。
それが、「水」というキーワードを介して、731部隊という日本の暗い歴史に繋がりました。
そして、その歴史の記憶が、現代の映画や国際関係、さらには一人の政治家の理念や行動にまで影響を与えている。
普段、私たちが何気なく見過ごしている日常の中にも、実はたくさんの「歴史のヒント」が隠されているのかもしれません。
道端に咲く花の名前の由来を調べてみたら、万葉集の歌に行き着くように。
一つの言葉やニュースをきっかけに、少しだけ深く掘り下げてみることで、世界はもっと面白く、もっと立体的見えてくるのではないでしょうか。
私たちができること – 知り、考え、対話する
「歴史は難しそう」「政治は自分には関係ない」
そう感じてしまう気持ちも、よく分かります。
でも、731部隊の問題が問いかける「人間の倫理」や、石破氏の「水月会」が掲げた「無私無欲の理想と現実」といったテーマは、政治家だけの話ではなく、私たちの仕事や人間関係の中にも通じる、普遍的な悩みでもあるように思うのです。
大切なのは、まず「知る」こと。
そして、一方的な情報だけを鵜呑みにせず、「これってどういうことなんだろう?」と自分なりに「考える」こと。
もしよければ、今日の内容を、ご家族や友人と「対話」してみるのも素敵だと思います。
「水無月って、本当は『水の月』って意味なんだって!」という気軽な話題からで、全く構いません。
そんな小さな一歩の積み重ねが、歴史の教訓を未来に活かし、より良い社会を作っていく力に繋がると、私は信じています。
暦の上では、もうすぐ秋。
皆さんの毎日にも、心豊かな実りの秋が訪れることを願っています。
<PR>暦の話題にちなんで、お部屋に季節のお花を飾ってみませんか?暮らしに彩りが生まれます。→こちら







