日本経済新聞 2025年8月10日(日)朝刊春秋の要約とアートが紡ぐ平和へのメッセージ
ピカソの「ゲルニカ」はその巨大さでも知られる。縦およそ3.5メートル、幅は7.8メートルにもおよぶ。被爆80年の企画展を開催中の長崎県美術館で、原寸大のレプリカが展示されている。陶板で精巧に再現されたもので、前に立つと視界を埋め尽くすかのように画面が迫る。
▼その名画と同じサイズの広大なカンバスに、子供たちが平和の絵を描く。そんなアートプロジェクトが「キッズゲルニカ」だ。戦後半世紀を機に始まって30年になる。理念への共感は世界に広がり、数十もの国々で絵筆がとられているそうだ。多くの作品が海を渡って行き来。。。。(有料版日経新聞より引用)
夏の強い日差しの中、ふと目にした新聞のコラム。そこに綴られていたのは、一枚の絵画から始まる、時を超え、国境を越えた平和への祈りの物語でした。
パブロ・ピカソが描いた「ゲルニカ」。そして、その魂を受け継ぐように世界中の子どもたちが平和を描く「キッズゲルニカ」。
「ゲルニカって、名前は聞いたことあるけど、詳しくは知らないな…」
「キッズゲルニカって、どんな活動なんだろう?」
「どうして今、この二つのアートが注目されているの?」
そんな風に感じた方もいらっしゃるかもしれませんね。
この記事では、新聞記事をきっかけに、この二つの「ゲルニカ」が私たちに何を語りかけてくるのか、一緒に探る旅に出かけたいと思います。巨大なモノクロの絵画に込められた悲痛な叫びと、子どもたちが描く色鮮やかな未来への希望。その両方に触れることで、私たちの日常の片隅に、平和を想う優しい時間が生まれるきっかけになれば嬉しいです。
圧巻のスケールと悲劇の物語:ピカソの「ゲルニカ」を巡る旅
まずは、すべての始まりであるピカソの「ゲルニカ」について、少しだけ詳しく見ていきましょう。この絵が持つ背景を知ると、子どもたちが描く「キッズゲルニカ」の意味も、より深く心に響いてくるはずです。

実はこんなに大きい!「ゲルニカ」のサイズを体感してみよう
新聞記事にもあるように、「ゲルニカ」のサイズは縦約3.5メートル、幅約7.8メートル。
数字だけ聞いても、なかなピンとこないかもしれませんね。
身近なもので例えるなら、こんな感じです。
- 路線バス:ちょうど車体と同じくらいの幅があります。
- 学校の教室:黒板の横幅の、2倍近くになるでしょうか。
- バレーボールのコート:横幅(9m)に迫る大きさです。
想像してみてください。もしこの絵の前に立ったら、視界のすべてが絵に覆われて、まるで絵の世界に迷い込んでしまったかのような感覚に陥るでしょう。長崎県美術館では、原寸大のレプリカが展示されているとのこと。その場に立つ人々が、いかにその迫力に圧倒されるか、目に浮かぶようですよね。
ピカソはなぜ、これほど巨大なキャンバスを選んだのでしょうか。それはきっと、彼が伝えようとした衝撃と悲しみの大きさを、私たちに「体感」してほしかったからなのかもしれません。

モノクロの世界に描かれた9つのシンボルとその意味
「ゲルニカ」のもう一つの大きな特徴は、色が一切使われていないこと。黒、白、そして様々な濃さの灰色だけで、混沌とした悲劇の世界が描かれています。まるで、当時のニュース映画や新聞紙面から切り取られた生々しい記録のようです。
この絵の中には、様々なモチーフが登場します。一つひとつに、ピカソが込めたとされる象徴的な意味があるんですよ。
| シンボル | 描かれているもの | 考えられる意味 |
| 1. 牡牛 (Bull) | 絵の左端で、すべてを見下ろすように佇む。 | 理不尽な暴力、野蛮さの象徴。あるいはスペインそのものを表すとも。 |
| 2. 嘆き悲しむ母親 (Mourning Mother) | 亡くなった我が子を抱き、天に向かって叫んでいる。 | すべての戦争犠牲者の母の悲しみ、奪われた未来。 |
| 3. 兵士 (Soldier) | バラバラになった体で、折れた剣を握りしめている。 | 敗北した抵抗、無力さ。でも、その手には花が咲いていることから、かすかな希望も。 |
| 4. 馬 (Horse) | 体を槍が貫き、苦痛に嘶(いなな)いている。 | 苦しみ、もだえる民衆の象徴。 |
| 5. 電灯 (Light Bulb) | 絵の中央、太陽のような形で光っている。 | 近代文明がもたらした冷たい破壊の光、あるいは真実を照らす神の目とも。 |
| 6. ランプを持つ女性 (Lamp-Bearing Woman) | 窓から身を乗り出し、ランプを掲げて惨状を照らす。 | 真実を明らかにしようとする世界の良心、希望の光。 |
| 7. 逃げ惑う女性 (Fleeing Woman) | 右側から中央に向かって、必死の形相で走ってくる。 | 爆撃から逃れようとする市民たちのパニック。 |
| 8. 炎に包まれる女性 (Woman in Flames) | 燃えさかる家の中で、両手を挙げて助けを求めている。 | 逃げることすらできず、命を落としていく人々の苦しみ。 |
| 9. 鳥 (Bird) | 牡牛と馬の間で、かろうじて見える。平和の象徴である鳩か。 | 平和へのかすかな願い、しかしその声は悲鳴にかき消されそうになっている。 |
こうして見ると、一枚の絵の中に、たくさんの悲しい物語が詰め込まれていることがわかりますよね。直接的な爆弾や戦闘機は描かれていません。でも、残された者たちの表情や姿を通して、戦争がいかに無慈悲で、人々の日常を破壊し、深い傷を残すものなのかを、静かに、しかし力強く訴えかけてくるのです。
すべての始まり:1937年、スペインの小さな町で起きたこと
では、ピカソをこれほどまでに駆り立てた出来事とは、何だったのでしょうか。
それは、1937年4月26日に、スペインの北部にある「ゲルニカ」という小さな町で起きた悲劇でした。
当時のスペインは、国内が二つに分かれて戦う「スペイン内戦」の真っ只中。その日、フランコ将軍を支援するナチス・ドイツの空軍「コンドル軍団」が、何の軍事的な重要性も持たないゲルニカの町に、突如として爆弾の雨を降らせたのです。
それは、週に一度の市場が開かれ、多くの市民で賑わう日でした。近代的な兵器による、一般市民を狙った歴史上初めての無差別爆撃と言われています。数時間で町は炎に包まれ、多くの罪のない命が奪われました。
パリにいたピカソは、このニュースを新聞で知り、激しい怒りと悲しみに震えます。そして、その年に開催されるパリ万国博覧会のスペイン館のために、この悲劇をテーマにした巨大な壁画の制作に、取り憑かれたように没頭しました。
「ゲルニカ」は、単なる一枚の絵画ではありません。それは、非人道的な暴力に対するピカソの魂の抗議であり、歴史の証人として、そして未来への警告として、今なお私たちに重い問いを投げかけ続けているのです。
平和への祈りをキャンバスに:「キッズゲルニカ」プロジェクトの輪
ピカソが「ゲルニカ」に込めた平和への強いメッセージ。その魂は、時を経て、世界中の子どもたちの手によって、新しい形で受け継がれています。それが「キッズゲルニカ」です。

「キッズゲルニカ」ってなあに?子どもたちのためのアートプロジェクト
「キッズゲルニカ」は、ピカソの「ゲルニカ」とまったく同じ大きさ(縦3.5m × 幅7.8m)のキャンバスに、子どもたちが自由な発想で「平和」をテーマにした絵を描く、国際的なアートプロジェクトです。
1995年、戦後50年を機に日本で始まりました。その目的は、とてもシンプルで、そして深いものです。
- 子どもたちが、自分たちの国のこと、世界の出来事に関心を持つきっかけを作ること。
- 「平和」とは何かを自分たちで考え、話し合う場を提供すること。
- 言葉や文化が違っても、アートという共通言語を通して、世界中の子どもたちと心で繋がること。
巨大なキャンバスに共同で絵を描くという体験は、子どもたちにとって特別な意味を持ちます。一人ではできないことも、みんなで力を合わせればできるという達成感。意見を出し合い、時にはぶつかりながらも、一つの作品を創り上げていくプロセスそのものが、多様性を受け入れ、協力しあう「小さな平和」の実践の場となるのです。
世界とつながる一枚の絵:国境を越える作品たち
この素敵なプロジェクトは、日本から世界へと広がり、今では50以上の国と地域の子どもたちが参加しているそうです。すごいことですよね。
そして、「キッズゲルニカ」の素晴らしいところは、描くだけで終わりではない点です。
完成した作品は、国際展や交流展を通じて、世界中を旅します。日本の子供たちが描いた絵がアメリカへ、インドの子供たちが描いた絵がロシアへ。そうして、お互いの国の子供たちが、どんなことを考え、どんな平和を願っているのかを知る「心の窓」になるのです。
インターネットで写真を見るのとは違い、目の前に広がる巨大な絵は、その国の空気や、描いた子どもたちの息づかいまで伝えてくれるような気がしませんか? そこに描かれた笑顔や、色鮮やかな自然、未来への夢。それらは、私たち大人がニュースで見る「紛争」や「対立」といったイメージとは全く違う、その国の素顔を教えてくれます。
心揺さぶる子どもたちの絵:ウクライナ、そしてガザから届いたメッセージ

新聞のコラムでは、特に私たちの胸を打つ二つの作品が紹介されていました。
一つは、ウクライナの子どもたちが描いた、麦畑と青空を背にした大きな木の絵。
広大な黄金色の麦畑は、ウクライナの豊かな国土の象徴です。その真ん中に、力強く根を張る一本の木。それはきっと、どんな困難にも負けずに立ち続ける、彼らの国の姿であり、自分たちの未来への希望なのでしょう。青い空には、ミサイルではなく、鳥が飛んでいてほしい。そんな切実な祈りが聞こえてくるようです。
もう一つは、数年前にガザ地区で障害のある子どもたちが描いた作品。
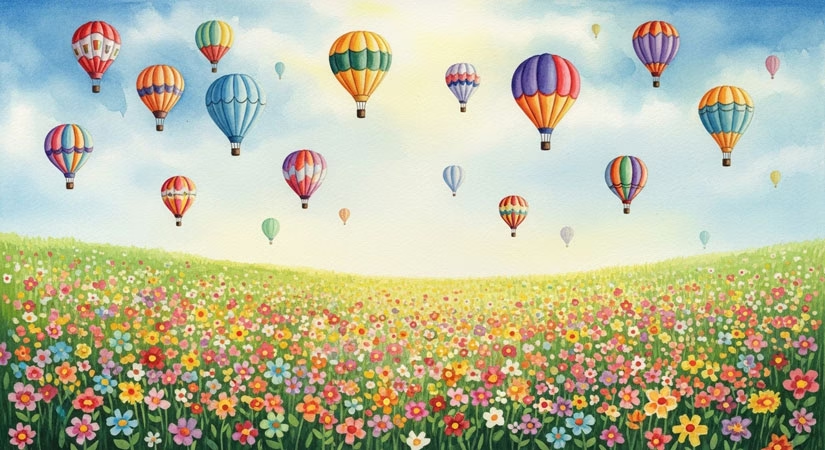
花でいっぱいの草原に、カラフルな気球が浮かんでいる絵だといいます。それは、空から見たガザの姿を想像して描いたものだそう。壁に囲まれ、自由に行き来することが難しい日常の中で、子どもたちの心は気球に乗って、どこまでも高く、自由に空を飛んでいたのかもしれません。
その後、この地域で何が起こったかを思うと、その明るく希望に満ちた絵は、あまりにも切なく、私たちの胸に深く突き刺さります。子どもたちが夢見た色鮮やかな世界は、今どうなってしまったのか。その絵を描いた子どもたちは、今、無事でいるのだろうか。そう考えずにはいられません。
ピカソが描いたモノクロの「ゲルニカ」は、起きてしまった悲劇への「怒りと告発」でした。
それに対して、子どもたちが描くカラフルな「キッズゲルニカ」は、これから創りたい未来への「祈りと希望」です。
この二つの「ゲルニカ」は、まるで光と影のように、私たちに戦争の残酷さと平和の尊さの両方を、同時に見せてくれているのです。
アートが照らし出す未来への道しるべ
戦争のニュースが毎日のように流れてくる今、私たちは時に無力感に襲われることがあります。でも、そんな時代だからこそ、アートが持つ力に、もう一度目を向けてみたいと思うのです。
長崎で「ゲルニカ」に出会う意味:被爆80年の夏に考える
新聞記事の冒頭にあったように、今年の夏、長崎県美術館では、被爆80年という節目の年に、原寸大の「ゲルニカ」のレプリカが展示されています。
長崎とゲルニカ。
この二つの地名が並ぶ時、私たちは歴史の重なりを感じずにはいられません。
1937年のゲルニカ無差別爆撃。
そして、その8年後の1945年8月9日、長崎に投下された原子爆弾。
どちらも、軍人ではない、ごく普通に暮らしていた人々の頭上に、突然、破壊と死が降り注いだという点で共通しています。ピカソが「ゲルニカ」で告発した非人道的な行いは、残念ながらその後も止まることなく、広島と長崎でその極点を迎えてしまいました。
そんな長崎の地で、巨大な「ゲルニカ」と向き合う。それは、過去の悲劇をただ追悼するだけでなく、「あの日」から80年経った今もなお、世界で同じような悲しみが繰り返されている現実を、私たち自身の問題として捉え直すための、大切な時間になるはずです。
展示されているレプリカが、劣化しにくい「陶板」で再現されているという点も、象徴的に感じられます。この悲劇の記憶と平和へのメッセージを、決して風化させることなく、未来永劫伝えていこうという強い意志の表れなのかもしれませんね。
◇あなたの想いを、未来への確かな支援に◇平和への願いを、何か具体的な形で行動に移したい。もしあなたがそう感じていらっしゃるなら、「ふるさと納税」という仕組みを使ってその想いを届ける方法があります。→ふるさと納税はこちらから
私たちにできること:平和について考え、語り合うきっかけとして
「でも、アートを見たからって、何かが変わるわけじゃない…」
そう感じる気持ちも、よくわかります。一枚の絵が、直接ミサイルを止めることはできないかもしれません。
でも、アートには、人の心に小さな種をまく力があります。
「ゲルニカ」を見て、戦争の恐ろしさを肌で感じる。
「キッズゲルニカ」を見て、子どもたちの純粋な願いに心を動かされる。
その感動や衝撃は、きっと誰かに話したくなるはずです。
「今日、こんな絵を見たんだよ」
「ウクライナの子どもたち、こんな絵を描いていたんだって」
そんな家族や友人との何気ない会話が、平和について考える小さな輪を広げていきます。一つの絵をきっかけに、遠い国の出来事を身近に感じ、そこに暮らす人々の痛みに思いを馳せる。その想像力こそが、無関心という壁を壊し、平和な世界を築くための、最初の一歩になるのではないでしょうか。
もし、お近くで「キッズゲルニカ」の展示会が開かれていたら、ぜひ足を運んでみてください。あるいは、インターネットで過去の作品を探してみるのもいいかもしれません。子どもたちが描いた色とりどりのキャンバスは、きっと、ささくれだった心を優しく癒し、未来への希望をそっと灯してくれるはずです。
まとめ:せみ時雨のなかで想う、色鮮やかな未来

新聞のコラムは、こんな言葉で結ばれていました。
ピカソが黒と灰色で糾弾した暴虐が過去のものとなり、子供が祈る色鮮やかな世界が実現するのはいつの日か。せみ時雨の下、考え込む。
けたたましく鳴り響くセミの声は、時に、空襲警報のサイレンを思い出させると言います。そんな声を聞きながら、筆者が想いを馳せたのは、いつになったら、子どもたちが描くような、ただただ明るく、平和な世界がやってくるのだろうか、という切実な問いでした。
ピカソが描いたモノクロの悲劇の世界。
子どもたちが描くカラフルな希望の世界。
今、私たちは、その二つの世界の間に立っています。
どちらの未来を選ぶのか。それは、私たち一人ひとりの心の中に委ねられています。
アートに触れることは、その選択のための、道しるべを見つける旅のようなものなのかもしれません。次に美術館を訪れるとき、街角で子どもの絵を見かけたとき、今日の話を少しだけ思い出していただけたら、とても嬉しいです。
私たちの小さな想像力が集まって、いつの日か、子どもたちが夢見る色鮮やかな世界が、本当に実現しますように。そんな祈りを込めて。






