日本経済新聞 2025年9月24日水曜日 朝刊春秋の要約と科学捜査の信頼性
信頼される科学捜査の背景にあるもの
探偵小説の主人公として、時代を超えて今なお世界中の人々に愛され続けているシャーロック・ホームズ。彼の物語がこれほどまでに私たちを惹きつけるのは、単に難事件を解決する彼の類まれな観察力や、天才的な推理力だけではありません。その魅力の核心には、当時の最先端科学を大胆に、そして効果的に捜査に取り入れていく、いわば「科学捜査のパイオニア」としての彼の姿があります。これは、アメリカの科学者であるJ・オブライエン氏が、彼の著書『科学探偵シャーロック・ホームズ』の中で深く考察している点です。
当時の最新技術が、事件を解き明かす鍵として登場するたびに、読者はまるで自分がホームズと一緒に事件に挑んでいるかのような、不思議な「信頼感」を覚えます。例えば、まだ一般には知られていなかった指紋鑑定技術を、個人を特定する重要な証拠として活用する場面。あるいは、犯人が残した足跡から、その人物の体格や歩き方の癖まで読み取る驚くべき技術。さらには、犬の鋭い嗅覚を利用したり、筆跡鑑定で人物を絞り込んだり…といった手法が、物語の中で説得力を持って描かれています。これらの描写があるからこそ、私たちは物語の展開を心から信じ、その後の結末にわくわくさせられるのです。オブライエン氏によれば、ホームズはまさに「科学捜査のパイオニア」であり、それゆえに「読者は信頼性を感じ、考えさせられる」のだと、通訳の日暮雅通氏は述べています。

科学捜査の光と影:現代に揺らぐ信頼性
ホームズが活躍した時代には想像もつかなかったような科学技術が、現代の犯罪捜査には欠かせないものとなっています。特にDNA鑑定は、事件の真相を解明する上で、もはや「決定的な役割」を果たすまでに進化しました。ほんのわずかな体液や毛髪から、個人の遺伝子情報を特定し、犯人と被害者を結びつける、まさに魔法のような技術です。
しかし、この強力なツールが、私たちに安心をもたらすばかりではありません。日経新聞のコラムが指摘するように、その信頼性が根底から揺らぐような、恐ろしい事態が現実には起こっているのです。佐賀県警で発覚したDNA鑑定を巡る不正は、まさにその象徴的な出来事でした。データの改ざんや虚偽報告が1件や2件ではなく、複数にわたって行われていたという事実は、私たちに大きな衝撃を与えました。
「捜査や公判には影響がない」と県警は主張していますが、もし万が一、この不正によって無実の人が犯罪者に仕立て上げられたとしたら…。そう考えると、背筋が凍るような思いがします。科学は客観的で、嘘をつかないはずです。それなのに、それを扱う「人間」の手に渡った途端、その信頼性はもろくも崩れ去ってしまう。この現実が、どれほど恐ろしいことか、私たちは改めて認識する必要があるのです。
| 科学捜査の代表的な手法 | ホームズの時代 | 現代 | 現代における問題点 |
| 指紋鑑定 | ○ | ○ | 偽造指紋や意図的な混入の可能性 |
| 足跡鑑定 | ○ | ○ | 不十分な採取や分析による見落とし |
| 筆跡鑑定 | ○ | ○ | 鑑定士の経験と主観に依存する部分 |
| 犬の嗅覚 | ○ | △ (科学的分析が主流に) | 飼育環境や訓練状況による能力差、精神状態 |
| DNA鑑定 | × | ○ | 採取時の汚染、データの改ざん、虚偽報告 |
| 科学的分析 | △ (化学物質の分析など) | ○ (多岐にわたる) | 分析機器の不備、人為的なデータ操作 |
なぜ科学捜査の不正が起こるの?その根深い理由
「科学は嘘をつかない」。元警視庁の科学捜査官である服藤恵三さんが、地下鉄サリン事件などの捜査に関わった経験から自著に記したこの言葉は、私たちに深い示唆を与えます。しかし、その言葉には「使う人間が正しければ」という、もう一つの重要な前提条件が隠されているのです。では、その前提が崩れてしまうのは、なぜなのでしょうか。
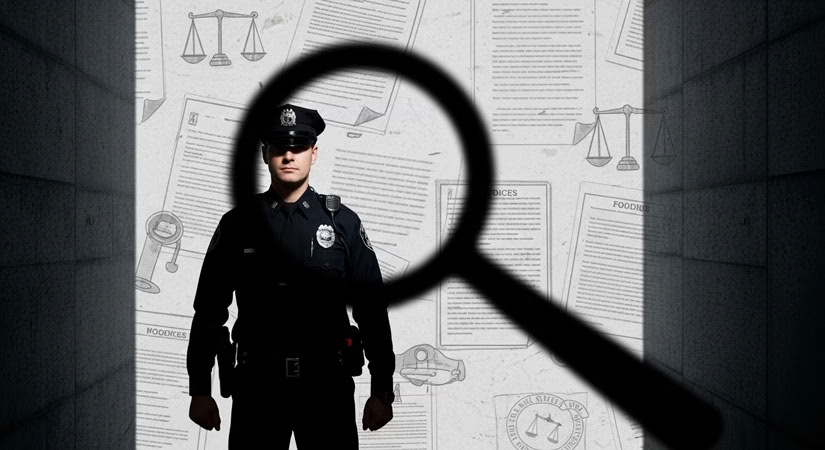
1. 「結果を出せ」という組織的な圧力
警察や捜査機関は、事件の早期解決や犯人逮捕という成果を強く求められます。このプレッシャーは想像を絶するほど大きなものです。特に、世間から注目されるような重大事件では、その傾向は顕著になります。そうした環境下では、捜査員や科学捜査官は、たとえわずかな疑問点があっても、都合の悪い結果を無視したり、見込み捜査に合うようにデータを「調整」したりしてしまうことがあります。一度「この人が犯人だ」と決めてしまうと、その「予断と偏見」を覆すことは、組織的にも個人的にも非常に難しくなるのです。
2. 個人の倫理観の欠如と専門家としての孤立
科学捜査は、高度な専門知識を必要とします。そのため、その鑑定内容を外部の人が詳細にチェックすることは、非常に困難です。この「専門家としての孤立」が、不正の温床となることがあります。少数の人間しか理解できない分野だからこそ、倫理観が欠如した者が、安易な気持ちで不正に手を染めてしまうリスクが高まるのです。データの改ざんや虚偽報告は、ほんの些細な「見逃し」や「手抜き」から始まり、それがエスカレートして、組織的な隠蔽へと発展してしまうことも少なくありません。
3. 科学捜査の「魔法」への過信
私たち一般の人々も、科学捜査の「魔法」を過信しすぎている面があるかもしれません。DNA鑑定の結果が出れば、それが絶対的な真実だと信じて疑わない。しかし、DNA鑑定は、あくまで「科学的な分析結果」であり、それを「事件の真相」と結びつけるのは人間の役割です。採取の過程で他人のDNAが混入したり、保管方法に不備があったりすれば、全く無関係な人が容疑者になってしまう可能性もゼロではないのです。
冤罪(えんざい)事件から学ぶ、科学捜査の教訓
日本の司法史には、科学捜査の不備が原因で多くの冤罪を生んでしまった、悲しい歴史があります。
- 足利事件、飯塚事件:これらの事件では、DNA鑑定の信頼性が大きく問われました。当時の鑑定技術や証拠の取り扱い方法に問題があったことが、再審につながる大きな要因となりました。特に足利事件では、「DNAの型が一致した」という科学的な証拠が、無実の人を長期間刑務所に閉じ込めることになったのです。
- 大川原化工機事件:この事件では、無実の企業が、警察当局が要求した再実験を怠ったことなど、科学的な手続きの不備が指摘されています。捜査機関が「科学は嘘をつかない」という前提を自ら裏切ったことで、企業の信用は地に落ち、多大な損害を被りました。
これらの事件は、私たちに「科学的証拠は絶対ではない」という、極めて重要な教訓を教えてくれています。科学捜査は、「誰が、どのようなプロセスで、何のために行ったのか」という、背景にある人間的な部分と切り離して考えることはできないのです。
科学捜査の信頼を取り戻すために私たちができること
では、この揺らいでしまった科学捜査の信頼を回復し、未来の冤罪を防ぐために、私たちは何ができるのでしょうか。それは、捜査機関や司法の努力だけでなく、私たち一人ひとりの意識改革も含まれます。
1. 倫理教育の徹底と内部告発制度の強化
警察や科学捜査機関において、倫理教育を徹底的に行うことが不可欠です。不正をしない、させないという高い職業意識を育むための研修や、定期的なコンプライアンスチェックを義務付けるべきです。また、組織内部の不正を、外部に告発しやすいような仕組み(内部告発制度)を強化することも、不正の抑止力として非常に効果的です。不正を見つけたら、正義感を持って声を上げられるような、風通しの良い組織文化を築くことが求められます。
2. 外部監査とセカンドオピニオンの導入
捜査機関が行った科学鑑定について、第三者の独立した機関が客観的に監査する仕組みを導入することは、公正性・透明性を高める上で非常に重要です。また、裁判の際には、弁護側が独自に専門家を雇い、提出された科学的証拠を再検証する「セカンドオピニオン」の機会を確保することも、冤罪防止につながります。これは、医療の世界で患者が複数の医師の意見を聞くのと同じように、司法の場でも複数の専門家の目で証拠を吟味する、という意味合いです。
3. 科学捜査の専門家育成と社会的地位の向上
高度な専門知識と高い倫理観を兼ね備えた人材を育成し、科学捜査官の社会的地位や処遇を向上させることも、不正防止につながります。プロフェッショナルとしての誇りを持って仕事に取り組めるような環境が整えば、安易な不正に手を染めるリスクは減るはずです。
最後に:私たち一人ひとりの「疑う力」

今回のコラムは、現代社会における科学捜査の信頼性という、非常に重く、考えさせられるテーマを扱っていましたね。科学は、私たちに多くの恩恵をもたらしてくれますが、それを扱うのは、不完全な私たち人間です。
「科学は嘘をつかない」。この言葉を信じる一方で、私たちは「使う人間が正しければ」という、もう一つの真実を忘れてはなりません。ニュースや情報に接する時、その情報が「誰が、どのような意図で、どのようなプロセスを経て生み出されたのか」を考えることが大切です。特に科学的な情報については、一つの情報源だけを鵜呑みにせず、複数のソースを確認し、自分なりに考える姿勢を持つことで、私たち自身が情報に惑わされず、正しい判断ができるようになるのではないでしょうか。
科学捜査の信頼回復は、一朝一夕にはいきません。しかし、私たち一人ひとりがこの問題に関心を持ち、「疑う力」を磨き続けることが、より公正で安全な社会へとつながる第一歩だと信じています。







コメント