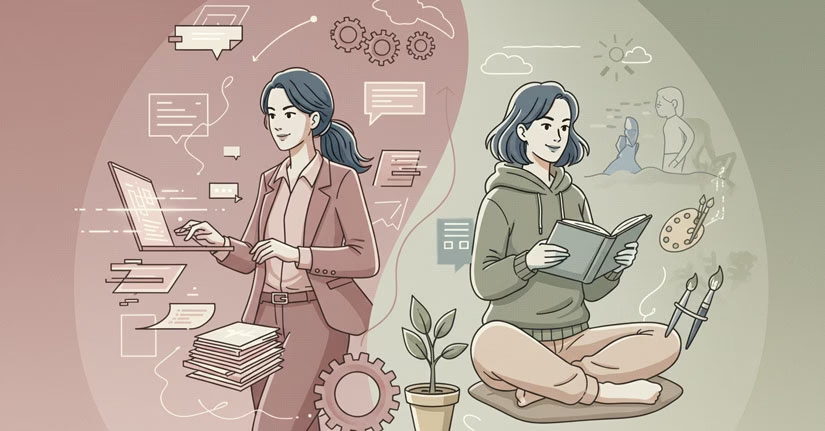日本経済新聞 2025年10月6日(月)朝刊春秋の要約と政治家の発言・政策への多角的な視点
はじめに:コラム「春秋」が問いかける、政治家の「生き方」と「政策」
この記事は、日本経済新聞の朝刊コラム「春秋」の内容をきっかけに、政治家個人の「生き方」や「価値観」が、どのように政策論争や世論に影響を与えているのかを掘り下げます。
特に、小泉進次郎氏の育児休業取得や、高市早苗氏の「ワークライフバランスを捨てる」発言、そして選択的夫婦別姓制度への見解を巡る議論から、私たちがリーダーに求める資質や、社会の多様性への向き合い方について考えていきます。
コラム「春秋」の引用
「ワークライフバランスを捨てる」。気合の入った宣言を聞いたとき、これかもと思い当たった。高市さんの勝因ではなく、小泉さんの敗因だ。現役閣僚として初めて育休を取った。イクメンアピールに対しては、恵まれた4世議員ならではの特権、と冷めた声もあった。
▼就職氷河期で望まぬ非正規職に就き、家庭を築く余裕のない同世代は多い。手放しで「ロスジェネの星」と応援しかねる気分もわかる。その点、高市さんも似ている。小泉さんが同世代なら高市さんの場合は同性。「自らが属する集団」の支持が厚くない。「初の女性総理」に複雑な思いを抱いた女性は少なくないだろう。
検索キーワードから見る読者の関心と課題
コラムの内容から、読者が特に知りたいであろう、あるいは議論の的となっているテーマを抽出し、それぞれのキーワードで検索する人が求めている情報を整理します。
| 検索キーワード | 読者が知りたい情報(課題・疑問) | 記事の構成要素 |
| 小泉進次郎 育休 | 育休取得への世間の評価は?特に同世代の非正規社員の反応は? 政治家の育休は一般にどう影響する? | 「政治家の育休」への世論の光と影、実態と制度への影響 |
| 高市早苗 ワークライフバランス | 「WLBを捨てる」発言の真意や背景は?女性・同性からの評価は? 政治家と仕事への「覚悟」 | リーダーシップと「ワークライフバランス」、現代女性の葛藤 |
| 高市早苗 夫婦別姓 | なぜ高市氏は夫婦別姓に反対なのか? 「通称使用拡大」で本当に不便は解消されるのか? | 選択的夫婦別姓制度の論点:反対派・推進派の主張と制度の現状 |
| ロスジェネの星 | 「ロスジェネ」世代の現状と政治家への期待・諦め。 | 「自らが属する集団」からの支持の複雑性:ロスジェネ世代の苦悩 |
| リーンイン・フェミニズム 批判 | 「リーンイン」とは? 批判の具体的な内容は? 成功した女性の論理が抱える問題とは? | 「リーン・イン」論争と「強者の論理」:女性の多様な成功とは |
| 姓はアイデンティティー | 姓を変えることがアイデンティティーにどう影響するのか? 選択の自由が奪われることの意味。 | 「姓」と「アイデンティティー」:選択の自由と多様な価値観 |
政治家の「私」と「公」の議論:育休と仕事への「覚悟」

政治家が公の場で語る「私生活」や「仕事への姿勢」は、しばしば世論を二分します。特に「育休」や「ワークライフバランス」といったテーマは、私たち自身の生活と直結するため、非常に注目されます。
政治家の育休:小泉進次郎氏への世論の光と影
小泉氏が閣僚として育休を取得したことは、男性の育児参加を促す上で画期的な一歩と評価されました。しかし、コラムが指摘するように、彼のような「恵まれた立場」の人物の行動は、すべての人に当てはまるわけではないという冷めた視線も存在します。
育休取得への世間の複雑な感情
| ポジティブな評価 | ネガティブ/複雑な評価 |
| 男性政治家がロールモデルとなることで、社会全体での育休取得が促進される。 | 恵まれた立場だからこそ取れる特権であり、一般の会社員や非正規雇用者にはハードルが高い。 |
| **「イクメン」**という言葉を浸透させ、育児への関心を高めた。 | **「アピール」**に終始し、根本的な制度改革や企業の意識改革には繋がりにくい。 |
| 政治家も家庭を大切にする姿勢は、国民の共感を呼ぶ。 | 政治家としての**「職責」**を全うしているのかという疑問。 |
リーダーシップと「ワークライフバランス」:高市氏発言の波紋
高市氏の「ワークライフバランスを捨てる」という発言は、「命がけで仕事に取り組む」という覚悟を示すものとして、一部からは評価されました。しかし、コラムが触れているように、この発言は現代の女性、特に子育てや介護をしながら働く多くの女性にとっては、共感しにくい、あるいはプレッシャーを与える言葉でもあります。
「WLBを捨てる」発言が抱える問題点
- 「成功」の定義の画一化:「ワークライフバランスを捨てる=成功」という図式は、仕事も生活も大切にしたいという多くの人の価値観を否定し、「仕事に全てを捧げられない人はリーダーになれない」というメッセージになりかねません。
- 「強さ」の押し付け:コラムにあるように、「みんなが高市さんほど強いわけでない」のです。家庭の事情や体力、精神的な強さは人それぞれです。リーダーには、「多様な生き方」を認める懐の深さが求められます。
- 現代社会との乖離:少子化が進む現代において、「子育てや家庭生活も大切にする社会」こそが持続可能な社会です。「仕事か家庭か」という二項対立ではなく、「仕事も家庭も」を可能にする社会づくりを目指すべきです。
「自らが属する集団」からの支持の複雑性:ロスジェネと女性
コラムは、小泉氏が高市氏のいずれも「自らが属する集団」からの支持が厚くないという点を指摘しています。これは、同じ属性を持つからこそ、「成功した個人の論理」に対する厳しい視線が存在するためです。
ロスジェネ世代の苦悩と政治家への視線
小泉氏と同世代とされる就職氷河期(ロスジェネ)世代には、望まぬ非正規職に就き、経済的な理由から結婚や家庭を築く余裕がない人が多くいます。
| ロスジェネ世代の状況 | 政治家への期待と複雑な思い |
| 経済的に不安定な生活を強いられてきた。 | 「個人の覚悟」や「成功者の論理」ではなく、「公助」による格差是正を求める。 |
| 家庭を持つ余裕がない人が多い。 | 政治家が「恵まれた育休」をアピールしても、現実とのギャップに共感しにくい。 |
| **「自助努力」**ではどうにもならない問題を抱えている。 | 「個人の覚悟」や「成功者の論理」ではなく、**「公助」**による格差是正を求める。 |
「初の女性総理」に複雑な思いを抱く女性たち

高市氏に対する女性からの視線も同様に複雑です。女性のリーダーシップを歓迎しつつも、高市氏が体現する「男社会に適応した勝ち組」の論理に、違和感を覚える女性も少なくありません。
「リーン・イン」論争と「強者の論理」
コラムに登場する米フェイスブック(現メタ)の女性重役による世界的ベストセラー『リーン・イン(Lean In)』は、「前に出よう」「臆せず上を目指そう」と女性を鼓舞しました。
| 「リーン・イン」論争のポイント | 私たちが考えるべきこと |
| 成功者の論理:主に経済的に恵まれ、能力のある女性に対して有効な戦略であるという批判。 | 成功の形は多様であり、**「前に出る」**ことだけが正解ではない。育児や介護と両立しながら働く女性、非正規雇用の女性など、多様な女性の困難にも目を向けるべき。 |
| 「男社会」への適応:既存の組織のルールを変えずに、女性側が努力して適応すべきというメッセージと受け取られた。 | 組織や社会の側が変わることが、真の女性活躍に繋がる。 |
選択的夫婦別姓制度の論点:「自分は平気」で済ませないリーダーの姿勢

コラムの結びは、選択的夫婦別姓制度に対する高市氏の反対姿勢に焦点を当てています。これは、リーダーの「多様な価値観への理解」の深さが問われる重要なテーマです。
選択的夫婦別姓制度の現状と論点整理
現在、日本では結婚すると夫婦のどちらかが必ず姓を変える「夫婦同姓(強制同姓)」が義務付けられています。これに対し、夫婦が結婚後もそれぞれ結婚前の姓を名乗ることを選べるようにするのが「選択的夫婦別姓制度」です。
制度をめぐる主な意見と高市氏の見解
| 推進派(制度導入を望む声) | 反対派(制度導入に慎重な声) | 高市氏の見解(コラムより) |
| 姓はアイデンティティーであり、変更の自由を保障すべき。変更による手続きや精神的負担を避けたい。 | **「家族の一体感」**や「伝統」が失われる。 | 強く反対。自身は結婚後も旧姓で活動し、不便は通称使用拡大で「ほとんど解消される」としている。 |
| 職業上の旧姓使用では社会的な不便(例:銀行口座、不動産登記、海外での通用度)が残る。 | 子どもの姓をどうするか、という問題が複雑になる。 | 姓を選ぶ自由の否定は多様な価値観の抑圧に通じる(コラム筆者の批判)。 |
「通称使用拡大」で不便は解消されるのか?
高市氏が主張する「通称(旧姓)使用拡大」は、姓を変更した人の負担を軽減する一つの手段です。しかし、これが本当に「姓を選ぶ自由の否定」を解消するのかについては、疑問が残ります。
通称使用の限界と「選択の自由」
| 通称使用が有効な場面 | 通称使用では対応が難しい・不十分な場面 |
| 名刺やメール、一部の公的書類(住民票など)での旧姓併記。 | 法律上の名前(本名)が必要な場面(例:不動産登記、銀行の正式な口座名義)。 |
| 旧姓で培ってきたキャリアや実績を維持したい場合。 | 海外でのパスポートや公的書類など、通称使用が認められない場合。 |
| **「姓はアイデンティティー」という価値観を持つ人にとって、「選べない」**ことによる精神的な負担。 |
重要なのは、「選択の自由」です。姓を変えることに抵抗がない人は同姓を選べばよく、姓を変えたくない人は別姓を選べばよいのです。「自分は平気だから」「通称で済むから」という理由で、他者の「選ぶ自由」を奪うことは、多様な価値観を抑圧することにつながります。
リーダーに求められる「懐の深さ」
コラムがリーダーに求めるのは、「自分は平気」で済ませず懐深く社会に相対することです。
真のリーダーシップとは、「自分の成功体験」や「自分の価値観」を基準に政策を決めることではありません。自分とは異なる立場、異なる生き方をしている人々の声なき声に耳を傾け、最も弱い立場の人々が抱える困難を解消できる制度設計を目指す姿勢こそが、私たちが必要としているリーダーの姿です。
まとめ:私たち一人ひとりが目指すべき「多様な社会」

今回のコラムは、政治家の発言をきっかけに、私たち自身の「働き方」「生き方」「家族のあり方」といった多様な価値観について深く考える機会を与えてくれました。
「ワークライフバランスを捨てる」ことや「男社会に適応した成功」だけが、素晴らしい生き方ではありません。
私たちが目指すべき社会は、誰もが自分らしく、無理なく、大切にしたいものを大切にしながら生きられる社会です。リーダーの「覚悟」や「強さ」を求めるだけでなく、社会の仕組みや制度を、多様な人々を受け入れる「懐の深いもの」に変えていくことが、私たち一人ひとりの課題です。