「静かな退職(Quiet Quitting)」という言葉を、最近よく耳にするようになりました。
これは、実際に会社を辞めることではなく、「残業をせず、最低限の仕事をきちんとこなす」という働き方のこと。
アメリカの若者たちがSNSで発信したことをきっかけに、世界中で共感が広がりました。
■ なぜ「静かな退職」が注目されているのか

発端は、米国の20代女性が投稿した「9時から5時の仕事に耐えられない」という動画でした。
帰宅するころには疲れ果て、料理も読書もする気力が残らない――そんな嘆きに、多くの人が共感。
「人生を仕事に奪われたくない」という声が広がりました。
ニューヨーク大学のスコット・ギャロウェイ教授も、TEDトークで「若者は貧しくなった」と指摘。
企業の利益は拡大しても給与は伸びず、住宅価格は高騰。努力しても報われにくい社会では、「働きすぎない勇気」が新しい価値観として浮上したのです。
■ 日本でも広がる「仕事中心の人生」への違和感
日本でも、三宅香帆さんの著書『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』がベストセラーになりました。
「本を読む時間さえ取れないほど働いて、これでいいのか」と疑問を感じる人が増えているのです。
アーティストのスプツニ子!さんは、自身のコラムでこう語っています。
「長時間働かないと良質な仕事ができないという考えは、もう変えた方がいい」
イギリスのデザイン会社で働いていた頃、午後5時には役職者も帰宅していたそうです。
時間よりも成果を評価する文化が根づいており、「自分の生活を犠牲にしない働き方」が当たり前だったのです。
■ 「静かな退職」は、甘えではない
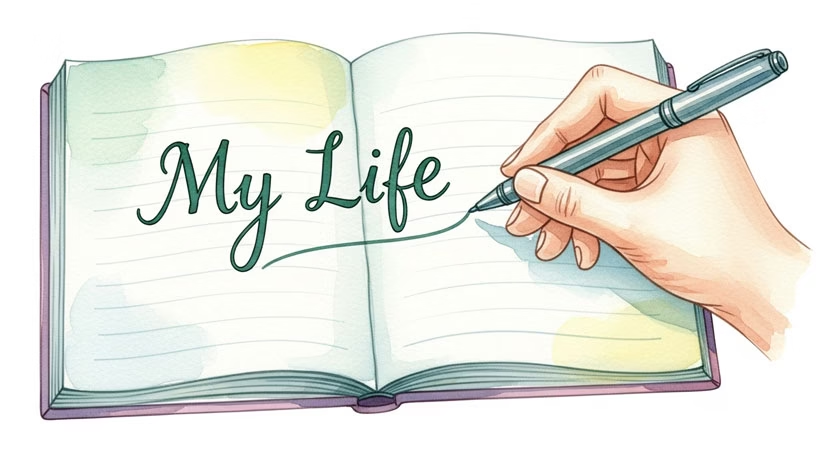
日本の広告やデザイン業界には、今も「ハッスルカルチャー(頑張り続ける文化)」が残っています。
育児などで一時的に仕事を離れると不利になりやすく、才能ある人ほど疲弊していく現実。
スプツニ子!さんは、
「静かな退職は甘えではない。人生を労働に搾取されないための、新しい価値観の見直し」
と述べています。
つまり「静かな退職」は、人生を取り戻すための小さな反逆でもあるのです。
■ がんばりすぎない勇気を持つ

かつては「長時間働く=立派な社会人」という価値観がありました。
しかし今、多くの人が気づき始めています。
本当に大切なのは、仕事だけでなく“自分の人生そのもの”だということに。
静かに退職するとは、
「自分の幸せを中心に置き、他人の期待ではなく自分の基準で生きる」ということ。
仕事にすべてを捧げるのではなく、余白を持つ。
その静かな選択こそが、これからの時代をしなやかに生き抜く力になるのかもしれません。
🌿まとめ
「静かな退職」は怠けでも逃げでもありません。
それは、自分の時間を取り戻し、心の健康を守る“新しい働き方”です。
「ほどよく働き、よく生きる」——そんな価値観が広がっていくことで、
多様な生き方が尊重される社会に、一歩近づいていくのではないでしょうか。






