2025年10月31日(金)朝刊春秋の要約とクマの現状
例年にも増して、クマの出没に関するニュースが全国を駆け巡っていますね。私たちの生活圏に近い場所で目撃情報が相次ぎ、犠牲者の数も過去最悪を更新するなど、もはや山間部に限った話ではなくなってしまいました。「遠い存在」だったはずのクマが、なぜこんなにも身近になってしまったのでしょうか。
私たちが「安心」して暮らすために必要なのは、ただ不安を煽ることではなく、クマの生態を正しく理解し、彼らの存在を尊重しながら、どう境界線を引いていくか、その知恵を持つことです。本日の日本経済新聞朝刊「春秋」コラムも、九州での経験を交えながら、この現代的なテーマを深く掘り下げています。
- コラム引用(最初の2段落):1カ月ほど前、九州を旅した。福岡から阿蘇、霧島と回って薩摩半島へ。東京から訪れたと話すと、先々で言われた。「こっちはクマがいなくて安心でしょう」。よく知られているが、九州にクマは生息していないとされる。環境省が2012年に「絶滅」を宣言した。
- ▼すでに連日のように出没や人身被害が全国ニュースで報じられていたから、関門海峡の向こうはただならぬ状況だと思われたのかもしれない。それも当然か。先日出張した長野県のある街では、駅の近くにまでツキノワグマが現れたそうだ。タクシーの運転手が「夜に繁華街を歩く人がだいぶ減りました」とこぼしていた。(有料版日経新聞より引用)
🚨 クマの出没、これは他人事じゃない!~もしもの時のための緊急対策
最近の出没報道を見ていると、私たちの不安は募るばかりですよね。特に、お子さんやペットを連れての散歩、あるいは夜道を一人で歩くときなど、女性としては特に気を張ってしまいます。でも、過度に怖がりすぎる必要はありません。
まずは、私たちの日常の中でできる具体的で実践的な安全対策から確認していきましょう。これは、クマに遭わないための「見えない防犯」として、とても大切ですよ。
街中でツキノワグマに遭わないための「見えない防犯」
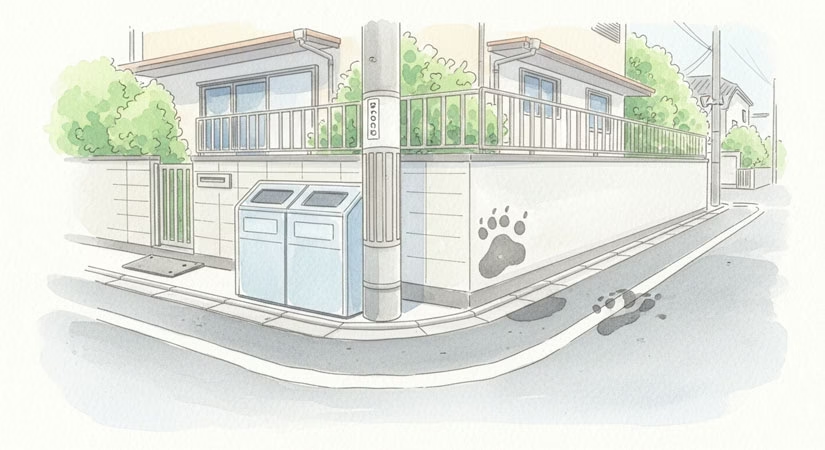
クマを人里に引き寄せてしまう原因の多くは、実は私たち人間側にあるんです。クマにとって「ここは食べ物が手に入りやすい場所だ」と学習させない工夫が、何よりも重要になります。
生活圏での三大対策:食べ物・臭い・音の管理
クマは嗅覚が非常に優れていて、犬の7倍とも言われています。この優れた鼻で、私たちの生活圏にある「ごちそう」を見つけてしまうんですね。
| 対策項目 | 具体的なアクション | 予防効果のポイント |
| 食べ物を放置しない | 生ゴミは密閉容器に入れ、当日早朝に出す。ペットフードの食べ残しを外に置かない。 | クマを誘引する最高のサインである臭いを断つ。 |
| 庭や畑の管理 | 収穫しないまま放置された果実や作物は速やかに撤去する。 | クマに立ち寄る**理由(餌)**を与えない。クマは楽な獲物を探すためです。 |
| 音と光で予防 | 早朝・夕方の外出時は、ラジオや鈴、ライトの利用で人間の存在を知らせる。 | クマに「人間がいる」と事前に認識させ、遭遇を避けてもらう。 |
よく、「クマ鈴を鳴らしていれば安心ですか?」という質問を聞きますが、実は、鈴の音に慣れてしまったクマもいるため、鈴だけで100%安全とは言えません。鈴に加えて、ラジオの音や、複数人でのおしゃべりなど、不規則な人間の音を出すことがより効果的だと言われています。
特に気を付けたい時間帯と場所
クマは夜行性と思われがちですが、実は私たち人間を避けるために、活動が活発な時間帯や、人間の目の届きにくい場所を選んで行動しています。
| 注意が必要な時間帯 | 具体的な外出時の注意点 |
| 早朝(明け方) | 人間の活動が少ないため、警戒心が薄れやすい。明るくなるまでは外出を控えましょう。 |
| 夕方~夜 | クマが冬眠前の栄養補給に活発になる時間帯。帰宅が遅くなる場合は、必ず二人以上で歩くなどの工夫を。 |
| 特に注意が必要な場所 | なぜ危険性が高い? |
| 山際・河川敷 | クマの通り道(獣道)になっている可能性が高く、遮蔽物も多い。 |
| 耕作放棄地 | 放置された作物がクマの食料源となり、隠れ場所にもなりやすい。 |
👜 女性が持ち歩くべき「クマ避けグッズ」とその使い方

万が一に備えて、持ち歩くべきアイテムとその正しい知識も確認しておきましょう。これは、自分と大切な人を守るための「お守り」のようなものです。
基本の三種の神器と専門家の視点
| アイテム名 | 役割と使い方 | 専門家からのアドバイス |
| クマ鈴 | 自分の存在を知らせる。バッグの外側に付け、確実に音を出す。 | 鈴だけに頼らず、複数の音(話し声やラジオ)を出すとより効果的。 |
| 強力なLEDライト | 暗い場所の視界確保と、遭遇時の目くらまし。 | 遠くから照らすのではなく、遭遇時にクマの顔に向けて使うと威嚇になる。 |
| クマ撃退スプレー | 最終手段として、クマの攻撃から身を守る。 | 使用時は風上から噴射し、必ず顔や目、鼻など粘膜部分を狙うこと。使用には事前講習を推奨。 |
「クマ撃退スプレーって、本当に効くの?」と不安に思う方もいるかもしれませんね。アメリカなどクマ対策が進んでいる地域でのデータを見ると、スプレーは正しく使用した場合、銃器よりも遭遇時の生存率が高いという報告もあります。ただし、非常に強力なため、購入したら必ず模擬訓練キットなどで使い方を練習しておくことが大切です。間違って自分にかかってしまったら、その時点で無防備になってしまうからです。
🌲 なぜ今、クマの出没が増えているの?~生態と環境の変化
全国的に出没が増えている現状を見て、「なぜ?」という疑問が湧いてきますよね。これは、クマの生態を知るとともに、私たち人間社会の変化を考えるきっかけにもなります。
ツキノワグマってどんな動物?その基本的な生態
ツキノワグマ(月輪熊)は、胸の白いV字型の模様が特徴的です。彼らの習性を知れば、「なぜ人里に降りてくるのか」という理由がより明確に見えてきますよ。
ツキノワグマのプロフィール
| 特徴 | 詳細(平易な言葉で) | 補足説明 |
| 食性 | 雑食ですが、メインはドングリや木の実、山菜などの植物質。約9割が植物質です。 | 肉食動物ではありません。人里の食べ物は「楽な食べ物」として学習してしまいます。 |
| 行動 | 基本的に臆病で、人目を避けて単独で暮らしています。 | 子グマを連れた母グマは警戒心が強く、特に危険なので、静かに離れることが重要です。 |
| 生息域 | 奥山のブナ林やミズナラ林など。 | 私たちの生活圏と山林の境界(里山)まで降りてくることが多くなっています。 |
冬眠前の「秋の準備期間」にご注意を
特に注意が必要なのは、秋、つまり「ハイパーフェイジア(異常な食欲)」の時期です。クマは冬眠に備えて体脂肪を蓄えるため、通常よりもはるかに大量の食べ物を必要とします。
もし、山でドングリやブナの実が不作(凶作)になると、クマは深刻な食料不足に陥ります。
「冬眠までに必要な栄養の確保」という切実な理由から、危険を冒してでも人里に降りてきてしまうのです。
この時期のクマは、普段よりも必死で食べ物を探しているため、遭遇リスクが最も高まります。
人里への出没が増えた「本当の理由」
クマの出没が増加している背景には、単に「クマが増えた」だけではない、より根深い問題があります。
自然環境の変化と人間活動の影響
| 増加要因 | 人間の活動との関係 | 対策の方向性 |
| 食料の凶作 | 気候変動やブナ林の衰退など、人間が直接的・間接的に環境に影響を与えている。 | 山林の植生を豊かにする活動が長期的には必要。 |
| 人間の領域拡大 | 道路開発、宅地造成、ゴルフ場建設などで、クマの住処を分断・縮小した。 | 人間活動エリアとクマの生息エリアを明確に分ける(ゾーニング)。 |
| 里山の荒廃 | 農業人口の減少で里山が手入れされず、藪が増えてクマの隠れ場所になっている。 | 適切な里山管理(下草刈りなど)で、クマが近づきにくい環境を作る。 |
「人間の優しさ」がクマを人馴れさせる危険性
クマが人里に出てくる最大の問題は、一度「人間の食べ物はおいしくて楽に手に入る」と学習してしまうことです。これを「人馴れ(じんあれ)」と言います。
- 簡単な食料源の例:
- 放置された家庭菜園の野菜や果物。
- 無人の畑に残ったままのトウモロコシなど。
- アウトドアでの食べ残しや、キャンプ場での食料管理の不備。
人馴れしたクマは、警戒心が非常に薄くなり、昼間でも堂々と人前に現れるようになります。この状態になったクマは、もはや自然のクマではなく、人間の社会にとって最も危険な「問題個体」となってしまうのです。コラムでも触れられているように、危険な個体を駆除するだけでなく、「人の営みに近づけない対策」こそが、根本的な解決につながるのです。
🏔️ もし遭遇してしまったら!~命を守るための正しい対処法
ニュースで遭遇の報道を見るたびに、「もし自分だったらどうしよう」とドキッとしますよね。でも、パニックになってしまうと、かえって危険な行動をとってしまいがちです。ここでは、冷静に行動するためのマニュアルをご紹介します。
🚶 クマとの距離が離れている場合の対処法
クマが私たちに気づいていない、または遠くにいる場合は、刺激せずに静かに立ち去るのが鉄則です。
- まずは静かに立ち去る:クマに背を向けず、クマから目を離さずに、ゆっくりと後ずさりしてその場を離れましょう。
- ポイント:絶対に走らないでください。走るとクマの「追いかける本能」を刺激してしまいます。
- 大声はNG、静かに話しかける:クマに人間の存在を認識させることは大切ですが、威嚇するような大声はかえって危険です。
- 「人だよ」「ごめんね」といった低い声で、優しく話しかけることで、相手を刺激せずに認識させましょう。
😨 近くで遭遇してしまった場合の「やってはいけないこと」
もし、クマとの距離が非常に近く、クマが私たちに気づいている状態であれば、あなたの一挙手一投足がクマの行動を決めます。
| 間違った行動 | クマの反応 | 正しい行動のヒント |
| 急に動く、走って逃げる | 捕食対象と見なし、本能で追いかける。 | ゆっくりと動き、クマの動きを観察する。 |
| 大声で叫ぶ、威嚇する | 攻撃と捉え、身を守るために反撃してくる。 | 静かに話しかけ、目を合わせたまま冷静に後ずさりする。 |
| カメラを向ける | 威嚇行動(目を合わせる)と誤解される。 | 可能な限り目をそらさず、静かに距離をとる。 |
「死んだふりは効果があるのでしょうか?」という疑問をよく耳にします。しかし、多くの専門家は「死んだふりは推奨しない」と助言しています。死んだふりをしても、クマが興味本位で体に触れてきたり、嗅いだりすることで、かえって致命傷を負うリスクが高まります。
🐻 最終手段としての対処法:あなたの身を守るために
万が一、クマが私たちに向かってきたり、攻撃を仕掛けてきたりした場合は、命を守るための行動をとる必要があります。
- 体を大きく見せる:上着を広げたり、リュックを頭上高く持ち上げたりして、自分の体をできるだけ大きく見せましょう。クマは体の大きさを確認し、攻撃対象として見極めることがあります。
- 荷物を囮にする:食料品などが入ったリュックやバッグをそっと地面に置き、クマの関心をそらします。その隙に、自分はゆっくりと安全な場所へ移動しましょう。
- 防衛姿勢:もし攻撃を受けてしまったら、地面に伏せ、手で首や顔、頭など命にかかわる部分をしっかりと守り、体を丸くして動かないように耐えます。これを「防御姿勢」と呼びます。クマの攻撃は短時間で終わることが多いので、この姿勢で耐え抜くことが重要です。
🗾 九州にクマはいるの?~「絶滅宣言」の意味を考える
コラムの冒頭で触れられていた「九州にはクマがいない」という話。なんだか不思議に思いませんか?この事実の裏側には、私たち人間とクマとの長く複雑な歴史が隠されています。
九州にクマがいないのは本当?「絶滅」の歴史
環境省による「絶滅」宣言の意味
2012年、環境省は九州地方に生息していたニホンツキノワグマを「絶滅」と発表しました。これは、「九州にクマは一頭もいない」という意味ではなく、「過去数十年間にわたり確実な生息確認がなく、今後も定着する可能性は極めて低い」という科学的な判断に基づいています。
- 過去の生息状況:かつて九州にもクマは生息していましたが、明治以降、乱獲や森林伐採による生息地の破壊によって数を激減させました。
この「絶滅」宣言は、日本の豊かな自然の象徴であるクマが、人間活動の影響でその姿を消したという、非常に重い事実を私たちに突きつけているのです。
💡 「いない安心」と「種の存続」のジレンマ
私たちが「こっちはクマがいなくて安心でしょう」と言われたとき、安堵する一方で、心の中に引っかかるものがありますよね。コラムで引用されていた専門家の言葉は、まさに私たちの心の内を言い表しているように感じます。
「人間にとってヒグマは自然と結びついた崇高な存在であり『物理的には遠くにいてほしい反面、精神的には心の深くに入り込んでいる』(「ヒトとヒグマ」)」
クマは、単なる「危険な動物」ではなく、太古の昔から日本の自然の一部であり、神聖な存在として崇められてきた歴史もあります。
- 私たちの心の中のジレンマ
- 「いない安心」:日々の生活で不安を感じずに済むこと。
- 「いてほしい願い」:豊かな自然の象徴として、クマという種がこの大地に存在し続けてほしいという願い。
私たちは、この「心のジレンマ」をどう解決すれば良いのでしょうか。それは、クマを絶滅させることなく、彼らが奥山で豊かに暮らせる環境を守ること。そして、人間の生活圏との間に明確な「境界線」を引くことこそが、私たちが目指すべき真の共存の形だと感じます。
🤝 安心して暮らせる社会のために~私たちにできること
個人の対策だけでなく、地域社会全体でクマ対策に取り組むことが、私たち一人ひとりの安心にもつながります。

地域社会で取り組むべき対策
クマ対策は、個人が鈴を鳴らすだけでは解決しません。地域全体で「クマを寄せ付けない環境づくり」を進めることが、非常に重要です。
| 地域でできる対策 | なぜ有効? | 連携すべき主体 |
| 電気柵の設置推進 | クマが人里の味を覚えるのを物理的に防ぎ、侵入を諦めさせる。 | 自治体、農協、地域の住民団体。 |
| 出没情報の共有 | リアルタイムで正確な情報を地域内で共有し、警戒態勢を敷く。 | 警察、役場、学校、地域の防犯パトロール。 |
| 放置果樹の計画的な伐採 | クマの餌となる要因を、地域ぐるみで組織的に排除する。 | 自治体、地権者。 |
特に、電気柵の費用負担については、「個人で全ては難しい」という声が多いのが現状です。自治体や国による補助金を積極的に活用し、地域全体で費用を分担し合う仕組みが必要です。
「クマ活」で奥山を守る
クマが安心して暮らせる奥山が荒れてしまうと、彼らは必ず人里へ降りてきます。つまり、奥山を守ることが、私たち自身の安全を守ることにもつながるのです。
- 奥山への配慮:登山やキャンプなど、奥山に入る際は、ゴミを絶対に持ち帰りましょう。
- 里山整備への関心:農業人口の減少で荒れてしまった里山(山と人里の緩衝地帯)を、ボランティアなどで整備する活動に関心を持つことも、間接的な「クマ対策」になります。
コラムが指摘するように、「危険な個体を駆除するだけでなく、人の営みに近づけない対策に本腰を入れねば」なりません。クマが安心して「奥山におかえり」と言える環境を、私たち人間の手で整えることが、何よりも大切なのですね。
結び

今回の記事では、クマの出没問題について、私たちの身の回りの安全対策から、九州の「絶滅」宣言が問いかける自然との関係まで、幅広く見てきました。
クマの出没は、私たちに「自然との距離」を改めて考えさせてくれる機会なのかもしれません。怖がるだけでなく、彼らの生態を理解し、お互いを尊重することが、自分自身の安全を守り、私たちが願う「安心」につながっていくのではないでしょうか。
私たち一人ひとりの小さな注意と、地域社会全体の協力で、クマも人間も安心して暮らせる未来を築いていきたいですね。







