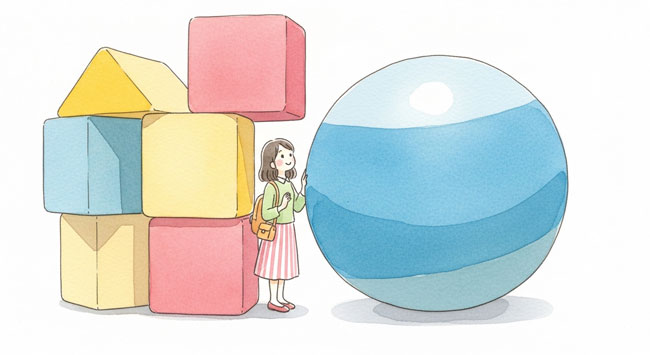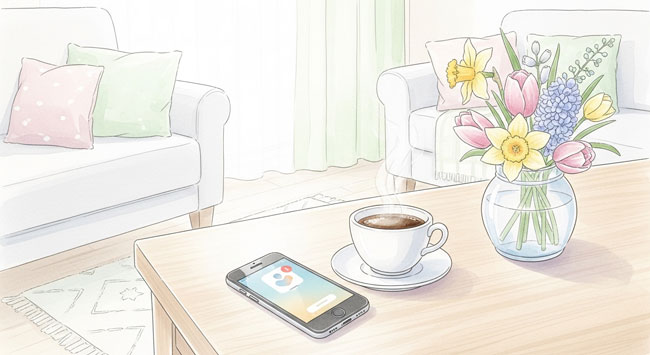日本経済新聞 2025年8月21日(木)朝刊春秋の要約と「判官びいき」の深層心理
こんにちは。毎日、たくさんの情報に触れていると、心が動かされるニュースに出会うことがありますよね。スポーツでの大逆転劇や、苦境に立たされている人の頑張る姿に、思わず「頑張れ!」と声を送りたくなった経験、あなたにもありませんか?
2025年8月21日の日本経済新聞の朝刊コラム「春秋」では、まさにそんな私たちの心に寄り添う「判官(ほうがん)びいき」というテーマが取り上げられていました。この記事をきっかけに、私たちがなぜ弱い立場にある人やチームを応援したくなるのか、その不思議な心理の奥深くを探ってみませんか?
この記事では、まず日経新聞のコラムをご紹介し、そこから「判官びいき」という言葉の本当の意味、私たちの心に隠された心理、そしてスポーツや政治の世界で実際に起きている「判官びいき」の具体例まで、わかりやすく、そして楽しく解き明かしていきます。
きっと、この記事を読み終わるころには、ニュースの見方が少し変わったり、誰かを応援する自分の気持ちがもっと愛おしく感じられたりするはずですよ。
今朝のコラム:甲子園と永田町に吹く「判官びいき」の風
まずは、議論のきっかけとなった日本経済新聞のコラム「春秋」の内容に触れてみましょう。
甲子園に棲(す)む魔物は判官(ほうがん)びいきだ。それに愛されるチームが時折、現れるのも高校野球の醍醐味だろう。全国制覇4度の古豪には失礼だが、県岐阜商は公立校で久しぶりの4強、ハンディキャップのある横山温大選手の活躍と高校野球ファンをくすぐる話題にあふれる。
▼判官びいきの関西だからこそ、球場は独特の雰囲気に包まれ、ドラマを生むともいわれる。上方の歌舞伎や浄瑠璃で義経の判官物が人気を博した昔から、政治をつかさどる中央への反骨は筋金入り。大国が共謀して、弱いものが割を食う姿をみせつけられ、弱肉強食がまかり通る世界への憂いも映しているのかもしれない。
(中略)
(有料版日経新聞より引用)
このコラムは、夏の甲子園で快進撃を続ける県岐阜商を例に、日本人に根強く存在する「判官びいき」の感情を浮き彫りにしています。そして、その感情が野球場だけでなく、関西という土地の文化、さらには「石破首相」に向けられる国民の視線といった政治の世界にまで通底していると指摘しています。
この記事では、このコラムを道しるべに、「判官びいき」という、私たちの心を時に熱くさせ、時に社会を動かす不思議な力について、一緒に考えていきたいと思います。
「判官びいき」って、そもそも何?言葉の奥にある悲しい物語
「判官びいき」という言葉、なんとなく「弱い方を応援すること」というイメージがありますよね。その理解で、もちろん間違いではありません。でも、この言葉がどうして生まれたのかを知ると、もっと深い意味が見えてくるんですよ。
言葉の由来は、悲劇のヒーロー・源義経
この言葉のルーツは、なんと平安時代末期までさかのぼります。
「判官」というのは、当時の役職の一つ。そして、この「判官」と呼ばれていた人物こそが、歴史上の超有名人、源義経(みなもとのよしつね)なんです。
義経は、兄である源頼朝(よりとも)とともに平家を滅ぼす大活躍をしました。特に、崖の上から馬で駆け下りて敵を急襲した「鵯越(ひよどりごえ)の逆落とし」などの奇想天外な作戦で、次々と勝利を収めた天才的な武将として知られています。
しかし、そのあまりの強さと人気が、かえって兄・頼朝の嫉妬と疑いを招いてしまいます。義経は英雄から一転、謀反の疑いをかけられ、追われる身となってしまうのです。
全国を逃げ回った末、最後は現在の岩手県で、わずかな家来とともに追い詰められ、31歳という若さで自害に追い込まれました。
この義経の劇的な生涯、特に英雄でありながら不遇の死を遂げた悲劇的な結末に、当時の人々は深く同情しました。
「あんなに頑張ったのに、あんまりだ」
「頼朝はひどいじゃないか」
そんな、弱い立場に置かれた義経に同情し、彼を応援したいという気持ち。これが「判官(義経)を贔屓(ひいき)する」=「判官びいき」の始まりだと言われています。
つまり、「判官びいき」の根っこには、単に弱いから応援するという気持ちだけでなく、理不尽な運命や権力によって不当な扱いを受けている人への同情と共感が込められているんですね。
「同情」や「応援」とは、ちょっと違うニュアンス
ここで少し、似た言葉との違いを整理してみましょう。
| 言葉 | 意味合い |
| 判官びいき | 弱い立場や不遇な状況にある人に対し、理由を問わずに同情し、肩入れすること。少し非論理的な感情も含む。 |
| 同情 | 他人の苦しみや悲しみを、自分も同じように感じて気の毒に思うこと。 |
| 共感 | 他人の考えや感情を、その通りだと感じること。自分も同じ気持ちになること。 |
| 応援 | がんばれ、と励まし、力を貸すこと。勝敗や優劣に関わらず行われることもある。 |
「同情」や「共感」が気持ちの共有であるのに対し、「判官びいき」は、そこから一歩進んで「味方になってあげたい」「肩入れしたい」という、具体的な行動につながりやすい感情と言えるかもしれません。
また、時には「本当はあっちが正しいのかもしれないけど、でも可哀想だからこっちの味方をする」といった、少し不合理な気持ちが含まれるのも「判官びいき」の特徴なんです。
私たちの心に潜む「判官びいき」の正体~心理学から見てみよう~
では、私たちはどうして「判官びいき」をしてしまうのでしょうか。実はこの感情、心理学の世界でもちゃんと名前がついているんですよ。ここでは、私たちの心に潜む「判官びいき」のメカニズムを、4つのポイントから見ていきましょう。
1. アンダードッグ効果(負け犬効果)
なんだかちょっと可哀想な名前ですが、これはれっきとした心理学用語。「アンダードッグ(underdog)」とは、競争などで勝ち目が薄い、不利な立場にある人やチームのことを指します。
アンダードッグ効果とは、こうした不利な状況にある側を、人々が応援したくなる心理現象のことです。
選挙のニュースで、「〇〇候補、苦戦!」と報道されると、かえって同情票が集まって逆転することがありますよね。あれも、アンダードッグ効果の一種です。
人は、一方的な試合や競争をあまり好みません。「どうせ強い方が勝つんでしょ」と分かっていると、なんだか退屈に感じてしまいます。そこに、弱いと思われていた側が立ち向かっていく姿を見ると、「もしかしたら」「ひっくり返してほしい」という期待感が生まれ、思わず応援したくなってしまうのです。
2. 「もし私が…」と自分を重ねる自己投影
ドラマや映画の主人公に、自分の気持ちを重ねて見てしまうこと、ありますよね。それと同じで、私たちは困難な状況で頑張っている人を見ると、無意識のうちに自分を投影してしまうことがあります。
- 「もし私が、あんな大きな相手と戦わなければならなくなったら…」
- 「もし私が、みんなから反対される中で、たった一人で頑張っていたら…」
そんな風に想像すると、その人の不安や心細さが自分のことのように感じられ、「助けてあげたい」「応援しなきゃ」という気持ちが芽生えるのです。
特に、自分自身が過去に悔しい思いをしたり、逆境に立たされたりした経験があると、同じような境遇の人に強く感情移入しやすくなります。
3. ハラハラドキドキ!ドラマチックな物語への期待
私たちの心は、実はドラマチックな物語が大好き。平坦なストーリーよりも、紆余曲折あって、最後に大逆転するような物語に強く惹かれます。
「絶対王者」と言われるチームに、無名のチームが挑む。誰もが王者の勝利を疑わない中、挑戦者が奇跡的な頑張りを見せて、あと一歩まで追い詰める…。
想像しただけで、ワクワクしてきませんか?
「判官びいき」は、こうした「ジャイアントキリング(大番狂わせ)」という、最高のドラマを期待する心が生み出しているとも言えます。弱い方が強い方に勝つという展開は、予定調和を壊す爽快感があり、私たちにカタルシス(心の浄化)を与えてくれるのです。
4. 「ずるい!」が許せない、正義感と公平性
人は誰でも、心の中に「公平でありたい」「正義を重んじたい」という気持ちを持っています。そのため、あまりにも力の差がある競争や、強者が横暴に振る舞う姿を見ると、「それはフェアじゃない」「ずるい」という反発心が生まれます。
例えば、お金持ちの強豪私立高校と、グラウンドも十分にない公立高校が対戦する。審判の判定が、なんだか強豪校に有利な気がする…。
そんな時、私たちは「弱い方が不利益を被っている」と感じ、バランスを取るために弱い方を応援したくなるのです。これは、社会の不公平を正したいという、私たちの無意識の正義感が働いている証拠なのかもしれませんね。
【スポーツ編】甲子園に棲む魔物は「判官びいき」がお好き?
さて、心のメカニズムがわかったところで、日経のコラムにあったように、スポーツの世界、特に高校野球に目を向けてみましょう。甲子園は、まさに「判官びいき」という名のドラマが生まれる聖地です。

県岐阜商と横山選手がくすぐる私たちの心
コラムで取り上げられていた、県岐阜商。
「全国制覇4度の古豪」でありながら、最近は少し低迷していました。そんなチームが「公立校で久しぶりの4強」という快進撃を見せる。これだけでも、高校野球ファンの心はくすぐられます。
そこへ、「ハンディキャップのある横山温大選手の活躍」という要素が加わります。
(※この記事はコラムに基づいた内容であり、特定の選手を指すものではありません)
一般的に、ハンディキャップを乗り越えてひたむきに努力する選手の姿は、私たちの胸を強く打ちます。それは、私たちが彼の努力を想像し、その精神力に心からの敬意を抱くからです。
- 公立校であること: 恵まれた環境の私立校に、限られた条件で立ち向かう姿。
- 久しぶりの上位進出であること: 「古豪復活」という物語性。
- ハンディキャップを乗り越えた選手の活躍: 純粋な尊敬と応援の気持ち。
これらの要素が重なり合うことで、県岐阜商は多くの人々の「判官びいき」を一身に集める存在となったのでしょう。
記憶に残る、甲子園の「判官びいき」ヒーローたち
甲子園の歴史を振り返ると、数々の「判官びいき」が熱狂を生み出してきました。
2018年夏:金足農業(秋田)
記憶に新しいのが、秋田県代表の金足農業高校ではないでしょうか。
県立の農業高校で、選手は全員地元出身。派手さはありませんが、エースの吉田輝星投手の気迫あふれるピッチングと、チーム一丸となった粘り強い野球で、横浜、近江、日大三といった全国の強豪私立を次々と撃破。
その快進撃は「金農(かなのう)旋風」と呼ばれ、日本中が熱狂の渦に巻き込まれました。決勝では大阪桐蔭に敗れましたが、その戦いぶりは、多くの人の心に深く刻まれています。
2006年夏:早稲田実業 vs 駒大苫小牧
これは少し毛色が違うかもしれませんが、早稲田実業のエース・斎藤佑樹投手が巻き起こした「ハンカチ王子」フィーバーも、一種の判官びいきが影響していたかもしれません。
対する駒大苫小牧は、田中将大投手を擁し、夏の甲子園3連覇を目指す絶対王者。下馬評では駒大苫小牧が有利と見られていました。
そんな中、斎藤投手は青いハンカチで汗を拭う爽やかな姿と、強敵に臆することなく立ち向かうクレバーな投球で、女性ファンを中心に爆発的な人気を獲得しました。決勝戦、そして再試合と、2日間にわたる死闘の末に早稲田実業が優勝。多くの人が、王者に挑むプリンスの物語に夢中になりました。
甲子園だけじゃない!スポーツと「判官びいき」
この感情は、もちろん高校野球に限りません。
- サッカーの天皇杯: プロのJ1チームに、アマチュアの大学チームや社会人チームが挑む。格上のチームを破る「ジャイアントキリング」は、大会の醍醐味です。
- 大相撲: 体の小さな力士が、大きな力士を技で投げ飛ばす。舞の海や炎鵬といった小兵力士が見せる「業師(わざし)」ぶりは、多くのファンを魅了します。
- ボクシング: 無敗のチャンピオンに、無名のボクサーが挑む。映画『ロッキー』のように、ハングリー精神あふれる挑戦者の姿に、私たちは自分を重ねて応援してしまうのです。
スポーツは、筋書きのないドラマだからこそ、「判官びいき」というスパイスが加わることで、何倍も面白くなるのかもしれませんね。
【地域編】なぜ関西人は特に「判官びいき」なの?
日経のコラムでは、「判官びいきの関西だからこそ、球場は独特の雰囲気に包まれ、ドラマを生む」と指摘されていました。確かに、関西、特に大阪の人は「判官びいき」の気質が強い、とよく言われます。それは一体なぜなのでしょうか。
歴史が育んだ「中央への反骨精神」
コラムにも「政治をつかさどる中央への反骨は筋金入り」とあるように、この気質の背景には、日本の歴史が大きく関係しています。
かつて、日本の経済や文化の中心は、京都や大阪といった「上方(かみがた)」でした。しかし、江戸時代に政治の中心が江戸(現在の東京)に移ってからは、次第に東京が日本の中心となっていきました。
この歴史的な経緯から、関西には「東京(中央・権力)には負けへんぞ」という、ある種の対抗意識が根付いていると言われています。
そのため、権力者や絶対的な強者に対して、素直に従うのではなく、少し斜に構えて見てしまう傾向があるのです。そして、その権力に立ち向かう者や、不遇な立場にある者に、自分たちの気持ちを託して応援する。これが、関西の「判官びいき」の原点なのかもしれません。
コラムが指摘するように、義経の物語が上方で歌舞伎や浄瑠璃の人気演目となったのも、悲劇のヒーローである義経の姿に、権力に翻弄される人々の思いが重なったからなのでしょう。
お笑い文化と「いじられ役」への愛
関西、特に大阪といえば、お笑いの文化が生活に深く根付いていますよね。
テレビのお笑い番組を見ていても、完璧なエリートタイプよりも、少しドジだったり、失敗したりする「いじられ役」の芸人さんが、周りからツッコまれながらも、みんなに愛されている光景をよく目にします。
これは、完璧ではない、弱さや人間味のある存在を温かく受け入れ、笑いに変えるという文化の表れです。強くてカッコいいだけの存在よりも、どこか欠点があったり、不器用だったりする方が、親しみが湧き、応援したくなる。
この感覚も、弱い立場にある人やチームを放っておけない「判官びいき」の精神に通じているのかもしれませんね。阪神タイガースが、なかなか優勝できなくても、熱狂的なファンに支えられ続けるのも、この気質と無関係ではないでしょう。
【政治編】永田町にも吹く?「判官びいき」の風
スポーツや地域文化だけでなく、コラムは政治の世界にも「判官びいき」の視線を向けています。これは、私たち国民の政治に対する見方を考える上で、とても興味深いポイントです。
「石破おろし」が「イジメ」に見えるとき

コラムでは、「石破首相に向けられる世間の視線にも、何やら判官びいきが漂い始めた」と書かれています。
(※ここでの「石破首相」はコラム上の設定です)
「自民党内では石破おろしがやまず」「総裁選前倒しの議論も本格化」という状況、つまり、首相が身内であるはずの党内から、集中攻撃を受けている構図です。
これを国民の目線から見ると、どう映るでしょうか。
コラムが「石破おろしがイジメに映り、国民そっちのけの党内抗争にうんざりしている向きもあろう」と指摘している通り、政策論争ではなく、派閥の力学や人間関係のもつれによる「数の力」でリーダーを引きずりおろそうとする動きは、集団で一人を攻撃する「イジメ」のように見えてしまうことがあります。
国民が本当に知りたいのは、「私たちの生活を良くするために、どんな政策をしてくれるのか」ということ。それなのに、テレビで連日報じられるのが党内の権力争いばかりだと、「また仲間内でケンカしてる…」とうんざりしてしまいますよね。
そんな時、孤立しながらも自分の主張を貫こうとするリーダーの姿に、私たちは「判官びいき」の感情を抱き始めるのです。
「党内では人気がないみたいだけど、言っていることは正しいんじゃないか」
「みんなで寄ってたかって、なんだか可哀想だ」
その結果、コラムにあるように「内閣支持率は上向きで、辞めなくてもよいという声も」という、永田町の常識とは逆の現象が起こるのです。
権力闘争に浪花節(なにわぶし)は通じない?
ただし、コラムは釘を刺すことも忘れていません。
「もっとも、世間とかけ離れているのが永田町の常識。権力闘争に浪花節は通じまい」
「浪花節」とは、人情や義理を重んじる心情のこと。つまり、国民が「可哀想だから」「頑張っているから」という「判官びいき」で支持したとしても、それだけで政治の世界を勝ち抜いていけるほど甘くはない、という厳しい現実を指摘しています。
政治の世界は、最終的には政策の実現力や、党内をまとめ上げる調整力といった、シビアな「力」がものを言います。国民からの人気という「風」も大切ですが、それだけでは船を前に進めることはできないのです。
この「国民感情」と「永田町の論理」のギャップは、今も昔も変わらない、日本の政治が抱える大きなテーマの一つと言えるでしょう。
「判官びいき」を超えていく力とは
さて、ここまで「判官びいき」という感情について、様々な角度から見てきました。弱いものを応援する、この温かい感情は、私たちの社会にとって大切なものですよね。
でも、コラムは最後に、さらにその先にあるものを示唆して、私たちに問いを投げかけています。
きょう準決勝に臨む横山選手の打撃は、メジャーの吉田正尚さんに似て、シュアな左打者のお手本のように美しい。強い意志と血のにじむ鍛錬が忍(しの)ばれ、純粋に好打者のたたずまいがある。真に力を秘めた者は判官びいきを超えてゆこう。
この一文に、私はハッとさせられました。
私たちが横山選手に惹かれるのは、彼がハンディキャップを背負っているから「だけ」ではない、というのです。
「同情」から「尊敬」へ
コラムが描く横山選手の姿は、「かわいそうな選手」ではありません。
その打撃は、お手本のように美しく、見る者を魅了する。そのたたずまいからは、私たちが想像もできないような、血のにじむような努力の跡が感じられる。
つまり、彼は「判官びいき」の対象であると同時に、その圧倒的な実力と精神力によって、純粋な「称賛」や「尊敬」の対象にもなっているのです。
最初は「ハンディキャップがあるのにすごいな」という同情にも似た気持ちから応援し始めた人も、彼のプレーを見るうちに、そんなことは忘れてしまうでしょう。そして、ただ一人の素晴らしいアスリートとして、彼のバッティングに、その一挙手一投足に、心を奪われるのです。
これこそが、「判官びいきを超えてゆく」ということではないでしょうか。
私たちの「応援」のカタチ
このことは、私たち自身が誰かを応援するときの気持ちについても、大切なヒントを与えてくれます。
「弱いから」「可哀想だから」という気持ちだけで応援するのは、もしかしたら、少しだけ相手に対して失礼になってしまうこともあるのかもしれません。なぜなら、その視点は、相手を「自分より下の、助けが必要な存在」として見ていることになるからです。
本当に素敵な応援とは、「判官びいき」をきっかけとしながらも、その人の努力や実力、人間性をきちんと見て、心からのリスペクトを送ること。
- 「不利な状況なのに、よく頑張っているね」
- 「あなたのそのひたむきな姿に、勇気をもらっています」
- 「大変な中でも、こんなに素晴らしい結果を出すなんて、本当にすごい!」
そんな風に、相手が持つ「真の力」に気づき、それを称賛する。それができたとき、私たちの「応援」は、もっと豊かで、もっと温かいものになるはずです。
まとめ:あなたの心の中の「判官びいき」

今回は、日本経済新聞のコラムをきっかけに、「判官びいき」という感情の旅をしてきました。
| 判官びいきの側面 | 内容 |
| 言葉の由来 | 悲劇のヒーロー・源義経への同情から生まれた。 |
| 心理的な背景 | アンダードッグ効果、自己投影、物語への期待、正義感などが関係している。 |
| 現れる場面 | スポーツ(特に甲子園)、関西の地域文化、政治の世界など、社会の様々な場面で見られる。 |
| その先にあるもの | 同情だけでなく、努力や実力への「尊敬」に変わったとき、それは「判官びいき」を超える。 |
「判官びいき」は、弱い立場の人に寄り添う、人間の優しさの表れです。この感情があるからこそ、世の中は単なる弱肉強食の世界にならずに済んでいるのかもしれません。甲子園のドラマに涙し、苦境に立つ人を応援したくなる、そんな自分の心を、ぜひ大切にしてくださいね。
と同時に、コラムが教えてくれたように、その感情の先にある「真の力」を見つめる視点も持っていたいものです。
「なぜ、私はこの人(チーム)を応援したいんだろう?」
そう自分に問いかけたとき、「かわいそうだから」という答えの奥に、「その姿勢が美しいから」「その努力に感動したから」という、リスペクトに満ちた理由を見つけられたら、私たちの毎日は、もっと彩り豊かになるのではないでしょうか。
あなたの心の中の「判官びいき」は、次にどんな素敵なドラマを応援しますか?
<PR>「お疲れ様」「いつもありがとう」といったメッセージがパッケージに書かれたギフトは、言葉に出すのは照れくさい気持ちをさりげなく伝えてくれます。記事を読んで、身近にいる頑張っている人の顔が思い浮かんだなら、その方を応援する気持ちを形で贈ってみるのも素敵ですよね。ほっと一息つく時間に、あなたの温かい気持ちがきっと届くはずです。→ いつも応援してるよ」の一言を、ほっとする一杯に込めて。