2025年8月7日(木)日本経済新聞夕刊「明日への話題」の要約と、私たちが考えるべき「記憶の継承」
映画「オッペンハイマー」は、「原爆の父」の苦悩を通して、人類が手にしてしまった禁断の技術の恐ろしさを描いています。世界的に評価される一方、日本では「なぜ被爆者の苦しみが直接描かれていないのか」という声も上がりました。これに対しコラムの筆者は、映画があくまでオッペンハイマーの視点で描かれており、彼の内面的な葛藤は丁寧に表現されていると指摘。その上で、被爆体験の継承について、当事者ではない私たちが「体験を受け継ぐ」ことの難しさに触れ、個人の主観的な体験(一人称の語り)を、誰もが共有できる客観的で普遍的な物語(三人称の語り)に変換していくことが、体験の風化を防ぐために重要なのではないかと提案しています。
こんにちは。
日本経済新聞の夕刊コラムを読んで、深く考えさせられることがありました。それは、映画「オッペンheimer」をきっかけに、戦争や原爆といった「個人の強烈な体験」を、私たち後の世代がどう受け止め、未来に伝えていけばいいのか、というテーマです。
被爆者の方々の平均年齢は86歳を超え、2025年3月末にはその数がとうとう10万人を下回ったと報じられました。
「直接お話を聞ける機会が、もうほとんどなくなってしまう」
そんな焦りを感じている方も多いのではないでしょうか。
「体験を風化させてはいけない」
私たちはそう強く願う一方で、「その場にいなかった自分が、あの日の苦しみを本当に『受け継ぐ』ことなんてできるんだろうか…」と、途方もない気持ちになることもありますよね。
今日の記事では、このコラムの内容をヒントに、私たちに何ができるのかを一緒に考えてみたいと思います。大切な記憶を、一部の人たちだけのものではなく、世界中の人々と共有できる「みんなの物語」にしていくには、どうしたらいいのでしょうか。

映画「オッペンハイマー」が私たちに投げかけた問い
まずは、今回の議論のきっかけとなった映画「オッペンハイマー」について、少し整理してみましょう。
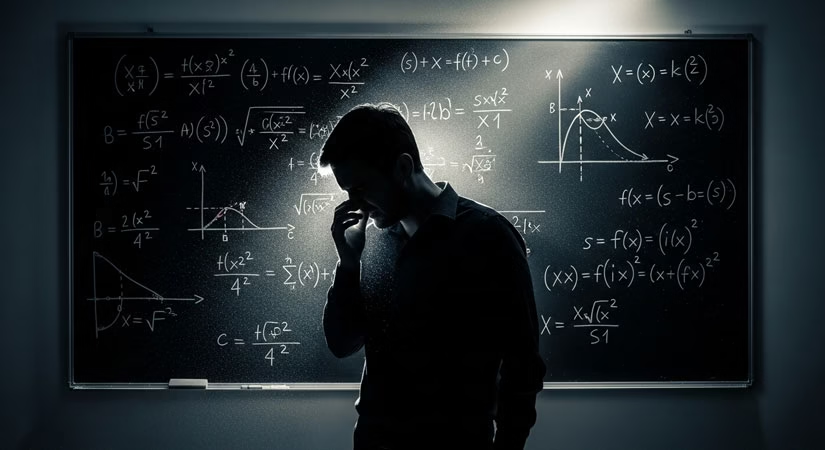
なぜ「原爆の父」の視点で描かれたの?
この映画は、原子爆弾を開発した物理学者、ロバート・オッペンハイマーの視点で物語が進みます。彼の知的な好奇心、国家プロジェクトを率いるプレッシャー、そして原爆がもたらした結果に対する後悔や苦悩が、3時間という上映時間の中で克明に描かれています。
監督のクリストファー・ノーランは、一貫してオッペンハイマーの「主観」にこだわりました。彼が何を見て、何を聞き、どう感じたのか。観客は彼の目を通して、歴史的な出来事を追体験することになります。だからこそ、彼が直接見ていない広島や長崎の惨状は、あえて直接的には描かれていないのです。
それは、歴史の事実から目を背けたのではなく、「一人の人間が、自らの創造物が世界をどう変えてしまったのかを、どう受け止めたか」という、極めて個人的な葛藤に焦点を当てた演出だったと言えるでしょう。
「被害者の姿がない」という批判について考える
一方で、特に日本では「なぜ、実際に苦しんだ日本の被爆者の姿が描かれていないのか」という批判や疑問の声が上がりました。これは、原爆の被害を直接経験した国として、当然の感情だと思います。
| 批判の背景にある気持ち | 映画の制作意図 |
| 原爆の非人道性を訴えるには、被害の悲惨さを直接見せることが不可欠だ。 | 原爆投下という「結果」ではなく、そこに至る「過程」と開発者の「内面」を描きたかった。 |
| 加害者の苦悩ばかりが描かれ、被害者の痛みが軽視されているように感じる。 | オッペンハイマーの主観に徹底的に寄り添うことで、彼の行動の是非を観客自身に問わせたかった。 |
| 日本人の犠牲が、物語の背景としてしか扱われていないのではないか。 | 彼が直接見聞きした範囲で世界を描くことで、彼の視点の「限界」をも示唆している。 |
この対立は、どちらが正しくてどちらが間違っている、という単純な話ではありません。
むしろ、この映画は、見る人の立場や経験によって、全く異なる受け止め方が生まれる「鏡」のような作品なのかもしれません。
そして、この「視点の違い」こそが、私たちが歴史を語り継ぐ際の難しさを象徴しているように思えてなりません。
「体験を受け継ぐ」って、本当にできること?
「被爆体験を継承する」
私たちはこの言葉をよく耳にしますが、その本当の意味を深く考えたことはあるでしょうか。

「直接聞く」ことの圧倒的な価値と、その限界
被爆者の方から直接、あの日の出来事を聞く。それは、どんな本や映像よりも強く心を揺さぶる、かけがえのない経験です。声の震え、表情、言葉にできない沈黙…その全てが、活字になった証言録とは全く違う重みで、私たちに迫ってきます。
しかし、時間というものは残酷です。
体験者の方々が高齢になり、語り部が減っていく中で、この「直接聞く」という貴重な機会は失われつつあります。これが「体験の風化」への危機感につながっているのです。
「受け継ぐ」という言葉の重みと難しさ
では、直接体験していない私たちが、その体験を「受け継ぐ」とはどういうことでしょう。
想像してみてください。
語り部の方が、家族を失った悲しみや、ご自身が受けた火傷の痛み、その後の差別や病気への不安を、言葉を振り絞るように話してくださったとします。
私たちは涙し、胸を痛め、「大変でしたね」「お辛かったでしょう」と心から思います。
でも、私たちは本当にその方の痛みを「わかった」のでしょうか。
「わかるよ」と安易に言うことは、かえってその方の孤独を深めてしまうかもしれない。そんな怖さを感じたことはありませんか?
「体験を受け継ぐ」という言葉には、どこか「同じ気持ちになる」というニュアンスが含まれている気がします。でも、それはとても難しい、もしかしたら不可能なことなのかもしれません。だからこそ、私たちは別の方法を探る必要があるのではないでしょうか。
大切な記憶を「みんなの物語」に変える方法
ここで、冒頭のコラムが提案する「普遍化」という考え方が、大きなヒントになります。
「普遍化」なんて言うと少し難しく聞こえるかもしれませんが、要は「個人の体験」を「みんなに関係のある話」として捉え直してみよう、ということです。
「私の物語」から「みんなの物語」へ

コラムでは「一人称」と「三人称」という言葉が使われていました。少し分かりやすく言い換えてみましょう。
- 一人称の語り(私の物語)
- 「私はあの日、こんなに辛い思いをしました」という、主観的で感情に強く訴えかける語り口です。
- 特徴:非常に強い共感を呼びますが、あまりに個人的な体験は、時に「自分とは違う世界の話だ」と他者を遠ざけてしまう可能性もあります。
- 三人称の語り(みんなの物語)
- 「あの日、街では多くの人々が、このような悲劇に見舞われました」という、少し引いた視点からの客観的な語り口です。
- 特徴:事実や状況を伝えることで、より多くの人が「なぜそんなことが起きたのだろう」「もし自分の街だったら」と、自分事として考えるきっかけを与えます。
これは、どちらが良い悪いという話ではありません。
例えば、世界中で読まれている『アンネの日記』。これはアンネという一人の少女の「私の物語」ですが、同時に、戦争という極限状況に置かれた人間の希望や絶望を描いた「みんなの物語」でもありますよね。
個人の切実な体験談という「一人称の物語」を入り口にしながら、それを歴史的な事実やデータといった「三人称の視点」で補強し、誰もがアクセスできる形に整えていく。この両方の視点を行き来することが、「普遍化」の鍵なのかもしれません。
なぜ「普遍化」が必要なの?
もし、私たちが「原爆の悲劇」を「日本人だけの特別な悲劇」として語り続けてしまったら、どうなるでしょう。
もちろん、世界で唯一の被爆国としての経験は、絶対に忘れてはならない事実です。
しかし、その特殊性だけを強調しすぎると、海外の人々からは「それはあなたたちの国の話ですよね」と、心のシャッターを下ろされてしまうかもしれません。共感を呼ぶ一方で、「でも、戦争を始めたのは…」といった反発を招き、対話がそこで終わってしまう危険性もあります。
それでは、本当に伝えたいはずの「核兵器の非人道性」や「平和の尊さ」が、当事者以外には共有されなくなってしまいます。それこそが、本当の意味での「風化」ではないでしょうか。
大切なのは、共感だけでなく「理解」を広げること。
反発を乗り越え、対話のテーブルにつくこと。
そのために、私たちの体験を、人類全体の歴史の中に位置づけ、「これは、あなたにも起こり得た、私たちの物語なのです」と語りかける視点が必要なのです。
歴史から学び、未来につなげるために私たちができること

では、具体的に私たちは何をすればいいのでしょうか。
大それたことをする必要はありません。日々の暮らしの中でできる、小さな一歩から始めてみませんか。
多様な「三人称の物語」に触れてみよう
被爆者の方の体験談(一人称)に心を寄せると同時に、少し視野を広げてみましょう。
- いろいろな本や映画を見てみる
- 今回の「オッペンハイマー」のように、加害者側の視点で描かれた作品。
- 原爆投下に至るまでの国際情勢を解説した歴史書。
- 科学技術と倫理の問題をテーマにしたドキュメンタリー。
- 資料館や平和公園を訪れてみる
- 個人の遺品や手記だけでなく、被害全体の規模を示すデータや年表にも目を向けてみましょう。
- なぜ、この街が選ばれてしまったのか。その歴史的背景を知ることも大切です。
- 海外の視点に触れてみる
- 海外の教科書では、原爆投下はどのように教えられているのでしょうか。
- 「戦争を終わらせるために必要だった」という意見があることも知り、その上で自分の考えを深めていきましょう。
まずは「知る」そして「話す」
大切なのは、感情的に「悲しい」「ひどい」で終わらせるのではなく、客観的な事実(ファクト)を知る努力をすることです。
知るためのステップ
- いつ?:1945年8月6日、9日
- どこで?:広島市、長崎市
- 誰が?:アメリカ軍が
- 何を?:原子爆弾を投下した
- なぜ?:その背景には、太平洋戦争という大きな流れがあった
- どうなった?:数十万人の市民が亡くなり、街は壊滅。その後も多くの人が後遺症に苦しんだ。
こうした基本的な事実を押さえた上で、感じたことや考えたことを、家族や友人と話してみましょう。「この映画、どう思った?」「この本にこう書いてあったんだけど…」そんな何気ない会話が、記憶をつないでいく第一歩になります。
主観と客観のバランスを大切に

私たちの心は、どうしても個人の悲しい物語(主観)に強く惹きつけられます。それは、人間として自然なことです。
しかし、その感情に流されるだけでなく、一歩引いて「なぜ、この悲劇は起こったのか」「どうすれば繰り返さないで済むのか」と考える客観的な視点も、同じくらい重要です。
| 大切にしたいこと | 具体的なアクション |
| 個人の痛みへの共感(主観) | 被爆者の方の体験記を読んだり、証言映像を見たりする。 |
| 事実への理解(客観) | 歴史書や資料を読み、事件の背景や全体像を学ぶ。 |
| 自分自身の思考 | 両方の情報をもとに、「自分ならどう考えるか」を言葉にしてみる。 |
| 他者との対話 | 自分の意見とは違う考え方にも耳を傾け、議論を深める。 |
この両方の視点を行き来することで、私たちの理解はより深く、立体的になっていくはずです。
まとめ:未来へのバトンを、私たち自身の手で

今日のコラムは、映画「オッペンハイマー」という一つの作品を通して、私たちにとても大切な宿題をくれました。
「風化」とは、単に体験者がいなくなっていくことではありません。
私たちが、その出来事について「考えることをやめてしまう」ことなのだと思います。
「あの日のことなんて、知りたくない」
「自分には関係ない」
そうやって目を背けた瞬間に、歴史は力を失い、ただの古い物語になってしまいます。
被爆者の方々の「一人称の叫び」を、しっかりと胸に刻むこと。
そして、その叫びを、国や世代を超えて共有できる「三人称の物語」へと翻訳し、語り継いでいくこと。
その両方が、原爆後の時代に生まれた私たちに託された、大切な役割なのかもしれません。
難しいテーマですが、諦めずに考え、学び、語り続ける。
それこそが、悲劇を二度と繰り返さないための、最も確実な一歩なのだと、私は信じています。














