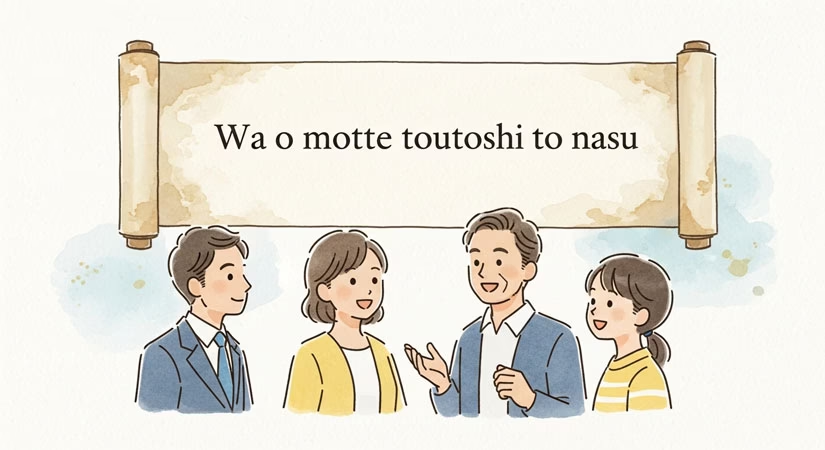日本経済新聞 2025年10月25日(金)朝刊春秋の要約と政治・古典の教訓
連立政権の合意書に「国家観」などと書いてあったので所信表明演説でどんなものものしいことを言うのかと思っていたら、十七条憲法の一節をひいて、日本は古来、衆議が重視される国であったと締めくくっていた。高市首相はなかなか懐の深い人なのかもしれない。
▼「和をもって貴しとし」で始まる十七条憲法は第一条で、人には党派の心があり、俯瞰(ふかん)的に悟っている者は少ない、それで争うわけだが、話し合えば、ことはおのずと道理にかなってくるのだと述べている。首相が引用した「事独り断(さだ)む可(べ)からず。必ず衆(もろとも)と与(とも)に宜(よろ)しく論(あげつら)ふ可し」の第十七条も、独善を戒める大意は同じだ。
この記事は、高市首相(架空)の所信表明演説で引用された「十七条憲法」に焦点を当て、その教えが現代の政治や私たちの生活にどう活かせるのかを探求し、読者の皆さんが古典から現代的なヒントを得られるように構成します。
📜 「十七条憲法」の基本情報:難しくない!日本の精神の礎

聖徳太子が制定したとされる「十七条憲法」は、日本で最も古い成文法であり、法律というよりも役人や貴族たちが心がけるべき「道徳的な指針」として作られました。難しそうに聞こえますが、その根底には、現代にも通じる「みんなで協力して、より良い社会を作ろう」というシンプルな願いが込められています。
📅 いつ・誰が作ったの?
| 項目 | 内容 |
| 制定時期 | 推古天皇12年(西暦604年) |
| 制定者 | 聖徳太子(厩戸皇子) |
| 目的 | 国家の役人の服務規律と国民の道徳的な指針を示すこと。特に、豪族たちが勝手に振る舞うことを戒め、天皇中心の統一国家の建設を目指しました。 |
📖 特徴は「和」と「議論」の重視
十七条憲法の有名な一節は、日本の精神文化を象徴するものとして、現代でも頻繁に引用されます。
| 条文と現代語訳(一部) | 込められた教え |
| 「独断の禁止と衆議」を意味します。大切なことは一人で決めず、必ず皆で話し合い、道理にかなった答えを導き出すべき、という教えです。 | **「調和」**を何よりも大切にし、無用な対立を避けること。みんなが仲良く協力し合うことが基本、という教えです。 |
| 第十七条:「事独り断(さだ)む可(べ)からず。必ず衆(もろとも)と与(とも)に宜(よろ)しく論(あげつら)ふ可し」 | **「独断の禁止と衆議」**を意味します。大切なことは一人で決めず、必ず皆で話し合い、道理にかなった答えを導き出すべき、という教えです。 |
この第十七条こそが、今回のコラムで高市首相が引用した部分であり、「衆議(しゅうぎ)」の重要性を訴える核となっています。
🗣️ 「衆議」とは? 現代社会で活かす話し合いの力
「衆議」とは、簡単に言えば「多くの人の意見を集め、議論すること」です。十七条憲法では、この「衆議」を通じてこそ、物事が正しい道理(筋道)にかなうと説いています。
🧠 なぜ「独り断ずべからず」なのか?
コラムにもあるように、十七条憲法の基底には「人は誰もが自分が正しいと考えるが、それは間違いだ」という、人間と社会への深い洞察があります。
| 人間への洞察 | 現代へのメッセージ |
| 人は完璧ではない | 誰もが視点や知識の限界を持っています。自分一人だけの考えでは、必ずどこかに見落としや偏りが生まれてしまいます。 |
| 「党派の心」 | 第一条にあるように、人はどうしても自分に近い考えやグループに偏りがちです。これは、無意識の「バイアス(偏見)」のようなものです。 |
| 正しいとは何か? | 「正しさ」は一つではありません。立場や状況によって異なる「正しさ」があることを認め、多様な意見をぶつけ合うことで、より多角的な「道理」に近づくことができます。 |
🤝 独断を避けるための「衆議」の実践ポイント
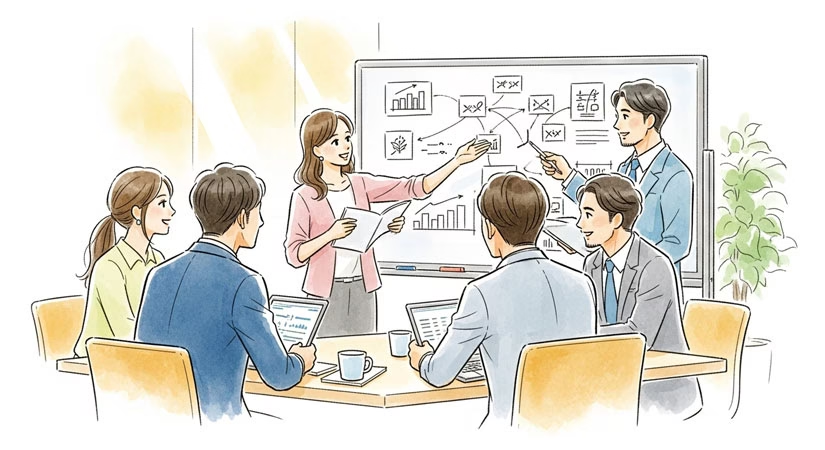
仕事や家庭、地域活動など、あらゆる場面で「衆議」を活かすための具体的なヒントをご紹介します。
1. 心理的安全性の確保
- 傾聴の姿勢を持つ: まずは相手の意見を否定せずに、最後まで聞くことを徹底しましょう。「意見を言っても無駄だ」と感じさせない雰囲気作りが大切です。
- 発言しやすい場作り: 立場や役職に関係なく、誰もが自由に意見を言えるよう、会議では年長者からではなく、あえて若手から意見を聞くなど工夫してみましょう。
2. 多様な視点の取り込み
- 「異論」を歓迎する: 反対意見や異なる視点は、「間違い」ではなく「ヒント」だと捉えましょう。「あえて反対の意見を出す人」を会議に加えるのも効果的です。
- 目的の明確化: 何のための議論なのか、最終的な目標(道理にかなうこと)を全員で共有することで、感情的な対立を防ぎ、建設的な議論に集中できます。
🏢 現代の「公僕」のあり方:第8条と「実務」への期待
コラムでは、十七条憲法の中から、現代の公務員制度を連想させるユニークな条文も取り上げられています。
▼十七条憲法は全体として一個の思想だから興味深く読んでいると、第八条に官吏は朝早く出勤して遅くに帰れとあり、これは例の話かと思ったが、意識してのことだろうか。
第八条: 「諸の公事には、早朝にまゐり、晩に退(まか)れ」
この条文は、現代でいう「働き方改革」とは正反対に聞こえるかもしれません。しかし、その真意は「長時間労働の推奨」ではなく、**「公務(人々のためになる仕事)を何よりも優先し、熱心に、献身的に取り組むべし」**という、役人としての責任感と心構えを説いたものです。
🎯 政治へのメッセージ:衆議と道理にかなった「実行」
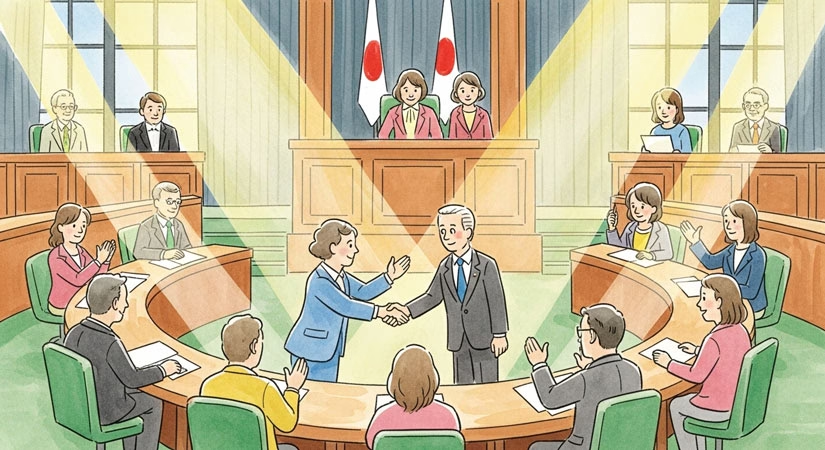
コラムの結びには、「演説は実務的で頼もしさを感じさせた」とあり、多党化時代だからこそ、「衆議と道理にかなった実行で深みある高市カラーを作っていってほしい」という期待が述べられています。
| 求める姿勢 | 具体的な行動のイメージ |
| 衆議 | 連立政権内や国会での多様な意見を丁寧に聴き、幅広い国民の声に耳を傾ける「懐の深さ」を持つこと。 |
| 道理にかなった実行 | 議論で導かれた最適解を、絵に描いた餅で終わらせず、国民生活に直結する政策として着実に実行に移す「実務能力」を示すこと。 |
| 多党化時代をひらく | 独善的にならず、少数意見や野党の意見にも謙虚に耳を傾け、協力と対話を通じて政治を前に進める柔軟さ。 |
💡 私たちの生活への応用:仕事の「実務」を大切に
私たち一人ひとりの仕事や生活でも、派手なスローガンや理念だけでなく、地道で真面目な「実務」の積み重ねが信頼を生みます。
- 目立たなくてもいいから、丁寧に: 誰かの役に立つ実務を、愚直に、真心を込めてやり遂げる姿勢は、必ず周囲に伝わります。
- 公私のケジメ: 聖徳太子が官吏に求めたのは、公の仕事への高い意識です。私たちも、自分の役割や責任を意識し、誠実に取り組むことが大切です。
🌸 まとめ:十七条憲法に学ぶ「対話の美徳」

高市首相の演説から見えてきたのは、日本の古典に根付く「対話と協調」の精神です。十七条憲法は、遠い昔のルールブックではなく、人が集団で生きていく上で、いかにして争いを避け、より良い答えを導くかという、永遠のテーマを私たちに投げかけています。
| 十七条憲法から学ぶ教訓 | 現代の私たちが実践すべきこと |
| 和を以て貴しと為す(第一条) | 家族、職場、地域で、まずはお互いを認め合い、調和を大切にする。 |
| 事独り断ずべからず(第十七条) | 自分の考えが絶対だと思い込まず、大切なことは必ず他者の意見を聞き、議論してから決める。 |
| 朝早く出勤し晩に退く(第八条の真意) | 自分の役割を認識し、誠実に、責任感をもって公私の務めを果たす。 |
この教えをヒントに、私たちの日常から「独断」を減らし、「衆議」の対話の力を活かして、深みのある、豊かな日々を築いていきましょう。