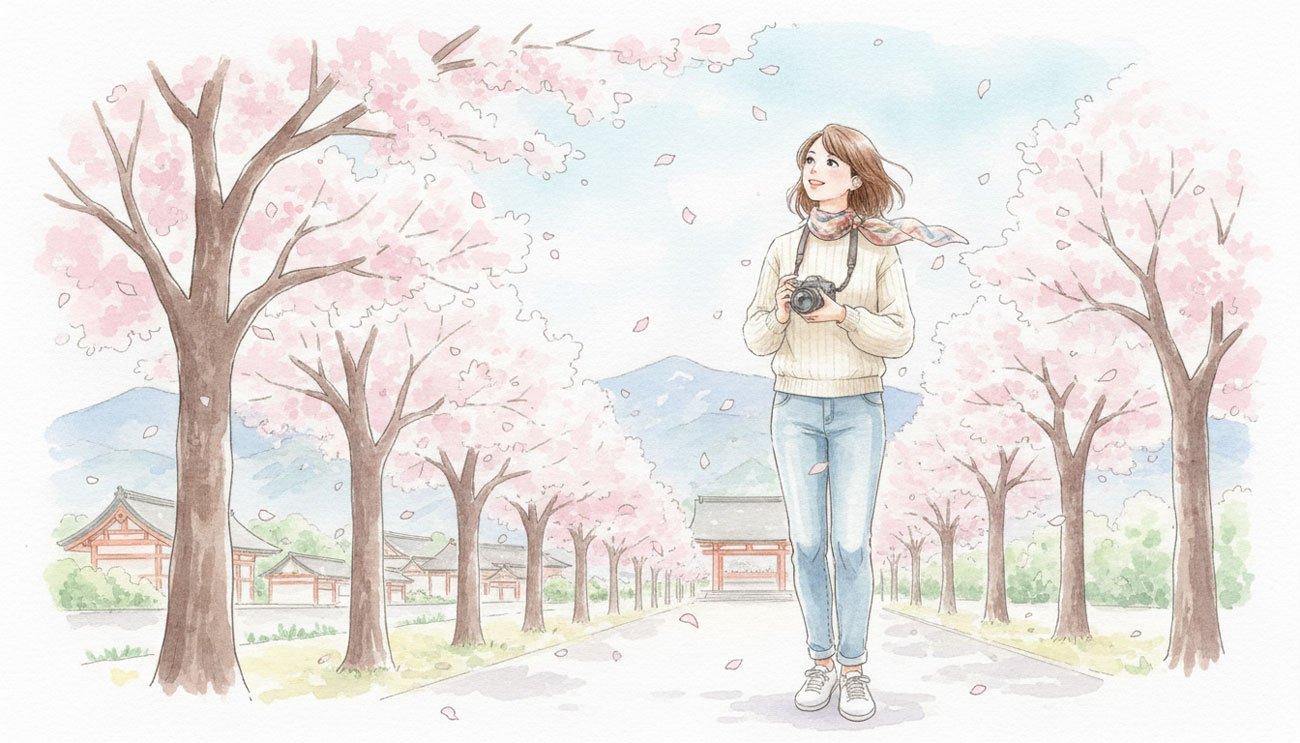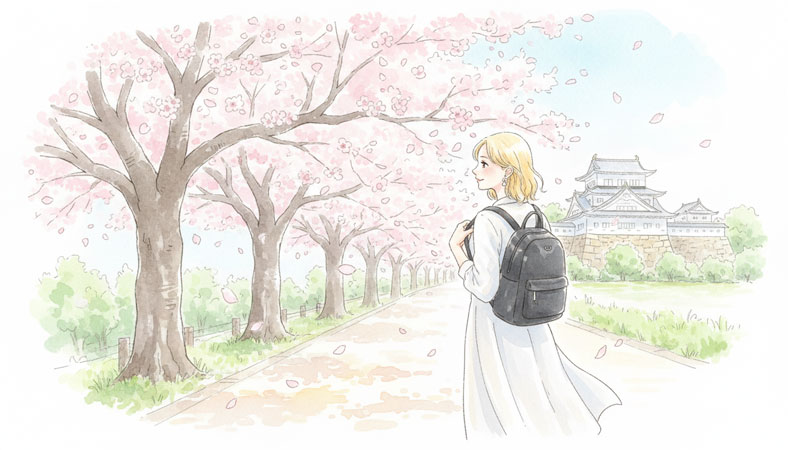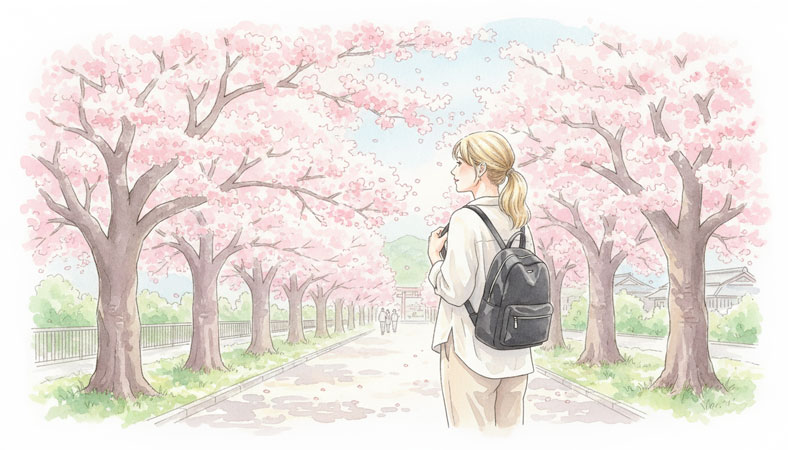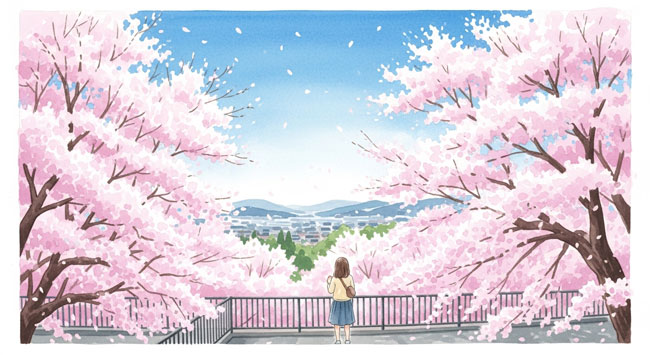日本経済新聞 2025年8月25日月曜日朝刊春秋の要約と人里に出没するクマ
日本経済新聞の朝刊コラム「春秋」は、冬の季語である「熊」について触れています。ヒグマもツキノワグマも、冬は冬眠しているはずなのに、なぜ冬の季語なのかという疑問から始まります。
古来、日本には冬に巣穴にこもったクマを狙う「穴狩り」という狩猟法があったため、この時期にクマがもっとも身近な存在だったのではないか、と推測しています。また、貴重な栄養源でもありました。
「熊」は冬の季語である。「羆(ひぐま)」も「月輪熊(つきのわぐま)」もしかり。ともに森の奥深くで冬眠しているはずなのになぜ、という疑問がわく。はっきりしないが、日本人の営みと深くかかわっているとも言われる。古来、巣にこもったクマを狙う「穴狩り」と呼ばれる狩猟法がある。
▼「熊撃てばさながら大樹倒れけり」(松根東洋城)。この動物をもっとも身近に感じる季節だったのか。貴重な栄養源だったからかもしれない。手元の歳時記をめくると、春には「熊穴を出(い)づ」、秋は木の上で餌をあさった痕跡を指す「熊の架(たな)」などがあるが夏の巻には登場しない。人との距離がうかがえるようでもある。
検索キーワード:人里に出没するクマ
この記事を読んだ人が、より詳しく知りたいと思うであろうキーワードは「人里に出没するクマ」「クマ 人間被害」「クマ 対策」「クマ 共存」などでしょう。この記事では、これらのキーワードで検索する人が求めている情報を網羅し、クマとの安全な共存について考えていきたいと思います。
なぜクマが人里に出てくるの?〜背景にある環境の変化〜
最近、テレビやニュースで「クマが住宅街に出没した」というニュースをよく耳にするようになりましたね。なぜ、本来は山にいるはずのクマが、私たちの生活圏にまで降りてくるのでしょうか?そこには、さまざまな要因が複雑に絡み合っています。

クマの生息域の変化
クマの生息域は、実は日本全国に広がっています。特に本州ではツキノワグマ、北海道ではヒグマが主な生息種です。しかし、近年、人間が開発を進めたことで、クマが暮らす森林が減ってしまい、彼らの生活圏が狭まっています。
人間とクマの生息域が重なり合う場所が増え、クマが餌を求めて人里に近づきやすくなっているのです。
餌不足が引き起こす問題
クマは、どんぐりやクリ、山菜、昆虫などを食べて暮らしています。しかし、気候変動の影響でこれらの木の実が不作になったり、森林の環境が変わったりすると、クマは深刻な餌不足に陥ってしまいます。お腹を空かせたクマは、人間が出す生ゴミや家庭菜園の野菜、畑の農作物などを求めて、人里に降りてくることが多くなります。
【クマの餌になる可能性のあるもの】
- 生ゴミ:特に、匂いの強いもの(肉や魚、調理くずなど)はクマを引き寄せやすいです。
- 果樹や野菜:庭に植えている柿や栗、家庭菜園のトウモロコシやカボチャなども、クマにとってはごちそうです。
- ペットフード:屋外に置きっぱなしにしたペットフードも、クマの餌になってしまいます。
クマと人間の距離が近くなる理由
- 過疎化と高齢化:中山間地域では、人口が減少し、管理されなくなった里山が増えています。これにより、クマが人里に近づきやすくなっています。
- 登山やレジャーの多様化:山登りやキャンプなど、自然を楽しむ人が増える一方で、クマの生息域に入り込んでしまうケースも増えています。
クマに遭遇しないための対策
クマとの不要な遭遇を避けることが、被害を防ぐ一番の鍵です。日常生活やレジャーでできる対策をまとめました。
1. 普段の生活でできること
- 生ゴミの管理を徹底する
- ゴミは収集日の朝に出し、夜間は家の外に置かないようにしましょう。
- 匂いが漏れないように、しっかりと密閉できる容器に入れましょう。
- 農作物や果樹を放置しない
- 収穫時期になったら早めに収穫し、畑や庭に放置しないようにしましょう。
- 不要な果樹は伐採することも検討しましょう。
- 庭の手入れをする
- クマが隠れられるような茂みや藪をなくし、見通しを良くしておきましょう。
- ツタが絡まったフェンスなども、クマの通り道になってしまうことがあるので注意が必要です。
- クマ出没情報をチェックする
- お住まいの地域や、これから出かける場所の自治体が発信するクマ出没情報をこまめに確認しましょう。
2. 山や森に入る時の対策

- クマよけの対策をする
- クマは聴覚が優れているため、鈴やラジオなどで音を出すことが有効です。
- 複数人で行動し、会話をしながら歩くことも、自分の存在をクマに知らせる上で大切です。
- 匂いの強いものを持ち込まない
- お弁当の食べ残しや、お菓子のゴミなどは、必ず持ち帰りましょう。
- 特に、甘い匂いはクマを引き寄せやすいので注意が必要です。
- 単独行動を避ける
- 登山やハイキングは、できるだけ複数人で行くようにしましょう。
- 早朝や夕方、夜間の行動は避け、日中に活動するように心がけましょう。
もしクマに遭遇してしまったら?〜落ち着いて行動することが大切〜
万が一、クマと出会ってしまったら、どうすればいいのでしょうか。パニックにならず、落ち着いて行動することが何より大切です。
1. クマとの距離を保つ
- 静かに後ずさりする
- 決して走って逃げてはいけません。クマは人間より速く走れます。
- クマに背を向けず、ゆっくりと後ずさりしながら距離をとりましょう。
- クマを刺激しない
- 大声を出したり、石を投げたり、棒で威嚇したりしてはいけません。
- 目を合わせることも避けましょう。クマに敵意があると誤解させてしまう可能性があります。
2. 状況に応じた対処法
| 状況 | 対処法 |
| クマがこちらに気づいていない | 静かに、ゆっくりと後ずさりしてその場を離れる。クマに背を向けない。 |
| クマがこちらに気づいている | 落ち着いて、ゆっくりと後ずさりする。できるだけクマとの距離をとる。 |
| クマが威嚇してくる | 腕で顔や頭を守り、地面に伏せる。クマスプレーを持っている場合は、使用を検討する。 |
| クマが突進してきた | 致命的な被害を防ぐため、うつ伏せになり、首の後ろを両手で覆う。 |
クマスプレーの活用
クマスプレーは、クマとの遭遇時に被害を最小限に抑えるための有効な手段です。使用する際は、風向きに注意し、クマの顔めがけて噴射します。
クマとの共存を考える〜保護と駆除のバランス〜
クマによる被害が増加している一方で、「クマを殺さないで」という声や、「絶滅させろ」といった極端な意見も聞かれます。これは、クマの保護と人間の安全という、難しい問題が背景にあるからです。
専門家の視点
野生動物の専門家や、自治体の職員は、この問題に日々向き合っています。彼らは、単にクマを駆除するだけでなく、被害を防ぐための対策や、クマの生態を調査し、保護と駆除のバランスを探っています。
- 捕獲と放獣:人里に出てきたクマを捕獲し、山奥へ放すことも行われています。
- 生態系の理解:クマが本来の生息地で安心して暮らせるように、森林の整備や餌となる木の実を増やす取り組みも重要です。
私たちにできること

クマとの共存は、私たち一人ひとりの意識にかかっています。
- クマの生態を正しく理解する:クマは、むやみに人を襲う動物ではありません。正しく理解することで、過剰な恐怖や誤解をなくすことができます。
- 生活圏への誘引を防ぐ:この記事で紹介したような、クマが人里に近づかないようにする対策を実践することが、最も効果的です。
クマは、日本の豊かな自然を象徴する大切な存在です。彼らと私たちが、お互いの命を尊重し、安全に暮らせる社会を目指していきたいですね。この問題について、これからも一緒に考えていきましょう。