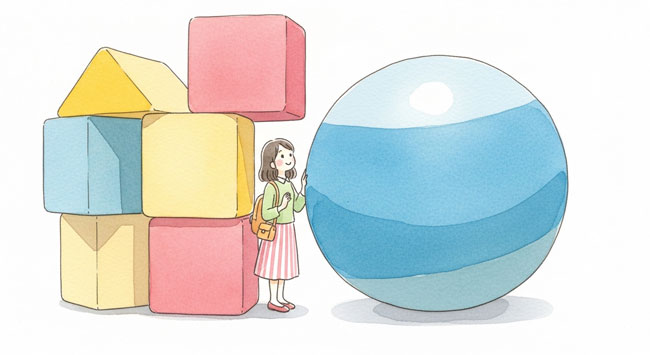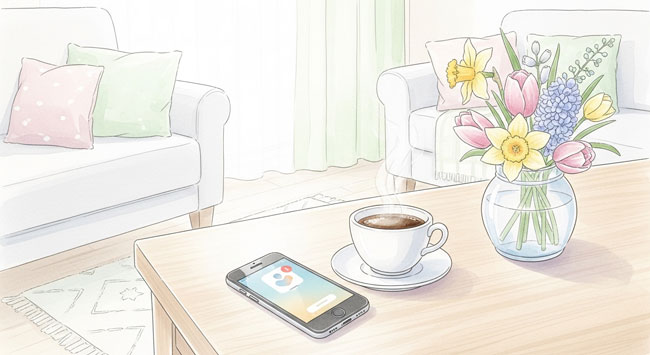2025年10月28日(火)日本経済新聞 朝刊 春秋の要約とインバウンド・オーバーツーリズム
ねえ、最近、観光地で外国人旅行者の方を本当によく見かけるようになったと思わない? 特に京都や東京だけじゃなくて、地方の小さな街でも。
今日の日本経済新聞の「春秋」コラムを読んでいたら、まさにそのインバウンド(訪日客)の存在感と、それに伴う地域の戸惑いがリアルに描かれていたの。
まずは、記事に書かれていた印象的なエピソードを引用するね。
遅めの夏休みを使い、瀬戸内の島々で開催中の芸術祭に足を運んだ。ある美術館では入り口付近で10人程度ずつ集められ、「館内では静かに」「写真は禁止」などルールの説明を受けた。冒頭で、まずこう聞かれた。「日本語での説明が必要な方はいらっしゃいますか」
恥ずかしながら、という思いでおずおず手を挙げたのはわれわれ夫婦のみ。他は欧米・アジア系のカップルやグループ、一人旅など、英語を解する外国人だけ。大阪・関西万博の閉幕前でミャクミャク人形をかばんにつけた若者も目立つ。日本発のコンテンツのパワーと、インバウンド(訪日客)の存在感を改めて知った。
これって、ちょっと衝撃的じゃない? 日本の芸術祭なのに、「日本語での説明が必要な人」が少数派だなんて。日本のコンテンツが世界で愛されている証拠だけど、私たち日本人自身が、海外の旅行者の方に囲まれて、アウェイ感を感じる、という状況。これが今の日本の現実なのよね。
そして、記事はこんな風に続くの。
- インバウンドの増加で、地域の「風向きが揺れて」いる。
- 観光ツアーを提供する起業家が「自治体に企画を提案しても、インバウンドはもういいと言われるんです」という本音を漏らしている。
- 政府は対策を本格化するけど、準備不足のまま「数」の多さを追ったひずみは小さくない。
観光による経済効果は嬉しいけれど、その裏側で、「もうお腹いっぱい」と感じている地域住民の声がある。この「光」と「影」のバランスをどう取っていくか?これが私たちにとって、すごく大事なテーマになっているみたい。
この記事では、私たちが安心して暮らせる街で、海外のお客様にも心から喜んでもらえるような、「持続可能な観光」のヒントを、一緒に探っていきたいと思うの。

観光の「光」と「影」:オーバーツーリズムがもたらす影響
そもそもオーバーツーリズムってどういうこと?
ニュースで「オーバーツーリズム」という言葉をよく聞くけれど、これって簡単に言うと「観光客が多すぎて、地域の生活や環境がパンク状態になっていること」を指す言葉なの。
観光地って、ホテルやお店、交通機関、ゴミ処理能力など、「受け入れられる量(キャパシティ)」が決まっているのね。その許容量を観光客の「数」が超えてしまうと、いろんな問題が起きてしまうの。
| 影響を受ける対象 | 具体的な事例 | 地域の住民はどう感じる? |
| 日常生活 | バスや電車が満員で乗れない、通勤通学に影響が出る、道路が渋滞して救急車が遅れる。 | 「生活の場を荒らされている気分になる」 |
| 文化・景観 | 人気の場所でのゴミのポイ捨て、私有地への無断立ち入り、大勢の人が押しかけることによる文化財の摩耗。 | 「大切にしてきたものが壊れていく不安がある」 |
| 経済活動 | 観光客向けの飲食店やホテルが増え、住民が日常的に使うスーパーや病院が減ってしまう。 | 「物価が高くなった」「自分たちが暮らしにくい街になった」 |
例えば、口コミサイトで「京都のバスに乗れない」「観光地の近くのスーパーは品薄」なんていう書き込みを見かけるけれど、これはすべてオーバーツーリズムの影響なの。特に、女性や子どもにとっては、人混みや治安の悪化が安心・安全を脅かす要因になりかねないわよね。
「数の多さ」を追ったことのひずみ:なぜ問題が深刻化したの?
日本は長い間、政府主導で「とにかく外国人旅行者を増やそう!」という「ビジット・ジャパン・キャンペーン」を続けてきて、その目標は達成できたと言えるわ。でも、その成功の裏で、「受け入れ側の準備」が間に合っていなかったという、大きな「ひずみ」が生まれたの。
例えるなら、引っ越し先の家に、いきなり何万人もの来客が押し寄せたようなものよ。
具体的に、どんな準備が足りなかったのか見てみましょう。
- インフラの整備:多言語対応の案内板が少ない、ゴミ箱が足りない、交通インフラ(バスや電車)の増強が追いつかない。
- 「マナー」の周知:日本の、特に「住居と観光地が近い」地域独特のルール(夜は静かにする、私有地に入らないなど)を伝えるツールが不足していた。
- 一極集中への対策:東京、京都、大阪の「ゴールデンルート」と呼ばれる人気のエリアに、観光客が集中しすぎるのを防ぐ仕組みが足りなかった。
特に、瀬戸内の芸術祭のように、住民の生活と密接に関わるイベントや地域では、「日本語が通じる人が少ない」ほどの国際化が進む一方で、地元住民の戸惑いや疲労感が、表面化してしまっているのね。
揺れる「風向き」の裏側:住民意識と地域の本音

「インバウンドはもういい」という声の背景にあるものは?
「自治体に企画を提案しても、インバウンドはもういいと言われるんです」という声は、地域のSOS(助けを求める声)だと捉えるべきだと思うの。
この「もういい」は、決して「外国人旅行者が嫌い」という単純な理由ではないのよ。その裏側には、こんな複雑な気持ちが隠れていることが多いわ。
- 生活の快適さが失われた「量」への疲弊観光客が「限界を超えた数」になったことで、住民は日常の「当たり前の快適さ」を失い、ストレスを感じている状態。
- 一部のマナー違反による「質」への不安残念ながら、中にはマナーを守らない人もいるわ。ゴミをポイ捨てしたり、夜中に騒いだり…。こうした一部の行動が、「すべての観光客が迷惑だ」というイメージに繋がってしまい、地域全体の不安感を煽ってしまうの。
- 「利益」の不公平感観光による収益が、ごく一部の大きなホテルや観光業者に集中してしまい、一般の住民には「迷惑」だけが残る、という不公平感がある。
想像してみて。朝、出勤のために駅に行ったら、いつも激混みの観光客で満員で乗れない。夜、家に帰ったら、近所の民泊が騒がしい。これでは、「観光客のおかげで豊かになった」とは、なかなか思えないわよね。
観光客と住民の意識のギャップを埋めるヒント
海外から来る旅行者の方も、「日本の文化を尊重したい」と思っているはず。でも、「どこまでが生活の場で、どこからが観光地か」という線引きは、旅行者には本当にわかりにくいものなの。
例えば、京都の細い路地は、日本人でも「ここって観光地? 誰かの家?」って迷うことがあるくらいよね。
このギャップを埋めるには、私たち受け入れ側が、「ここは生活の場ですよ」というメッセージを、わかりやすく、優しく伝える工夫が必要よ。
| 対策の方向性 | 具体的なアクション例と効果 |
| 環境とルールの見える化 | 「静かにご通行ください」「撮影禁止(プライベートエリア)」などのサインを、多言語(英語、中国語、韓国語など)で、親しみやすいデザインで設置する。 |
| 観光客の視線誘導 | 観光客に迷惑がかからない**「公式の撮影スポット」**を積極的に案内し、人の流れを意図的に誘導する。 |
| 地域の慣習を学ぶ機会の提供 | 宿泊施設でチェックイン時に、地域のマナーを記載したウェルカムシート(例:夜10時以降は静かに、ゴミの分別方法など)を手渡す。 |
| 地元住民の収入に繋がる仕組み | 住民が運営する**「地域密着型の体験ツアー」を用意し、観光客が地域にお金を落とすことで、「迷惑」ではなく「恩恵」**を感じてもらう。 |
持続可能な観光へ:数から「質」へのシフト
政府のオーバーツーリズム対策の方向性
「春秋」でも触れられていたように、政府もついにオーバーツーリズム対策を本格化させるの。この対策の大きな方向性は、「観光客の『数』を抑えつつ、『質』を高める」ということに尽きるわ。
これまでは「量を増やすこと」が経済効果の目標だったけれど、これからは「一人あたりの消費額を増やし、満足度を高め、かつ地域に負担をかけないこと」が目標になっていくわね。
具体的な対策の柱は、主にこの3つよ。
| 対策の柱 | 目的と期待される効果 | 住民へのメリット |
| 料金・制度の活用 | 混雑する時期や時間帯の料金を高く設定する(ダイナミックプライシング)や、人気スポットを予約制にする。 | 観光客が分散することで、混雑が緩和される。 |
| 地方・分散 | 東京や京都などの大都市だけでなく、地方の魅力的な体験ツアーへの補助金を出すなど、誘致を強化する。 | 観光による経済効果が全国各地に広がり、地方が潤う。 |
| 多言語でのマナー啓発 | 多言語の注意喚起動画や、日本の生活習慣を教えるツールの作成、宿泊施設でのルールの徹底。 | 観光客のマナーが向上し、住民のストレスが減る。 |
地域活性化のための「新しいインバウンド」の形

「自治体にインバウンドはもういいと言われる」という起業家の声があったけれど、これからのインバウンドは、「地域に貢献してくれる、質の高い観光」を目指すべきよね。
消費額が多く、滞在時間が長く、地域の文化や暮らしを尊重してくれる観光客は、地域にとって「宝」になるはず。
例えば、「田舎のおばあちゃんと一緒に地域の伝統料理を作る体験ツアー」や、「地元の工芸家から直接技術を学ぶワークショップ」なんて、すごく魅力的だと思わない?
こういうツアーに参加する人は、
- 消費額が多い:参加費だけでなく、地域の食材や工芸品を購入してくれるから、地域にお金がしっかり落ちる。
- 滞在時間が長い:地域独自のプログラムは、一過性の観光地巡りよりも滞在が長くなるため、地元に宿泊してくれる可能性が高まる。
- マナーが良い:そもそも地域の文化に興味を持っているから、住民との交流を大切にし、マナーを守ってくれる傾向がある。
| これまでの「量」の観光 | これからの「質」の観光(サステイナブル・ツーリズム) |
| 目的:ひたすら有名スポットで写真を撮ること | 目的:地域独自の体験や文化への深い理解 |
| 移動:大型バスで一気に移動し、渋滞を招く | 移動:地域の公共交通機関や、徒歩でのんびり散策 |
| 経済:一部の大企業やホテルに利益が集中する | 経済:体験料などで地域の農家や商店に利益が分散する |
私たちが目指すのは、地域の日常を壊す「消費型の観光」ではなく、地域の価値を高める「共創型の観光」なんだと思うの。
私たちにできること:共存の心地よさを探して
観光客が抱える疑問を先回りして解決しよう
私たちが海外旅行で困るように、日本に来る外国人観光客の方も、きっとたくさんの疑問や戸惑いを抱えているはず。特に、日本特有のルールはわかりにくいものよね。
例えば、外国人観光客が疑問に思うことのトップクラスはこれ。
| 観光客の疑問 | 日本のルール(補足説明) | 私たちの工夫 |
| ゴミの分別がわからない | ゴミは細かく分けて捨てる必要があり、公共のゴミ箱が少ない。 | 宿泊施設で写真付きの分別表を用意する、コンビニなどで多言語で案内する。 |
| どこで喫煙できる? | 喫煙所以外は原則禁止。路上喫煙は条例で罰則がある場所も多い。 | 喫煙所をわかりやすいサインで示す。 |
| 静かにしなくてはいけない場所は? | 住宅街、公共交通機関、旅館の廊下など、静寂が求められる場所が多い。 | **「Quiet Zone(静かなエリア)」**などの表示で、意図を明確に伝える。 |
| Wi-Fiが繋がらない | フリーWi-Fiスポットが少ないため、日本の旅行者よりも通信に困る。 | フリーWi-Fiの場所を地図で案内し、モバイルルーターのレンタルを推奨する。 |
「言わなくてもわかるだろう」ではなく、「伝わるように、丁寧に伝える」という姿勢が大切ね。私たち女性同士でも、言葉にしなくても察してほしい、と思うことはあるけれど、文化や習慣が違う方には、優しく、明確に伝えることが、お互いのストレスを減らす一番の近道よ。
私たち一人ひとりができる「小さな行動」

この記事を読んでくれているあなたも、旅人であると同時に、地域に住む住民の一人よね。この「観光」と「生活」のバランスを取るために、私たち一人ひとりができる小さな行動があるの。
| 私たちの立場でできること | アクションの内容と期待される効果 |
| 地域住民として | 困っている外国人観光客がいたら、笑顔で簡単な道案内や助け船を出す。 |
| 日本の旅行者として | 観光地を訪れる際、自分も「観光客」としてマナーを守る。 |
| 消費行動として | 旅行先では、地元の小さな商店や、地域独自の体験ツアーにお金を落とす。 |
「数」を追った結果、疲弊してしまった地域があるのは事実。でも、だからといって「外国人はもう来ないで」とシャッターを閉ざしてしまうのは、あまりにももったいないことだと思うの。
日本の豊かな自然や、丁寧な文化は、世界中の人に愛されるべきものだから。
私たちが目指すべきは、「来てくれてありがとう」と心から言えて、「また来たい」と思ってもらえる、心地よい共存の形よ。それは、地域の日常を守りながら、経済的な豊かさも享受する、という、わがままかもしれないけれど、誰もが幸せになれる道だと思うの。
この大きな「風向きの変化」を、私たち一人ひとりの行動で、より良い方向へ変えていきましょう。
この記事が、あなたの住む街と、旅する街について考える、素敵なきっかけになりますように。