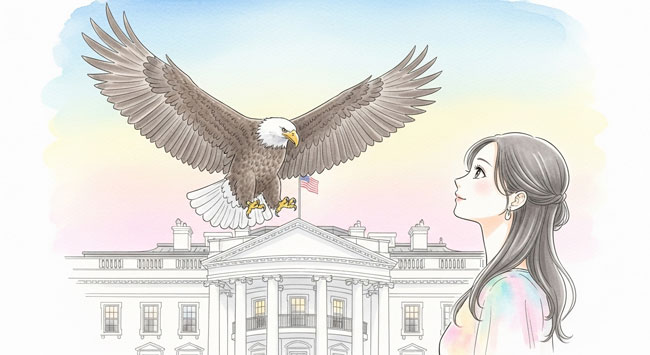日本経済新聞 2025年8月9日(土曜日)の春秋の要約と、言葉で紡ぐ平和への祈り
あの日から80年という歳月が流れました。1945年8月9日、一発の原子爆弾が長崎の街を破壊し、多くの尊い命を奪いました。その記憶は、時が経っても決して色褪せることはありません。
今日の日本経済新聞のコラム「春秋」には、原爆投下直後の長崎で、愛する家族を次々と失った俳人・松尾敦之さんの壮絶な体験が綴られていました。
俳人の松尾敦之さんがガリ版刷りの句集「火を継ぐ」をまとめたのは1946年のことだ。長崎に原爆が投下された前年8月9日から15日までの7日間に、妻と3人の子を次々亡くした。「降伏のみことのり妻をやく火いまぞ熾(さか)りつ」。遅すぎた敗戦への無念がにじむ。
▼原爆についての発信は当時、占領軍により厳しく禁じられた。松尾さんも雑誌掲載を拒まれやむなく手製の句集を編む。長崎の全俳句結社が協力し「句集 長崎」の刊行に至るのは原爆10周年。反原爆の感情が火をふいた。「魔の殺戮(さつりく)に対する憎悪、憤怒、そして呪詛(じゅそ)のありったけをぶちまけてもなほ足りない」(序より)
このコラムを読むと、言葉を奪われた時代に、それでも何かを伝えようとした人々の痛切な思いが伝わってきますよね。
この記事では、コラムをきっかけに、「怒りの広島」と対比される「祈りの長崎」という言葉の本当の意味、原爆の悲劇が俳句という短い言葉でどのように表現されてきたのか、そして、その記憶を私たちがどう受け継いでいけばいいのかを、一緒に考えていきたいと思います。
特に、お子さんを持つお母さんや、次の世代に平和な未来を残したいと願うすべての女性にとって、心に響く何かが見つかるかもしれません。少し長い旅になりますが、どうぞ最後までお付き合いくださいね。
「怒りの広島、祈りの長崎」- この言葉、本当はどういう意味?

広島と長崎。同じ原爆の悲劇を体験した二つの都市ですが、しばしば「怒りの広島、祈りの長崎」と対比されてきました。この言葉を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
でも、どうして長崎は「祈り」と表現されるようになったのでしょう。そして、その言葉は長崎の人々の本当の気持ちを表しているのでしょうか。
なぜ「祈り」のイメージ?- 浦上地区とカトリック信仰
この言葉の背景には、長崎、特に爆心地となった浦上地区の歴史が深く関わっています。
浦上は、江戸時代の厳しい弾圧を乗り越え、400年以上にわたってキリスト教の信仰が守り継がれてきた土地。多くのカトリック教徒が暮らす、信仰の中心地でした。原爆が投下された時、美しいステンドグラスで知られた浦上天主堂は、ミサの準備をする信者の方々もろとも、一瞬にして崩れ落ちてしまったのです。
原爆で亡くなった約7万4千人のうち、浦上のカトリック信者約1万2千人のうち約8千5百人が犠牲になったと言われています。まさに信仰の共同体が根こそぎ破壊された悲劇でした。
「神の摂理」という言葉の重み
この想像を絶する悲劇の中で、長崎医科大学の教授であり、自らも被爆しながら救護活動にあたった永井隆博士が発した言葉が、長崎のイメージに大きな影響を与えました。
彼は、浦上天主堂の廃墟で行われた葬儀ミサの際に、「原爆は神の摂理であった」と語ったのです。これは、戦争という人類の罪を償うために、最も清らかな子羊であった浦上の信者たちが、神へのいけにえとして捧げられたのだ、という考え方でした。
この「神の摂理」という言葉は、悲しみのどん底にいた信者たちの心を慰め、悲劇を受け入れるための支えとなった側面があったのかもしれません。しかし、時が経つにつれて、この言葉だけが一人歩きしてしまいました。
「長崎は、原爆の悲劇を神の試練として静かに受け入れ、怒りを表に出さなかった」
そんなイメージが作られ、「祈りの長崎」という言葉が定着していったのです。
「祈り」の奥に秘められた怒りと悲しみ
でも、本当にそうだったのでしょうか。愛する家族を、隣人を、一瞬にして奪われた人々が、ただ静かに祈っていただけだったのでしょうか。
もちろん、そんなはずはありませんよね。
日経新聞のコラムにあった「魔の殺戮に対する憎悪、憤怒、そして呪詛のありったけをぶちまけてもなほ足りない」という言葉。これは、原爆から10年後に刊行された『句集 長崎』の序文の一節です。
この言葉からは、静かな祈りだけでは到底収まりきらない、燃え盛るような怒りの感情が伝わってきます。長崎の人々もまた、広島の人々と同じように、理不尽な暴力に対する激しい怒りと深い悲しみを心に抱えていたのです。
「祈り」という言葉は、決して怒りや悲しみの「不在」を意味するのではありません。むしろ、言葉にならないほどの怒りと悲しみを抱えながら、それでもなお、天を仰ぎ、平和への願いを手放さなかった。その深く、強く、そして複雑な心の在り様こそが、「祈りの長崎」という言葉の真実の姿なのかもしれません。
言葉を奪われた時代 – 占領下で紡がれた俳句
今でこそ、私たちは自由に原爆について語り、その悲劇を伝えることができます。しかし、終戦直後は、それが許されない時代でした。当時の日本は、GHQ(連合国軍総司令部)の占領下にあり、厳しい言論統制が敷かれていたのです。
原爆を語ることを禁じた「プレスコード」
GHQは「プレスコード」と呼ばれる指令を出し、新聞や雑誌、ラジオなど、あらゆるメディアを厳しく検閲しました。その目的は、日本の軍国主義的な思想をなくし、民主化を進めるというものでしたが、その中には、アメリカに対する批判を封じ込める狙いもありました。
特に、原爆に関する報道は徹底的に制限されました。
| GHQプレスコードで制限された主な内容 |
| SCAP(連合国軍最高司令官総司令部)への批判 |
| 極東国際軍事裁判(東京裁判)への批判 |
| GHQが起草した日本国憲法への批判 |
| 原子爆弾への言及や批判 |
| 検閲制度への言及 |
この表を見るとわかるように、原爆の被害の実態や、その非人道性を訴えることは、固く禁じられていました。もし書けば、発行停止などの厳しい処分が待っていたのです。
多くのジャーナリストや作家、詩人たちが、目の前で起きた地獄のような光景を伝えたいのに伝えられない、というもどかしい思いを抱えていました。
松尾敦之さんとガリ版刷りの句集『火を継ぐ』

そんな中で生まれたのが、日経新聞のコラムで紹介されていた松尾敦之さんの句集『火を継ぐ』です。
松尾さんは、1897年(明治30年)に長崎で生まれた俳人です。原爆が投下された時、彼は48歳でした。あの日、市街地にあった職場から郊外の自宅へ帰る途中、彼は地獄を見ます。そして、8月9日からわずか7日間で、妻のキクノさん、長男の剛さん、次男の陽さん、そして三男の力さんという、愛する家族全員を失ってしまいました。
想像してみてください。昨日まで当たり前にあった家族の笑顔、声、温もりが、たった数日で全て消え去ってしまう絶望を。
降伏のみことのり妻をやく火いまぞ熾(さか)りつ
8月15日、日本が降伏を受け入れた玉音放送が流れる中、松尾さんは妻の亡骸を荼毘に付していました。「もっと早く戦争が終わっていれば…」。遅すぎた終戦への無念と、燃え盛る炎へのやるせない思いが、この一句に凝縮されています。
彼は、この地獄のような体験と家族への思いを俳句に詠み続けました。しかし、プレスコードの壁に阻まれ、雑誌に発表することはできません。
それでも、彼は諦めませんでした。どうしてもこの記憶を形に残したい。その一心で、謄写版、いわゆる「ガリ版」を使って、たった一人で句集を刷り上げたのです。インクの匂いが立ち込める中、一枚一枚、手作業で紙を重ねていく。その作業は、失われた命への鎮魂の祈りそのものだったのかもしれません。
こうして1946年に生まれたのが、50部限定の私家版句集『火を継ぐ』でした。それは、言論が封殺された暗い時代に、人間の尊厳をかけて灯された、ささやかだけれど、決して消えない希望の光でした。
10年目の叫び – 『句集 長崎』の刊行
松尾さんのような個人の抵抗だけでなく、長崎の俳人たちは、水面下で連帯を続けていました。そして、原爆投下から10年、サンフランシスコ講和条約によって日本が主権を回復し、言論統制がなくなった後の1955年。ついにその思いが結実します。
長崎にあった全ての俳句結社が垣根を越えて協力し、『句集 長崎』が刊行されたのです。
この句集の序文に刻まれた「憎悪、憤怒、そして呪詛」という言葉は、10年間、心の奥底に押し込めてきた感情の爆発でした。それは、検閲によって歪められた「静かな長崎」というイメージに対する、俳人たちの力強い反論でもあったのです。
この句集には、松尾敦之さんをはじめ、多くの俳人たちの句が収められています。そこには、被爆した瞬間の閃光、燃えさかる街、水を求めてさまよう人々、そして家族を失った悲しみが生々しく刻まれています。
五・七・五に刻まれた記憶 – 長崎原爆の俳句たち

俳句は、たった17文字という世界で最も短い詩です。でも、その短い言葉の中には、情景や感情、そして作者の人生そのものが凝縮されています。特に、原爆という極限状況を詠んだ俳句は、どんなに長い文章よりも雄弁に、私たちにその悲劇性を伝えてくれます。
ここでは、『句集 長崎』などに収められた句をいくつかご紹介しながら、そこに込められた思いを一緒に感じてみたいと思います。
あの日の情景を詠む
秋の空一瞬にして無くなれり
(橋本武)
「秋の空」という、穏やかで美しい季語。その後に続く「一瞬にして無くなれり」という衝撃的な言葉。青く澄み渡っていたであろう空が、ピカッと光った次の瞬間には、きのこ雲に覆われ、暗闇に変わってしまった。その恐ろしい光景が、鮮やかに目に浮かぶようです。
鉄橋も真赤に溶けて夏終る
(磯野充伯)
頑丈なはずの鉄の橋が、真っ赤に溶けてしまうほどの熱線。その一句だけで、原爆の想像を絶する破壊力が伝わってきます。「夏終る」という季語が、多くの命と共に、当たり前の日常が終わってしまった悲しみを静かに物語っています。
焼跡に遺りしものは墓標のみ
(菅原鬨也)
すべてが焼き尽くされた街。そこに残っていたのは、誰のものとも知れないおびただしい数の墓標だけだった。この句からは、命の尊厳さえも奪われた、むごたらしい光景が広がります。
失われた命への鎮魂歌
原爆俳句には、家族や友人など、大切な人を失った悲しみを詠んだものが数多くあります。先ほどご紹介した松尾敦之さんの句もその一つです。
生きてゐしわが子のからだ蟬しぐれ
(松尾敦之)
「生きてゐし」という過去形が、胸に突き刺さります。少し前まで確かにここにいて、生きていた我が子。今は冷たくなってしまったその体を抱きしめながら聞く蝉時雨は、どれほど悲しく響いたことでしょう。降りしきる蝉の声が、父親の慟哭のように聞こえてきませんか。
原爆忌真水を欲りし声今も
(内藤雅子)
「水をください、水を…」。熱線で全身を焼かれ、亡くなっていった人々が最後に求めたのは、一杯の水でした。作者は、8月9日が来るたびに、耳の奥でその苦しい声を聴き続けてきたのでしょう。決して消えることのない罪悪感と、鎮魂の祈りが込められた一句です。
それでも未来へ – 生き残った者の誓い
絶望の中にも、かすかな光を見出し、未来へと歩み出そうとする句もあります。
八月九日堪へて生き抜く誓ひせり
(早崎治)
「堪へて生き抜く」。それは、亡くなった人々の分まで生きるという、生き残った者の責任と覚悟の表明です。地獄のような体験をしてもなお、前を向こうとする人間の強さに、胸を打たれます。
子のために積木くづさじ原爆忌
(野中からたち)
子どもが一生懸命に積み上げた積木。それを崩さないように、そっと見守る親の姿。この句は、子どもたちが築いていく未来の平和を、決して壊してはならないという強いメッセージになっています。「積木」が象徴するささやかでかけがえのない平和を、私たち大人が守っていかなければならない、と改めて感じさせられますね。
これらの句を読むと、原爆が単なる歴史上のできごとではなく、一人ひとりの人生をめちゃくちゃにした、生々しい体験だったことが痛いほど伝わってきます。17文字に込められた魂の叫びは、80年経った今も、私たちの心を強く揺さぶる力を持っているのです。
「ピース・フロム・ナガサキ」- 平和への祈りを世界へ
「ノーモア・ヒロシマ」というスローガンに比べると、「ピース・フロム・ナガサキ(長崎から平和を)」という言葉は、少し弱々しく聞こえるかもしれません。日経新聞のコラムでも、そのように評されたことがあると書かれています。
しかし、長崎が発信してきた平和のメッセージは、決して弱々しいものではありませんでした。むしろ、「祈り」の奥にある強い意志と行動力によって、世界に静かで、しかし確かな影響を与え続けてきたのです。
高校生が届ける平和のメッセージ

長崎の平和活動を象徴するのが、「高校生平和大使」の存在です。
1998年に始まったこの活動は、全国から選ばれた高校生たちが、スイス・ジュネーブにある国連ヨーロッパ本部に赴き、核兵器廃絶を求める署名を届けるというもの。これまでに集まった署名は、なんと200万筆を超えています。
制服姿の高校生たちが、世界の外交の中心地で、自分たちの言葉で懸命に平和を訴える姿は、多くの人々の心を動かしてきました。彼らは、被爆者の体験を直接聞き、学び、それを自分の言葉で世界に伝えます。それは、まさに記憶の「継承」そのものです。
この活動は、ノーベル平和賞の候補に何度もノミネートされるなど、国際的にも高く評価されています。派手さはないかもしれませんが、地道な草の根の活動が、着実に世界へと広がっているのです。
アートや文化を通じた発信

長崎は、俳句だけでなく、音楽や文学、映画など、さまざまな文化・芸術活動を通して、原爆の記憶と平和への願いを発信し続けてきました。
- 音楽: 歌手のさだまさしさんが、長崎の被爆体験をテーマに作った楽曲『無縁坂』や『祈り』は、多くの人々の心を打ちました。また、毎年8月9日には、平和祈念式典で合唱が捧げられます。
- 文学: 作家の林京子さんは、自らの被爆体験をもとにした小説『祭りの場』で芥川賞を受賞しました。彼女の作品は、原爆が人々の心に残した深い傷を、静かな筆致で描き出しています。
- 映画: 長崎を舞台にした映画も数多く作られています。近年では、吉永小百合さんが主演した『母と暮せば』が話題になりました。原爆で亡くなった息子が、亡霊となって母親の前に現れるというファンタジーの形をとりながら、戦争の理不尽さと残された者の悲しみを深く描いた作品です。
これらの作品は、声高に反戦を叫ぶのではなく、個人の物語に寄り添うことで、戦争の悲惨さを静かに、しかし深く訴えかけます。これもまた、「祈りの長崎」らしい、平和へのアプローチだと言えるかもしれません。
記憶のバトンをつなぐ – 私たちにできること
コラムの最後に、心に残る一句が紹介されていました。
平和の詩暗記するほど朗読す
これは、長崎原爆忌平和祈念俳句大会のジュニアの部に入賞した中学生の句だそうです。
平和の詩を、ただ読むだけでなく、暗記するほど何度も何度も朗読する。その姿を想像すると、胸が熱くなりますね。言葉を繰り返し口にすることで、その意味を深く心に刻みつけようとしている。これは、まさに「継承」の原点です。
被爆者の方々の平均年齢は85歳を超えました。あの日のことを直接語れる人は、年々少なくなっています。私たちは今、その記憶のバトンをどう受け取り、次の世代に渡していくのか、真剣に考えなければならない岐路に立っています。
では、具体的に私たちに何ができるのでしょうか。
まずは「知る」ことから始めよう
難しく考える必要はありません。まずは、関心を持って「知る」ことが、大切な第一歩です。
- 本を読む:
- 子どもと一緒に: 小さなお子さんがいるなら、絵本から始めてみるのはいかがでしょう。『かわいそうなぞう』や『おこりじぞう』など、戦争の悲しさを伝える名作がたくさんあります。
- 大人の学び直し: 永井隆博士の『長崎の鐘』や『この子を残して』、林京子さんの『祭りの場』などを読んでみるのもいいですね。被爆者の手記も、胸に迫るものがあります。
- 映画やドラマを観る:
- 先ほど紹介した『母と暮せば』のほかにも、『この世界の片隅に』など、戦争と平和をテーマにした優れた映像作品がたくさんあります。家族で一緒に観て、感想を話し合うのも素敵な時間になるはずです。
- 資料館を訪れる:
- もし機会があれば、長崎や広島の平和公園、原爆資料館を訪れてみてください。展示されている遺品や写真の一つひとつが、声なき証言者として、原爆の真実を語りかけてきます。その場に立つことでしか感じられない空気があります。
自分の言葉で「伝える」勇気
知ったことを、自分の中に留めておくだけでなく、身近な人と話してみることも大切です。
- 家族との対話: 「今日、こんな記事を読んだんだけど…」「この俳句、どう思う?」。そんな風に、食卓で気軽に話してみる。子どもたちの素朴な疑問に、一緒に考えながら答えてあげる。そんな日々の対話が、記憶のバトンをつなぎます。
- おじいさん、おばあさんの話を聞く: もし、ご自身の祖父母や身近な高齢者の方で、戦争を体験された方がいらっしゃるなら、ぜひその話を聞かせてもらってください。「昔の話だから」と遠慮されるかもしれませんが、「聞かせてほしい」というあなたの真剣な気持ちは、きっと伝わるはずです。それは、あなたにとってかけがえのない宝物になるでしょう。
- SNSでシェアする: この記事を読んで感じたことや、心に残った俳句を、SNSでシェアしてみるのも一つの方法です。あなたの小さなアクションが、誰かの心に平和の種をまくきっかけになるかもしれません。
平和な日常に感謝する
そして、何よりも大切なのは、今ここにある平和な日常に感謝することではないでしょうか。
朝起きて、家族と「おはよう」と言い合えること。
美味しいごはんを食べられること。
子どもたちが元気に学校へ行く後ろ姿を見送れること。
これらの一つひとつが、決して当たり前ではない、かけがえのない奇跡なのだと、8月9日は改めて気づかせてくれます。
「平和の詩暗記するほど朗読す」。
あの中学生のように、私たちも平和への思いを心の中で反芻し、日々の暮らしの中で実践していく。それこそが、80年前の悲劇から私たちが学ぶべき、最も大切なことなのかもしれません。
この記事の旅も、もうすぐ終わりです。
「祈りの長崎」という言葉の奥に秘められた、深い悲しみと怒り、そしてそれを乗り越えようとする人間の強さと尊厳。俳句という短い言葉に込められた、魂の叫び。
80年という長い歳月をかけて紡がれてきた長崎の物語は、私たちに静かに、しかし力強く語りかけてきます。
悲劇を繰り返さないために。
そして、子どもたちに平和な未来を手渡すために。
あなたも、あなたの言葉で、平和への祈りを紡いでみませんか。