ねぇ、最近「静かなる退職(Quiet Quitting)」っていう言葉、よく聞かない?
「それって、こっそり会社を辞めること?」って思っている人もいるかもしれないわね。実は、ちょっと違うの。
静かなる退職というのは、実際に会社を辞めるわけではないのよ。簡単に言うと、「与えられた仕事以上のことは一切しない」という働き方を指すの。
「必要最低限の仕事しかしなくなる状態」と言い換えることもできるわ。
この言葉が世界中で注目されているのは、パンデミック以降、私たち一人ひとりの「働き方」や「人生における仕事の重み」に対する考え方が大きく変わったからなの。
この記事では、この「静かなる退職」について、その実態から、会社側・働く個人側がどう向き合っていくべきかまで、詳しく解説していくわね。
1. 「静かなる退職(Quiet Quitting)」の定義と現状
1-1. 正しい定義と具体的な行動・兆候
まずはっきりさせておきたいのは、「静かなる退職」は決して「怠け」ではないということ。
これは、頑張りすぎた結果、心と体を守るために、意識的に「努力のストップライン」を引く行為なの。
検索結果や専門家の分析によると、「静かなる退職」には主に3つの側面があると言われているわ。
| 側面 | 内容 |
| 離脱 | 仕事から意識的に距離を置くこと。仕事の量や責任を最小限に抑えようとする。 |
| 主体性の欠如 | 新しい仕事や挑戦を避ける。自分の意見を述べることをやめる。 |
| 意欲の欠如 | 仕事へのやりがいやモチベーションを感じられなくなる。 |
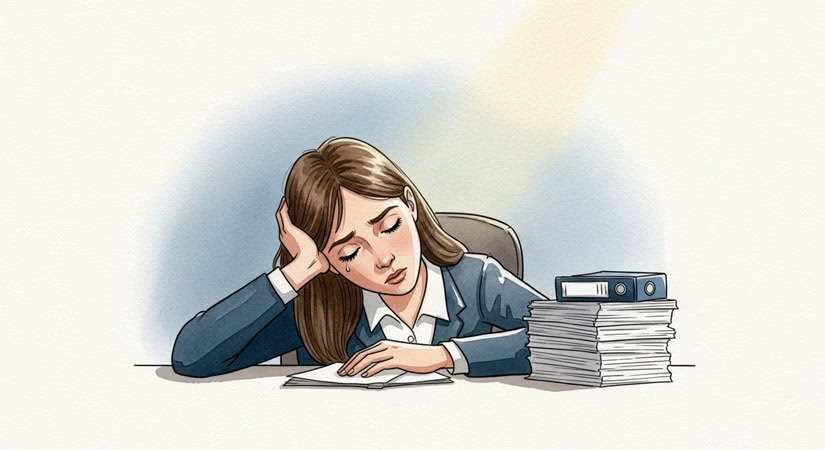
静かなる退職者の具体的な行動
じゃあ、具体的にどんな行動が「静かなる退職」の兆候になるのかしら?
周囲からは「あの人、どうしたんだろう?」と見えがちな行動をいくつか挙げるわね。
- 残業や休日出勤の拒否、定時退社を徹底する
- 「勤務時間外は仕事のメッセージは確認しない」と割り切るの。
- 職務範囲外の仕事は断る
- 「それは私の仕事ではありません」とはっきり、またはやんわり伝える。ボランティア扱いの仕事はしない。(Mind Map「具体的な行動(行動)」より)
- 会議やミーティングでの発言が少なくなる
- 自分の意見を言ったり、新しい提案をしたりしなくなる。
- キャリアや将来の目標に関する言及が減少
- 昇進やキャリアアップへの意欲を一切示さなくなる。
- タスクに余分な労力を費やさない
- 完璧を目指さず、求められた最低限の品質で完了させる。(検索結果2.8より)
1-2. 国内外の認知度・現状(データ)
この現象は世界的なムーブメントになっていて、特にデジタルネイティブな若年層を中心に広まっているわ。
Mind Mapのデータを見ても、日本国内でも多くの人がこの言葉を知り、関心を持っていることが分かるわね。
| 項目 | データ(Mind Map「国内外の認知度・現状」より) |
| 「静かなる退職」の認知度 | * 聞いたことがある:約5割(50.2%) |
| 静かなる退職経験者の割合 | * 現在行っている:13.8% |
| 実施意向 | * 行いたいと思わない:約6割(59.5%) |
「知ってはいるけれど、やりたい人は意外と少ない」という日本の現状が見えてくるわね。
でも、この働き方を実践することで、実際に得られたものもあるのよ。

静かなる退職で得られたもの
マイナビキャリアリサーチLabの調査(2025年実績)によると、静かなる退職で得られたものは、主に次の2点だったわ。
- 休日や労働時間、自分の時間への満足感(23.0%)
- 仕事量に対する給与額への満足感(13.3%)
多くの人が、失いかけていた「自分の時間」を取り戻し、「仕事と給与のバランス」に納得感を得ているのね。
これは、働きすぎで心身が疲弊しきっていた人たちにとって、自分の人生を守るための「自己防衛策」としての側面が強いことを示しているわ。
2. 静かなる退職が発生する根本的な原因
「静かなる退職」は、決して一人の社員のワガママで起きているわけではないの。
むしろ、組織や社会構造、そして私たち自身の価値観の変化が複雑に絡み合って生まれているのよ。
この原因を正しく理解することが、次の対策につながるわ。
2-1. 組織・マネジメント層に起因する要因
まずは、会社や上司との関係の中で生まれてくる原因を見ていきましょう。
| 要因 | 詳細と背景 |
| 評価への不満・不公平感 | 頑張りや成果が正当に評価されない、または昇進や昇給に結びつかないと感じる。「どうせ頑張っても報われない」という諦めと無力感が、意欲を失わせるの。( |
| 報われない経験によるバーンアウト(燃え尽き) | 長時間の残業や過剰な期待に応え続けた結果、心身が疲弊してしまう。「これ以上すり減りたくない」という自己防衛本能が働くわ。 |
| コミュニケーション不足とミスマッチ | 上司との1on1や面談で、本音や悩みを話せない。仕事の内容や会社の文化が自分に合っていないと感じていても、相談する機会がない。 |
| 業務の役割・責任の不明確さ | 誰の仕事か曖昧な業務(名もなき仕事)が増えたり、人によって業務量が偏ったりすることで、「なぜ自分ばかりが…」という不公平感が生まれるの。 |
2-2. 個人の価値観の変化と内面的な要因
次に、働く人自身の価値観や内面の変化から生まれる原因を見ていきましょう。
| タイプ(検索結果2.1より分類) | 詳細な内容 |
| 損得重視タイプ | 「お金のために働いているのでそれに見合った仕事量はしている」など、金銭的な対価と仕事量をシビアに計算し、費用対効果(コスパ)を重視する。(Mind Map「個人の心境、価値観の変化」) |
| 無関心タイプ | 「キャリアアップすることに興味がない」など、もともと出世欲や昇進意欲がなく、現状のままで安定したいと考える。(Mind Map「個人の心境、価値観の変化」) |
| 不一致タイプ | 「今の職場にはやりがいがある仕事がない」など、仕事内容や環境との不適合を感じ、意欲が低下している。 |
| ワークライフバランス重視 | 「仕事が人生のすべてではない」と割り切り、プライベートを最優先する傾向。これは特に若い世代で顕著よ。(検索結果3.1) |
読者の疑問を先取り:静かなる退職は「世代の問題」?
「結局、今の若い子は根性がないってこと?」って思った人もいるかもしれないわね。
でも、それは違うわ。
静かなる退職は、特定の世代だけの問題ではないの。Mind Mapのデータ(「静かなる退職経験者の割合」)を見ても、20代、30代だけでなく、40代、50代でも一定数この働き方を実践している人がいることが分かるわ。
これは、時代と共に「人生の主導権を仕事ではなく自分に戻したい」と考える人が全世代で増えている証拠なの。
3. 企業が取るべき「静かなる退職」への対策(予防と改善)
静かなる退職を放置すると、組織の活力が失われ、優秀な人材の「見えない離脱」が続き、やがては本当の離職につながってしまうわ。(検索結果2.2)
企業側は、この現象を「社員の意識の問題」として片付けず、「組織からのシグナル」として真摯に受け止める必要があるの。
3-1. マネジメントの改善と透明性の確保
まず取り組むべきは、社員が「報われている」「公平だ」と感じられる環境づくりよ。
信頼感を高める組織づくりのためのアクション
- 公平で透明性の高い人事評価制度の設計・運用
- 何をどれだけ頑張れば評価されるのか、その基準を明確にし、社員が納得できるフィードバックを行うこと。
- 職務記述書(ジョブディスクリプション)の導入
- 一人ひとりの「役割と責任の範囲」を明確に言語化するの。これにより「あの人は楽をしているのではないか」といった不公平感を軽減し、「評価に見合った仕事のみをする」という考え方の誤解も防げるわ。(検索結果2.4、2.8)
- 1on1や面談の質の向上
- 業務の話だけでなく、「最近どう?疲れてない?」といった雑談ベースの対話を交えることが大切。相手の心身の状態や本音に触れやすくなるわ。(検索結果2.2、2.5)

3-2. 働きやすい環境と支援の整備
社員が「自分の人生と健康を大切にしながら働ける」と感じられる制度も不可欠よ。
- ワークライフバランス支援の強化
- 有給休暇の取得を奨励し、むしろ義務化するくらいで良いわ。時間単位の有休取得など、柔軟な働き方をサポートする制度を導入して。(Mind Map「対策:従業員への支援」)
- メンタルヘルスケアの強化
- 産業医や外部EAP(従業員支援プログラム)相談窓口を、社員が遠慮なく利用できる環境を整えて。
- キャリア支援・育成の充実
- キャリアパス制度を導入し、昇進だけではない多様なキャリアの選択肢を示すの。(例:「スペシャリストコース」「管理職コース」など)(検索結果2.8)
- 「どうせ頑張っても意味がない」と感じている社員に、新たな成長機会や学びの場を提供し、仕事への意欲を再燃させるきっかけを作ることも重要よ。
3-3. 静かなる定着(Quiet Committing)を促す視点
ここで、少し発想を転換してみましょう。
「静かなる退職」をネガティブに捉えるだけでなく、「静かなる定着(Quiet Committing)」というポジティブな側面に目を向けることが大切よ。
これは、過度な野心や昇進意欲はないけれど、「自分の領域でプロフェッショナルになりたい」「今のチームの人間関係が好きだから定時で帰るけれど、仕事はしっかりやる」という人たちを指すわ。
Quiet Committingを促すためのポイント
| ポイント | 具体的行動 |
| 会社に留まる理由の把握 | 社員が「給料が安いかもしれないけれど、働きやすい」「人間関係が良くてストレスがたまらない」など、会社に留まる理由をヒアリングし、それを会社の強みとして生かす。 |
| 多様な貢献を認める | 昇進や売上貢献だけでなく、チームの雰囲気を良くすることや、後輩の育成といった「見えにくい貢献」も評価の対象とする。 |
| 私生活の充実を支援 | 仕事だけでなく私生活の充実のための支援(副業の解禁、趣味との両立支援など)も重要。仕事とプライベートが満たされていれば、働くことにも前向きになるわ。 |
4. 個人が「静かなる退職」とどう向き合うか
会社側の対策を見てきたけれど、最後は私たち個人の問題よ。
もしあなたが今、「静かなる退職」の状態にあるなら、この働き方をどう自分のキャリアに生かすべきか、一緒に考えてみましょう。
4-1. 静かなる退職のメリット・デメリット
「静かなる退職」は、心を休ませるための必要なステップかもしれないけれど、長期的に見ると、自分のキャリアにデメリットをもたらす可能性があるわ。
| 側面 | メリット | デメリット |
| 心身・生活 | ストレス軽減、バーンアウトの防止、自分の時間・心の余裕の確保。 | モチベーションの低下、職場での孤独感、周囲との人間関係の悪化リスク。 |
| キャリア | 自分の能力を高めるための時間(転職活動、副業など)の確保。 | 成長機会の喪失、新しいスキルアップの停滞、昇進・昇給機会の減少。 |
特に気をつけたいのは、「成長機会の喪失」よ。必要最低限の仕事しかしなくなると、新しいプロジェクトや難易度の高い仕事から外され、結果的に自分の市場価値が上がりにくくなるリスクがあるわ。
4-2. 従業員としての適切な心構え
静かなる退職を「逃げ」で終わらせず、自分の人生を豊かにするための「戦略的な一時停止」にするためには、心構えが大切よ。
心と体の回復のためのアクション
- 「損得」を明確に言語化する
- 自分が会社から求めているもの(給与、休暇、人間関係など)と、会社に提供している労力(仕事量、残業時間)のバランスを紙に書き出してみて。
- 「お金のために働いている」と割り切るなら、コスパを重視した働き方を徹底する。(検索結果2.1)
- 「静かなる退職」を次のステップの準備期間にする
- 定時退社で得た時間を、単なる休息だけでなく、転職活動、資格取得、スキルアップのための学習に充てるの。(検索結果3.2)
- 「報われない頑張り」を完全に手放す
- 「頑張っても誰も見てくれない」という考えに固執せず、「自分で自分を報いる」ことにフォーカスする。仕事は最低限にして、自分の趣味や家族との時間に全力を注ぐの。
建設的な「静かなる定着」を目指す
最も理想的なのは、「建設的な静かなる定着」を目指すことよ。
これは、過剰なプレッシャーから離れつつも、「この会社で自分の能力を発揮したいこと」は明確に保つ働き方。
「出世は望まないけれど、自分の担当業務では誰にも負けないプロフェッショナルになる」というように、仕事のモチベーションを「外部からの評価」ではなく「自己満足・専門性の追求」に切り替えるの。
そうすれば、会社は無理なくあなたを評価し、あなたはストレスなく自分の価値を発揮できる。これこそが、新しい時代の賢い働き方の一つと言えるんじゃないかしら。
まとめ:「静かなる退職」は組織と個人、双方にとって重要な変化のシグナル
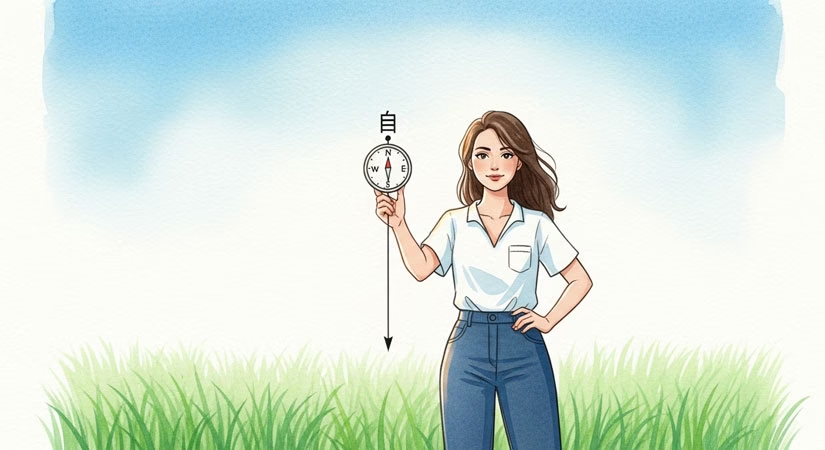
「静かなる退職」というムーブメントは、私たち一人ひとりが、仕事と自分の人生のバランスを見つめ直すきっかけを与えてくれているわ。
会社にとっては、「社員の心と体の健康を真剣に考える時代が来た」という警鐘。評価制度やコミュニケーションのあり方を見直す大きなチャンスよ。
個人にとっては、「自分の頑張りのストップラインはどこか」「自分の人生で本当に大切なものは何か」を定義し直す、自己防衛のための重要な戦略と言えるわね。
もし、今あなたが「静かなる退職」の状態にあるなら、決して自分を責めないで。それは、あなたが頑張りすぎた証拠よ。
この時期を、次に進むための「戦略的な充電期間」として大切に過ごしてほしいわ。
最後まで読んでくれてありがとう。あなたの働き方が、もっとあなたらしく、輝くものになりますように!














