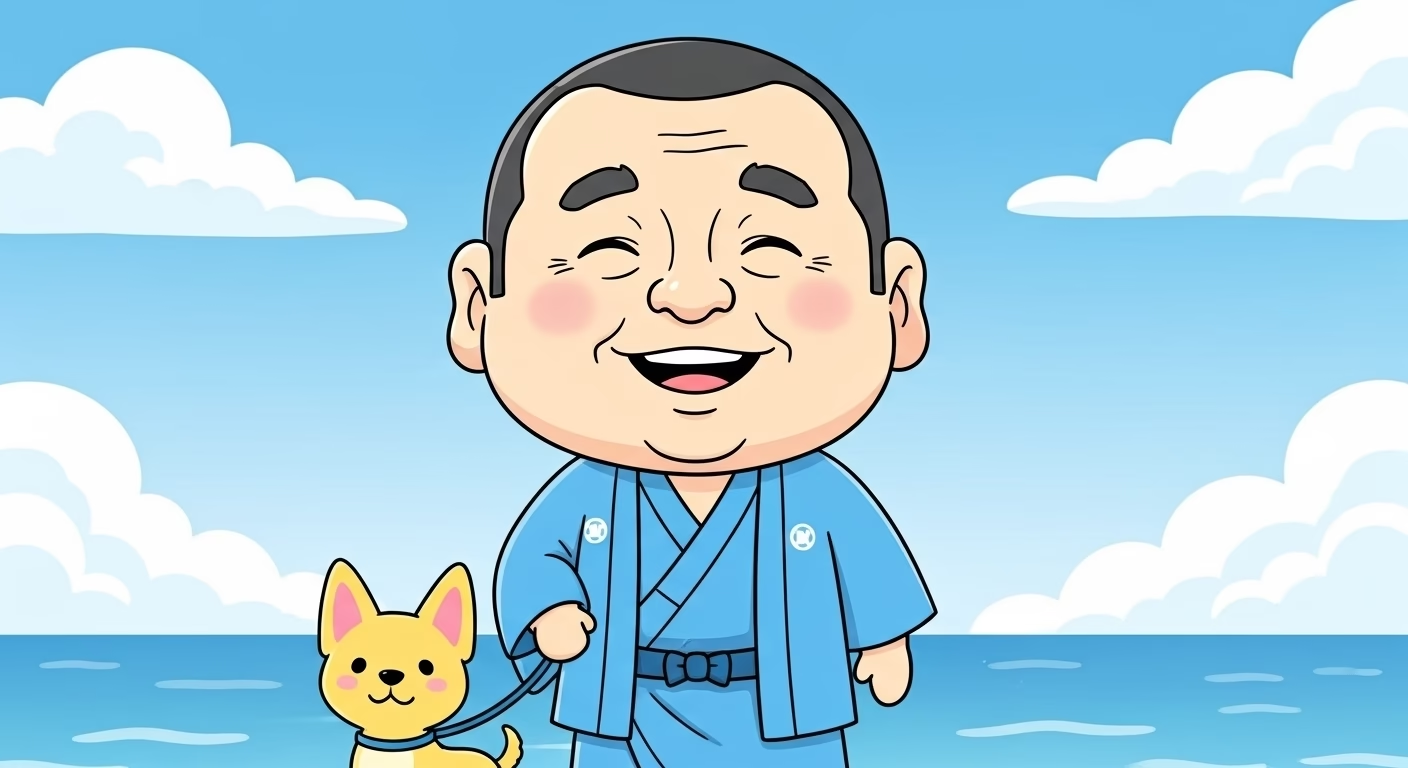日本経済新聞 2025年10月9日(木)朝刊春秋の要約と西郷隆盛の思想が現代に投げかける問い
日経新聞「春秋」より:西郷隆盛の言葉と現代政治のリアル
「南洲翁遺訓」が投げかける人事の厳しさ
今日の日本経済新聞朝刊「春秋」では、幕末の英傑、西郷隆盛の言葉をまとめた「南洲翁遺訓」が取り上げられています。その内容は、現代の政治における「論功行賞」のあり方について、非常に厳しい視線を向けているのが印象的です。
引用された部分をまずご紹介します。
西郷隆盛の言行をまとめた「南洲翁遺訓」は、論功行賞のあり方に厳しい注文をつけている。いわく、政治とは職務にふさわしい能力のある人材を広く選び、政権を担わせるものである。大きな勲功があっても、その任にたえない人物は官職で処遇すべきではない――。
▼功に報いるのはポストではなく給料で、とも言っている。政治家の間にもファンが多いという古典だが、さて西郷どん、自らの戒めが後世でほぼスルーされていると知ったらどう思うだろう。人事による論功行賞は、現代の政界でごく当たり前の風景である。勝った者が重要ポストに座り、敗れた者は冷や飯に泣いてきた。
「南洲翁遺訓」とは? なぜ現代の私たちに必要なのか
西郷隆盛の「南洲翁遺訓」:その誕生と核となる思想
そもそも「南洲翁遺訓」ってどんな本?
西郷隆盛(号:南洲)の教えや言行を、門弟たちがまとめたものです。西郷が亡くなった後に編集されました。
これは、政治の哲学、人としての生き方、国家のあり方について、西郷の考えが詰まった「魂の教科書」とも言えるものです。
- いつ頃できたの?:西郷が亡くなった後、明治時代初期にまとめられました。
- 主な内容:修養(自己を磨くこと)、教育、国家経営、政治のあり方、人材登用など多岐にわたります。
- 特徴:非常に厳格で道徳的。私利私欲を戒め、公のために尽くす姿勢を説いています。
現代人が「西郷どんの言葉」に惹かれる理由
なぜ、明治の偉人の言葉が現代の政治家やビジネスパーソンにまで影響を与えるのでしょうか。
それは、時代が変わっても変わらない「人間の真理」や「組織運営の基本」を説いているからです。特に、「公私混同をしない」「私心を捨てる」という教えは、現代社会における倫理観やリーダーシップの指針となります。
私たちが共感する主なポイントを表にまとめました。
| 西郷の教えのポイント | 現代社会での意味合い |
| 敬天愛人 | 自然の摂理を尊重し、人を慈しむ心を持つこと。人間関係の基本。 |
| 私心を去る | 個人の欲望や利益を優先せず、公(会社、組織、社会)のために尽くすこと。リーダーに求められる倫理観。 |
| 職にふさわしい能力 | ポストに見合うスキルと人格を持つ人材を選ぶこと。現代の適材適所の人事。 |
| 功績への報い | 報酬は金銭(給料)で。ポストは能力で決める。現代の評価制度とキャリアパスの分離。 |
現代政治における「論功行賞」の功罪:西郷の教えとのギャップ
「論功行賞」とは? 政治の現場でなぜ避けられないのか
「論功行賞」の意味を分かりやすく解説
論功行賞(ろんこうこうしょう)とは、「功績や手柄を論じ(評価し)、それに見合った賞を与えること」です。
簡単に言えば、「頑張った人に、その頑張りに見合ったご褒美をあげる」ということです。
政治の世界では、主に「選挙で勝利に貢献した」「総裁選で指示をくれた」「党の運営で重要な役割を果たした」といった功績に対して、賞として「大臣や党の幹部などの要職(ポスト)」を与えることを指します。
政治における「論功行賞」のメリットとデメリット
政治家がポストを競うのは、単なる名誉欲だけではありません。権力を集中させ、政策を円滑に進めるための「組織論」としての一面もあります。
| 視点 | メリット(なぜ必要か) | デメリット(西郷が批判した点) |
| 組織運営 | 協力者への報奨となり、次の選挙や党内協力への**インセンティブ(動機付け)**になる。党内の結束を一時的に高める。 | ポストが**能力ではなく「ご褒美」**になるため、適任ではない人物が就任し、政治全体の質が低下する恐れがある。 |
| 公正さ | 頑張りや貢献度が報われるという**「フェアな競争原理」**の一部となる。 | 功績の評価基準が**「派閥の力」や「個人の忠誠心」に偏り、「国民のため」という本来の目的**から外れる。 |
| 西郷の教え | (この視点でのメリットはない) | **「能力がない者を官職につけるな」**という教えに真っ向から反する。 |
西郷が提案した「功に報いる方法」:ポストではなく給料で
西郷隆盛の思想が現代に特に響くのは、「功に報いるのはポストではなく給料(金銭)で」という考え方です。
これは、現代の組織論で考えると非常に合理的です。
- 政治ポスト(大臣など):これは「社会への奉仕」と「高い専門能力」が求められる「職務」であり、個人の功績への「ご褒美」であってはならない。
- 功績への報い(ご褒美):これは「金銭的な報酬」で適切に行うべき。名誉やポストは、「仕事の能力」によってのみ与えられるべき、という厳しい線引きです。
もし、政治家たちがこの教えを実践していたら、「能力はあるが派閥に属さない人」や「若手で実力がある人」が、もっと早く重要ポストに登用され、国民にとってもより良い政治が行われたかもしれません。
西郷隆盛が現代の政治に突きつける3つの教訓
教訓1:政治とは「職務にふさわしい能力」で人を選ぶこと
西郷隆盛は、「能力のない者が要職につくこと」を最も恐れました。現代の政治家やリーダーにとって、これは「適材適所」を徹底せよという強いメッセージです。
| 現代の政治家に求められる視点 | 西郷の教えとの関連 |
| 能力評価の客観性 | 派閥の論理や総裁選での貢献度ではなく、政策立案能力、国民への説明責任、危機管理能力といった職務能力を厳正に評価すること。 |
| 長期的な視点 | 目の前の選挙や党内人事に気を取られず、10年後、20年後の国家の未来を見据えて、能力ある若手を登用し育てること。 |
| 国民への責任 | 人事の失敗は、そのまま国民生活に直結します。**「国民生活」**という職務に見合う人選こそが、政治の責任です。 |
教訓2:強大な外国を恐れて言いなりになってはいかん
日経新聞のコラムにもあったように、西郷の遺訓には「強大な外国を恐れて言いなりになってはいかん」という教えもあります。
これは、現代の国際政治において、同盟国であれ、経済大国であれ、「日本の国益」を第一に考え、自立した姿勢を持つことの重要性を示唆しています。
- トランプ対策にも通じる:コラムで指摘されていたように、自国の利益を最優先する国との交渉においても、毅然とした態度と明確な戦略を持つことが必要です。
- 主体性を持つ:外交交渉では、相手の要求をただ受け入れるのではなく、日本が何をしたいのか、世界にどう貢献したいのかという主体的な視点を持つことが不可欠です。
教訓3:己を慎み品行を正しくせよ
「裏金議員らには耳が痛いはず」とコラムが指摘したように、「己を慎み品行を正しくせよ」という教えは、政治家にとっての基本中の基本です。
- 「皆がつまずきがちだからこその教訓」:西郷は、人間は誰でも私欲に流されやすいものだと知っていたからこそ、あえてこの教訓を遺したのでしょう。
- 信頼の土台:国民の信頼は、政策の良し悪しだけでなく、政治家一人ひとりの「人間性」によって築かれます。「清廉潔白」な政治姿勢こそが、揺るぎない政治基盤となります。
私たちが西郷の思想から学ぶ、組織とキャリアのヒント
政治家だけでなく私たちにも通じる「南洲翁遺訓」
西郷隆盛の言葉は、企業やNPO、学校など、あらゆる組織で働く私たちにも当てはまります。
組織で実践したい「西郷式」人事と評価
西郷の思想を取り入れた、現代の組織における理想的な人事のあり方を考えてみましょう。
| 西郷の教え | 現代の企業・組織での具体的な行動 |
| 「能力でポストを与える」 | 昇進や役職への登用は、実績と**未来の職務に対する適性(スキルやリーダーシップ)**を厳正に評価する。年功序列や派閥(社内の力関係)を排除する。 |
| 「功績は給料で報いる」 | 特別な功績やプロジェクトの成功に対しては、一時金や特別ボーナスで報いる。これにより、**「ポスト」と「金銭的報酬」を分離し、「能力のない部長」**が生まれるのを防ぐ。 |
| 「私心を捨てる」 | 自分の好き嫌いや個人的な利益で部下や同僚を評価・依怙贔屓しない。あくまで組織全体の利益と公平性を最優先する。 |
キャリアを考える私たちが大切にしたい「西郷の心」
私たちが自分のキャリアを築く上で、西郷の思想をどう生かせるでしょうか。それは、「自己研鑽」と「公の意識」です。
- 「職務にふさわしい能力」を常に磨く:
- 「私には能力がないから」と努力を怠ることは、西郷の教えに反します。常に新しい知識を学び、スキルを磨き続けることが、私たちの「職務」に対する責任です。
- 自分の仕事に「公の視点」を持つ:
- 自分の仕事が誰のためになっているのか、社会にどう貢献しているのか、という「公」の視点を持つことで、仕事の意義は深まり、「私心」に流されない強さが生まれます。
- 品行を正しくする:
- 信頼は一瞬で失われます。日々の言動、特にデジタル時代における倫理観(情報管理、ハラスメント、公正な振る舞い)は、キャリアを左右する重要な要素です。
まとめ:西郷隆盛の問いかけに、現代のリーダーはどう答えるべきか
求められる「解党的出直し」と「挙党体制」の本当の意味
日経新聞のコラムは、新しい自民党体制が「解党的出直し」や「挙党体制」から遠い印象であると結んでいます。
西郷の教えに照らすなら、「解党的出直し」とは、単に人を入れ替えることではなく、「論功行賞」という私心に基づく人事の仕組みそのものを根本から改めることでしょう。
そして、「挙党体制」とは、派閥や総裁選での勝利者・敗者という垣根を超え、「能力」によって選ばれた者たちが、「国民のため」という一つの公の目標に向かって団結することです。
政治家であるならば、自身の「功」に報いることよりも、「職務」を全うする「能力」が今、自分にあるのかを、西郷隆盛の遺訓を通して常に自問自答してほしいものです。そして、私たち国民もまた、「能力」を基準に政治家を選ぶという、西郷の教えに沿った厳しい視点を持ち続けることが、より良い政治を実現するための鍵となるでしょう。