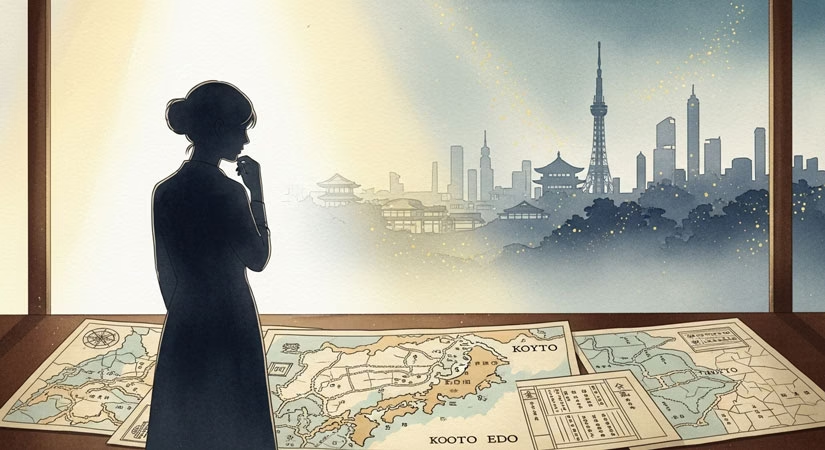日本経済新聞 2025年10月27日(月)朝刊春秋の要約と日本の「都」の移り変わりと未来
本日(2025年10月27日)の日本経済新聞朝刊「春秋」の内容です。日本の「都」をめぐる歴史的な背景から現代の議論まで、非常に示唆に富む内容でした。
明治維新で大坂への遷都を考えていた大久保利通は、前島密の手紙に感服して東京遷都に転じた――。よく知られるこの逸話は真偽不明とされるが、司馬遼太郎は好んだらしく掌編「江戸遷都秘話」「東京遷都」を残した。歴史にロマンをみる司馬史観の一つであろう。
▼江戸は倒幕で人々が離散し、都を置かなければ廃れる。不満のくすぶる東北、北海道をにらむのにも都合がいい。無血開城で役所の建物も残った。そう考えての東京遷都だが、京都や大坂にも配慮が要るデリケートな問題である。慎重な大久保は矢面に立たぬよう、前島を持ち出したのだろう。遷都はなし崩しでなされた。
この記事では、
- 明治維新時の大久保利通が大坂(大阪)への遷都を考えていたという説と、前島密の書簡で東京(江戸)遷都に方針転換したという逸話。
- この逸話は真偽不明ながら、司馬遼太郎が好み作品に残していること。
- 東京遷都の背景には、江戸の衰退防止、東北・北海道に対する戦略的視点、無血開城による建物の利用といった実利的な理由があったこと。
- 遷都が京都や大坂への配慮から、大久保利通が前島密を利用してなし崩し的に行われたという見方。
- 現代に至るまで、東京を首都と定める法律がないという「戦略的あいまいさ」が引き継がれていること。
- その中で浮上した、根拠法のない首都に遠慮したような「副首都構想」への批判的な視点。
- 司馬遼太郎が国会移転を促し、「都が移るたびによくなってきた」と語っていたこと。
- 関西が再び注目され、新たな時代の幕開けが西から来るというロマンへの期待。
などが語られています。
このコラムは、日本の都の位置が、単なる地理的な問題ではなく、政治、経済、そしてロマンが絡み合う、非常にデリケートなテーマであることを示していますね。
🏛️ 明治維新!江戸が東京になったデリケートな決断の舞台裏
東京が日本の中心になったのは、単なる成り行きではなく、非常に慎重な判断と配慮が重ねられた結果でした。

1. 「東京遷都」はなぜデリケートな問題だったの?
明治政府にとって、都を移す「遷都(せんと)」は、新時代の象徴であると同時に、長年日本の中心であった京都や商業の中心地であった大坂(大阪)の感情を逆なでしかねない、最大級のデリケートな問題でした。
- 京都:1000年以上にわたり天皇の住まいとされてきた場所です。ここから天皇(御所)を移動させることは、「遷都」と捉えられ、京都の人々だけでなく、旧来の価値観を持つ人々の間に大きな反発を生む可能性がありました。
- 大坂:古くから「天下の台所」と呼ばれるほどの経済の中心地。大久保利通が当初大坂を検討したのも、経済力を重視したためとされます。
このため、政府は「遷都」という言葉を公式には使いませんでした。
2. 「前島密の手紙」は真相?大久保利通の「戦略的あいまいさ」
コラムで触れられている大久保利通と前島密の逸話は、歴史のロマンを感じさせますが、実は遷都をめぐる政府の思惑を象徴しているとも言えます。
| 説 | 内容 | 示唆される背景 |
| 前島密書簡説 | 前島密が、廃れていく江戸を救うため、そして戦略的な理由から、江戸への遷都を大久保利通に強く提言した、というもの。大久保はこの手紙に感服し、東京遷都を決めたとされる。 | 大久保が矢面に立つのを避けたかったという見方です。「私一人の意見ではない」という形を取り、京都や大坂からの批判の矛先をかわす狙いがあったかもしれません。 |
| 実利優先説 | 倒幕後の江戸は人口が激減し、このままでは廃墟化してしまうという危機感がありました。また、無血開城で旧幕府の立派な役所(庁舎)がそのまま使えるという実利的なメリットも大きかったのです。 | 費用をかけずに国の基盤を作れるという、当時の財政事情から見ても合理的で現実的な判断が優先されたと考えられます。 |
結局、明治政府は天皇が一時的に滞在するという名目で江戸城を「東京城(のちに皇居)」と改め、天皇が京都に戻ることなくそのまま滞在を続けました。これが「なし崩し的な遷都」と呼ばれる所以です。デリケートな問題に対して「戦略的あいまいさ」をもって対応した、非常に巧妙な政治手法でした。
3. 司馬遼太郎が見た「都の移転」のロマン
作家の司馬遼太郎さんは、この東京遷都の逸話を好み、日本の歴史における「都の移動」には、いつも新しい時代の幕開けというロマンを見ていました。
- 都が移るたびに、国は新しく、より良くなってきたという考え方です。
- 例えば、奈良から京都、あるいは江戸への変遷といった大きな節目は、新しい政治体制、新しい文化、新しい経済が生まれるエネルギーを秘めていました。
司馬さんは、戦後、「国会移転(首都機能移転)」を促す政府の調査会で熱心に旗を振り、東京一極集中から脱して、日本をもう一度ダイナミックに変化させるべきだと主張しました。変化を恐れない心意気を、日本の歴史の移り変わりの中に見出していたのですね。
⚖️ 東京は「首都」じゃない?法律上のデリケートな現実
現代の日本において、東京が事実上の首都であることは誰もが認めるところですが、コラムにもあるように、「東京を首都と定める法律」は現在ありません。
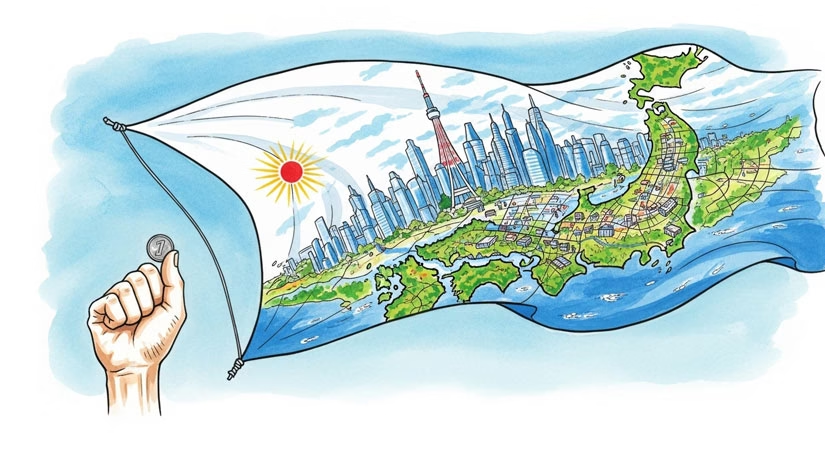
1. なぜ「首都法」がないの?
実は、戦後間もない1950年に「首都建設法」という法律ができましたが、これは首都を東京と明示したわけではなく、東京を「文化国家の理想を達成する総合的な建設を行う都市」と位置づけ、東京の復興・建設を目的としたものでした。この法律は1956年に廃止されています。
それ以降、東京を首都と正式に定める法律はありません。これには、主に二つの理由が考えられます。
| 理由 | 説明 |
| 歴史的経緯と配慮 | 明治維新時のデリケートな問題が今も尾を引いています。京都や大阪など、他の都市への政治的な配慮から、あえて「首都」を法で明記することを避けてきた側面があります。**「戦略的あいまいさ」**が現代にも残っているのです。 |
| 首都機能移転への含み | 東京一極集中のリスク(地震などの災害、過密問題)や、国土の均衡ある発展の観点から、**「将来的に首都機能の移転も選択肢として残しておく」**という政府の姿勢の表れとも言えます。 |
私たちが普段使っている「首都圏」という言葉は、「首都圏整備法」という法律に定義されていますが、これは東京を中心に周辺の埼玉、千葉、神奈川、茨城、栃木、群馬、山梨の1都7県を指すもので、「東京が首都である」ことを直接定義しているわけではありません。
2. 「首都」と「都」の違いを分かりやすく解説
私たちは日常で「首都」と「都」という言葉を特に意識せず使いますが、違いを整理すると以下のようになります。
| 用語 | 意味 | 法律上の根拠 |
| 首都(しゅと) | 国の政治の中心(国会、政府機関、外国大使館などが集まる)となる都市。 | 法律による明確な定義はない(事実上の首都は東京)。 |
| 都(と) | 都道府県の一つの名称(東京都)。 | 地方自治法に基づく、他の道府県と同等の地方公共団体。 |
東京は「東京都」という地方自治体であり、同時に「事実上の首都」という二つの顔を持っているのです。
🚀 現代のロマン?「副首都構想」と関西のエネルギー
コラムの結びは、現代の日本における新たな「都」の議論、副首都構想へと繋がります。

1. なぜ今、「副首都」の議論が盛り上がるの?
「副首都構想」とは、東京以外に首都機能の一部(あるいは大部分)を移転させ、災害時のリスク分散や経済の活性化を目的として、「もう一つの中心」を確立しようという考え方です。
特に大阪を中心とした関西圏で議論が熱心なのは、以下の理由からです。
| 理由 | 内容 |
| 災害リスクの分散 | 東京圏で大地震などの大規模災害が発生した場合、国の機能が完全に麻痺することを避けるため、代替の中枢機能を確保する必要性が高まっています。 |
| 地域経済の活性化 | 副首都となることで、国の投資や企業の進出が促され、関西圏の経済活性化の大きな起爆剤になると期待されています。 |
| 万博など国際イベント | 2025年の大阪・関西万博や、カジノを含む**統合型リゾート(IR)**の誘致など、国際的なイベントを契機に、関西の存在感を高めたいという機運が高まっています。 |
2. コラムが指摘する「せこい」副首都構想とは?
コラムでは、現在の副首都構想の進め方について「いかにもせこい」と批判的な視点を投げています。これは、主に以下の点に向けられた批判です。
- 「副首都」という名称への遠慮:東京が法的に首都と定められていないことに配慮し、「副首都」という二番手のような名称を使っている点。これは、「首都機能の移転」という本来の目的やロマンを矮小化しているという批判です。
- 「都構想」との関連性:大阪市を廃止・分割して「特別区」を設けるという、住民投票で二度否決された「大阪都構想」を前提に進めようとしている点。「副首都」の議論を利用して、「都構想」という地方政治のテーマを実現しようとする「抱き合わせ」への批判です。
せっかくの大きな構想なら、司馬さんが愛したように、「この国がより良くなるための大風呂敷」を広げ、堂々と「日本の第二の心臓を作る」くらいの意気込みで進めるべきだ、というメッセージが込められています。

3. 関西のエネルギー!新たな時代の幕開けは西から
コラムの結びには、「思えば新たな時代の幕開けはいつも西からやってきた」という、ロマンあふれる言葉があります。
- 古代から近代まで、文化や政治の中心は西日本から興り、東へと伝播してきました。
- 近年、万博や阪神(タイガース)の活躍、連立政権を巡る政治的な役割など、関西が注目を集める機会が増えています。
東京一極集中が長く続いた日本において、関西の持つ独自の文化、経済力、そして人を引きつけるエネルギーは、日本全体をもう一度活性化させる大きな力となるはずです。
私たち女性は、新しい変化や暮らしやすさに敏感です。
| 変化の期待 | 地方創生のロマン |
| 新しい働き方 | 東京以外にも国の中枢機能が分散されれば、働く場所の選択肢が広がり、地方でのキャリア形成がしやすくなります。 |
| 子育て・生活環境 | 過密でない地方で、より豊かな自然やゆとりのある生活環境の中で子育てや生活ができる可能性が高まります。 |
| 文化の多様性 | 個性豊かな地方都市がさらに発展することで、多様な文化や価値観が育まれ、日本全体の魅力が増します。 |
「副首都構想」が単なる政治的な駆け引きではなく、司馬さんが見たような「国がより良くなるためのロマンあふれる大風呂敷」として実現することを、私たちも期待したいですね。
💡 まとめ:日本の「都」の未来は私たち次第
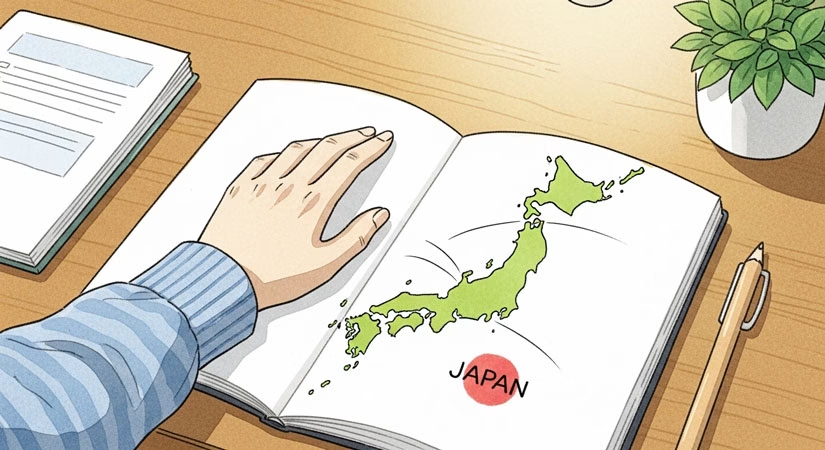
この記事では、
- 明治維新時の「東京遷都」が、政治的配慮と実利から「なし崩し的」に行われたデリケートな決断だったこと。
- 現代の東京が「事実上の首都」でありながら、「首都法」がないという「戦略的あいまいさ」が続いていること。
- 現代の「副首都構想」は、災害リスク分散や経済活性化という大きな目的を秘めながらも、その進め方には「ロマン」が足りないという批判もあること。
を解説しました。
都の位置は、政治家や法律が決めるだけではなく、私たち国民一人ひとりの暮らし、経済、そして未来への夢に直結する大きなテーマです。このデリケートでロマンあふれるテーマに、これからも注目していきましょう。