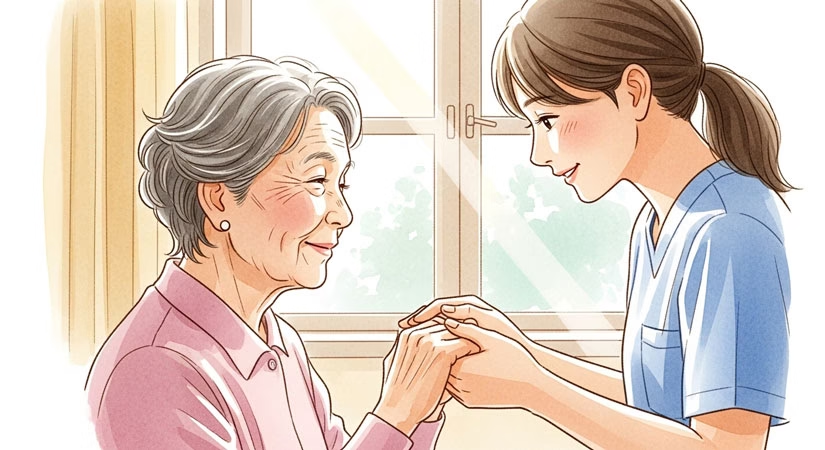日本経済新聞 2025年10月23日(木)朝刊春秋の要約と透析終末期医療の課題
記事作成の背景:日経新聞「春秋」コラムより
突然ですが、あなたは今、人工透析を受けている、あるいは大切なご家族が透析治療を続けているかもしれませんね。
透析は命をつなぐ大切な治療ですが、同時に「もし、この治療が難しくなったら、どうなるんだろう?」という不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
今回の記事は、2025年10月23日の日本経済新聞朝刊「春秋」で取り上げられた、とても重要な問題提起をきっかけに書いています。
コラムでは、作家の堀川惠子さんのノンフィクション「透析を止めた日」が紹介されていました。この本で、人工透析の実情が、ハッとさせられる言葉で表現されています。
「入り口が片道4車線の高速道路だとすれば、出口は歩くことすら難しい畦(あぜ)道だ」。堀川惠子氏は昨年出版したノンフィクション「透析を止めた日」(講談社)で、人工透析の実情をそう評した。夫の死を巡る記録を軸に、この医療について課題を丁寧に記した1冊だ。
腎臓の悪い夫は長く人工透析とともに生きてきた。全身状態の悪化で透析が難しくなると夫婦で「途方にくれた」そうだ。クリニックから切り離されれば医療とのつながりが途絶える。そもそも透析中止後の苦痛に対し、緩和ケアを受ける仕組みがない――。透析の終了から生の終わりまでをみとる医療体制がないと知る。
(有料版日経新聞より引用)
この記事のテーマは、まさにこのコラムが指摘している「透析中止後の苦痛に対する緩和ケアの仕組みがない」という課題です。自分の親や夫、妻、そして自分自身の「もしも」の時に、どうすれば苦痛を和らげ、穏やかな最期を迎えられるのか。そのために今、私たちが知っておくべきことを、一緒に見ていきましょう。
人工透析の「やめどき」:患者と家族が直面する大きな壁
透析を長年続けていると、いつか「やめどき」が来るかもしれない、という漠然とした不安があると思います。でも、「やめる」って、具体的にどういうことなんでしょうか?
透析を「やめる」という選択肢
透析は、腎臓の代わりに血液をきれいにしてくれる、命を守る治療です。だから、治療をやめるというのは、患者さんにとってもご家族にとっても、ものすごく重い決断ですよね。
では、どんな時に「透析を中止する」という選択が浮上するのでしょうか。
誰のための選択? 透析中止が検討される背景
透析を「やめる」という選択肢が検討されるのは、主に次のような状況の時です。
- 全身状態の著しい悪化
- 高齢になり、体力が極度に衰えた時。
- がんや重度の心臓病など、他の重い病気が進行し、透析ベッドまで移動すること自体が大きな負担になった時。
- 透析中に毎回ひどい血圧低下を起こすなど、命に関わるリスクが高くなった時。
- 患者さん自身の意思
- 「もう十分生きたから、これ以上つらい治療はしたくない」という本人の強い希望がある時。
- 透析治療によるメリットよりも、苦痛の方が上回ってしまった時。
この場合、医師は「医学的に透析を継続することが困難」と判断するか、あるいは「患者さんの意思を尊重すべき」と判断し、ご家族と話し合いを進めます。
知っておきたい「透析困難症」
特に医学的な理由で透析が難しくなる状態を、「透析困難症」と呼ぶことがあります。
これは、ただ単に「体調が悪い」というレベルではなく、透析を続けても生命維持が難しくなったり、逆に透析が命を危険にさらすリスクになったりする状態です。
- 例えば、透析中に血圧が極端に下がり、意識を失ってしまう。
- 全身の衰弱が進み、透析のために体位を変えることさえ大きな苦痛になる。
このような状態になると、医療者側も「これ以上は無理だ」という判断をせざるを得なくなります。そして、ご家族は「どうしたらいいんだろう」と途方に暮れてしまうのです。
医療現場の現状:「出口がない高速道路」の例えが示すもの
堀川惠子さんの「入り口は高速道路、出口は畦道」という表現、本当に胸に迫るものがありますよね。

なぜ「出口」が難しいのか?
透析治療のスタート(入り口)は、現代医療の進歩のおかげでスムーズです。透析センターや専門クリニックが「高速道路」のように整備されています。
ところが、透析を中止してからの終末期ケア(出口)については、従来の医療体制に大きな穴がありました。
- 透析施設と緩和ケア施設の連携不足
- 透析クリニックの多くは、透析以外の終末期医療や看取りの設備、体制を持っていません。
- 透析を中止すると、患者さんは「治療を受ける人」から「看取りの段階にある人」へと立場が変わりますが、これまでのクリニックでは、その後の医療を提供できないのです。
- 「医療とのつながりが途絶える」という恐怖
- コラムにあるように、透析をやめると「医療とのつながりが途絶える」と感じてしまう。これが、ご家族にとって一番の恐怖であり、不安です。
- 透析中止後こそ、苦痛を和らげるための医療が必要なのに、「もう診てもらえないの?」という不安に襲われてしまうのです。
家族の声:「準備不足だったわけではなかった」
コラムの筆者の方も、「わが家だけが特に準備不足や無知だったわけではないとわかり、少しだけ救われた」と書かれています。
これは、多くの透析患者さんのご家族が抱える共通の思いです。「もっと早く知っていれば」「何かできたんじゃないか」と自責の念にかられる方が本当に多いんです。
でも、それはご家族のせいではありません。これまで、「透析中止後の緩和ケア」という医療体制が、社会全体で整備されていなかったことが大きな原因なのです。だからこそ、今からこの情報を知り、準備をすることが大切になってきます。
知っておきたい透析中止後のからだと心の変化
透析を中止すると、体はどのように変化していくのでしょうか。この変化を知っておくことは、ご本人とご家族が安心して過ごすための第一歩です。
透析中止後に起こる主な症状
透析をやめると、腎臓が老廃物や余分な水分を排出できなくなるため、体内にこれらが溜まっていきます。これによって、様々な苦痛が生じます。
| 症状 | なぜ起こるの?(原因) | ご家族が知っておきたいこと |
| むくみ・息苦しさ | 余分な水分が排出されず、肺に水が溜まる(肺水腫)ため。 | 息苦しさが強い場合は、医療的な処置(薬や酸素)で和らげられます。 |
| 吐き気・嘔吐 | 尿毒症物質(老廃物)が体内に溜まり、脳の嘔吐中枢を刺激するため。 | 無理に食事をとらなくても大丈夫です。吐き気止めで楽にできます。 |
| 痛み・けいれん | 老廃物の影響や、全身の衰弱によるもの。 | 痛みは必ず和らげられます。我慢せず、緩和ケアチームに伝えましょう。 |
| 意識レベルの低下 | 尿毒症の進行により、意識がぼんやりしたり、眠っている時間が長くなったりします。 | 苦しんでいるわけではありません。安楽に過ごしている状態です。 |
緩和ケアが「必要」とされる理由:苦痛は必ず和らげられる
これらの症状を聞くと、「すごくつらそう…」と不安になるかもしれません。でも、心配しないでください。緩和ケアの目的は、まさにこれらの苦痛を和らげ、患者さんが最期まで「その人らしく」過ごせるようにすることなのです。
緩和ケアは「がんだけ」じゃない!
緩和ケアというと、「がんの終末期」というイメージが強いかもしれません。しかし、世界保健機関(WHO)の定義では、緩和ケアは「生命を脅かす病気を持つすべての方」のために行われるべきものです。
腎不全も、心不全も、難病も、適切な緩和ケアを受ける権利が患者さんにはあります。
なぜ専門的なケアが必要なの?
透析中止後の症状は、通常の風邪や病気の時の苦痛とは違います。
- 老廃物が原因なので、普通の痛み止めでは効きにくいことがあります。
- 水分や電解質のバランスが崩れているため、薬の量や種類を細かく調整しないと、かえって体に負担をかけてしまうことがあります。
だからこそ、透析の知識と緩和ケアの知識、両方を持った専門家によるサポートが必要不可欠なのです。
透析患者さんのための緩和ケアとは?
ここからは、透析患者さんが受ける「特別な緩和ケア」について、もう少し詳しく見ていきましょう。
緩和ケアの基本:からだと心のつらさを支える
緩和ケアは、単なる延命治療の終了ではありません。残された時間を、いかに質の高いものにするかを目指すケアです。
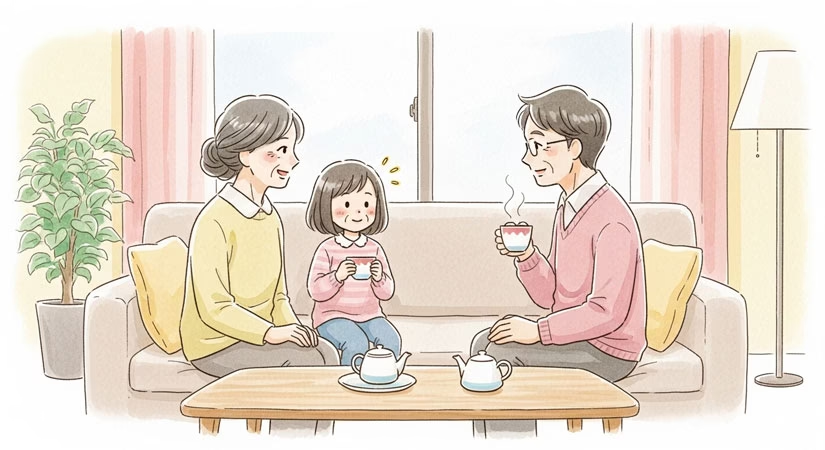
緩和ケアの多角的サポート
緩和ケアでは、患者さんの「つらい」と感じることを、身体面だけでなく、精神面、社会面など、多方面からサポートしていきます。
| つらさの種類 | 緩和ケアの主な役割 |
| 身体的な苦痛 | 痛み、息苦しさ、吐き気などの症状を和らげる薬の調整や処置。 |
| 精神的なつらさ | 不安、落ち込み、恐怖心など、心の状態を聴き、寄り添うカウンセリング。 |
| 社会的な悩み | 医療費、介護体制、退院後の生活の不安などを、ソーシャルワーカーが解決するサポート。 |
| スピリチュアルな苦痛 | 「なぜ私が」「生きる意味は」といった、根源的な問いや心の叫びを、そのまま受け止める。 |
透析患者さん特有のケアの重要性:薬のプロによる調整
透析患者さんの緩和ケアで特に重要なのは、薬の調整です。
腎臓が機能していないため、体から排出されるはずの薬の成分が、体内に残りすぎてしまう可能性があります。
専門薬剤師の存在
- 例えば、強い痛み止めである「医療用麻薬」を使う際、腎機能が悪い患者さんには、腎臓への負担が少ない種類の薬を選んだり、使う量を通常の何分の一かに減らしたりする慎重な調整が必要です。
- この調整には、腎臓病の知識と緩和ケアの知識を両方持った専門の医師や薬剤師(緩和薬物療法認定薬剤師など)が欠かせません。
「痛みを我慢する必要は絶対にない」と専門家は言います。適切な薬と量で、苦痛は和らげられます。「緩和ケアを受けても、透析中止後の苦痛は消えないのでは?」という不安は、どうぞ手放してくださいね。
多くの専門職によるチーム連携
あなたのつらさ、ご家族の不安を一人で抱え込ませないために、緩和ケアはチームで行われます。
- 医師:薬の処方や病状の説明。
- 看護師:日常的なケア、苦痛の訴えの傾聴、ご家族の精神的サポート。
- 薬剤師:薬の量や種類を正確に調整し、安全性を確保。
- ソーシャルワーカー:入院・退院先の調整や公的な制度(介護保険など)の利用支援。
このチームが、ご本人とご家族をしっかりと包み込むことで、「畦道」を進む不安を少しでも和らげてくれるはずです。
新しい動き:腎不全患者さんの緩和ケアの手引
長年、「出口がない」と言われ続けてきたこの問題に、いよいよ大きな光が差し込んできました。それが、日経新聞のコラムでも紹介されていた「緩和ケアの手引」の公表です。

長年の課題に対する国の動き
「必要性が認識されながらも、十分に普及してこなかった」腎不全の緩和ケア。なぜ、今、大きく動き出したのでしょうか。
- 患者さんとご家族の切実な声:堀川惠子さんの著作のように、多くの方が経験した「途方に暮れた」経験や「右往左往」した苦い思い出が、世論を動かしました。
- 医療者の倫理的なジレンマ:「苦しむ患者さんを、十分なケアなしに看取らなければならない」という医療現場の葛藤も、手引作成を後押ししました。
腎不全患者の緩和ケアの手引(ガイドライン)とは
先日、日本緩和医療学会や日本腎臓学会など、複数の専門学会が協力して、「腎不全患者の緩和ケアに関する手引き」が公表されました。
手引がもたらす最大の意義
この手引ができたことで、医療の現場は大きく変わることが期待されます。
| 変化のポイント | 以前(手引ができるまで) | 今後(手引の普及後) |
| 医療者の共通認識 | 腎不全の緩和ケアの方法が、病院や医師によってバラバラだった。 | 全国どこでも、ある程度統一された適切なケアが提供されるようになる。 |
| ケアの開始時期 | 「透析中止が決まってから」慌てて緩和ケアを探し始めることが多かった。 | 透析中から、将来を見据えた緩和ケアの計画を立てられるようになる。 |
| 看取りの場所 | 透析クリニックでは看取れないため、転院・退院を繰り返すことが多かった。 | 透析施設と、緩和ケア専門施設との連携がスムーズになり、患者さんの希望に応じた場所で看取れる体制が整う。 |
特に重要なのは、「透析中止後の看取り」について、医療側がどう対処すべきかの具体的な指針が示されたことです。この指針があることで、「どこにも行くところがない」という不安が少しずつ解消されていくでしょう。
私たちが期待できること
「費用だけでなく中身の改革も望みたい」とコラムの筆者は結んでいます。私たち患者や家族がすべきことは、この新しい手引が活用されているか、積極的に医療者に尋ねることです。
- 「先生、腎不全の緩和ケアの手引について、どうお考えですか?」
- 「もしもの時、こちらの病院(クリニック)では緩和ケアチームと連携してもらえますか?」
こうした質問が、医療機関の体制整備をさらに促す力になるはずです。
患者と家族のための「もしもの時」の備えと相談先
「途方に暮れる」状況を避けるために、私たちにできる最大の準備は、「話し合い」と「情報の収集」です。
大切な話し合い:ACP(アドバンス・ケア・プランニング)
「将来、体が弱って自分で意思を伝えられなくなった時、どうしたいか」をあらかじめ決めておくことを、ACP(アドバンス・ケア・プランニング)、または人生会議と呼びます。
透析患者さんにとって、この人生会議は、ただの「希望調査」ではなく、「最期の安心」を手に入れるための具体的なプロセスです。
なぜACPが必要なの?
透析治療は、時に突然、継続が難しくなることがあります。その時になって、ご家族が「本人はどう思っているんだろう…」と悩むことほど辛いことはありません。

- ご家族の負担軽減:事前に本人の意思が分かっていれば、ご家族は自信を持って医療者と話し合いを進められます。
- 後悔の軽減:コラムの筆者のように「右往左往が苦い思い出」になることを防ぎ、「できる限りのことはした」という納得感が残ります。
ACPで話し合うべき具体的な内容
元気なうち、あるいはまだ体力があるうちに、次のことを話し合っておきましょう。
- 透析中止の意思
- 全身状態が極度に悪化した場合、延命のための透析を続けるか。
- 苦痛や延命よりも、QOL(生活の質)を優先したいか。
- 看取りの場所の希望
- 自宅で最期を迎えたいか。
- 緩和ケア病棟やホスピス、病院を希望するか。
- 苦痛緩和の希望
- 痛みが強い場合、意識がぼんやりしても良いから、強い薬(医療用麻薬など)を使ってでも痛みを和らげたいか。
- 医療の代理決定者
- 自分の意思を伝えられなくなった時、誰に自分の代わりに意思決定を任せるか。
この話し合いの結果を、可能であれば書面(リビングウィルなど)に残し、医師やご家族と共有しておくことが大切です。
家族が「途方に暮れない」ための相談先
一人で悩まず、必ず専門家を頼りましょう。適切な相談先を知っていることが、何よりも力になります。
| 相談先 | どんな時に相談する? |
| 現在の主治医・看護師 | 病状の見通し、ACPの相談をしたい時。この病院(クリニック)で、もしもの時のサポート体制があるかを確認したい時。 |
| 医療ソーシャルワーカー(MSW) | 介護サービス、退院後の生活、医療費の不安、次の施設(緩和ケア病棟など)を探したい時。 |
| 地域連携室 | かかりつけのクリニックから、入院や専門施設への紹介をお願いしたい時。 |
| 地域包括支援センター | 在宅での生活が難しくなった時、介護保険や地域のサービスについて相談したい時。(特に高齢の方) |
口コミ例:ソーシャルワーカーさんの存在に救われた
「父の透析中止が決まった時、頭が真っ白になりました。でも、病院のソーシャルワーカーさんが、自宅近くの訪問診療をしてくれるクリニックや、緩和ケア専門の病院の情報を、すべて調べてリストにしてくれました。あの時、一人じゃなかったと思えて、本当に助かりました」(50代女性・主婦)
このように、医療と介護の制度、そして次のステップへの道筋を知っている専門家が、あなたの強い味方になってくれます。
終わりに:準備と知識が家族の「救い」に

長時間の記事を最後まで読んでくださり、ありがとうございます。とても重く、センシティブなテーマでしたが、一歩踏み込んで一緒に考えてくださったこと、本当に感謝しています。
日経新聞のコラムの筆者の方が感じた「救い」のように、
- 「課題は個人のせいではなく、医療体制の問題だった」と知ること。
- 「今、新しい手引によって体制が変わろうとしている」と知ること。
- 「何を話し合い、どこに相談すればいいか」という具体的な道筋を知ること。
これらは、これから先、あなたやあなたの大切なご家族が、不安な「畦道」を歩む際の、確かな道しるべになります。
透析の終末期医療について、情報を得ることは、決して「縁起でもないこと」ではありません。それは、大切な人の最期を穏やかに見送るために、私たちができる愛と責任ある準備なのです。
どうか、この記事が、ご家族で率直に話し合うための、優しいきっかけとなりますように。