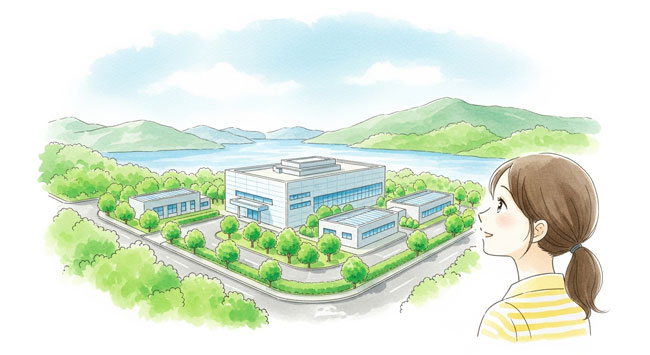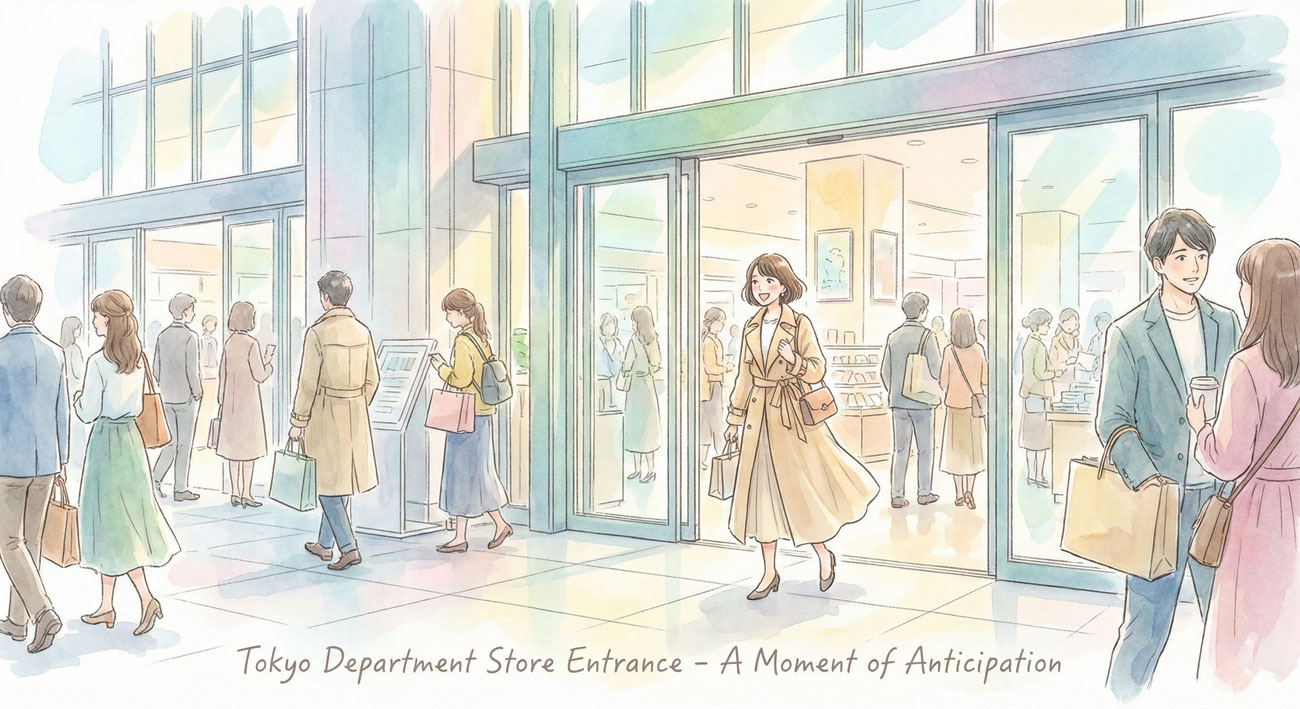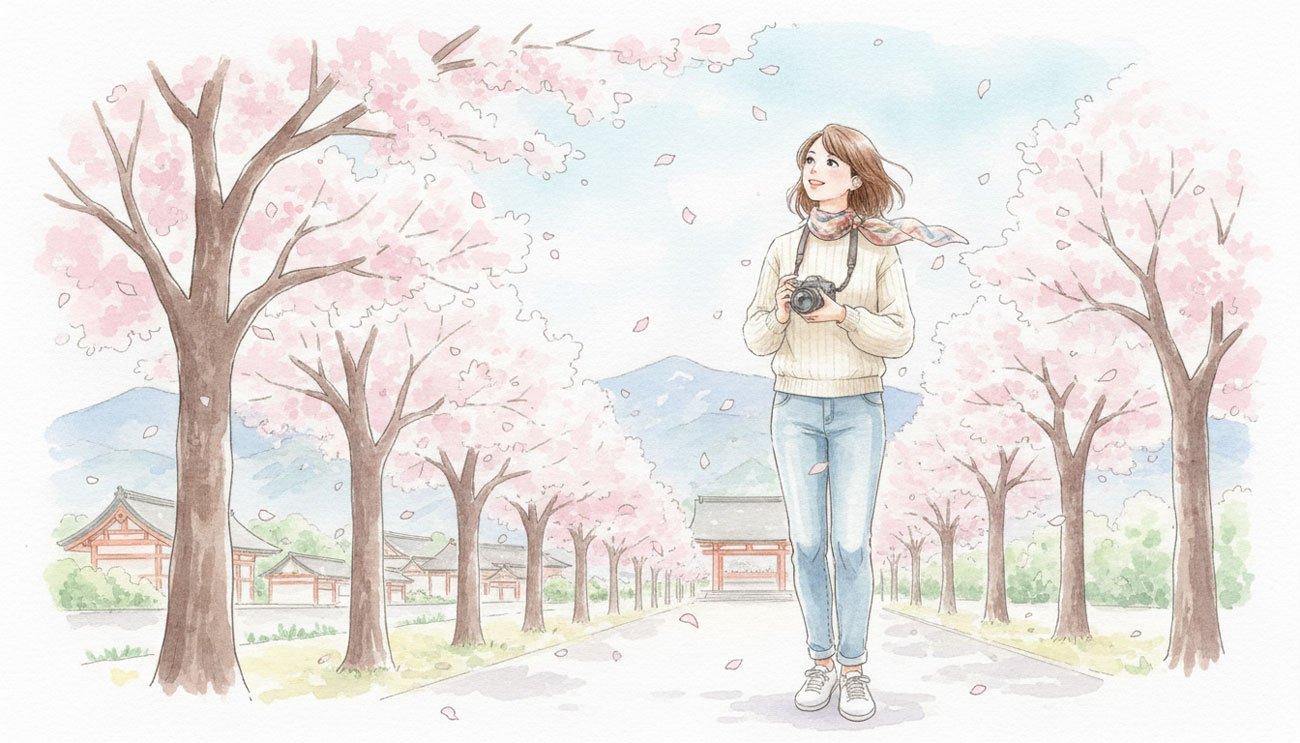🗓️日本経済新聞 2025年9月17日(水)朝刊春秋の要約と社会の多様性と政治のあり方
こんにちは!日経新聞の「春秋」って、たまにすごく心に残るコラムがありますよね。先日掲載されたコラムは、連休中に見たという世界陸上のマラソンレースの様子から、今の社会や政治について語られていて、とても考えさせられる内容でした。
今回は、そのコラムの内容を一緒に掘り下げながら、私たちが感じていることや、これからどうしていくべきかについて、お話ししていきたいと思います。
引用: 日本経済新聞 朝刊「春秋」
連休中、世界陸上のマラソンレースを沿道で見た。しなやかにくるくる回る脚。ぶれぬ体幹には鋼の芯でも入っていそうだ。コロナ禍のような応援自粛要請もなく、都心のコース沿いは幾重もの人垣で埋まっていた。目の前をランナーが通るたび、拍手と歓声があがる。
▼上位集団から遅れ、一人旅になった選手にも熱い声援が飛んだ。「メヒコ!メヒコ!」。大声で励まされたメキシコの選手は口元を緩め、手を上げて応じた。肌の色も国籍も分け隔てなく、皆が一心にエールを送る。そんな場の空気に普段以上に爽やかさを覚えたのは、このところ排外的な話題に接する機会が多いゆえか。
🏃♀️国境を越えた感動!世界陸上マラソンが教えてくれたこと
世界陸上ってどんな大会?
世界陸上って、テレビでしか見たことがない人も多いかもしれませんね。陸上競技の世界一を決める大会で、オリンピックと並ぶくらい権威のある大きな大会なんです。その中でも、マラソンは特に多くの人に注目される花形種目の一つ。
マラソンの魅力って何?

マラソンって、ただ走るだけじゃない、まるで人生そのものを見ているような感動がありますよね。
- 人間ドラマが詰まっている: 42.195kmという長い距離を、トップランナーでも2時間ちょっと、私たち一般ランナーなら何時間もかけて走り抜きます。速く走る選手もいれば、途中で苦しんで、もうダメか…と思うような選手もいる。でも、歯を食いしばってゴールを目指す姿に、私たちは心を動かされるんです。
- 応援がダイレクトに届く: マラソンコースって、普通に私たちが歩いている道路が使われます。だから、テレビで見るのとは違って、選手を間近で応援できるのが大きな魅力。手を伸ばせば届きそうな距離で「頑張れ!」って声をかけると、選手と目が合って、笑顔で応えてくれることもあります。その瞬間って、本当に感動しますよ。
- 国境や人種を超えた一体感: 今回のコラムにもあったように、沿道の観客は、日本の選手だけでなく、上位から遅れてしまったメキシコの選手にも、惜しみない拍手と声援を送っていました。肌の色も、国籍も関係なく、頑張っている人にはみんなでエールを送る。そういう場所って、今の社会ではなかなか見られないからこそ、余計に心に響くんですよね。
この「国境や人種を超えた一体感」って、どうしてこんなに清々しい気持ちになるんでしょう?
それは、私たちが普段、ニュースなどで「排外的な話題」に触れる機会が増えているからかもしれません。特定の国の人を悪く言ったり、よそ者扱いしたりするような話を聞くと、心がザワザワしますよね。そんな中で、マラソンの沿道で見られるような、純粋に「頑張る人」を応援する温かい空気に触れると、「ああ、本来の社会ってこうだよね」って、改めて気づかされるのかもしれません。
なぜ応援が心に響くの?
マラソンを走る選手への応援って、本当に不思議な力を持っています。選手にとってはもちろん、応援する私たちにとっても、心が満たされるような感覚がありますよね。
- 共感と連帯感: マラソンは「孤独な戦い」と言われますが、沿道の応援は、その孤独を和らげてくれます。応援する側も、自分を選手に重ねて、「私も頑張ろう!」と元気をもらったり、同じ場所で応援している人たちとの連帯感を感じたりします。
- 純粋な応援: 勝敗だけではない、純粋に努力を称える気持ちが、選手にも、私たちにも温かい気持ちをもたらします。例えば、トップランナーに負けてしまったとしても、最後まで走り抜いた選手に送られる拍手は、その選手の努力や勇気を讃えるものです。これは、私たちの社会で一番大切にすべきことの一つですよね。
🇯🇵政治に求められる「芯の太さ」とは?
コラムの話題は、世界陸上から日本の政治へと移ります。一見、全く違う話に聞こえますが、筆者はここに一つの共通点を見出しています。それは、マラソン選手の「ぶれぬ体幹」のように、政治家にも「芯の太さ」が求められる、ということです。

政治とマラソン、意外な共通点
マラソン選手が、どんなに苦しい局面でも、姿勢を崩さず走り続けるには、強い体幹が必要です。政治家も同じで、どんなに厳しい状況でも、社会の不安に正面から向き合い、責任を持って行動するには、「芯の太さ」が不可欠なんです。
- 「一人旅」の覚悟: マラソンで上位集団から遅れても、一人で走り続ける選手がいるように、政治家にも、たとえ孤立しても、国民のために信念を貫き通す覚悟が必要だということでしょう。
過去の自民党と総裁選
コラムでは、1991年の世界陸上東京大会と、当時の首相だった海部俊樹氏について触れられています。なぜ、突然過去の話が出てくるのでしょうか?
それは、当時の政治状況と今の状況がどこか似ているからかもしれません。1991年は、ちょうどバブルが崩壊し、日本経済が大きな岐路に立っていた時代です。そして、今の日本も、少子高齢化や経済の停滞など、さまざまな課題を抱えています。
1991年の歴史的背景
- 世界陸上東京開催: この年は、日本で初めて世界陸上が開催され、マラソンでは谷口浩美選手が見事優勝しました。日本中が沸いた、とても感動的な出来事でしたね。
- 海部政権: 谷口選手に金メダルを授与した海部首相は、実は党内での支持基盤が弱かったんです。そのため、わずか1年ちょっとで退陣に追い込まれてしまいました。その後、後継の宮沢政権も、後に自民党が初めて政権の座を降りる(下野する)という歴史的な出来事を経験します。
| 年 | 出来事 | 政治の動き |
| 1991年 | 世界陸上東京開催 谷口浩美選手が優勝 | 海部内閣が退陣 宮沢内閣が発足 |
| 1993年 | 宮沢内閣が総辞職<br>自民党が下野し、非自民政権が誕生 |
この話からわかるのは、政治のリーダーが国民にどう映るかが、政権の運命を左右するということです。どんなに立派な政策を掲げても、国民の不安に寄り添い、信頼を得られなければ、支持は離れていってしまいます。
私たちが政治に期待すること

コラムの筆者は、今の政治に「社会がどうもおかしな方向へ行こうとしてはいないか」という不安に正面から応える「芯の太さ」を期待しています。これは私たち多くの国民が感じていることかもしれません。
例えば、最近の政治のニュースを見ていると、どうしても「誰が勝った、負けた」という権力争いに見えたり、国民の暮らしと直接関係のない話ばかりが取り上げられたりして、「本当に私たちのことを考えてくれているのかな?」と不安になることがありますよね。
私たちが政治家に求める「芯の太さ」って、具体的にはどんなことなのでしょうか?
- 誠実さ: どんなに言葉を飾っても、心からの誠実さがなければ、国民の心には響きません。
- 行動力: 不安を解消するために、具体的にどんな行動を起こすのか。口先だけでなく、実行できる人が信頼されます。
- 包容力: 自分と違う意見を持つ人たちの声にも耳を傾け、社会全体をより良い方向に導こうとする包容力。
これらの資質を持つリーダーこそ、今の私たちが本当に求めているのではないでしょうか。
💡まとめ:私たちが作る社会の未来

今回の「春秋」のコラムは、世界陸上というスポーツイベントを通して、私たちの社会や政治について深く考えるきっかけを与えてくれました。
- マラソン: 目の前で頑張る人を応援し、国境を越えた連帯感を味わう場。
- 政治: 社会の不安に正面から向き合い、「芯の太さ」をもって責任を果たす人を求める場。
どちらにも共通しているのは、私たちが「どうありたいか」を映し出す鏡のような存在だということです。多様性を認め、お互いを尊重し、そしてより良い未来を築くために、私たち一人ひとりができることはたくさんあります。





![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4c6fd410.3d86dff2.4c6fd411.e3bbcc28/?me_id=1430033&item_id=10000000&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Flaqunstore%2Fcabinet%2Flaqun2%2Fmain2507.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)