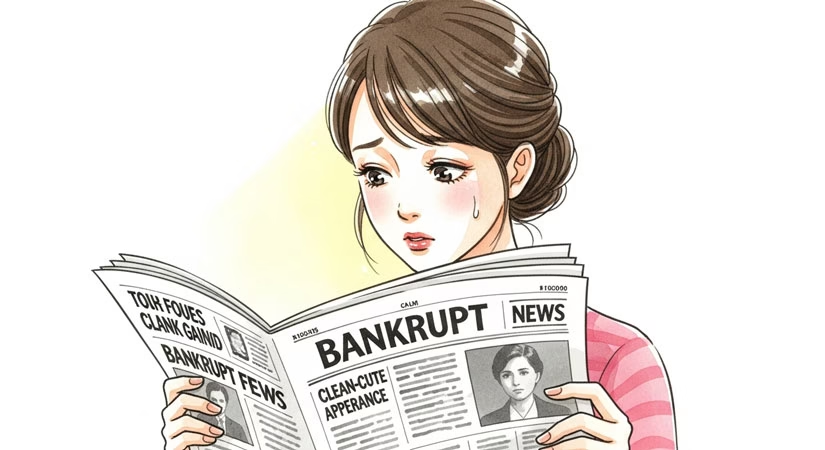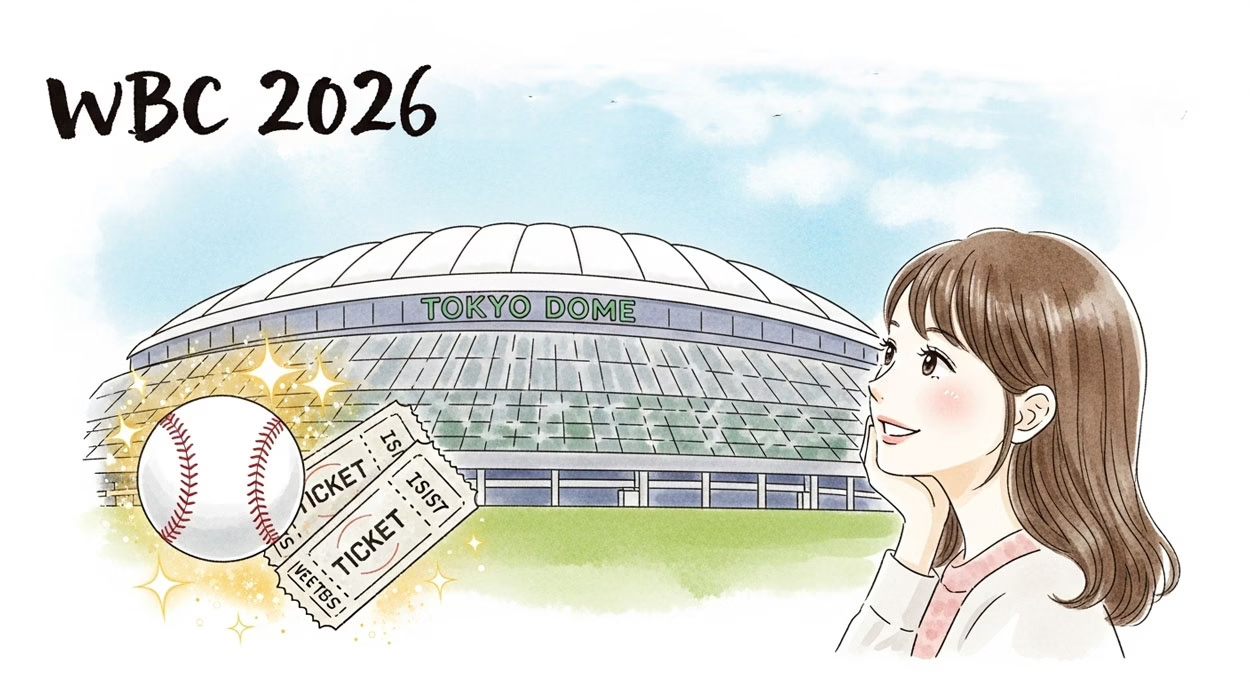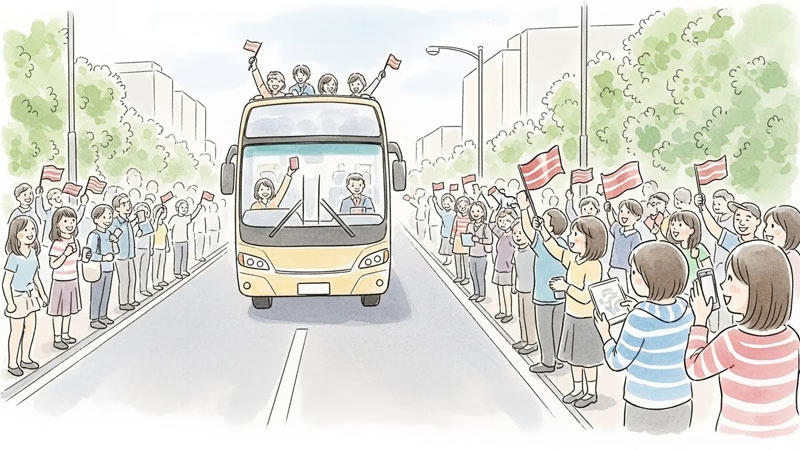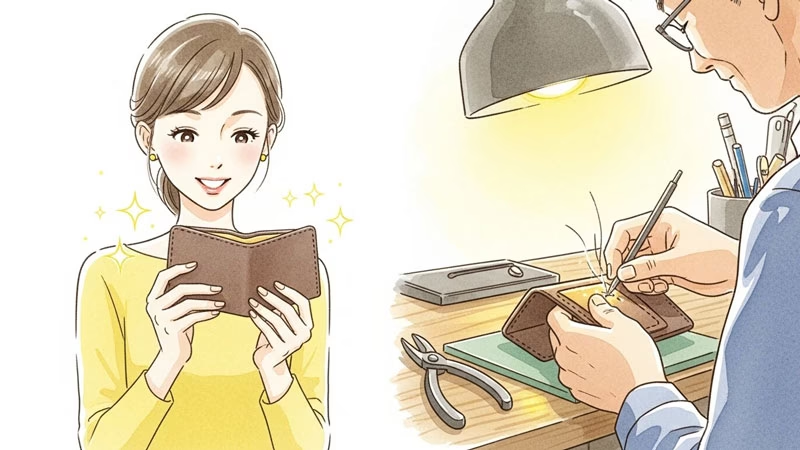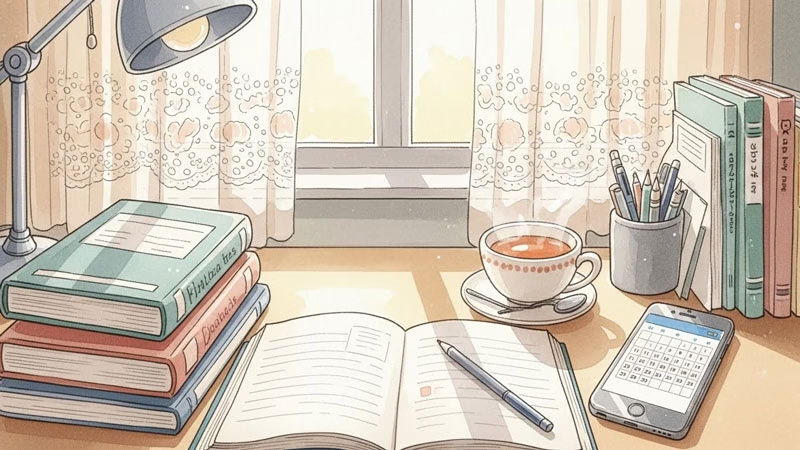日本経済新聞 2025年11月11日(火)夕刊明日への話題の要約と金融危機対応の歩み
1997年11月3日の三洋証券破綻を皮切りに、17日北海道拓殖銀行破綻、24日山一証券自主廃業発表、26日仙台の徳陽シティ銀行破綻と連鎖した。当時、大蔵省銀行局で預金保険制度担当として渦中にいた。邦銀が調達するドル金利は大きく上昇し、調達できないとの連絡が殺到した。銀行の取り付け騒ぎの経験は誰にもなく、皆すごく不安だった。
銀行の経営悪化が最終局面になると資金繰りに窮してくる。国債などの担保があれば日銀が融資する。毎晩、日銀と銀行局の担当者があと何日持つか議論している。もうだめとなれば合併などの相手を見つけ「破綻」を発表、預金保険料を原資として預金保険機構から資金供与が決まる。それを担保に日銀が融資を行い、預金は全額保護され取引先への融資も継続される仕組みだ。
🔍 この記事を読み進めるためのキーワード
今回のコラムは、1997年11月を起点とする日本の金融危機とその対応について書かれています。
この記事に関心を持つ方は、当時の状況や、それを乗り越えるために作られた今の「お金を守る仕組み」についての内容です。
| キーワード | 概要 | 読者の主な関心事 |
| 1997年金融危機 | 三洋証券、北海道拓殖銀行、山一証券などが破綻・自主廃業した一連の出来事。 | どんなことが起こったのか、当時の社会の様子。 |
| 山一証券 | 「自主廃業」という異例の形で市場から姿を消した大手証券会社。 | なぜ自主廃業を選んだのか、その影響。 |
| 北海道拓殖銀行 | 戦後初の都市銀行の破綻。 | 都市銀行が破綻する衝撃、預金はどうなったのか。 |
| 金融国会 | 1998年に金融危機対応の法律を成立させるために開かれた国会。 | どんな法律が作られたのか、危機対応の具体策。 |
| 預金保険制度 | 銀行が破綻した際に、預金者を保護するための公的な仕組み。 | 自分の預金は守られるのか、現在の保護範囲。 |
| 公的資金注入 | 銀行の資本を強化し、破綻を防ぐために国のお金を投入すること。 | なぜ税金が使われたのか、効果はあったのか。 |
🌸 知っておきたい!1997年「金融危機」連鎖の衝撃
1997年11月の「まさか」の連鎖とは?
1997年の秋、日本の金融界に衝撃が走りました。立て続けに大手金融機関の破綻や自主廃業が発表されたのです。まるでドミノ倒しのように次々と危機が表面化し、「日本のお金を守る仕組みは大丈夫なの?」という不安が、社会全体を覆いました。
特に、北海道拓殖銀行のような大きな銀行や、山一証券のような大手証券会社が経営を続けられなくなったことは、「まさかこんなことが起こるなんて」と当時の人々に大きな衝撃を与えました。
立て続けに起こった金融機関の破綻・自主廃業
| 日付 | 金融機関名 | 事象 | 影響 |
| 11月3日 | 三洋証券 | 破綻 | 危機連鎖の始まり。 |
| 11月17日 | 北海道拓殖銀行 | 破綻 | 戦後初の都市銀行破綻。 |
| 11月24日 | 山一証券 | 自主廃業発表 | 大手証券の自主廃業という異例の事態。 |
| 11月26日 | 徳陽シティ銀行 | 破綻 | 地方銀行にも波及。 |
「取り付け騒ぎ」の不安とドル調達の危機
コラムにもある通り、当時、現場で働く人々の不安は計り知れないものでした。
1. 誰も経験したことのない「不安」
- 「取り付け騒ぎ」の恐怖:銀行の経営が危ないと聞くと、預金者が一斉に自分の預金を引き出そうと銀行に押し寄せる現象を「取り付け騒ぎ」といいます。当時は、この事態を実際に経験した人が少なく、「もしそうなったらどうなるのか」という見えない恐怖がありました。
- 現場の緊迫感:コラムでは、大蔵省(現在の財務省)の担当者が、破綻する銀行の「資金繰りがあと何日持つか」を毎晩、日本銀行(日銀)と議論していたとあります。これは、まさに時間との闘いだったことを示しています。
2. ドル金利急騰という「国際的な危機」
日本の銀行は、海外との取引のためにドル(アメリカのお金)を調達しています。しかし、日本の銀行が次々と破綻するかもしれないというニュースが世界に広がると、海外の金融機関は日本の銀行にお金を貸すことに非常に慎重になりました。
その結果、邦銀がドルを借りる際の金利が大きく上昇し、「ドルが調達できない」という事態に陥りました。これは、日本の金融危機が国内だけの問題ではなく、世界経済に影響を与えかねない、国際的な信用問題に発展していたことを意味します。
🏦 危機を乗り越えるために作られた「お金の安心」の仕組み
コラムには、金融機関の破綻時に預金を保護し、経済の混乱を防ぐための仕組みが描かれています。この仕組みこそが、私たちが今、安心して銀行にお金を預けられる根拠となっています。
破綻時の緊急対応フロー
銀行が経営破綻という「最終局面」に至った際の対応は、次のステップで進められます。
| ステップ | 実施機関 | 内容 | 目的 |
| 1. 資金繰りの確認 | 日銀・銀行局 | 銀行の資金が「あと何日持つか」を最終確認。 | 破綻のタイミングを見極める。 |
| 2. 受け皿探しと破綻発表 | 破綻処理担当者 | 合併相手(受け皿)を見つけ、「破綻」を公に発表。 | 預金者や取引先に迅速に情報を公開する。 |
| 3. 資金供与の決定 | 預金保険機構 | 預金保険料を原資として資金提供を決定。 | 預金者保護の財源を確保する。 |
| 4. 日銀による融資 | 日本銀行(日銀) | 預金保険機構からの資金供与を担保に、日銀が緊急融資。 | 預金の払い戻しを可能にし、取り付け騒ぎを防ぐ。 |
| 5. 事業の継続 | 合併相手または受け皿銀行 | 預金は全額保護され、取引先への融資も継続。 | 経済活動の混乱を最小限に抑える。 |
「預金保険機構」と「ペイオフ」の役割
私たちが銀行に預けているお金は、銀行が万が一破綻しても「預金保険制度」によって守られています。
預金保険制度とは?
銀行などの金融機関が、毎年「保険料」を出し合い、それを預金保険機構という組織が管理しています。この保険料を元手に、金融機関が破綻した際に預金者に保険金が支払われる仕組みです。
| 項目 | 概要 | 備考 |
| 保護の対象 | 当座預金、利息のつかない普通預金など(決済用預金) | 全額保護されます。 |
| 保護の範囲(一般預金) | 利息のつく普通預金、定期預金、貯蓄預金など | 元本1,000万円とその利息までが保護されます。(これを「ペイオフ」といいます) |
※ペイオフが一時凍結されていた時期もありましたが、現在は上記の通りです。この制度のおかげで、私たちは「銀行が潰れてもすべてのお金を失うわけではない」という安心感を得ることができます。
🏛️ 国の仕組みが変わった!「金融国会」で決まったこと
コラムの通り、当初は預金保険料だけでは足りず、国のお金(税金)の投入が必要になりました。この危機を教訓に、日本は「金融危機対応」の仕組みを根本から作り直すことになります。
1. 財源不足と「税金投入」の決断
金融機関の破綻が連鎖すると、預金保険機構の持っているお金だけでは、すべての預金者を守りきれないことが判明しました。
- 預金者保護のための税金投入:国民の財産である預金を守るため、やむを得ず国(政府)のお金、すなわち税金を投入する決断がなされました。これは、国が「金融システムの安定」を最重要課題と位置づけたことを示しています。
2. 「公的資金注入」で未然に防ぐ仕組みへ
破綻してから対応するだけでは遅い、という教訓から、「破綻を未然に防ぐ」ための仕組みも作られました。
- 公的資金注入制度:これは、経営が悪化しそうな銀行に対し、国のお金を一時的に入れて資本を強化し、健全な経営に戻すことを助ける制度です。銀行の「体力」を回復させ、破綻の連鎖を防ぐための予防的な措置です。
3. 受け皿銀行という「奥の手」の登場
もし破綻した銀行を引き継いでくれる合併相手が見つからなかったら?
コラムでは、その時のために「受け皿銀行を一時的に設立する仕組み」が必要になったと述べられています。これは、市場の混乱を避けるための「奥の手」ともいえる措置でした。
- 受け皿銀行の役割:破綻銀行の業務を一時的に引き継ぎ、預金者や取引先への影響を最小限に抑えるための「つなぎ役」として機能します。
4. 1998年「金融国会」と与野党の協力
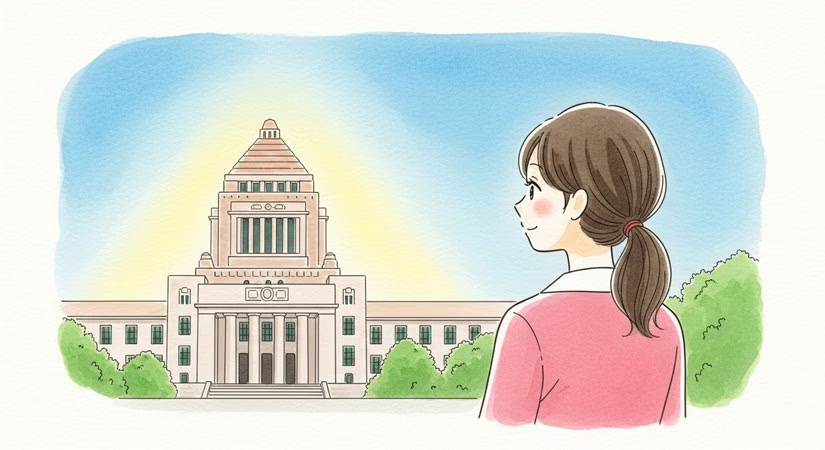
1998年の参議院選挙で自民党が敗北し、国会は与党と野党が拮抗する「ねじれ国会」となりました。この中で、金融危機への対応は待ったなしの状況でした。#
- 異例の協力体制:コラムで印象的に語られているのが、この「金融国会」における国会議員たちの姿です。「国難を乗り切ろう」という強い使命感のもと、与野党の枠を超えて、土日返上や徹夜で議論が重ねられ、金融危機関連法案が成立しました。
- 危機を乗り越えるための団結:この時の「党派を超えた対応」は、日本の政治史においても特筆すべき出来事であり、国家的な危機に際して国民を守るという政治の役割が示されました。
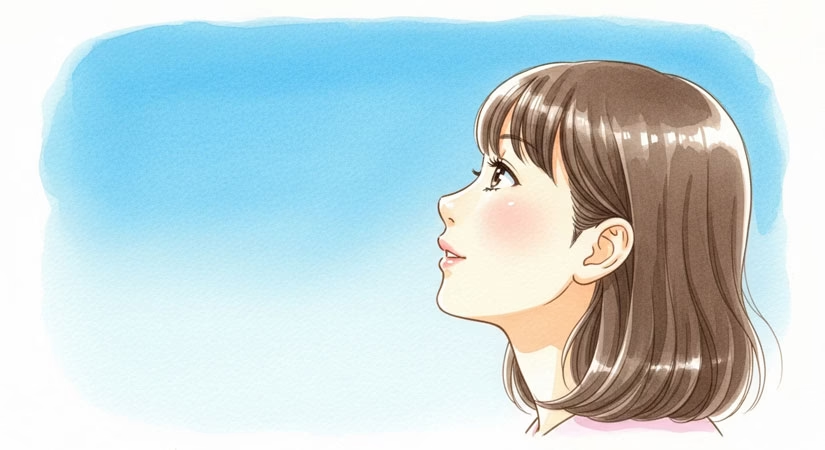
💡 私たちが学ぶべき「お金との付き合い方」
1997年の金融危機は、当時の不安や混乱だけでなく、日本の金融システムをより強く、安定したものに変えるきっかけとなりました。この経験から、私たち自身が学ぶべき教訓は何でしょうか?
1. 「絶対安全」はないことを知る
銀行や証券会社であっても、破綻のリスクはゼロではありません。この事実を認識することが、賢い資産管理の第一歩です。

- 預金保険制度を理解する:自分の預金が「ペイオフ」によって1,000万円と利息まで保護されることを理解し、一つの金融機関に多額の資産を集中させすぎないよう意識しましょう。
- 金融機関の状況に関心を持つ:銀行や証券会社のニュースや経営状況に、無関心でいるのではなく、時々目を向ける習慣をつけましょう。
2. 「分散」の重要性
「一つのカゴにすべての卵を盛るな」という投資の格言があるように、資産を「分散」させることはリスク管理の基本です。
- 複数の金融機関に分ける:預金(1,000万円超)のリスクを避けるために、複数の銀行に分けて預けることも一つの方法です。
- 資産の種類を分ける:預金だけでなく、株式、債券、保険など、性質の異なる資産に分けて保有することで、どこかの危機が起きても全体への影響を小さくできます。

3. 「国難」に立ち向かう人々の努力を忘れない

私たちが今、比較的安心して生活できるのは、1997年当時に危機に直面し、不安の中で必死に対応策を作り上げた現場の担当者や、政治家の方々がいたからです。
- 私たちの「安心」の裏側:コラムに書かれていたように、彼らは家族や自分の時間を犠牲にして、文字通り国を救うために働きました。
- 感謝の気持ちと教訓の継承:過去の教訓を風化させず、今の「お金の安心」の仕組みが、どれほどの努力と議論の末に作り上げられたものかを知り、次の世代に伝えていくことが大切です。