日本経済新聞 2025年9月13日(土)朝刊春秋の要約と秋の静寂と気候変動
今日取り上げるのは、日本経済新聞の朝刊コラム「春秋」(2025年9月13日付)です。
秋という季節が持つ静けさの魅力と、近年増えている異常気象によって揺らぐ季節感について語られています。
四季はそれぞれ固有の魅力で詩人の心を刺激してきた。「秋はしづかに手をあげ/秋はしづかに歩みくる」。明治生まれの詩人、室生犀星の「月草」にある一節だ。照りつける陽光で草木がぐんぐん枝葉を伸ばす濃緑の夏が去り、微風が肌に心地よい季節がやってくる。
▼キーワードは静寂。「見あげていると/すみわたった秋空のどこかで/ぽとん…/という けはいがした」。こちらはまど・みちおの「秋空」から。騒がしさとは無縁の風景。澄んだ空気を伝わる小さな音から、詩のイメージが膨らんでいく。夕暮れ後に虫たちが奏でる合唱が心に響くのも、背景にある静けさゆえだろう。
この記事をもとに、「秋の静けさを味わいたい」「異常気象で季節感が分かりにくい」「秋の恵みを暮らしに取り入れたい」といった読者の悩みに寄り添う形でまとめていきます。
秋がもたらす静寂の魅力
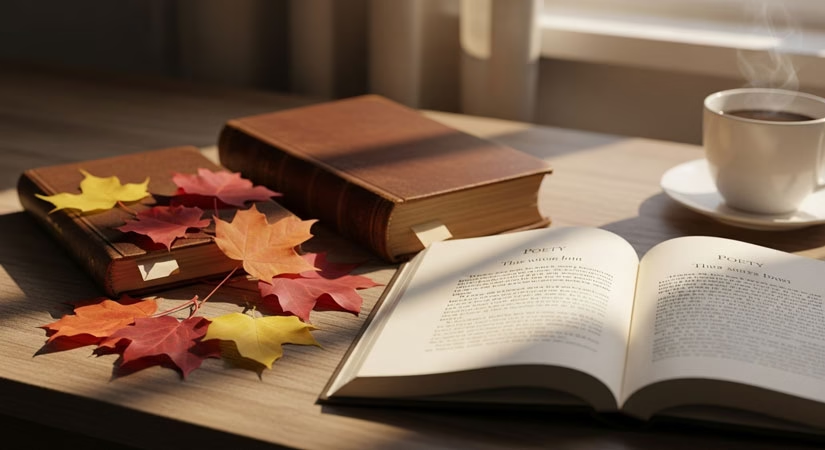
文学に描かれる秋の静けさ
秋の魅力を語るとき、やはり「静けさ」が大きなキーワードになります。
室生犀星の「秋はしづかに手をあげ」という一節からは、秋の訪れがゆっくりとした仕草で描かれているのが伝わります。
また、まど・みちおの「秋空」では「ぽとん…というけはい」という言葉が印象的です。小さな音にまで気づけるほどの澄んだ空気、静けさがあるからこそ想像力が広がっていきます。
文学作品に触れると、普段気づかない秋の細やかな表情に心を向けるきっかけになりますね。
秋の自然が心に与える効果
「静けさって、心に本当に良いの?」と思う方もいるかもしれません。
実際、心理学の研究では、自然の中で過ごすとストレスホルモンの分泌が下がることが分かっています。例えば森林浴をすると、血圧が安定し、気持ちが落ち着くというデータもあります。
秋の空気は澄んでいて深呼吸もしやすいので、夏の疲れを癒すには最適です。夕暮れに耳を澄ませば、虫の音が合唱のように聞こえてきます。都会に住んでいる人でも、少し公園を歩くだけでその雰囲気を味わえます。
女性にとっては、日々の家事や仕事で忙しい中でも「立ち止まる時間」として秋の静けさを取り入れることが心の栄養になります。
異常気象で揺らぐ季節感

最近の大雨・猛暑の記録
ここ数年、ニュースで耳にする「記録的豪雨」という言葉。もはや珍しくなくなっています。
今年の夏も首都圏で川が氾濫し、大きな被害が出ました。気象庁の統計では、ここ10年で1時間に50mm以上の「非常に激しい雨」の発生回数が全国で増えています。
「秋らしい秋がなくなってきている」と感じる人も多いのではないでしょうか。暑さが長引いたかと思えば、突然の大雨や湿気。体も心もついていくのが大変です。
季節のリズムが崩れることの生活への影響
では、この季節感の揺らぎが私たちの生活にどう影響するのでしょうか。
- 服装選びが難しい(朝晩は涼しいのに昼間は暑い)
- エアコンや除湿機の使用が増え、光熱費が上がる
- 野菜や果物の収穫時期がずれることで値段が不安定になる
例えば農林水産省のデータでは、ここ数年サンマやサケの漁獲量が激減しており、「秋の味覚」が例年通りに楽しめないことが増えています。
特に子育て世代や働く女性にとっては、毎日の献立や体調管理に直結するため悩みの種になりやすいですね。
それでも続く秋の恵み
室生犀星が詠んだ「いんげんの爪切り」
コラムでは室生犀星の句「秋をふかみいんげんの爪切りにけり」も紹介されています。
これは友人の堀辰雄から野菜が届いたことをきっかけに詠まれたそうです。小さな日常の中に季節を見つける視点が素敵ですよね。
季節が変わっても、収穫のリズムは続いています。異常気象があっても、農家の方が工夫を重ねて実りを届けてくれるから、私たちは食卓で季節を感じられるのです。

食卓に届く秋の味覚
秋といえば、やはり食欲の秋。
サツマイモや栗、新米などが並ぶと、それだけで心が弾みます。
口コミを見ても、「新米のふっくら感に毎年感動する」「秋の栗ご飯は家族が喜ぶ」といった声が多く聞かれます。食卓に小さな季節の幸せを加えるだけで、毎日の暮らしが豊かになります。
読者の悩みに応える実用情報
異常気象の中で秋を楽しむ工夫

では、「秋を感じたいけれど天気が不安定で難しい」という人はどうすれば良いでしょうか。
具体的にはこんな工夫が役立ちます。
- 大雨や台風シーズンには、折りたたみ傘と防水バッグを常備
- 湿度が高い日は、除湿器やサーキュレーターで空気を循環
- 寒暖差に備えて、薄手のカーディガンをバッグに忍ばせる
ちょっとした準備で「不快さ」を軽減できれば、安心して秋を楽しめます。
静寂を感じる生活アイデア
「忙しくて秋を味わう余裕がない」という方におすすめなのは、身近な中で静けさを感じる工夫です。
- 夜、照明を落として虫の声を聴く
- 朝、窓を開けて冷たい空気を吸い込む
- 1日5分だけでも日記を書いて季節を記録する
こうした習慣は、心をリセットする効果があります。忙しい毎日の中でも、自分だけの「秋の時間」を持つことが大切ですね。
季節とともに変わる心の在り方
秋の静けさがもたらす心のリセット
秋は「整える季節」とも言えます。夏の疲れを癒し、冬に向けて心と体を準備する時期。
静けさの中に身を置くことで、頭の中のざわつきも自然と落ち着きます。
心理学の調査でも、自然音を聞くだけでリラックス効果が得られると報告されています。秋はまさにその「自然音」が身近にあふれる季節です。
気候変動時代にどう向き合うか
もちろん、気候変動の影響で昔のように「きれいな秋空」が毎日広がるとは限りません。
それでも、「少しの秋を見つける工夫」をすることで、季節感を失わずに暮らすことができます。
例えば、
- スーパーで旬の果物を手に取る
- 公園を散歩して木々の色づきを観察する
- 家族と一緒に秋ならではの行事(お月見や芋煮会)を楽しむ
こうした行動が、次の世代に「季節を大事にする心」を伝えることにもつながります。
まとめ

- 秋は静けさの中にこそ魅力がある
- 異常気象が季節感を揺らしても、自然の恵みは続いている
- 暮らしの中で「小さな秋」を意識的に取り入れることが、心を豊かにする
秋は「感じる」季節。
天気に振り回されても、少し工夫をするだけで自分なりの秋を楽しむことができます。
透き通った青空や虫の声を心待ちにしながら、今年の秋を大切に過ごしてみませんか。





![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/34a76934.4e8752af.34a76935.23ae83db/?me_id=1406417&item_id=10000594&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fchakasho-dina%2Fcabinet%2F11797650%2Fsandbag_01.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)




コメント