ねえ、昨日の大河ドラマ『べらぼう』、見ましたか?
ついに物語も佳境に入って、あの謎の絵師「写楽」が登場しましたよね。「えっ、写楽ってあんな描かれ方なの?」「まさかチーム制だったの?」なんて、テレビの前で驚いた方も多いのではないでしょうか。
ドラマの中での解釈、すごく面白かったですよね。蔦屋重三郎たちが仕掛ける一大プロジェクトとしての「写楽」。
でも、見終わった後にふとこう思いませんでしたか?
「これってどこまでが本当の話なんだろう?」
「歴史の教科書で習った写楽と、ドラマの写楽、どっちが真実?」
実は、ドラマは物語を面白くするためのフィクションが含まれていますが、歴史的な研究で有力視されている「真実」も、ドラマに負けないくらいミステリアスで面白いんです。
今日は、ドラマの余韻に浸りつつ、歴史の定説とされている「本当の写楽の正体」と、キーワードとなる「べらぼう」の真実について、分かりやすくお話ししますね。ドラマのネタバレというよりは、ドラマをより深く楽しむための「副読本」として読んでいただけたら嬉しいです。
ドラマと史実はここが違う!写楽=チーム説の真相
まず最初に、皆さんが一番気になっているであろう「写楽の描き方」について整理しておきましょう。
ドラマならではの演出「プロジェクト写楽」
大河ドラマでは、写楽を特定の個人の才能というよりは、蔦屋重三郎を中心とした出版チームが作り上げた「現象」や「プロジェクト」として描く側面があったかと思います。
「写楽」という名前も、「しゃらくさい」という言葉から取ったり、「ありのままを写す楽しみ」という意味を持たせたりと、ドラマチックな意味付けがされていましたよね。
これは、「誰が描いたか」よりも、「なぜ蔦屋重三郎はリスクを冒してまでこの絵を世に出したのか?」という、プロデューサー蔦重の生き様にスポットを当てるための、素晴らしい演出(フィクション)だと言えます。
史実で有力なのは「ある一人の天才」説
では、現実の歴史研究ではどうなっているのでしょうか。
実は、近年の研究では「写楽はチーム名やプロジェクト名」ではなく、「実在したある一人の人物」であるという説が圧倒的に有力なんです。
その人物こそが、阿波徳島藩の能役者・斎藤十郎兵衛(さいとう じゅうろべえ)です。
そして、この斎藤十郎兵衛が、当時の人々から「べらぼう(型破りな人)」と呼ばれていた可能性があるのです。
つまり、ドラマのタイトル『べらぼう』は蔦重の生き様を指していますが、歴史の裏側では、写楽の正体そのものが「べらぼう」だったという、二重の意味が隠されているとも言えるんですね。
ここからは、その史実の「べらぼう」について、詳しく見ていきましょう。
東洲斎写楽とは?彗星のごとく現れた謎の絵師
そもそも、史実としての東洲斎写楽は、どのような活動をしていたのでしょうか。改めてその凄さを振り返ってみると、なぜ200年以上も語り継がれているのかが分かります。
わずか10ヶ月の奇跡
写楽が活動したのは、今から約230年前の江戸時代。寛政6年(1794年)の5月から、翌寛政7年(1795年)の1月まででした。
その期間、なんとわずか10ヶ月間。
この短期間に、写楽は約140点から150点もの作品を残し、忽然と姿を消してしまいました。
まるで誰かから「期限付きのミッション」を与えられたかのように、一気に描き上げて去っていった。このあまりに短い活動期間が、後世の人々に「彼は一体何者だったんだ?」という問いを投げかけ続けているんです。

描いたのは「役者絵」に特化
写楽の作品のほとんどは、当時の歌舞伎役者の肖像画、いわゆる「役者絵」です。
特に有名なのが、役者の顔や上半身を画面いっぱいに大きく描いた「大首絵(おおくびえ)」です。
現代で言えば、人気アイドルの顔をドアップにしたポスターのようなものですね。江戸の人々も、愛する役者の姿を刷った浮世絵を買い求めていました。
しかし、写楽の絵は、それまでの役者絵とは決定的に違う点がありました。
それまでの絵師たちは、役者を美しく、格好良く「盛って」描くのが常識でした。ファンへのサービスですね。
ところが写楽は、役者がふとした瞬間に見せる人間臭さや、顔のシワ、鷲鼻、受け口といった身体的な特徴を、容赦なくリアルに描いたのです。
当時の世評と現代の評価
ドラマの中でも、写楽の絵を見て「なんだこれは!」と驚く人々の様子が描かれていたかもしれませんが、史実でも写楽の絵は賛否両論だったと言われています。
あまりにリアルすぎて、「役者の欠点まで描いている」「美しくない」と酷評されたという記録も残っています。
当時の人々にとって、写楽の絵はあまりに前衛的で、まさに「べらぼう(常識外れ)」な作品だったのでしょう。
しかし、時が経ち、その芸術性は世界で認められることになります。ドイツの心理学者ユリウス・クルトが著書『SHARAKU』で絶賛したことをきっかけに、現在ではレンブラントやベラスケスと並ぶ「世界三大肖像画家」の一人と称されることもあるほどです。
写楽の正体は誰か?「べらぼう」説の真相
さて、ここからが本題です。歴史ミステリーの核心に迫りましょう。
なぜ、「能役者の斎藤十郎兵衛」が写楽の正体(=べらぼう)だと考えられているのでしょうか。
「べらぼう」説の根拠
長年、写楽の正体については、葛飾北斎説、喜多川歌麿説、円山応挙説など、様々な説が飛び交ってきました。しかし、現在最も学術的に有力視されているのが「斎藤十郎兵衛説」です。
その最大の根拠は、江戸時代の考証家が残した記録にあります。
『増補浮世絵類考』という資料に、「写楽は阿波の能役者、斎藤十郎兵衛である」と明確に記されているのです。
さらに、近年の調査で、徳島藩の史料から「斎藤十郎兵衛」という能役者が、写楽が活動していた時期に実在し、江戸の八丁堀(写楽が住んでいたとされる場所)に住んでいたことも裏付けられました。

能役者がなぜ浮世絵を?
でも、不思議に思いませんか? 能面をつけて静かに舞う「能役者」が、なぜ派手な歌舞伎の絵を描いたのでしょうか。
実は、これこそが写楽の絵の特殊性を解く鍵なんです。
- 観察眼の違い能楽師は、面(おもて)のわずかな傾きで感情を表現するプロフェッショナルです。人の動きや内面を観察する目が、常人とは違います。その鋭い観察眼で歌舞伎役者を見たからこそ、表面的な美しさではなく、内面から滲み出る個性を描くことができたのでしょう。
- 副業説活動期間が10ヶ月だったのは、彼が「参勤交代」などで江戸に滞在していた期間だけ活動したから、あるいは藩の仕事が忙しくなって描けなくなったから、という説があります。つまり、写楽はプロの浮世絵師ではなく、「超絶技巧を持ったアマチュア(副業作家)」だった可能性があるのです。
公務員の副業がバレないように、別名(ペンネーム)を使ってこっそり描いていた…なんて想像すると、急に親近感が湧いてきませんか?
「べらぼう」という言葉の意味
当時の江戸で、斎藤十郎兵衛のような人物や、彼の描く型破りな絵を指して「べらぼう」と呼んだのかもしれません。
大河ドラマのタイトル『べらぼう』は、主人公の蔦屋重三郎を指していますが、歴史の文脈では、写楽(斎藤十郎兵衛)の生き方や作品そのものが、当時の常識を打ち破る「べらぼう」な存在だったと言えます。
写楽作品に隠された意図:「べらぼう」的解釈
写楽の作品がなぜこれほどまでに人を惹きつけるのか、その魅力を「べらぼう」的な視点から深掘りしてみましょう。
役者の個性を際立たせた技法
写楽の絵には、写実(リアル)とデフォルメ(誇張)が絶妙なバランスで同居しています。
単に写真のように描くのではなく、役者の「クセ」を強調することで、その人らしさを爆発させているのです。
例えば、意地悪な役なら目つきを極端に鋭く、コミカルな役なら口元を大きく描く。
これは、現代の似顔絵やカリカチュアにも通じる手法です。「ちょっと悪意があるんじゃない?」と思えるギリギリのラインを攻めることで、役者の強烈な個性を焼き付けています。
魂が宿る「眼の表現」
私が個人的に一番注目してほしいのが、写楽が描く「目」です。

瞳の大きさ、黒目の位置、眉の角度。これらをわずかに変えるだけで、役者が演じているキャラクターの「感情」だけでなく、その役者本人の「役者魂」のようなものまで表現されています。
特に、キラリと光る雲母摺(きらずり)という豪華な背景を使った作品では、役者の目がより一層鋭く、まるでこちらを見透かしているかのように感じられます。
ドラマの中で、絵師たちが苦悩しながら役者の顔を見つめるシーンがあったかもしれませんが、まさにあの瞬間、彼らは役者の「魂」を紙に写し取ろうとしていたのでしょう。
現代における写楽ブームの背景
大河ドラマの影響もあり、今また写楽ブームが来ています。なぜ現代の私たちは、200年前の絵にこれほど惹かれるのでしょうか。
感情の普遍性
写楽が描いたのは江戸の役者ですが、そこに描かれている「人間の感情」は、現代の私たちと変わりません。
見栄、嫉妬、悲哀、滑稽さ。
SNSでキラキラした自分を見せようとする一方で、ふとした瞬間に見せる素の表情。写楽の絵には、そんな人間臭さが凝縮されています。だからこそ、時代を超えて共感できるのです。

ブランディングとプロデュースの視点
ドラマ『べらぼう』でも描かれているように、写楽の登場は、蔦屋重三郎による見事な「プロデュース」の結果でもありました。
- 無名の新人をいきなりデビューさせる。
- 豪華な雲母摺(きらずり)を惜しみなく使う。
- 全作品を一挙にリリースして話題をさらう。
これは現代のマーケティング戦略そのものです。「写楽」という謎めいた存在を作り上げ、世間をあっと言わせる。その仕掛け人たちの熱量が、作品を通して伝わってくるからこそ、私たちはワクワクするのかもしれません。
FAQ:読者が疑問に思う点への回答
ここで、ドラマを見た友人と話しているとよく出る疑問について、まとめてお答えしますね。
Q. ドラマのように、写楽は本当にチームで描いていたの?
A. 史実では「個人(斎藤十郎兵衛)」説が濃厚です。
ドラマでは「チーム写楽」のような演出がありましたが、これは物語としての解釈です。筆跡の分析や、当時の記録からは、一人の人物が描いたという見方が一般的です。ただ、版元である蔦屋重三郎や、彫師(ほりし)、摺師(すりし)といった職人たちがチームとして支えていたことは間違いありません。その意味では「チームの結晶」と言えるかもしれませんね。
Q. 写楽は本当に不人気で売れなかったの?
A. 評価は分かれますが、苦戦したのは事実のようです。
当時の浮世絵界は、歌川豊国のような「スマートでカッコいい」役者絵が人気上昇中でした。その中で、写楽の「アクの強い」絵は、一部の通(ツウ)には受けましたが、一般大衆には「気持ち悪い」と敬遠されることもあったようです。第1期(デビュー作)は豪華でしたが、徐々に絵のサイズが小さくなり、質素になっていったことから、売上が落ちていったことが推測されています。
Q. 写楽の作品はどこで見られるの?
A. 東京国立博物館や、海外の美術館に多く所蔵されています。
日本国内では、東京国立博物館や出光美術館などが所蔵しています。ただ、浮世絵は保存のために常設展示されていないことが多いので、展示スケジュールを確認する必要があります。実は、ボストン美術館や大英博物館など、海外の方が多くの良質なコレクションを持っていたりします。

まとめ:ドラマも史実も、どちらも「べらぼう」に面白い!

いかがでしたか?
大河ドラマ『べらぼう』で描かれる、熱い人間ドラマとしての写楽。
そして、歴史の闇に消えた、孤高の天才・斎藤十郎兵衛としての写楽。
どちらも魅力的ですよね。
ドラマを見て「写楽って面白い!」と思った今の気持ちのまま、ぜひ本物の写楽の絵もじっくり見てみてください。
「あ、この目つき、ドラマのあの俳優さんの演技に似てるかも?」
「蔦重は、この絵のどこに惚れ込んだんだろう?」
そんな風に想像を膨らませながら鑑賞すると、230年前の江戸の空気が、すぐそこに感じられるはずです。
もし美術館に行く機会がなくても、今はネットで高画質の画像が見られます。ぜひ一度、「東洲斎写楽」で検索して、その強烈な「目」と目が合ってみてください。きっと、あなたもその虜になるはずですよ。
🎬 あの感動と興奮を、最高画質でもう一度。
「べらぼう」の世界観、本当に色彩が鮮やかで美しいですよね。
豪華な着物の柄や、刷り上がったばかりの浮世絵の質感、そして記事でも触れた役者さんたちの繊細な「目の演技」。 テレビ放送やスマホの配信で見ているだけでは気づけない、細かいディテールまでじっくり味わいたくありませんか?
そんな方には、やっぱりブルーレイBOXでの鑑賞がおすすめです。
特にこの「完全版 第弐集」は、物語が大きく動き出す重要なパート。蔦重の仕掛けが世間をあっと言わせるシーンや、写楽をめぐる人間ドラマを、映画のような高画質で何度も見返せるのは、円盤(ディスク)を持っている人だけの特権です。
さらに、特典映像で見られるメイキングやインタビューは必見! 「あの一瞬のシーンに、こんな意図が込められていたんだ…」という裏側を知ってから本編を見直すと、感動がまた全然違うんですよね。
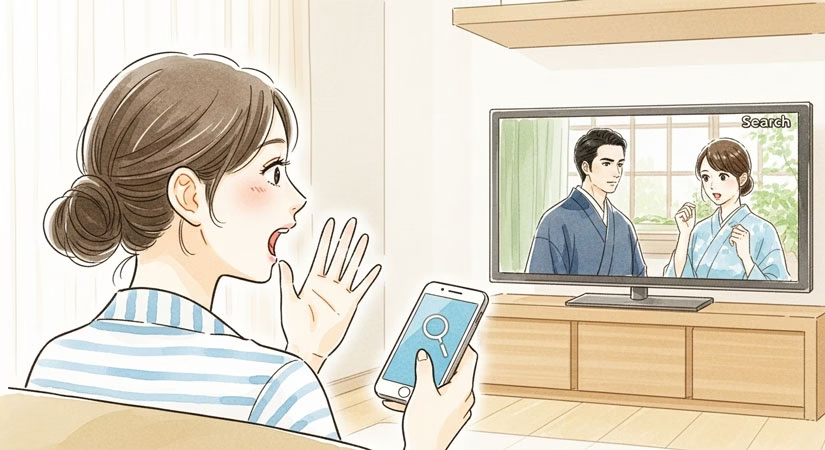




![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/204a0bb6.101fd84e.204a0bb7.daa35105/?me_id=1213310&item_id=21606440&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F8566%2F4988066248566_1_2.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)








