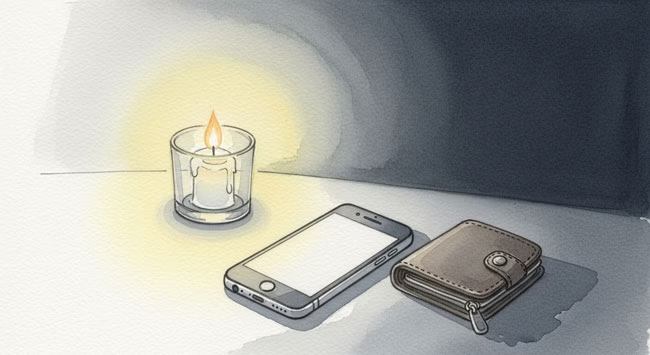こんにちは。毎日のスーパーでの買い物で、値上がりした野菜や卵を見るたびにため息が出てしまう今日この頃、皆さんはいかがお過ごしでしょうか?
ニュースを見れば「年収103万円の壁」の議論や、社会保険料の負担増の話ばかり。「私たちの手取りは全然増えないのに、どうして生活が苦しくなるばかりなんだろう」と不安になりますよね。
そんな中で飛び込んできたのが、「国会議員の給料引き上げ」のニュースです。「えっ、また上がるの?」「そもそも今いくらもらっているの?」と、モヤモヤした気持ちになった方も多いはずです。
実は、国会議員の収入には、私たちが普段目にする「給与明細」には載らない、驚くような「隠れ収入」や「特権」がたくさんあるんです。
今回は、そんなちょっと聞きづらいけれど絶対に知っておきたい「国会議員のお金」の話を、主婦目線、生活者目線で徹底的に掘り下げてみました。難しい専門用語は抜きにして、私たちが知るべき真実だけを分かりやすくお伝えしますね。
記事の後半では、「もし国会議員の人数を減らしたら、どれくらい税金が浮くのか?」というシミュレーションもしています。これが結構、驚きの金額なんです。ぜひ最後までお付き合いください。
【結論】国会議員の年収は実質いくらか?
まずは結論からズバリ言っちゃいましょう。「国会議員っていくらもらってるの?」という疑問への答えです。
ニュースなどで報じられる金額と、実際に彼らが自由に使える金額には、大きな差があるんです。
表向きの年収(課税対象)は約2100万円
まずは、法律で決められている「表向きの給料」を見てみましょう。これは会社員でいうところの基本給とボーナスにあたるものです。
- 歳費(月給):月額 129万4000円
- 期末手当(ボーナス):年額 約635万円(夏と冬の合計)
これらを合計すると、約2187万円になります。
「うわぁ、やっぱり高い!」と思いますよね。一般的なサラリーマンの平均年収が460万円程度と言われていますから、これだけでも約4倍以上です。でも、ここまでは「税金がかかるお金」なので、所得税や住民税が引かれます。手取りにすると、もう少し減りますよね。
ここまでは、まだ序の口なんです。
実はここが本丸!「第2の給与」を含めると4000万円超え
問題はここからです。国会議員には、給料とは別に「税金がかからない」「領収書もいらない(または公開しなくていい)」という、魔法のような手当が支給されています。
これを加味した「実質的な年収」を計算してみると、景色がガラッと変わります。
- 調査研究広報滞在費(旧文通費):月額 100万円 × 12ヶ月 = 1200万円
- 立法事務費:月額 65万円 × 12ヶ月 = 780万円
これらを先ほどの給与に足してみましょう。
- 表向きの年収(約2187万円)+ 非課税手当(1980万円)= 合計 約4167万円
なんと、4000万円を超えてしまいました。
しかも重要なのは、後半の約2000万円は「非課税」だということです。私たち一般庶民が手取りで2000万円をもらおうと思ったら、額面で3500万円以上稼がないといけませんよね。そう考えると、彼らの「経済力」は、実質的に5000万円プレイヤー並みと言っても過言ではないかもしれません。

給与(歳費)以外にもらえる「手当」と「特権」の中身
では、その「第2の給与」や「特権」の中身を、もう少し詳しく見ていきましょう。「えっ、そんなものまで無料なの?」と驚くかもしれません。
月100万円の「調査研究広報滞在費(旧文通費)」の闇
これ、ニュースでもよく話題になりますよね。「旧文通費」と呼ばれるものです。
- 金額:毎月100万円(年1200万円)
- 税金:かかりません(非課税)
- 使い道:何に使ったか公開する義務が不十分
これ、凄くないですか?毎月100万円が振り込まれて、税金も引かれず、何に使ったかの領収書も(現時点では完全には)見せなくていいんです。
「政治活動のための費用」という名目ですが、極端な話、そのまま貯金しても誰にもバレない仕組みが長年続いてきました。最近になって「日割り支給」や「公開」の議論が進んでいますが、民間感覚からすると信じられない制度ですよね。
月65万円の「立法事務費」と交通費無料パス
さらに、あまり知られていないのが「立法事務費」です。
- 金額:月額65万円
- 支給先:会派(議員グループ)に支払われますが、実質的な活動資金です。
- 税金:これも非課税です。
そして、移動費もタダ同然です。
- JR特殊乗車券:新幹線も含めてJR全線が乗り放題。
- 航空券:月に4往復分の航空券引換証がもらえます(選挙区が遠い人の場合)。
「仕事での移動なんだから経費でしょ?」という意見もありますが、先ほどの「調査研究広報滞在費」の中に交通費や滞在費も含まれているはずなんです。二重取りに見えてしまうのは私だけでしょうか。
公設秘書(3名)も税金負担(年間約2500万円)
議員活動を支える秘書さんのお給料も、議員のポケットマネーから出るわけではありません。国(税金)から支払われます。
- 公設第一秘書
- 公設第二秘書
- 政策担当秘書
この3人までは公費で雇うことができます。彼らの給与は経験や年齢にもよりますが、3人合わせると年間で約2000万円〜2500万円ほどになります。
もちろん、秘書さんは激務ですからお給料が出るのは当然ですが、これも「議員1人が活動するためにかかっているコスト」の一部であることは忘れてはいけません。
【シミュレーション】議員定数を削減したら、いくら税金が浮くのか?
さて、ここからが今回の記事のハイライトです。
「給料が高い!」と怒るのももっともですが、そもそも「国会議員の数が多すぎるんじゃないの?」と考えたことはありませんか?
現在、日本の国会議員は衆議院と参議院を合わせて713名います。
もし、この人数を減らしたら、私たちの税金はどれくらい浮くのでしょうか?電卓を叩いてみました。
国会議員1人にかかるコストは年間「約1億円」

まず、議員1人を養うために、国がどれくらいのお金を出しているかを計算します。給料だけでなく、活動費や政党への助成金も含めた「フルコスト」です。
| 項目 | 金額(概算) | 備考 |
| 歳費・期末手当 | 約2,200万円 | いわゆる給料 |
| 非課税手当 | 約2,000万円 | 旧文通費・立法事務費 |
| 公設秘書給与 | 約2,500万円 | 3人分の上限目安 |
| 議員会館・宿舎等 | 約1,000万円 | 維持管理費等の按分 |
| 政党交付金 | 約4,000万円 | 所属党に入るお金(議員数割) |
| 合計 | 約1億1,700万円 | 議員1人あたりの年間コスト |
※政党交付金は党によって異なりますが、議員一人当たりに換算すると平均で数千万円規模になります。
なんと、議員1人につき年間1億円以上の税金が動いている計算になるんです。
もし定数を「1割」減らしたら?驚きの削減効果
では、この「1人=1億円」という数字を使って、定数削減のシミュレーションをしてみましょう。
- 10人減らすだけで…
- 1億円 × 10人 = 10億円の削減
- 50人減らしたら…
- 1億円 × 50人 = 50億円の削減
いかがでしょうか?
「給料を月5万円上げる・下げる」という議論も大切ですが、定数を減らすことのインパクトがいかに大きいかが分かります。「身を切る改革」というなら、給与の2割カットよりも、定数削減の方がはるかに財政効果が高いのです。
50億円あれば、学校給食の無償化や、子育て支援の拡充など、もっと私たちの生活に近いところに使えると思いませんか?
諸外国との比較(日本は多い?少ない?)
「でも、日本の人口を考えたらこれくらいの人数は必要なの?」という疑問もあるかもしれません。
各国の「議員一人あたりの人口」を比較してみましょう。
- アメリカ(下院):議員1人あたり約76万人
- 日本(衆議院):議員1人あたり約27万人
- イギリス(下院):議員1人あたり約10万人
単純比較は難しいですが、アメリカと比べると日本は議員が多い(議員一人あたりの受け持ち国民が少ない)と言えます。一方でイギリスよりは少ないです。
ただ、アメリカの議員報酬は約2500万円と高いですが、手当の透明性は日本より厳しいと言われています。
日本の「高給取り」かつ「人数もそれなりに多い」という現状は、やはり見直す余地がありそうです。

なぜ今?2025年の「給与引き上げ」議論と世論の反応
そんな状況なのに、なぜ今「給料アップ」の話が出ているのでしょうか?
月額5万円アップ?引き上げの根拠とは
2025年に向けて議論されているのは、国会議員の給与(歳費)を引き上げるという案です。
報道によると、月額で数万円〜5万円程度の引き上げが検討されています。
理由はシンプルで、「民間企業の賃金が上がったから、公務員の給与も上げましょう(人事院勧告)」というルールがあり、それに連動して国会議員の給与も自動的に上がる仕組みになっているからです。
「みんなの給料が上がったんだから、私たちも上げるね」という理屈です。
世論の「ふざけるな」という怒りの背景
これに対して、ネットや街の声は猛反発しています。
「民間の賃上げって言っても、一部の大企業だけでしょ?」
「物価高で実質賃金は下がっているのに!」
「裏金問題の解決もしていないのに、自分の給料だけ上げるの?」
こんな怒りの声が上がるのは当然です。特に、自分たちで決めた「調査研究広報滞在費」の使途公開すら先送りにしている状態で、「給料アップのルールだけはきっちり守る」という姿勢が、国民感情を逆なでしているんですね。
一部の政党(日本維新の会など)は、「今は上げるべきではない」「自主返納する」といったパフォーマンスを見せていますが、国会全体として「削減」に向かう空気はまだ薄いのが現実です。

よくある質問(Q&A)
ここで、皆さんが疑問に思いそうなポイントをQ&A形式でまとめてみました。
Q. 国会議員に「退職金」や「年金」はあるの?
A. 昔はありましたが、今は廃止されました。
かつては「議員年金」というものすごく優遇された制度がありましたが、批判を浴びて2006年に廃止されました。現在は、私たちと同じ「国民年金」と「厚生年金(要件を満たす場合)」に加入しています。また、退職金制度もありません。ここは唯一、改革が進んだ部分と言えます。
Q. 落選したらどうなるの?
A. 収入はゼロになります。
これが国会議員の最大のリスクです。選挙に落ちた瞬間、ただの無職になります。失業保険もありません。
「だから現役のうちに高い給料をもらわないとやっていけないんだ」という意見もありますが、それにしても現役中の待遇が良すぎる気もしますよね。
Q. 定数削減が進まない理由は?
A. 自分たちの首を絞めたくないからです。
定数を減らすということは、次の選挙で自分が落選する確率が上がるということです。どの政党も「無駄は削る」と言いますが、いざ自分たちのポストが減るとなると、猛烈に抵抗します。これが「政治改革」がなかなか進まない最大の理由です。
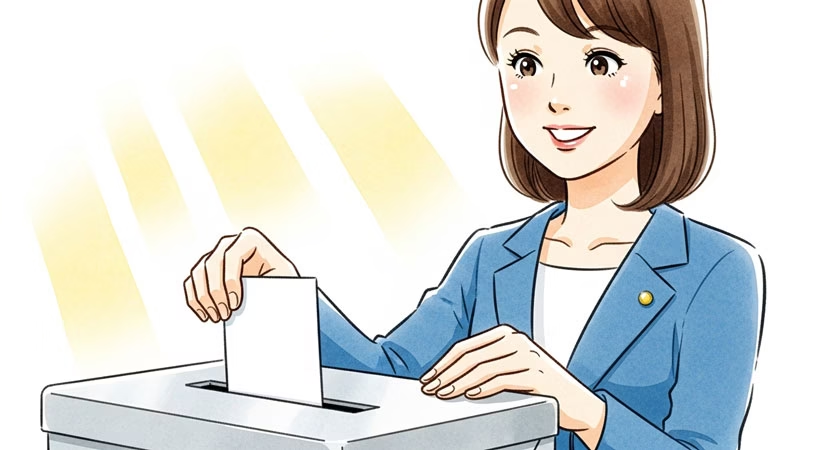
まとめ
長くなりましたが、国会議員のお金事情、いかがでしたでしょうか?
最後にポイントを整理しますね。
- 国会議員の収入は、表向きの約2100万円だけでなく、非課税の手当を含めると実質4000万円規模になる。
- 月100万円の「旧文通費」など、領収書不要の「つかみ金」がいまだに温存されている。
- 議員1人にかかる国のコストは年間約1億円。
- もし定数を50人減らせば、それだけで約50億円の税金が浮く計算になる。
私たちは日々の生活で、10円、20円の節約を重ねています。だからこそ、私たちの税金が使われる「政治の現場」で、これだけ大きなお金が、少し不透明な形で使われていることには、もっと声を上げていいはずです。
「政治家の給料なんてどうせ変わらない」と諦める前に、次の選挙では「定数削減」や「経費の完全公開」を本気で公約に掲げている候補者は誰なのか、しっかりチェックしてみませんか?
私たちの1票は、年間1億円の使い道を決める大切な権利なのですから。
私たちができる「ささやかな抵抗」と「賢い選択」
ここまで読んで、「腹が立つけど、私たちが何を言っても変わらないし…」と無力感を感じてしまった方もいるかもしれません。
確かに、明日の国会ですぐに定数削減が決まることはないでしょう。でも、私たちは指をくわえて見ているだけではありません。私たちには「税金の使い道」を自分で選ぶ権利がある制度があるのをご存知ですか?
そう、「ふるさと納税」です。
税金を「納得できる場所」へ移す
ふるさと納税は、実質2000円の負担で、自分が応援したい自治体に寄付ができる制度です。そして、その寄付した分は、翌年の住民税や所得税から控除されます。
つまり、これは「本来なら黙って国や今の自治体に取られていた税金」を、「自分で選んだ自治体」に移すことができる仕組みなんです。
もし、あなたが今の国の税金の使われ方に不満があるなら、その一部をふるさと納税を通じて、頑張っている地方の自治体に回してみてはいかがでしょうか?
たとえば、子育て支援に力を入れている町や、災害からの復興を頑張っている村に寄付をする。そうすれば、あなたの税金は、巡り巡って美味しいお米やオムツ、トイレットペーパーといった「返礼品」として、あなたの家計を助けてくれます。
議員の給料として消えてしまうかもしれないお金を、確実な「食費」や「日用品代」に変える。これもまた、物価高と戦う私たち庶民の、立派な「生活防衛策」であり、意思表示のひとつだと思いませんか?





![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4c877d9c.d6f1fc82.4c877d9d.4c5c7e8a/?me_id=1333990&item_id=10000125&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ff016446-ikeda%2Fcabinet%2F05165401%2Fimgrc0121381682.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)