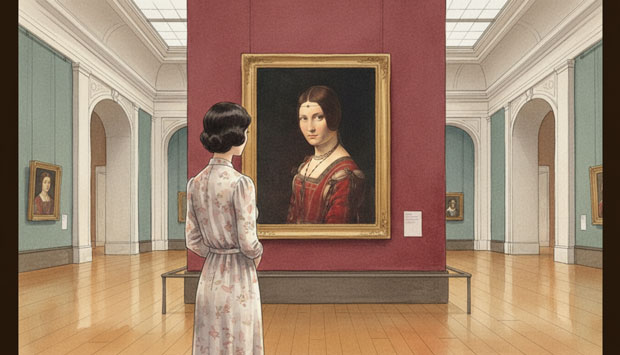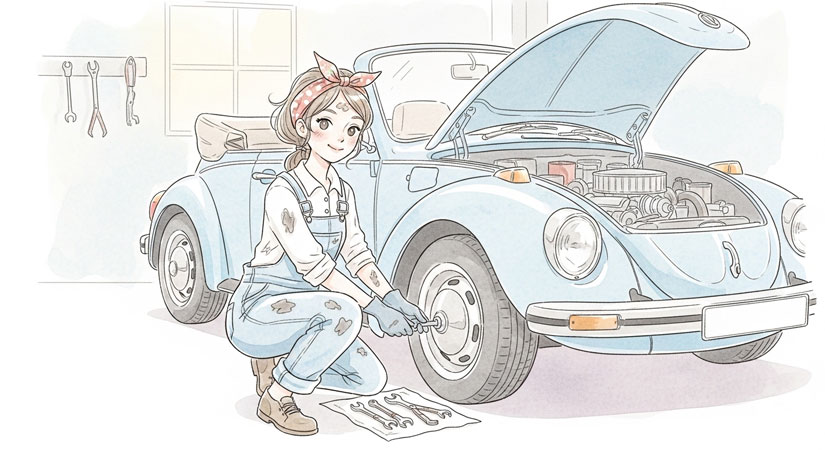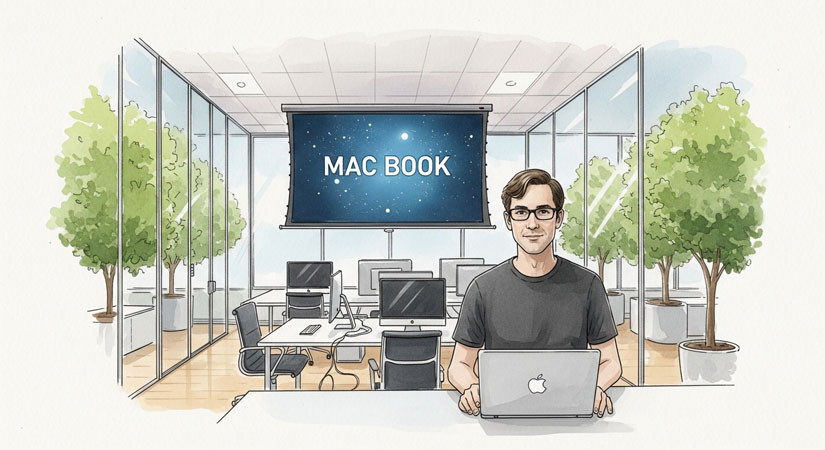日本経済新聞 今日の日付(2025年10月4日 金曜日)朝刊春秋の要約と「駅弁」文化の変遷
ねえ、突然だけど、駅弁って聞いて、あなたは何を思い浮かべる?
新幹線のホームで急いで買った幕の内弁当?それとも、ローカル線の窓の外を眺めながら、ゆっくり蓋を開けた郷土料理の詰まったお弁当かな?
日本経済新聞のコラム「春秋」で、この愛すべき駅弁文化が今、大変な状況にあることが取り上げられていたの。
高度成長期には駅弁がもてはやされた。旅を楽しむゆとりが生まれ、若者たちも家族連れも、沿線の珍しい弁当を競って求めたのである。1963年から翌年にかけては「駅弁日本一周」「駅弁パノラマ旅行」「駅弁」といったガイドブックが相次いで出版されている。
いまでも古書店でときどき見かけるから、よほど読まれたに違いない。ひもといてみると、失われた味のオンパレードである。函館本線滝川駅の「ジンギスカン弁当」、東北本線黒磯駅の「九尾ずし」、山陽本線柳井駅の「ドライカレー弁当」……。このころ、日本鉄道構内営業中央会には400社あまりが加盟していた。
コラムでは、昔は400社以上あった駅弁屋さんが、今は80社ほどに激減しているという、ショッキングな現実が伝えられているの。コンビニや駅ナカが便利になりすぎて、旅情を味わう余裕がなくなってしまったのかなって、少し寂しくなったわ。
この愛すべき日本の食文化、駅弁がなぜこんなに愛されて、そしてなぜ今、危機に瀕しているのか。そして、その魅力を未来へつなぐために私たちにできることは何なのか。一緒に深掘りしてみましょう!
🍽️ 「駅弁」って何?歴史から学ぶその定義と魅力
🍱 駅弁のルーツ:日本初の駅弁はいつ、どこで生まれた?
そもそも、駅弁っていつからあるんだろう?
諸説あるけれど、一般的に「駅弁の始まり」とされているのは、1885年(明治18年)の宇都宮駅。日本鉄道が開通した際に、旅館が握り飯2個とたくあんを竹の皮に包んで販売したのが最初だと言われているわ。当時の価格は5銭だったそうよ。
そこから140年近く、駅弁は日本の旅に寄り添ってきたのね。
じゃあ、コンビニで売っているおにぎりや、スーパーのお弁当と駅弁の違いって何だと思う?
それはね、「旅の体験の一部であること」、そして 「その土地で調理され、その駅で売られること」 、この二つがすごく大事なの。駅弁は、ただの食事じゃなくて、地域と旅人を結ぶ、特別な存在なのよ。
🚅 高度成長期「駅弁ブーム」の光景
コラムにもあったように、1960年代、日本の経済がグングン成長していた頃、駅弁はまさに旅の主役だったの。
どうしてそんなにブームになったかというと、 「旅のゆとり」 が生まれたことが大きいわ。新婚旅行や家族旅行、修学旅行といった、ちょっとした贅沢な旅が一般的になったのね。
そして、当時は今みたいに全国の美味しいものが簡単に手に入らなかったでしょう?だから、列車が停車する駅のホームで売られている 「沿線の珍しい食べ物」 は、旅のハイライトだったわけ。
1963年頃に「駅弁日本一周」なんてガイドブックが相次いで出版されるくらい、みんなが「あの駅の、あの駅弁を食べるぞ!」って、競うように楽しみにしていたのよ。
🍙 幻の駅弁たち:失われた味のオンパレード
コラムには、古書店で見かけるガイドブックに載っているという、今はもう食べられない駅弁たちが紹介されていたわね。名前を聞くだけで、どんな味だったんだろうって想像しちゃう!
| 幻の駅弁(コラムより) | 所在地 | どんな駅弁だった?(想定される魅力) |
| ジンギスカン弁当 | 函館本線 滝川駅(北海道) | 羊肉文化が根付く北海道ならではの、パンチの効いたお肉のお弁当。 |
| 九尾ずし | 東北本線 黒磯駅(栃木県) | 地元那須の伝説(九尾の狐)にちなんだ、稲荷寿司や巻き寿司の詰め合わせかな? |
| ドライカレー弁当 | 山陽本線 柳井駅(山口県) | 当時のハイカラな洋食メニューが駅弁になったモダンな一品。 |
この時代の駅弁は、その土地の食材を使い、手間ひまかけて手作りされていたからこそ、旅人の心を掴んだのね。一つのお弁当に、その地域の歴史や愛がぎゅっと詰まっていたのよ。
🖋️ 文学と「旅情」:作家が愛した駅弁の精神的な価値

🍱 吉田健一が愛した長岡駅の弁当
駅弁って、単なる「腹ごしらえ」じゃない。それは、旅のロマンを形にしたものなの。
それを象徴するエピソードが、コラムにもあった作家・吉田健一さんの話よ。彼は1971年の随筆で、信越線長岡駅の弁当をそれはもう大絶賛しているの。
彼が「何でも食べるのに値する」と褒めたのは、マスやカニの押し寿司、そしてサンドイッチまで!
「え、サンドイッチ?」って思うかもしれないけど、彼はそのサンドイッチの「手間がかかっている」ところに感動したそうよ。当時の駅弁は、一つ一つが職人さんのプライドと手間暇の結晶だったのね。
🚂 駅弁と「旅情」の関係を考える
皮肉屋としても知られる吉田健一さんが、ここまで熱烈に褒めちぎったのは、なぜでしょう?
それはきっと、彼が感じた 「旅情」 という言葉に尽きるわ。
- 風景との一体感: 列車に揺られ、目の前の景色が移り変わる中で食べることで、駅弁の味が何倍にも美味しくなる。
- 時間の価値: 今のようにスマホで時間を潰すのではなく、お弁当をじっくり味わう「ゆったりした時間」がそこにあった。
- 地域への想い: 故郷を離れ、旅をする中で、地元で採れた食材で作られた駅弁は、まるで地域からの「おもてなし」のように感じられたはず。
吉田健一さんは、単に食べ物が美味しいと言っているのではなくて、駅弁がもたらす旅全体の豊かさを評価していたのね。コラムの結びの通り、「旅情」という言葉が実感を失いつつある現代だからこそ、私たちはもう一度、この駅弁の精神的な価値を見直す必要があるわ。
🎁 駅弁が教えてくれる「一期一会」の出会い
駅弁って、基本的に 「その場所でしか買えない」 でしょう?(今は駅弁大会とか通販もあるけど、基本はね。)
この「一期一会」の特別感が、私たちをワクワクさせるの。
旅先で駅弁を買う時って、事前に調べてお目当てを決めることもあれば、ホームに降り立って、その場でパッケージの美しさや「限定」の文字に惹かれて衝動買いすることもあるよね。
それって、その地域の 「食の文化」 と私たち旅人が偶然出会う、素敵な瞬間だと思うの。だからこそ、駅弁は旅の思い出と強く結びつくのね。
📉 駅弁文化が直面する「冬の時代」:衰退の理由

こんなにも愛されてきた駅弁文化なのに、なぜ今、多くの老舗が廃業に追い込まれているのでしょう?
コラムにあったように、日本鉄道構内営業中央会の加盟社は400社から80社ほどに激減。この数字は、私たちが思っている以上に、駅弁業界が厳しい状況にあることを示しているわ。
🛍️ 時代の変化で駅弁が選ばれなくなった理由
衰退の背景には、私たちの生活や旅のスタイル、そして駅のあり方の変化が大きく関わっているの。
| 衰退の主な要因 | 詳細な説明と読者への補足 |
| 競合の台頭 | コンビニエンスストア: 駅周辺はもちろん、駅ナカにも多数出店。24時間営業で、温かいお弁当や種類豊富な軽食が安価に手に入る。**「手軽さ」**で駅弁を圧倒。 |
| 駅ナカ・駅ビルグルメの進化 | 乗り換え時間を利用して、座って食事ができるフードコートやレストランが充実。地域の名店と提携したお洒落なグルメも登場し、駅弁の需要を奪った。 |
| 列車の高速化・旅のスタイルの変化 | 新幹線・特急の移動時間が短縮。例えば東京―大阪間は2時間半ほど。車内でゆっくり食事をするよりも、到着後に目的地で美味しいものを食べる方が主流に。 |
| 採算性の悪化 | 駅弁は手作業が多く、人件費や原材料費の高騰の影響を受けやすい。大量生産が難しいため、価格を上げるとコンビニに勝てず、経営が苦しくなる。 |
| 後継者不足 | 伝統的な駅弁屋さんは家族経営のところも多く、技術や味を受け継ぐ若い世代がいなくなり、惜しまれつつ暖簾を下ろすケースが多い。 |
😢 失われゆく伝統の味:廃業の現実
コラムにも、伊東線伊東駅で「いなり寿し」を売ってきた祇園が、先月末で廃業に追い込まれたという悲しいニュースが書かれていたわ。
地元の食材を使い、長年愛されてきた味が、ある日突然なくなってしまうなんて、旅好きとしては本当に寂しいことよね。
私たち消費者からすると、「あの駅弁、いつでも買えるだろう」って思ってしまいがちだけど、駅弁屋さんの経営はギリギリのところで成り立っていることが多いの。
「もう少し早く買っておけばよかった」「もっと頻繁に利用していれば…」そんな後悔の声をSNSでもよく見かけるわ。この廃業の現実は、「駅弁文化」がもはや当たり前の存在ではないことを私たちに突きつけているのね。
💡 「伝統の味」を守る挑戦と工夫:生き残るための戦略
厳しい時代を迎えても、伝統の味を守り、新しい形で生き残ろうと頑張っている駅弁屋さんもたくさんあるわ。
🍱 事業継承と継続の道:折尾駅「かしわめし」の事例
コラムにもあった、鹿児島本線折尾駅の名物「かしわめし」をつくる東筑軒(とうちくけん)は、まさに伝統を守るための工夫と決断をした例よ。
報道によると、東筑軒は経営が苦しくなり、一度は事業譲渡という道を選んだそう。でも、この伝統ある「かしわめし」というブランドは、地元の人々にとって、そして鉄道ファンにとって 「なくてはならない味」 だった。
結果として、地元有力企業系の会社に事業譲渡することで、「かしわめし」の味と伝統は守り継がれたの。
- 伝統の継承: 調理方法や秘伝のタレの味を変えることなく、そのまま引き継ぐ。
- 経営の合理化: 新しい経営体制のもと、生産性や販売戦略を見直し、安定した経営基盤を確立。
「ブランド力」 がある商品は、例え経営が苦しくなっても、その価値を認める誰かが手を差し伸べ、残していこうとしてくれる。この事例は、駅弁が単なる食べ物ではなく、 地域にとっての「文化財」 であることを教えてくれるわね。
💖 現代のニーズに応える駅弁の進化
生き残っている駅弁屋さんは、厳しい環境の中でさまざまな工夫を凝らしているの。私たち女性客を意識した戦略もたくさんあるわよ!
| 進化のポイント | 具体的な工夫と例 |
| パッケージデザイン | 見た目がお洒落でSNS映えするデザインが増加。箱の形や風呂敷、掛け紙にこだわり、記念品としても価値を高める。 |
| コンセプトの明確化 | 豪華海鮮系(ウニ・カニ・イクラ)や、ヘルシー志向(野菜たっぷり、低カロリー)など、ターゲットを絞った商品開発。 |
| ご当地コラボ | 有名シェフや人気キャラクターとのコラボレーション駅弁。**「限定感」**を高めて話題性を創出。 |
| 販路の多様化 | 百貨店の駅弁大会(実演販売も含む)への積極参加や、オンライン通販への進出で、駅以外での購入機会を増やす。 |
| サービス | 温め機能付きの容器(加熱式駅弁)を導入し、温かいお弁当が食べたいという現代のニーズに応える。 |
昔ながらの駅弁の良さももちろんあるけれど、時代の流れに合わせて、「可愛さ」や「美味しさ」をアップデートしている駅弁に、私たちも注目したいわね。
例えば、百貨店の駅弁大会に行くと、毎回新しいデザインや斬新な具材の駅弁に出会えるでしょう?あれは、駅弁屋さんが必死に生き残ろうと工夫している証拠なのよ。
🌈 まとめ:駅弁文化を未来につなぐために私たちができること

高度成長期にブームとなり、多くの人々の旅路を彩ってきた駅弁文化。今は厳しい時代を迎えているけれど、その魅力は少しも色褪せていないわ。
駅弁は、「手軽さ」や「安さ」ではコンビニに敵わないかもしれない。でも、 「旅情」「地域愛」「職人さんの手間暇」という、数値では測れない「心の豊かさ」 を運んでくれる点では、他の追随を許さない、特別な存在なの。
🤝 消費者としてのエールと小さな行動
この愛すべき文化を守り、未来につなぐために、私たち一人ひとりができることはとてもシンプルよ。
- 「次の旅では、駅弁を選んでみる」
- 「少し高くても、その土地でしか買えないものを探してみる」
- 「旅の思い出と一緒にSNSで発信してみる」
私たちが意識して 「駅弁」 を選び、その魅力を広めることが、地域経済を支え、廃業の危機にある老舗を救う、何よりのエールになるわ。
吉田健一さんが愛した「旅情」 を、次の世代にも感じてもらうために。
あなたの次の旅では、ぜひスマホを少し置いて、窓の外の景色と、その土地ならではの駅弁をじっくり味わってみませんか? きっと、いつもの旅がもっと豊かで、心に残るものになるはずよ!