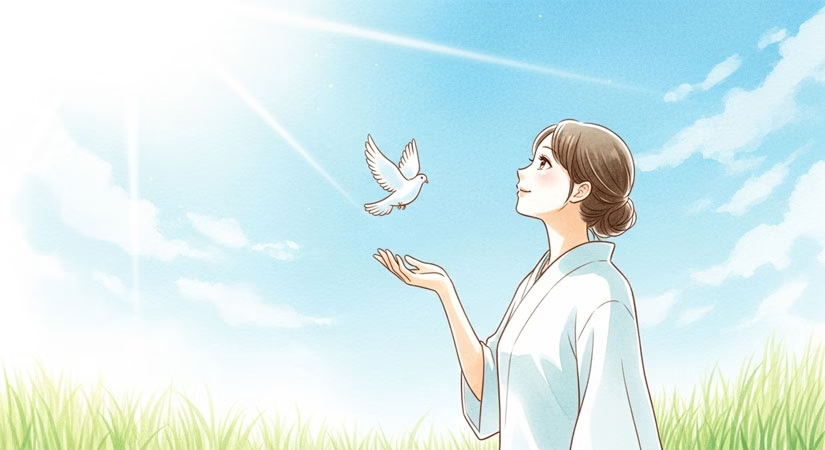日本経済新聞 2025年11月2日(日)朝刊春秋の要約と「はだしのゲン」に学ぶ平和への視点
この記事は、日本経済新聞のコラム「春秋」をきっかけに、漫画『はだしのゲン』の作者である中沢啓治さんが、なぜ原爆をテーマにした作品を描き続けたのか、そして彼の怒りが現代社会に何を訴えかけているのかを探ります。
核兵器の脅威が再び取り沙汰される今、私たちは「ゲン」の怒りから目をそらさず、平和について深く考える必要があります。
「はだしのゲン」作者の中沢啓治さんは広島から上京してデビューした当初、原爆がテーマの漫画を描くつもりはなかったという。東京でも就職などをめぐって被爆者への差別や偏見が横行していた。なにより父ときょうだいを奪った原爆のことを、早く忘れたかった。
転機は被爆21年後の母の死である。火葬すると骨も残らず灰になった。原爆は骨まで奪うのか。怒りは創作の熱量へと昇華し、核を指弾する作品を次々と世に送り出した。幼い息子を白血病で失う父親。被爆2世だからと婚約を破棄され自殺する女性。生きてなお原爆に引き裂かれる人々の悲劇をこれでもかと描き続けた。
🎨 漫画『はだしのゲン』とは? 中沢啓治さんの人生と創作の原点
中沢啓治さんが描いた『はだしのゲン』は、単なる戦争体験記ではありません。作者自身の壮絶な体験と、平和への強い願いが込められた、命の物語です。
😢 原爆の記憶から逃げたかった中沢さん
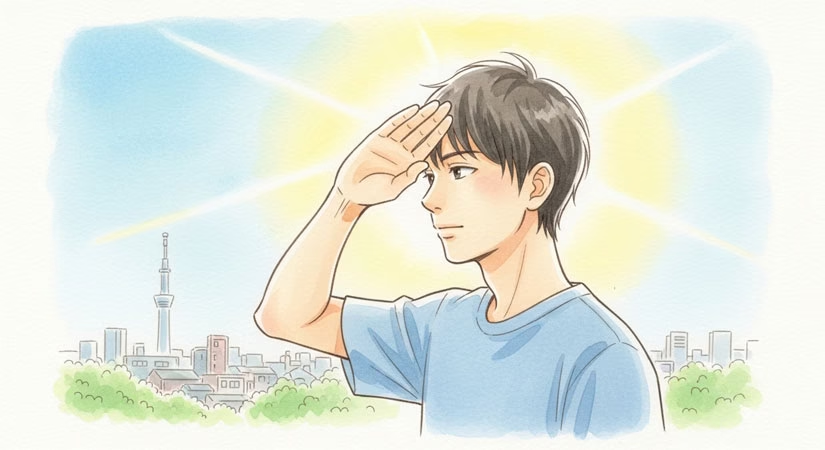
中沢さんは、デビュー当初、原爆の記憶から逃れたいと願っていました。それは、ご自身やご家族が経験された筆舌に尽くしがたい苦しみだけでなく、社会における被爆者への差別や偏見という「心の暴力」からも逃れたかったからです。
- 物理的な傷だけでなく、精神的な苦しみも大きかった
- 上京後も、就職などで被爆者に対する偏見や差別に直面
- 原爆の悲劇を忘れ、普通の生活を送りたいと願っていた
🔥 転機となった母の死と創作への昇華
原爆投下から21年後のお母様の死が、中沢さんの人生と創作活動を大きく変える転機となります。
お母様の遺骨がほとんど残らなかったという事実は、中沢さんに「原爆は骨まで奪うのか」という新たな怒りを呼び起こしました。この怒りが、彼を原爆を告発する作家へと押し上げ、創作のエネルギーとなったのです。
- 1966年(被爆21年後): お母様の死。火葬後の遺骨がほとんど残らない事実に衝撃を受ける。
- 怒りの昇華: 悲しみと怒りを作品にぶつけ、「核を指弾する作品」を次々と発表。
- 描かれた悲劇: 単行本化された『はだしのゲン』だけでなく、『黒い土の叫びに』など、被爆者や被爆二世の苦悩を描いた作品も多数執筆。
🌎 世界に広がる「ゲン」のメッセージ
『はだしのゲン』は、そのメッセージ性の高さから、国境を越えて多くの人々に読まれています。
| 翻訳されている言語の例 | 特徴と意義 |
| ロシア語 | 核大国の一つであるロシアにも、平和のメッセージが届いている |
| 中国語 | 歴史的な背景を超えて、人道的な視点から作品が共有されている |
| 英語 | 世界中の人々、特に核兵器を持つ国々の人々に読まれる機会が多い |
😠 ゲンの怒りはまだ届いていない? 核をめぐる現代の課題
コラムでは、これほどまでに熱い思いが込められた「ゲン」の怒りが、世界の指導者たちにはまだ届いていないのではないかと危惧しています。特に、核の脅しを軽く口にする姿勢への強い慄然が表明されています。
🗣️ 核の脅しを口にする政治家たち
核兵器を持つ国々の指導者の中には、**核の脅威を交渉の「材料」**として利用したり、核実験の再開を示唆したりする言動が見られます。
- 核の「ディール(取引)」: 核兵器を外交交渉の道具として軽々しく扱う姿勢。
- 核実験再開の示唆: 世界の平和と安定を脅かす行為。
- コラムが訴える危機感: 核兵器の持つ破壊力を理解せず、その存在を軽く見ていることへの警鐘。
💡 平和の賞と核兵器の矛盾
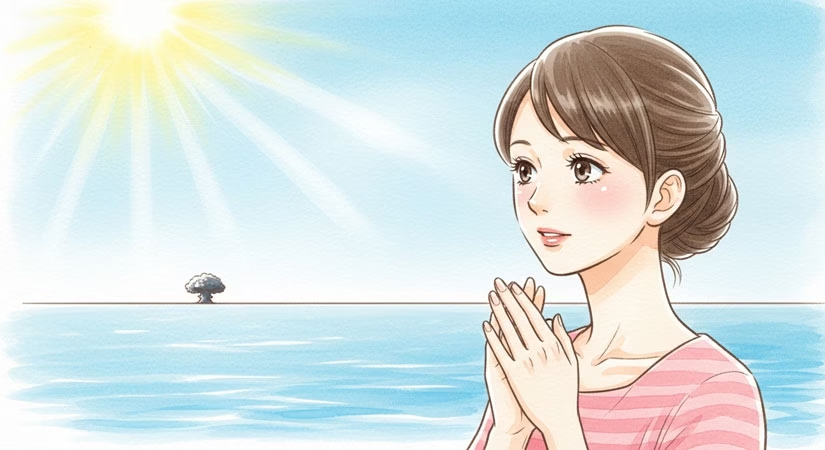
コラムでは、平和を熱望する指導者が、核兵器を軽々しく扱うことは大きな矛盾であると指摘しています。
| 求めるもの | 現実の行動 | 矛盾点 |
| 平和の賞 | 核実験の再開指示や核の脅し | 平和の実現には、核兵器の廃絶が不可欠。核兵器の保有・使用を示唆する行為は、平和とは相容れない。 |
📚 「黒い土の叫びに」が示す終わらない戦い
中沢さんの作品には、繰り返し行われる核実験のニュースを、主人公が険しい表情でにらみつけて終わる一編があります(『黒い土の叫びに』)。
これは、中沢さんの怒りが、広島の原爆投下で終わらず、その後の核開発競争や核実験にも向けられていたことを示しています。
- 過去の悲劇だけでなく、未来への脅威にも目を向ける。
- 核兵器は今もなお、人類を脅かし続けている。
- 作品は「怒り」を通して、私たちに無関心でいることを許さない。
👩👧👦 女性目線で考える『はだしのゲン』と平和のあり方
『はだしのゲン』に描かれているのは、戦争という巨大な暴力の中で、家族や子どもを守ろうとする人々の姿です。特に、女性の視点から見ると、平和への願いはより切実なものに感じられます。

💔 原爆に引き裂かれる人々の悲劇
中沢さんの作品には、原爆の直接的な被害だけでなく、その後の人生までを破壊される人々の姿が描かれています。
| 描かれた悲劇の例 | 伝えたいメッセージ |
| 幼い息子を白血病で失う父親 | 原爆の影響は時間とともに消えない。未来ある子どもたちの命まで奪う。 |
| 被爆2世だからと婚約を破棄され自殺する女性 | 被爆者への差別や偏見は、人の尊厳を奪い、生きていく希望すら断つ。 |
私たちは、ニュースの数字だけでは見えない、一人ひとりの心の痛みに寄り添うことが大切です。
🤱 核兵器のない世界を子どもたちへ
核兵器は、一瞬にしてすべてを奪い去る究極の暴力です。子を持つ親として、また未来を生きる人々として、私たちは核兵器のない世界を望みます。
| 私たちができること | なぜそれが大切なのか |
| 「ゲン」の物語を語り継ぐ | 悲劇を忘れず、核の非人道性を次世代に伝える。 |
| 差別や偏見をなくす | 被爆者とその家族が抱える**「目に見えない苦しみ」**に心を寄せる。 |
| 平和への声を上げる | 政治や社会の動向に無関心にならず、核廃絶への願いを表明する。 |
📝 まとめ:中沢啓治さんの「怒り」を、私たちの「願い」に

中沢啓治さんが生涯をかけて訴え続けた「怒り」は、私たち一人ひとりが平和な未来を築くための情熱へと変えることができます。
『はだしのゲン』は、過去の物語ではありません。核兵器の脅威が現実味を帯びる今こそ、私たちが何度も立ち返るべき平和への教科書なのです。
「ゲン」の怒りが、世界中の指導者の心に、そして私たち一人ひとりの心に深く届くことを心から願ってやみません。