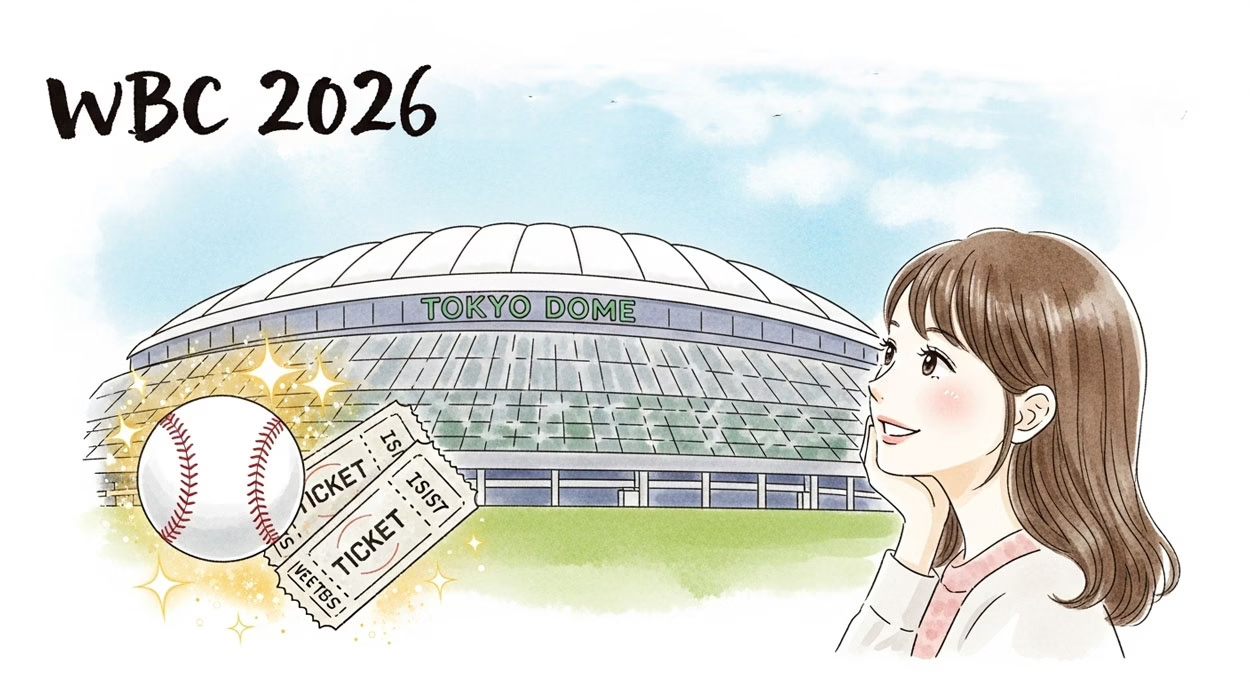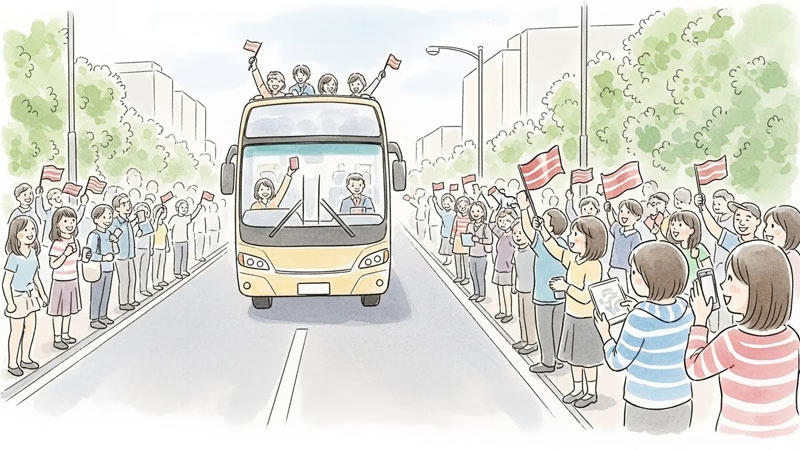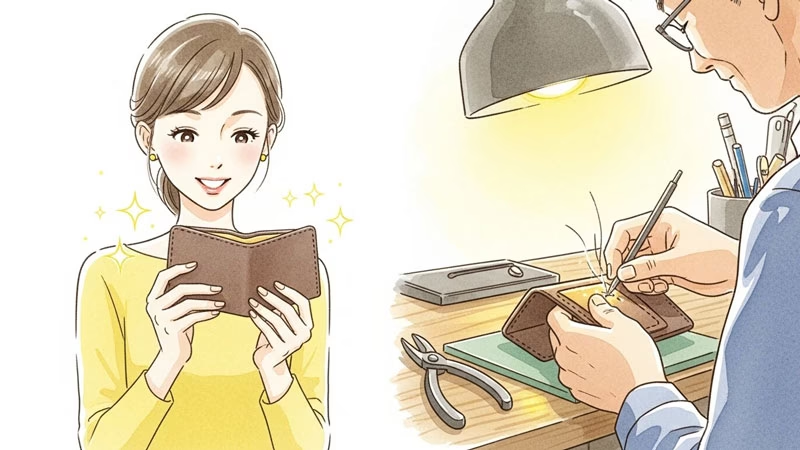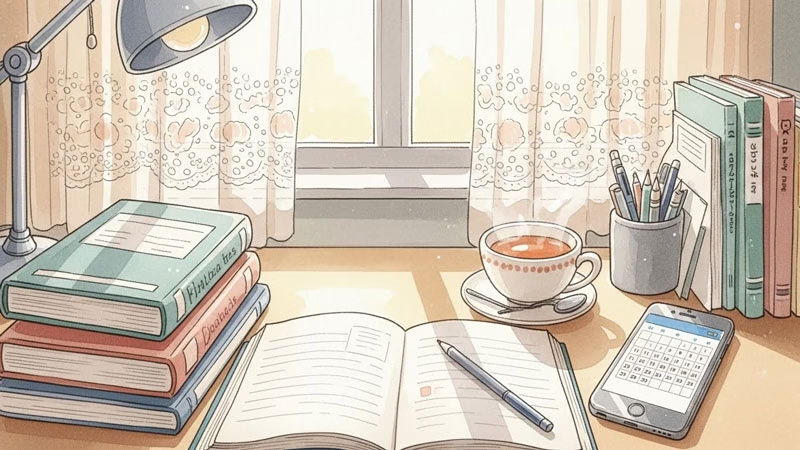日本経済新聞 2025年8月4日(月)の要約と名建築の保存問題
はじめに:なぜ今、香川の「船の体育館」が注目されているのか
2025年夏、建築ファンの間で一つの名建築が静かな、しかし熱い注目を集めています。それは、香川県高松市にある旧香川県立体育館。
日本を代表する建築家・丹下健三氏が手掛け、そのユニークな形状から「船の体育館」として県民に親しまれてきたこの建物が、老朽化を理由に来年にも解体されるというのです。
日本経済新聞のコラム「春秋」(2025年8月4日付)でも取り上げられたこの問題。
コラムでは、同じ丹下健三氏設計の国立代々木競技場(東京)と兄弟のような建築でありながら、解体の岐路に立たされている現状を指摘。市民団体から保存活用のための買い取り提案が出たものの、県側は予定通り解体手続きを進める方針であることが伝えられました。
この記事を読んで、多くの方がこう思ったのではないでしょうか。
- 「なぜそんなに価値のある建物が壊されなければならないの?」
- 「『船の体育館』って、一体どんな建物なの?」
- 「保存はもう不可能なの?何か方法はないの?」
- 「なくなってしまう前に、一度見てみたいけど、どうすればいい?」
この記事では、こうした疑問に一つひとつ丁寧にお答えしていきます。単に事実を伝えるだけでなく、問題の背景にある「なぜ?」を掘り下げ、この問題が私たちに何を問いかけているのかまで、一緒に考えていきたいと思います。
そもそも「旧香川県立体育館(船の体育館)」とは?
まずは、この建物の「すごさ」を分かりやすく解説します。専門知識は不要です。写真や身近なものに例えながら、その魅力を感じてみてください。 なお、現物写真はこちらのULRがとてもわかり易いですので御覧ください→こちら
建築の巨匠・丹下健三が手掛けた「兄弟建築」
この体育館を設計したのは、丹下健三(1913-2005)。
日本人で初めて国際的に評価された建築家であり、広島平和記念資料館や東京都庁舎など、数多くの有名建築を手掛けたレジェンドです。
そして、この旧香川県立体育館は、東京オリンピック(1964年)のために建設された国立代々木競技場と、ほぼ同時期に同じ技術を使って設計されました。そのため「兄弟建築」とも呼ばれています。
| 項目 | 旧香川県立体育館 | 国立代々木競技場(第一体育館) |
| 愛称 | 船の体育館 | – |
| 完成年 | 1964年 | 1964年 |
| 設計者 | 丹下健三 | 丹下健三 |
| 構造 | 吊り屋根構造 | 吊り屋根構造 |
| 特徴 | 和船のような有機的なフォルム | 未来的な宇宙船のようなフォルム |
| 現状 | 閉鎖中、解体予定 | 現役、重要文化財 |
代々木競技場が今も現役で、国の重要文化財に指定されているのに対し、なぜ香川の体育館は解体の危機に瀕しているのでしょうか。この対照的な運命が、問題をより一層複雑にしています。
なぜ「船の体育館」と呼ばれるのか?その驚くべき構造
この体育館の最大の特徴は、その見た目と構造にあります。
上から見ると、まるで**日本の伝統的な木造船(和船)**のよう。このユニークな形から、地元では自然と「船の体育館」と呼ばれるようになりました。
そして、この形を可能にしているのが「吊り屋根構造(つりやねこうぞう)」という特殊な技術です。
- 吊り屋根構造とは?
- 簡単に言えば、巨大な吊り橋の技術を屋根に応用したものです。
- 建物の両端にある太い柱(主柱)から、力強いワイヤーケーブルを何本も渡し、そのケーブルから屋根を吊り下げています。
- このおかげで、体育館の内部には一本も柱がありません。これにより、広々とした大空間が生まれるのです。
そばに立つと、まるで巨大な船が大地から浮き上がっているかのような錯覚を覚えます。コンクリートの塊なのに、不思議な浮遊感と躍動感がある。これが丹下健三の発想の非凡さであり、多くの建築ファンを魅了する理由です。
世界が認めたその価値とは?
この体育館の価値は、日本国内に留まりません。
近代建築の保存と記録を目的とする国際的な学術組織「DOCOMOMO Japan」によって、「日本におけるモダン・ムーブメントの建築20選」の一つに選定されています。これは、専門家たちが「日本の近代建築を代表する、文化的に価値の高い建物」であると認めた証です。
SNS上でも、訪れた人々から感動の声が上がっています。
「写真で見るのとは迫力が全然違う。コンクリートの曲線美に圧倒された。」
「まるで古代遺跡か、未来の乗り物か…。時間が経つのを忘れて見入ってしまった。」
「これが半世紀以上も前に造られたなんて信じられない。丹下健三は天才だ。」
伝統的な「和船」のイメージと、近代的な「吊り屋根」の技術。この二つを見事に融合させた点に、この建築の最大の価値があると言えるでしょう。
なぜ解体が決定されたのか?3つの大きな理由
これほど価値のある建物が、なぜ解体の危機にあるのでしょうか。その背景には、避けては通れない3つの現実的な問題があります。
理由1:老朽化と莫大な維持管理コスト
1964年の完成から約60年。人間と同じように、建物も歳をとります。
コンクリートのひび割れ、雨漏り、設備の旧式化など、様々な問題が深刻化していました。体育館としては2014年に閉館しており、その後は使われないまま時間が経過しています。
香川県の試算によると、この体育館を耐震補強して改修(リフォーム)する場合、約23億円もの費用がかかるとされています。さらに、改修後も年間約5,000万円の維持管理費が必要になると見込まれています。
これは、県の財政にとって非常に大きな負担です。限られた税金を、県民の暮らしや福祉、教育などに優先的に使うべきだ、という判断が働くのは自然な流れとも言えます。
理由2:現代の安全基準(特に耐震性)の問題
建設当時は最新の技術でしたが、その後の度重なる地震を経て、日本の建築物に対する耐震基準は格段に厳しくなりました。
旧香川県立体育館は、現在の耐震基準を満たしておらず、大規模な地震が発生した場合に安全を確保できないと判断されています。
特に、特殊な「吊り屋根構造」であることが、耐震補強を一層難しく、そして高コストにしている要因の一つです。
理由3:アスベスト(石綿)問題
建設当時に断熱材などとして使用された**アスベスト(石綿)**が、建物の各所で見つかっています。
アスベストは、飛散すると人体に深刻な健康被害を及ぼす可能性があるため、解体するにしても、改修するにしても、極めて慎重な除去作業が必要です。この除去費用も、全体のコストを押し上げる一因となっています。
決定までの経緯(タイムライン)
これらの問題を背景に、県は専門家を交えた検討委員会を設置し、時間をかけて議論を重ねてきました。
- 2012年:体育館の耐震診断を実施。耐震性が不足していることが判明。
- 2014年:安全面を考慮し、体育館としての利用を終了(閉館)。
- 2017年:県が設置した検討委員会が「解体がやむを得ない」との結論を出す。
- 2021年:香川県議会で、解体費用を含む予算案が可決され、正式に解体が決定。
- 2022年:市民団体から保存活用のための買い取り提案が提出される。
- 2022年7月:県知事が定例会見で、提案は具体的なものではないとし、予定通り解体手続きを進める方針を表明。
このように、解体の決定は突然下されたものではなく、10年近い検討の末の結論であったことが分かります。
「待った!」の声。市民による保存活用案とその壁
行政が解体の方針を固める一方で、「この文化的遺産を失うべきではない」と立ち上がった人々がいます。
どんな保存案が出されているのか?
地元の建築家や市民らで組織する団体「旧香川県立体育館の再生を願う会」などが中心となり、保存活用の道を模索しています。
彼らが提案しているのは、単に「残してほしい」という感情論ではありません。
民間が建物を県から買い取り、資金を調達して改修。ホテルや商業施設、アートスペースなど、新たな収益を生む施設として再生させるという、具体的なプランです。
この提案の画期的な点は、「行政に頼るのではなく、民間の力で価値を再生させる」という点にあります。税金に頼らず、建物の魅力そのものでビジネスを成立させようという試みです。
なぜ行政は「ノー」なのか?対立の構図
しかし、県側は「提案が具体性に欠ける」として、解体の方針を崩していません。なぜ両者の溝は埋まらないのでしょうか。
| 県(行政)の立場 | 市民団体(民間)の立場 |
| 【重視すること】 | 【重視すること】 |
| ・県民全体の公平性 | ・建物の文化的価値 |
| ・財政的な負担の回避 | ・民間活力による地域活性化 |
| ・計画通りの行政手続きの実行 | ・対話による解決の模索 |
| 【懸念点】 | 【懸念点】 |
| ・本当に民間が巨額の資金を調達できるのか? | ・行政が対話のテーブルについてくれない |
| ・事業が失敗した場合の責任の所在 | ・時間的な猶予がない(解体計画の進行) |
県としては、「もし民間での再生がうまくいかなかった場合、結局は県が責任を負うことになるのではないか」というリスクを最も恐れています。一方、市民団体側は「素晴らしいアイデアと情熱があっても、行政が聞く耳を持たなければ前に進めない」というジレンマを抱えています。
これは、「確実性と前例」を重んじる行政と、「可能性と未来」を信じる民間との間の、価値観の違いとも言えるかもしれません。
口コミ・SNSの声「私たちの船を残して!」
この問題は、専門家や行政だけでなく、多くの一般市民の関心事ともなっています。SNS上では、様々な意見が交わされています。
- 保存賛成派の声「壊すのは一瞬。でも二度と造れない。税金の問題は分かるけど、あまりに惜しい。」「ホテルやカフェになったら絶対行く!新しい高松のランドマークになるはず。」「子供の頃、ここで遊んだ思い出がある。思い出まで壊されるようで悲しい。」
- 解体やむなし派の声「古いものにばかりお金は使えない。未来の子供たちのために税金は使うべき。」「危険な建物を放置する方が問題。安全が第一。」「結局、誰がそのお金を出すの?って話になる。」
様々な意見があること自体が、この建物が多くの人々にとって無視できない存在であることの証左と言えるでしょう。
【読者ガイド】解体前に訪れたい人のための完全マニュアル
「議論の行方も気になるけれど、まずはこの目で見てみたい!」そう思った方のために、訪問ガイドを作成しました。
アクセス方法と注意点
- 所在地:香川県高松市福岡町
- 最寄り駅:ことでん(高松琴平電気鉄道)「片原町駅」または「高松築港駅」から徒歩約15分
- 注意点:
- 建物内部への立ち入りはできません。 体育館は閉鎖されており、敷地内もフェンスで囲まれている場合があります。見学は敷地外からとなります。
- 駐車場はありません。 公共交通機関を利用するか、近隣のコインパーキングをご利用ください。
- 周辺は住宅街です。 見学の際は、地域住民の方々の迷惑にならないよう、ご配慮をお願いします。
写真撮影のおすすめスポット
せっかく訪れるなら、この建物の魅力を最大限に引き出す写真を撮りたいもの。いくつかおすすめのアングルをご紹介します。
- 正面からの全景:まさに「船」の姿を捉えることができる王道のアングル。広角レンズがあると、その雄大さを余すところなく撮影できます。
- 斜め下からの見上げ:船底のようなカーブと、力強く天に伸びる柱のダイナミズムを同時に感じられるアングル。建物の力強さが際立ちます。
- ディテールの接写:風雨にさらされたコンクリートの質感や、特徴的な窓の形など、細部に目を向けるとその歴史とデザインの妙を感じることができます。
周辺のおすすめ立ち寄りスポット(香川の魅力を満喫)
高松には、他にも魅力的な場所がたくさんあります。体育館訪問と合わせて、ぜひ香川を満喫してください。
- 栗林公園(りつりんこうえん):国の特別名勝に指定されている大名庭園。「一歩一景」と言われるほど、歩くごとに景色の変わる美しい庭園は必見です。
- 北浜alley(きたはまアリー):古い倉庫街をリノベーションした複合商業施設。海沿いのおしゃれなカフェや雑貨店が並び、散策するだけでも楽しいスポットです。
- 高松港周辺:瀬戸内海の島々(直島、豊島、小豆島など)へ向かうフェリーが発着します。アートの島へ足を延ばすのもおすすめです。
- 讃岐うどんの名店:香川に来たら外せません。体育館周辺にも数多くの名店が点在しています。
他人事ではない。「名建築の保存」が難しい普遍的な課題
旧香川県立体育館の問題は、実は日本中の、そして世界中の都市が抱える普遍的な課題を象徴しています。
「コンクリートの寿命」と「文化財」の壁
木造の寺社仏閣などと異なり、鉄筋コンクリートで造られた「近代建築」は、一般的に寿命が50~60年と言われることがあります。そのため、文化的な価値が認識される頃には、物理的な寿命が尽きかけている、というジレンマに陥りがちです。
また、比較的新しいため、国宝や重要文化財といった法的な保護の対象になりにくいという側面もあります。
保存にかかるリアルな費用感
「保存」と一言で言っても、それには莫大な費用が伴います。
- 初期費用:耐震補強、改修、アスベスト除去など
- ランニングコスト:光熱費、清掃、警備、定期的なメンテナンスなど
これらの費用を誰が負担するのか(税金か、民間資金か、利用者か)という問題は、常に保存運動の大きな壁となります。
他の名建築はどうなった?(成功例と失敗例)
日本国内でも、近代建築の保存をめぐっては、様々な結末がありました。
- 【成功例】横浜赤レンガ倉庫(神奈川県)
- 明治・大正時代に国の模範倉庫として建設。
- 老朽化で一時は解体の危機に瀕したが、横浜市が取得。
- 耐震補強や改修を行い、現在は商業・文化施設として再生。年間600万人以上が訪れる人気スポットに。
- 【失敗例】中銀カプセルタワービル(東京都)
- 建築家・黒川紀章の代表作で、カプセルを交換できる未来的なデザインが世界的に評価された。
- 老朽化とアスベスト問題、そして住民間の合意形成の困難さから、2022年に解体。カプセルの一部は美術館などで保存されている。
これらの例から分かるように、名建築の運命を分けるのは、**「その建物を活用して、新たな価値や収益を生み出す具体的なビジョンを、地域社会全体で共有できるか」**という点にあるのかもしれません。
まとめ:私たちが未来に残すべきものとは?
旧香川県立体育館の問題は、単なる「古い建物を壊すか、残すか」という二元論では語れません。
そこには、
- 文化的な価値と財政的な現実の対立
- 過去への敬意と未来への責任の相克
- 行政の論理と民間の情熱のすれ違い
といった、現代社会が抱える多くの複雑なテーマが凝縮されています。
解体されれば、私たちは二度とあの雄大な姿を見ることはできません。
保存されれば、それは未来の世代に引き継がれる貴重な遺産となるかもしれません。しかし、そのために誰かが大きな負担を背負うことにもなります。
この記事を通じて、まずはこの問題に関心を持っていただくことが第一歩です。そして、もし機会があれば、ぜひ現地を訪れてみてください。写真では伝わらない建物の声が、きっと聞こえてくるはずです。
「船の体育館」の未来がどうなるにせよ、この議論そのものが、私たちが何を大切にし、何を未来に残していくべきかを考える、貴重なきっかけを与えてくれているのではないでしょうか。