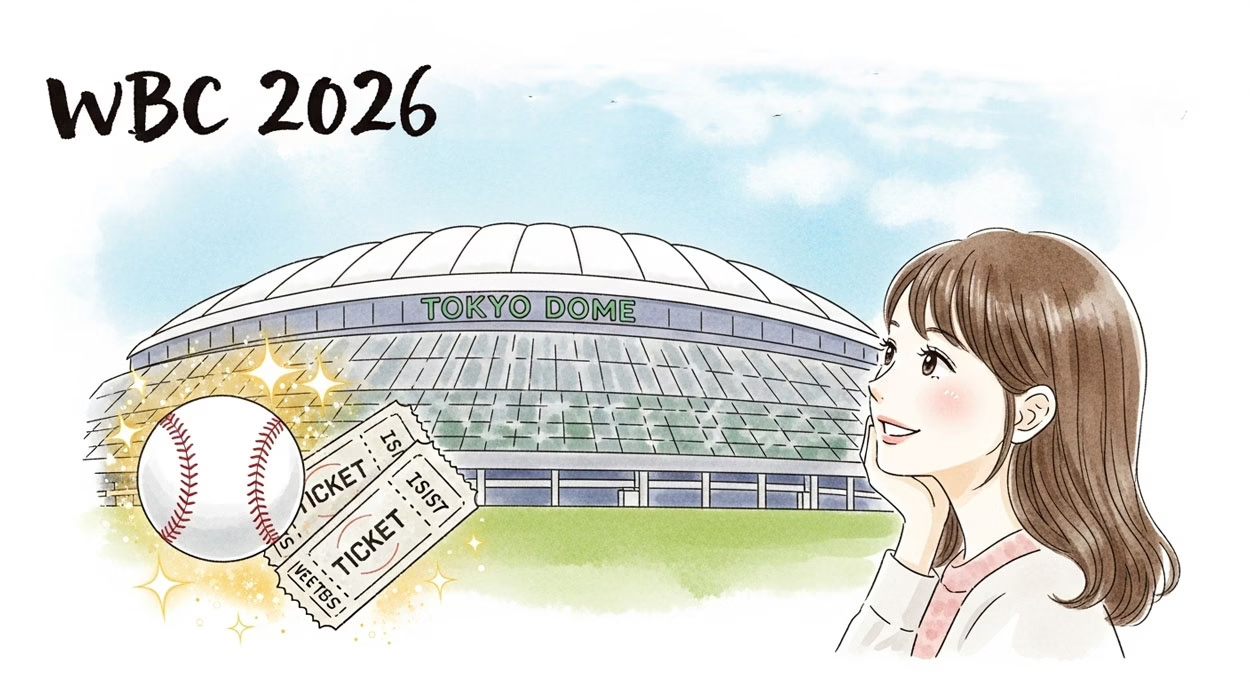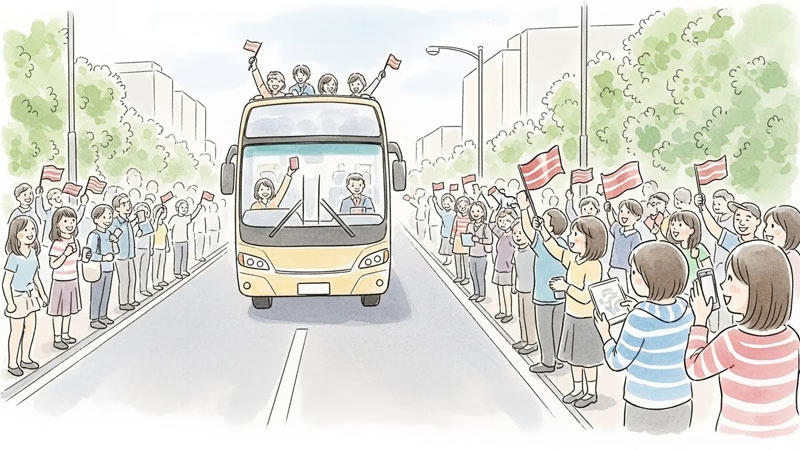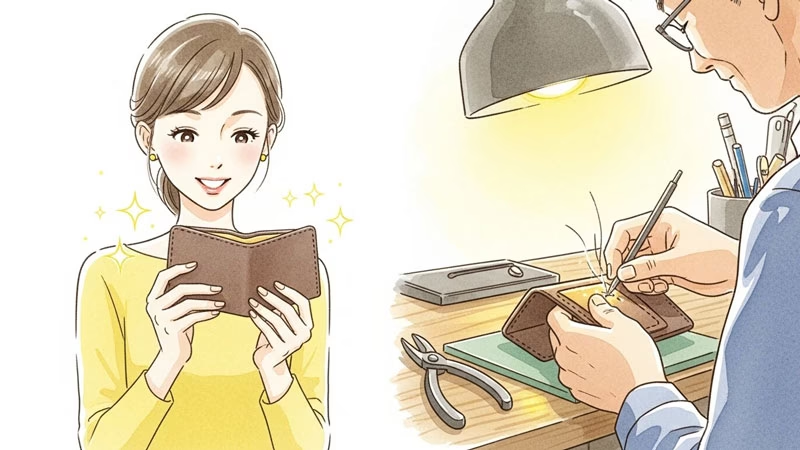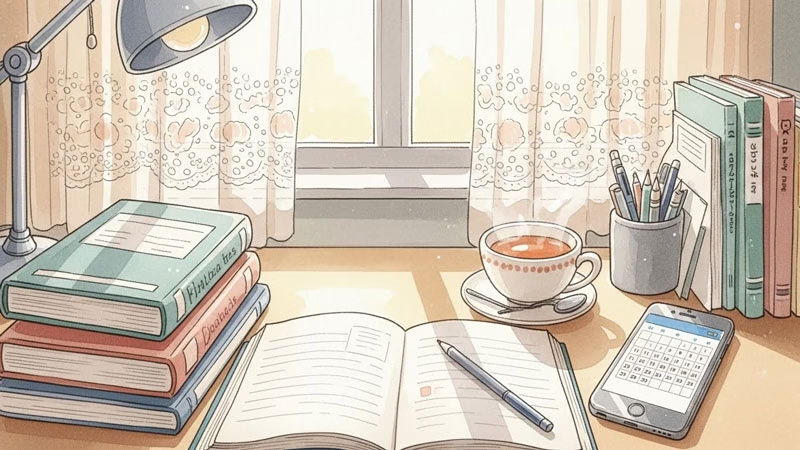日本経済新聞 2025年11月21日(金)朝刊春秋の要約と火災対策の再確認
「文化をもって誇る国家の恥辱であろうと思われる」。
これは、かつて「日本のエジソン」とも呼ばれた物理学者、寺田寅彦が1934年の函館大火に際して漏らした言葉です。
「文化をもって誇る国家の恥辱であろうと思われる」。寺田寅彦がこう嘆いたのは1934年のことだ。この年の3月21日、函館市で大火があった。死者は2千人を超え、1万棟以上が焼けた。強風により民家の屋根が飛び、囲炉裏の火が周囲に燃え広がったとされる。
▼自然災害への警鐘を鳴らし続けた物理学者だが、人為による災禍には抗(あらが)う術があるはずだと言いたかったのだろう。江戸時代ならいざ知らず、「昭和九年の大日本の都市に起こったということが実にいっそう珍しいことなのである」と断じた後で、火災を科学的に研究する必要性を説いている(「函館の大火について」)。
この記事は、2024年に発生した大分・佐賀関の火災の惨状を受けて書かれたものです。
古い木造家屋が密集する港町で起きた延焼は170棟以上にも及び、海を越えて1.4キロ先の離島にまで飛び火した可能性があるという、想像を絶する炎と風の猛威でした。
寺田寅彦は、科学が発達した昭和の時代に大火が起きたことを「珍しいこと」と嘆き、火災を科学的に研究する必要性を訴えました。それから約90年が経った現代で、なぜ私たちはまた、同じような大規模な火災を経験してしまったのでしょうか。
この記事では、このコラムから浮かび上がる「火災」、「大火の教訓」、「現代の備え」という3つの重要なテーマについて掘り下げ、私たち一人ひとりが、これから迎える空気が乾燥しがちな季節に向けて、どのように命と財産を守るべきかを考えます。
過去の大火から学ぶ教訓:時代を超えて変わらないリスク
寺田寅彦が言った「きのうあった事はきょうあり、きょうあった事はまたあすもありうる」という言葉は、大火のリスクがいつの時代にも潜んでいることを示唆しています。
火災の規模が大きくなる原因は、時代や場所が変わっても、実はとても共通しています。
大火の共通原因:火災の「三種の神器」
大火災に共通する原因として、主に次の3つの要素が挙げられます。
| 原因 | 発生場所・状況 |
| 強い風 | 火の勢いを加速させ、飛び火(遠くへ火の粉が飛んで新たな火事を起こすこと)を引き起こします。 |
| 建物の密集 | 隣の家にすぐに燃え移りやすい状態。特に古い木造家屋が多い地域は危険度が増します。 |
| 乾燥 | 燃料となるものがカラカラに乾いているため、小さな火種でも一気に燃え広がってしまいます。 |
函館大火は「強風で民家の屋根が飛び、囲炉裏の火が燃え広がった」とされ、最近の大分・佐賀関の火災も「想像を超える炎と風の暴威」と表現されています。これらはまさに、上記の要因が重なった結果と言えるでしょう。
特に、日本の多くの古い港町や中心市街地には、狭い路地に木造家屋が連なる風景が残っています。こうした場所は、ひとたび火災が発生すると消火活動が難しく、一気に燃え広がってしまうリスクを抱えています。
現代の私たちが直面する「火災の脅威」:見落としがちな盲点
火災予防と言うと、「火の元の確認」や「消火器の設置」をイメージしがちですが、大規模火災を避けるためには、それだけでは不十分です。私たちは現代ならではのリスクにも目を向ける必要があります。
1. 「飛び火」による遠隔地への延焼
佐賀関の火災では、1.4キロ離れた離島にまで飛び火した可能性が指摘されています。これは、風に乗った火の粉が、私たちの想像をはるかに超えた距離まで到達するということです。
「自分の家が火元でなくても」#PIC2、「隣近所で火事があっても大丈夫」という油断は禁物です。
- 私たちの対策: 自分の家や庭に燃えやすいものを放置しない(例:枯れ葉の山、不要な段ボール、ゴミ)。屋根やベランダ周りも日頃からきれいに保ち、火の粉が着地しても燃え広がりにくい環境にしておくことが大切です。
2. 住宅の高気密化と火の勢い
現代の家は、暖房効率を上げるために気密性が高くなっています。これは一見火災と無関係に思えますが、家の中で火災が発生すると、窓やドアが破れた瞬間に大量の酸素が流れ込み、一気に炎の勢いを増すことがあります。
- 私たちの対策: 初期消火の重要性がより増しています。家族全員が消火器の場所と使い方を把握し、火災警報器の点検を忘れずに行いましょう。
いますぐ確認したい!冬から春にかけての火災予防チェックリスト
コラムの結びには、「これから春先にかけ、さらに気を引き締めねばならない季節を迎える」とあります。空気が乾燥し、強い風が吹きやすいこの時期は、まさに大火のリスクが高まる時期です。
ご自身の家や家族のために、以下のチェックリストをぜひ確認してください。
【日常のチェック項目】

| 項目 | 確認内容 | 頻度 |
| 火災警報器 | 正常に作動するか、電池は切れていないか。 | 月に一度はテストする。 |
| 暖房器具 | ストーブやヒーターの周りに燃えやすいもの(洗濯物、カーテンなど)がないか。 | 使用前、使用中常に。 |
| コンセント | たこ足配線になっていないか、ホコリが溜まっていないか。 | 大掃除の際、半年に一度はチェック。 |
| ガスコンロ | 使用中にその場を離れない。周りに油汚れなどが溜まっていないか。 | 毎日使用時。 |
| タバコ | 吸い殻を完全に消し、指定の場所に捨てる。寝タバコは絶対にしない。 | 喫煙する度。 |
【地域のチェック項目】
火災は「個人の問題」ではなく「地域の問題」でもあります。#PIC4
- 消火栓・防火水槽の確認: 近くの消火設備がモノでふさがれていないか、機能しているか知っておきましょう。
- 避難経路の確認: 地域で火災が発生した際、どの道を通ってどこに避難するのか、家族で話し合って地図に書き込んでおくのがおすすめです。
- 近隣との協力: 「あそこは古い家が多いから心配ね」など、日頃から火災のリスクについて近所の方と情報交換をしておくのも大切です。
もしもの時に命を守る「初期消火」の心得
寺田寅彦は、人為による災禍には「抗う術があるはずだ」と言いたかったのではないでしょうか。その「抗う術」の最たるものが、火が小さいうちに食い止める初期消火です。

1. 消火器よりも身近なものを使う
消火器の使い方がわからない、または間に合わない場合でも、身近なもので消火を試みることはできます。
- 天ぷら油の火災: 絶対に水をかけないでください。濡れた大きめのタオルで鍋全体を覆い、空気(酸素)を遮断します。
- ゴミ箱の火災: バケツやペットボトルに入った水を静かにかけます。
- カーテンや衣類の火災: 叩きつけるようにして炎を消すのではなく、上から水をかけたり、大きな布などで覆い被せて窒息消火を試みます。
ただし、天井に炎が届いたら、すぐに避難が最優先です。 初期消火に固執し、逃げ遅れることだけは避けてください。
2. 「逃げる」タイミングの判断
火災発生から安全に避難できる時間は非常に短いものです。#PIC6
| 発生場所 | 逃げるタイミング |
| 自分の家 | 炎が天井に達したら、初期消火を諦め、すぐに「火事だ!」と叫んで家族を起こし、避難する。 |
| 近隣の家 | 自分の家へ延焼する可能性があると判断したら、火が来る前に避難準備をし、消防の指示を待つ。 |
火災が起きると、煙が急速に充満します。煙は熱く、有毒ガスを含んでいて、一瞬で意識を失う危険性があります。
避難する際は、姿勢を低くしてハンカチなどで口と鼻を覆い、少しでも新鮮な空気を吸えるように心がけましょう。
まとめ:過去の教訓を未来の備えに
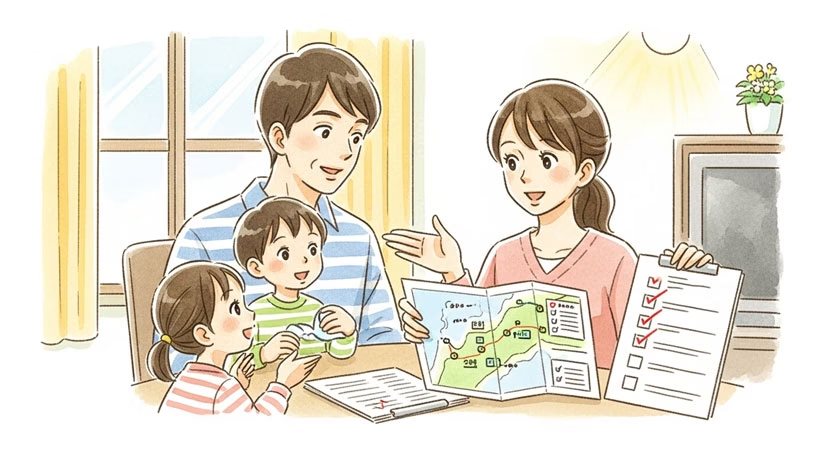
寺田寅彦が嘆いた大火から90年、そして近年も糸魚川や佐賀関での大規模な火災を経験しました。
科学技術は進歩しましたが、火の脅威、特に「風」と「密集」という自然と人為による条件が重なると、現代の都市でも想像を絶する災禍は起こりえます。
私たちができることは、このコラムが伝えたかったメッセージを真摯に受け止め、「きのうあった事はきょうあり、きょうあった事はまたあすもありうる」という警鐘を心に刻み、日々の備えを見直すことです。
乾燥と強風の季節を前に、ご家族や大切な人と一緒に、もう一度火災への備えについて話し合ってみませんか。それが、未来の安心につながる第一歩になるはずです。
🚒 炎を小さいうちにシャットアウト!女性でも簡単「エアゾール式簡易消火具」のススメ
初期消火が命運を分けることは、過去の大火の教訓からも明らかです。でも、「重たい消火器をいざという時に使えるかしら…」と不安に感じてしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そんな不安を解消してくれるのが、この「エアゾール式簡易消火具」、いわゆる消火スプレーです!
まるでヘアスプレーや殺虫剤を使うような感覚で、火元に向かって噴射するだけ。重さもサイズも一般的な消火器に比べてずっとコンパクトで軽量なので、女性やお年寄りの方でも片手でサッと持ち運び、操作することができます。
特に火災リスクが高いキッチンで、天ぷら油やゴミ箱から小さな火が出たとき、慌てずにすぐ手が届く場所に置いておけば、炎が天井に届く前に素早く火を消し止め、大切な家族と住まいを守る強力な味方になってくれますよ。





![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4e62e52f.ce11eab6.4e62e530.4f068f74/?me_id=1410974&item_id=10001441&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fign-store%2Fcabinet%2F11445425%2F11448789%2Fspray%2Fhi2.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)