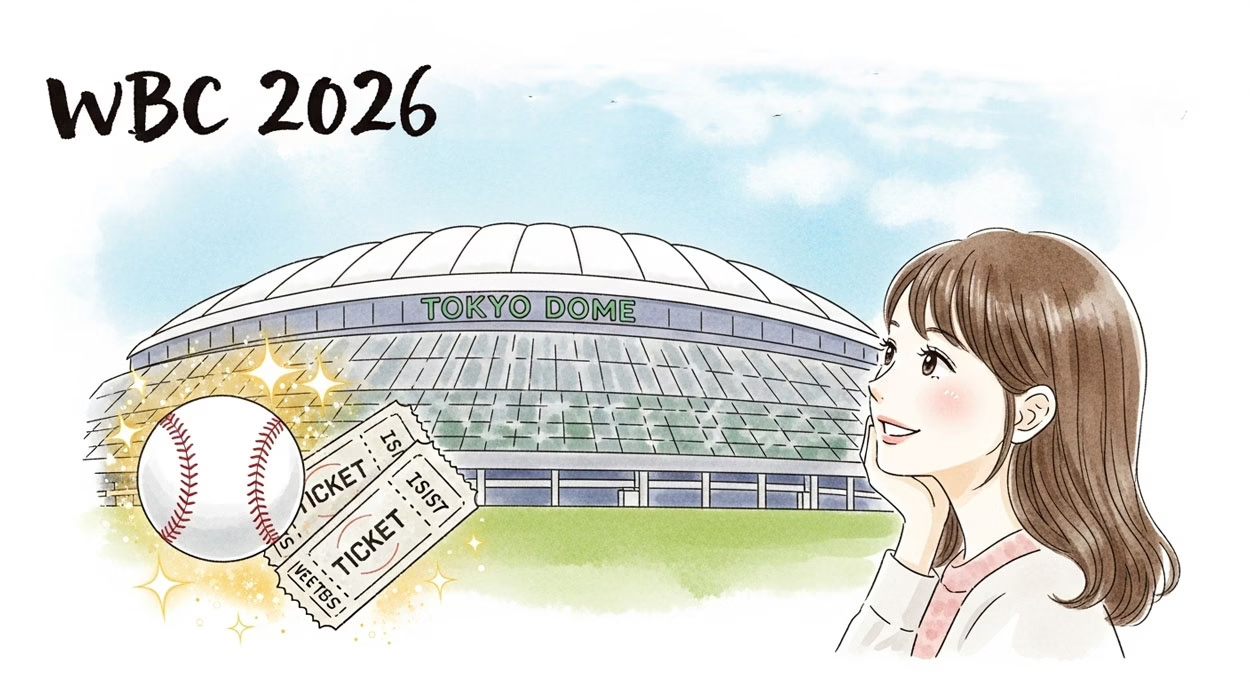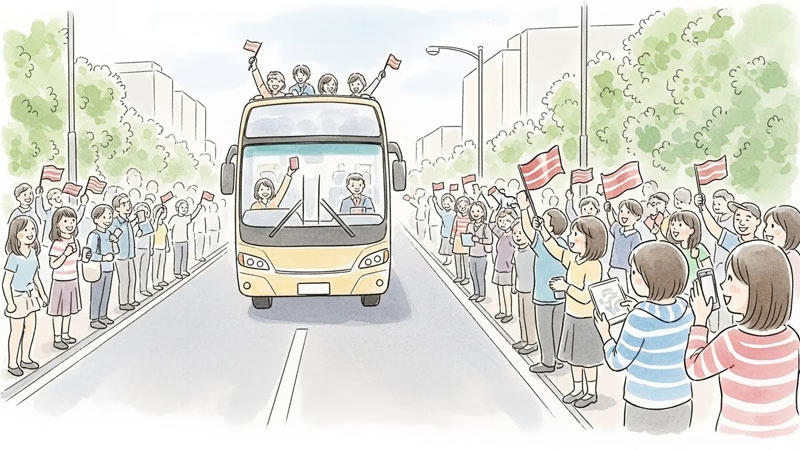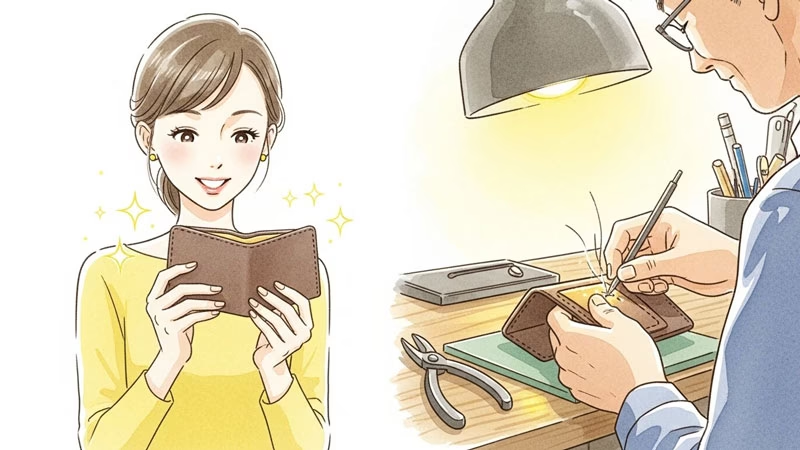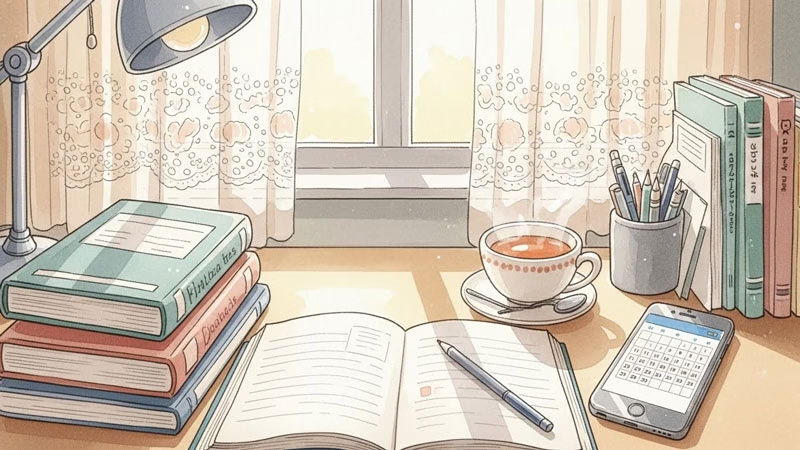日本経済新聞 2025年11月19日(水)朝刊春秋の要約とラオスとの交流
コラム「春秋」からのご紹介
本日(2025年11月19日)の日本経済新聞朝刊に掲載されたコラム「春秋」では、京都出身の異色の料理人、小松聖児さんの活動と、天皇家の長女である愛子さまのラオス公式訪問について紹介されています。
京都出身の小松聖児さんは京大の大学院で水産資源の流通を学んだ異色の料理人だ。フィールドワークをしたのは海なし内陸国のラオス。東南アジア最大のメコン川にすむ淡水魚は国民の大切なたんぱく源で、子供がとらえる雑魚もムダなく使う知恵に感心したという。
魚に塩と米ぬかを加えるパーデークという調味料がラオス料理の味の基本。ソムパーは日本でいうなれずしで、発酵食好きの日本人には親しみがわく。雨期と乾期で魚のとれる量が変動するため発酵保存の方法が発達した。親日の仏教国とされるこの国が外国を初めて公式訪問する天皇家の長女、愛子さまの旅先となった。
(有料版日経新聞より引用)
この記事では、このコラムから得られるキーワードを深掘りし、ラオスの食文化、愛子さまのご訪問、そして両国の長きにわたる友好関係について、分かりやすくご紹介します。
「パーデーク」と「ソムパー」:ラオスの食卓を支える知恵
ラオスは海を持たない内陸国です。そのため、国民の貴重なたんぱく源は、雄大なメコン川をはじめとする淡水魚が中心です。
🍛 海のない国で育まれた「発酵」文化 #PIC1
日本で海産物を塩漬けにしたり、干物にしたりして保存するように、ラオスでは魚を無駄なく長く食べられるようにする知恵が発達しました。その鍵となるのが「発酵」です。
| 調味料・食品名 | 現地の呼び名 | 概要 | 日本での近いもの |
| 発酵調味料 | パーデーク | 魚に塩と米ぬかを加えて発酵させた調味料。ラオス料理の味の基本となる。 | 魚醤(ナンプラーなど)や、塩辛に近いイメージ。 |
| 発酵漬物 | ソムパー | 魚を発酵させた食品。主に淡水魚を使う。 | 熟鮓(なれずし)や飯寿司。 |
パーデークは、日本の味噌や醤油のように、ラオス料理の土台となる調味料です。このパーデークの香りが、ラオス料理特有の風味を作り出します。ソムパーは、日本人が古くから親しんできた「なれずし」に近い発酵食品です。魚を発酵させる文化は、食材を大切にする両国の共通点と言えます。
🐟 琵琶湖の魚で「パーデーク」を作る料理人
記事に登場する小松聖児さんは、このラオスの食文化に感銘を受け、なんと琵琶湖の魚を使ってパーデーク作りをされています。
これは、海なし国ラオスと、やはり海のない滋賀県の琵琶湖という共通点に着目した、食を通じた素敵な文化交流です。琵琶湖の淡水魚は、昔から「ふなずし」などの発酵食品に使われてきた歴史があります。小松さんの活動は、日本の伝統的な食文化とラオスの知恵を結びつけ、両国の食卓を豊かにしてくれる、新しい試みと言えるでしょう。
愛子さまのご訪問:長年の友情と平和への思い
2025年、ラオスは愛子さまの外国への初公式訪問の地となりました。親日国として知られるラオスは、日本との間に深い歴史と友好の絆を持っています。
🇱🇦 日本とラオスの長きにわたる友好の歴史
- 外交関係樹立70周年: 日本とラオスは、外交関係を結んでから今年で70年を迎えます。長年にわたり、国を越えた友好が続いています。
- JICAによる支援60年: 国際協力機構(JICA)がラオスで途上国支援を始めてから60年。教育やインフラ、医療など、様々な分野で日本の支援が行われてきました。
この節目に愛子さまが訪問されることは、両国の友好関係をより一層深める、大きな意味を持っています。
💣 悲しい歴史と平和への願い

コラムには、ラオスが持つ悲しい歴史についても触れられています。ラオスはベトナム戦争中、アメリカ軍の激しい空爆の標的となり、世界一とも言われるほどの大量の不発弾(UXO:Unexploded Ordnance)が今も地中に残っています。
- 空爆の理由: 南北ベトナムをつなぐ「ホーチミン・ルート」がラオス国内を通っていたため、このルートを断ち切るために空爆が行われました。
- 不発弾の現実: 投下された爆弾のうち、使えずに残ってしまったものが、今も多くの人々の生活を脅かしています。
愛子さまは、首都ビエンチャンで不発弾の被害を発信する拠点も訪ねられました。これは、過去の悲劇を風化させず、平和の尊さを世界に伝えるという、日本の皇室の静かで強い願いを示す行動と言えます。不発弾除去の活動には、日本も長年技術や資金面で協力しており、平和な未来への願いが込められています。
🕊️ 旅が結ぶ文化と心:読者の皆さまへ
ラオスへの旅は、愛子さまにとって初めての公式外国訪問というだけでなく、日本とラオスの文化、歴史、そして未来を深く知る貴重な機会です。
🌏 世界に目を向けるきっかけに

私たちは普段の生活の中で、遠い国や文化について考える機会は少ないかもしれません。しかし、愛子さまのラオスご訪問のニュースや、小松さんのような活動を知ることで、世界には私たちと似た文化や知恵があり、また、想像もつかないような悲しい歴史を抱える国があることを改めて感じます。
- 食文化の共通点: ラオスの発酵食と日本のなれずし。
- 平和への共通の願い: 不発弾の脅威からの解放。
これらは、私たちがラオスという国に親しみを感じ、共感できる大切な要素です。
💖 旅の思い出を未来へ
コラムの結びには、愛子さまが2012年にラオスを訪問された天皇陛下(当時は皇太子さま)のアルバムを囲んで話されたというエピソードが紹介されています。
遠い異国の地で、愛子さまがどのような人々と出会い、どのような光景をご覧になり、どんな言葉を交わされたのか。その一つ一つの体験が、きっと未来の国際的な活動の糧となるでしょう。
私たち一人ひとりも、異文化を理解しようとする心、平和を願う心を持つことが、世界との「心の橋渡し」になると信じています。
まとめ:ラオスへの関心が高まる今

今回のコラムは、ラオスという国が持つ食の知恵、長年の日本との友好、そして平和への強い願いを、改めて私たちに教えてくれました。これを機に、ラオス料理を食べてみたり、文化を調べてみたりしてはいかがでしょうか。きっと、私たち自身の世界観が広がる素敵な発見があるはずです。





![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4e5112ea.255b1e0f.4e5112eb.c42cea92/?me_id=1409937&item_id=10000141&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fokcoffee%2Fcabinet%2Fitem%2Fcoffee-beans%2Flaosbig1.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)