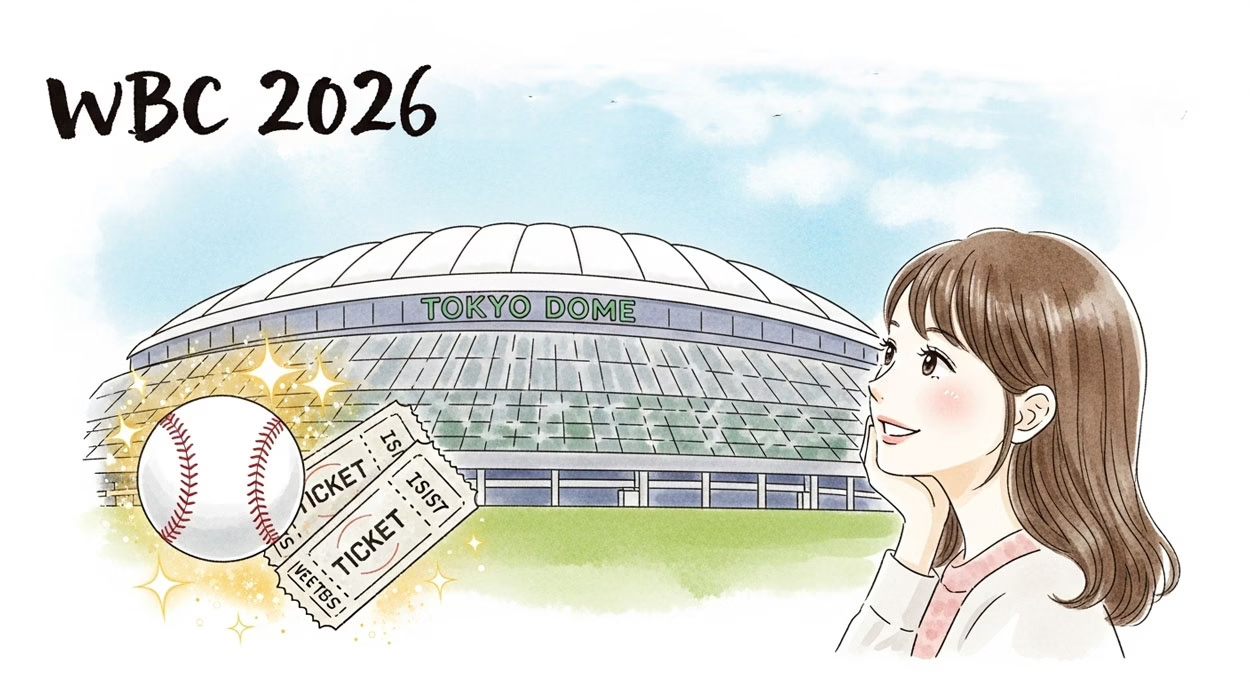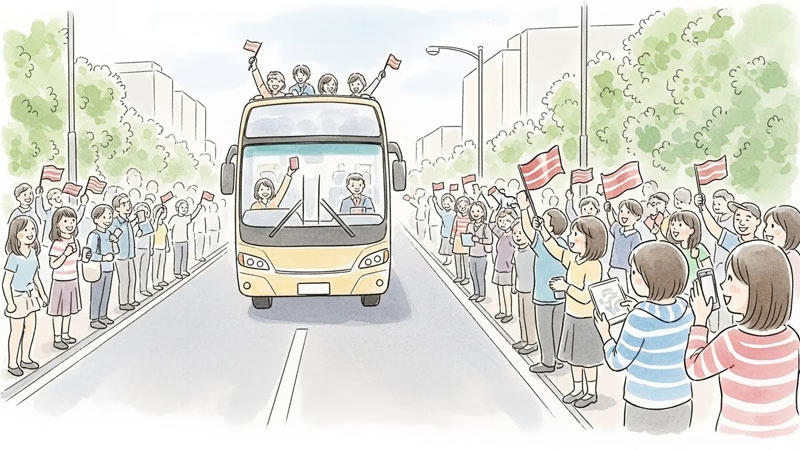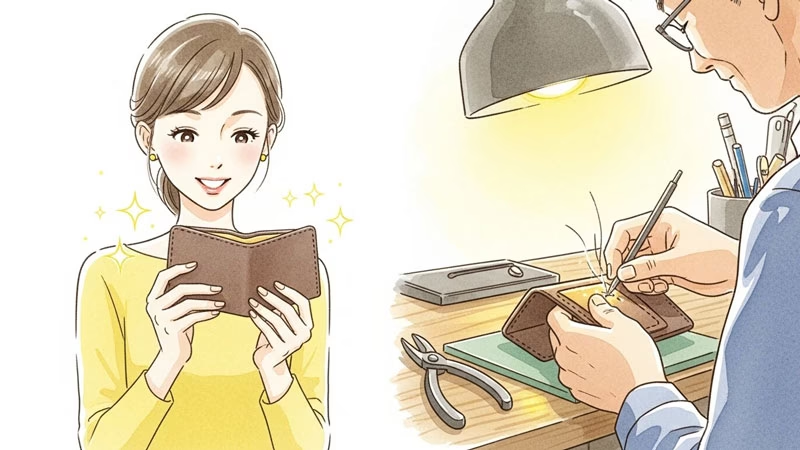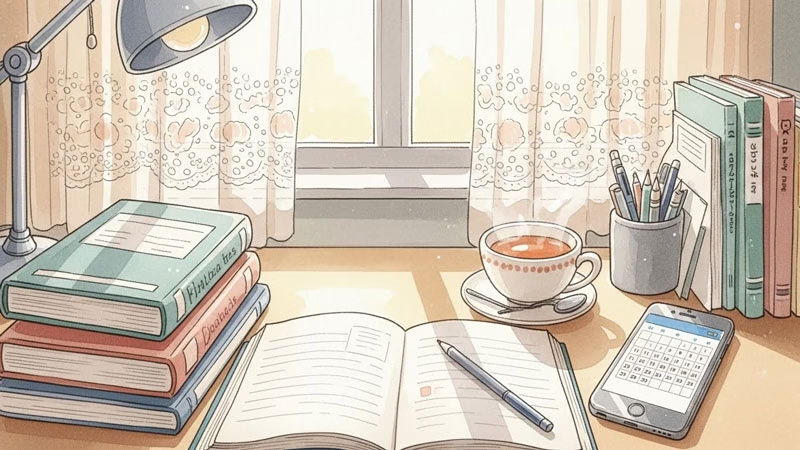日本経済新聞 2025年8月5日(火曜日)の要約と、統計との上手な付き合い方
なんだか「統計」って聞くと、ちょっと身構えてしまいませんか?「数字ばっかりで難しそう…」「自分には関係ないかな?」なんて感じている方も、実は少なくないかもしれません。
でも、今日の日本経済新聞のコラム「春秋」を読んで、そんな統計が、私たちの日常や社会のあり方と、とっても深く関わっていることを改めて感じさせられました。
この記事では、まずコラムの内容を優しく要約しながら、多くの人が抱く「統計って、なんだか信用できない…」というモヤモヤの正体を探っていきます。そして、どうして統計が「嘘」だと言われてしまうことがあるのか、そのカラクリを解き明かしながら、賢く数字と付き合っていくためのヒントを、分かりやすくお伝えしていきますね。
この記事を読み終わる頃には、ニュースで目にする数字やグラフが、今までとは少し違って見えてくるかもしれませんよ。
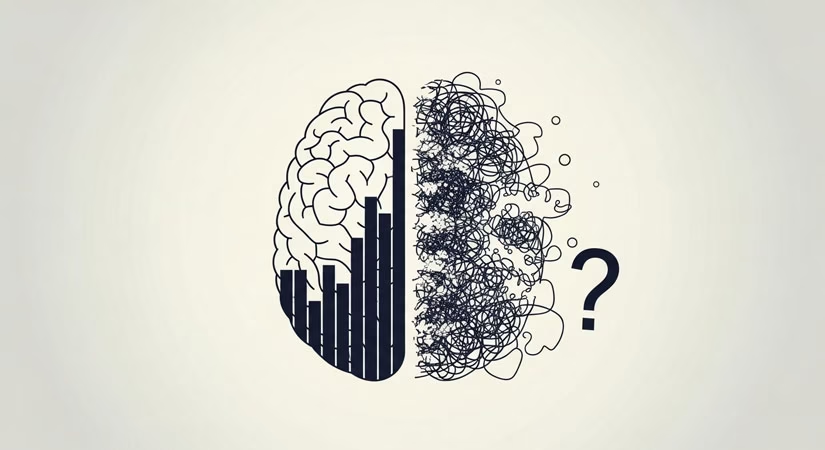
今日の日経「春秋」コラムをのぞいてみよう
まずは、今日のコラムがどんな内容だったのか、ポイントをかいつまんでご紹介しますね。
【2025年8月5日 日経新聞「春秋」要約】
総務省が毎年募集している統計の標語には、「論より数字 勘より統計」(2003年)のように、勘に頼ることの危うさを説く味わい深いものがある。一方で、「水と空気と統計と」(1989年)という標語は、これらが汚染されたら大変なことになる、という風にも読み取れる。
かの有名な作家マーク・トウェインが広めたとされる「嘘には3つの種類がある。嘘、大噓、そして統計だ」という言葉があるように、統計は時に不信の目で見られてきた。
しかし、複雑な現代社会で的確な判断を下すためには、統計データは絶対に欠かせない。
そんな中、アメリカで、雇用統計の結果(下方修正)に大統領が腹を立て、労働省の担当局長をクビにしたという驚きのニュースが。さらに「政治的な操作だ」とまで言い出したという。
統計の信頼性が、国のトップによって揺るがされるなんてことが先進国アメリカで起これば、その影響は計り知れない。「統計より独裁」なんて皮肉な標語が思い浮かぶほどの事態に、筆者は深い溜息をついている。
このコラムを読むと、統計って、私たちの生活に欠かせない「ものさし」のようなものなのに、その「ものさし」が権力によって歪められてしまうかもしれない、という怖さを感じますよね。
では、なぜ統計は「嘘つき」なんて言われてしまうことがあるのでしょうか?その秘密を探っていきましょう。
なぜ?「統計は嘘」と言われる3つのワナ

コラムにも登場した「嘘には3つの種類がある。嘘、大噓、そして統計だ」という言葉。これは、統計そのものが悪だと言っているわけではないんです。
本当の意味は、**「数字は嘘をつかないけれど、嘘つきは数字を巧みに使う」**ということ。つまり、見せ方や使い方次第で、人をだます強力な道具にもなり得る、という警告なんですね。
では、具体的にどんな「ワナ」があるのか、私たちの身近な例と一緒に見ていきましょう。
ワナ1:元になるデータ(サンプル)の偏り
統計は、何かを調べる時に、対象者全員に聞くのではなく、一部の人を抜き出して(これをサンプルと言います)調査することがほとんどです。でも、このサンプルの選び方に偏りがあると、結果も当然、偏ったものになってしまいます。
| ワナの例 | 解説 |
| 「都心で聞いた!今年の夏のボーナス平均額は100万円!」 | もしこの調査が、高所得者が多く住むエリアの、しかも平日の昼間に、駅前でスーツを着た人だけに聞いていたらどうでしょう?パートタイマーや学生、地方で働く人の状況は全く反映されませんよね。これでは、世の中全体の平均とは言えません。 |
| 「主婦100人に聞いた!今、一番人気の洗剤はコレ!」 | 例えば、特定のスーパーの会員だけにアンケートを依頼していたとしたら?そのスーパーでしか扱っていない商品が1位になるのは当たり前かもしれません。 |
このように、**「誰を対象に」「どうやって」**調査したのかが、とても重要なんです。
ワナ2:グラフの見た目にだまされる!
数字の羅列よりも、グラフになっていると、なんだか一目で分かった気になってしまいますよね。でも、このグラフこそが、視覚的なトリックを仕掛けやすい場所なんです。
一番よく使われるのが、**「縦軸の目盛りを操作する」**という手口です。
【例】ある商品の売上推移グラフ
<br>
Aのグラフ(正直なグラフ)
- 縦軸が「0」から始まっている
- 4月の85個と5月の90個の差が、それほど大きくないことが分かる
Bのグラフ(印象操作されたグラフ)
- 縦軸が「80」から始まっている
- 少しの変化が、ものすごく大きな伸びに見える!
- 「売上V字回復!」なんて見出しがついていたら、信じてしまいそうですよね。
他にも、円グラフの一部を立体的にして大きく見せたり、わざと項目を合算して特定の部分を多く見せたりと、様々なトリックがあります。グラフを見るときは、「お、すごい!」とすぐに飛びつかず、軸の数字や項目の分け方を冷静にチェックするクセをつけたいですね。
ワナ3:都合のいい部分だけの「切り取り」

これも、とてもよくあるパターンです。たくさんの調査結果の中から、自分たちの主張に都合のいいデータだけを抜き出して、それがあたかも全体の結論であるかのように見せる方法です。
コラムにあった米雇用統計の話も、ここに繋がります。もし、全体の数字が悪化している(下方修正された)のに、「一部の業種では雇用が増えている!」という部分だけを大々的にアピールしたら、全体の印象は大きく変わってしまいますよね。
| ワナの例 | 解説 |
| 「我が社の新商品の顧客満足度は95%!」 | 実は「非常に満足」「満足」「まあまあ満足」を全部合算した数字で、「不満」と答えた人の数は公表していない、なんてことも。 |
| 「このサプリで、80%の人がダイエットに成功!」 | 「ただし、適度な運動と食事制限を併用した方に限ります」という小さな注釈が、隅っこに書かれているかもしれません。 |
情報を受け取るときは、「何か隠されている部分はないかな?」「反対のデータはないのかな?」と、少しだけ探偵のような気持ちで見てみるのがおすすめです。
それでも統計が「社会のインフラ」である理由
ここまで聞くと、「やっぱり統計って怖い…」と感じてしまうかもしれません。でも、コラムの「水と空気と統計と」という標語が示すように、正確な統計は、私たちが安心して暮らせる社会に欠かせない、電気や水道のような社会インフラなんです。

理由1:勘や経験だけでは見えない「事実」を教えてくれる
「昔からこうだったから」「私の周りではこうだから」といった勘や経験は、もちろん大切です。でも、社会全体のような大きなものを動かすとき、それだけでは判断を誤ってしまうことがあります。
コラムの「論より数字 勘より統計」という標語は、まさにそのことを言っています。
- お店の経営:勘だけで商品を仕入れるのではなく、「どの年代の人が」「何時頃に」「何と一緒に」買っていくかというPOSデータを分析すれば、無駄な在庫を減らし、売上を伸ばすヒントが見つかります。
- 新しい街づくり:国勢調査などの統計データを使って、その地域に子育て世代が多いのか、お年寄りが多いのかを把握することで、本当に必要な施設(保育園なのか、介護施設なのか)を計画的に作ることができます。
客観的なデータという土台があるからこそ、私たちはより的確な判断ができるようになるんですね。
理由2:経済の「体温計」として健康状態をチェックする
コラムのテーマにもなっていた米国の雇用統計。なぜ、このニュースが世界中で大きく報じられるのでしょうか?
それは、雇用統計がアメリカ経済、ひいては世界経済の**「体温計」や「健康診断」**のような役割を果たしているからです。
| 統計指標 | 分かりやすく言うと… | 私たちの生活への影響 |
| 非農業部門雇用者数 | 「アメリカで、農業以外で働く人が先月から何人増えた(減った)か」という数字。景気の勢いを表します。 | 景気が良い(雇用が増える)と、アメリカの企業が儲かり、日本の株価も上がる傾向があります。 |
| 失業率 | 「働きたいのに仕事がない人が、どれくらいいるか」という割合。これが低いほど、景気が良いとされます。 | アメリカの景気が良くなると、ドルが買われて「ドル高・円安」になりやすく、輸入品の価格が上がったり、海外旅行の費用が高くなったりします。 |
| 平均時給 | 「みんなのお給料が、どれくらい上がっているか」という数字。物価の動き(インフレ)を予測する手がかりになります。 | お給料が上がりすぎると、インフレを抑えるためにアメリカが金利を上げるかもしれません。すると、日本の住宅ローン金利にも影響が及ぶ可能性があります。 |
このように、遠い国の経済指標が、巡り巡って私たちの給料や資産、日々の買い物にまで影響を与えているんです。だからこそ、その大元となる統計データの信頼性は、絶対に守られなければならないんですね。
ニュースの裏側!米国の「解任劇」がなぜ大問題なのか
コラムで触れられていた、「大統領が雇用統計の結果に怒って担当者をクビにした」という話。これがなぜ、ただのゴシップでは済まされない「大問題」なのか、もう少し掘り下げてみましょう。

問題点1:統計の「中立性」が脅かされる
公的な統計というのは、誰からも影響を受けない「中立」な立場で、ありのままの事実を数字で示すからこそ、価値があります。
そこに「この数字は、私(大統領)の政策のおかげだ」とか「この悪い数字は、何かの間違いだ」といった、政治的なトップの意向が入り込むとどうなるでしょう?
それは、審判がいるはずのスポーツの試合に、片方のチームの監督が「今の判定は気に食わないから、審判を交代させろ!」と介入してくるようなものです。そんな試合、誰もフェアだとは思いませんよね。
問題点2:「経済の体温計」が壊れてしまう
もし、「大統領を怒らせないように、少し数字を良く見せておこう…」なんて忖度が現場で働くようになったら、統計はもはや事実を映す鏡ではなくなります。
そうなると、先ほどお話しした「経済の体温計」が、完全に壊れてしまうことになります。
- 投資家:どの情報が正しくて、どの情報が操作されているのか分からなくなり、安心して投資ができなくなります。世界の金融マーケットは大混乱に陥るでしょう。
- 企業:信頼できるデータがなければ、設備投資や採用計画といった将来の計画を立てることができません。
- 私たち:政府が発表する景気判断や物価のデータが信じられなくなれば、将来への不安は増すばかりです。
コラムが「統計より独裁」と皮肉っていたのは、まさにこの点です。客観的なデータ(統計)を無視して、トップの考えだけで物事を進めるのは、独裁と何ら変わりがない、という強い警告が込められているんですね。
明日からできる!賢く数字と付き合うための3ステップ
「じゃあ、私たちはどうすればいいの?」「専門家じゃないし、難しいことは分からない…」
大丈夫です!なにも統計の専門家になる必要はありません。ちょっとした心構えを持つだけで、「数字にだまされる」リスクはぐっと減らすことができます。
今日からできる、3つの簡単ステップをご紹介しますね。
ステップ1:「本当かな?」と一度立ち止まるクセをつける
「衝撃!」「驚きの結果!」といったセンセーショナルな見出しや、あまりに良すぎる(または悪すぎる)数字に出会ったとき。すぐに信じてしまう前に、まずは「おっと、本当かな?」と、心の中で一度ブレーキを踏んでみましょう。
特に、SNSなどで情報が光の速さで広まる現代では、この**「一度立ち止まる」というワンクッション**が、とっても大切になります。感情的に「すごい!」「ひどい!」と反応する前に、一呼吸おいて冷静になる時間を作りましょう。
ステップ2:「誰が調べたデータ?」をチェックする
次に、その情報が**「どこから来たのか(情報源)」**を少しだけ気にするようにしてみてください。
- 公的機関(総務省統計局、厚生労働省など):
- 国勢調査のように、法律に基づいて行われる大規模な調査が多いです。
- 信頼性は非常に高いですが、結果が出るまでに少し時間がかかることも。
- 政府の公式サイト(URLの末尾が .go.jp になっているもの)で元データを確認できます。
- 民間企業・調査機関:
- 特定のテーマについて、スピーディーに調査が行われます。
- マーケティングや商品開発など、目的がハッキリしていることが多いです。
- 「どんな会社が」「何のために」調べているのかを考えると、データの背景が見えやすくなります。
「このグラフは、〇〇総合研究所の調査によるものです」といった一文があるかどうかを確認するだけでも、情報の信頼性を判断する大きな手がかりになりますよ。
ステップ3:数字の「背景」を想像してみる
これが、一番のキモかもしれません。数字そのものを見るだけでなく、その数字が生まれた「背景」に、少しだけ思いを馳せてみましょう。
- 「このアンケート、どんな人に聞いたんだろう?」
- (例:若者向け商品の調査なのに、答えているのが高齢者ばかりだったら…?)
- 「いつの時点のデータかな?」
- (例:コロナ禍前のデータを使って、「旅行業界は好調です」と言われても…?)
- 「比べ方は、おかしくないかな?」
- (例:A市の「犯罪件数」とB町の「犯罪発生率」を比べて、「A市の方が危ない!」と言うのは、フェアじゃないですよね)
完璧に分析する必要はありません。「もしかしたら、こういう見方もできるかも?」と、別の角度から考えてみる。この想像力こそが、数字の裏側を見抜く最強の武器になります。
まとめ:統計は「敵」ではなく、賢く付き合う「味方」

今日のコラムをきっかけに、「統計」という、ちょっととっつきにくいテーマを深掘りしてみました。
「統計は嘘つき」という言葉は、私たちに「数字を鵜呑みにしないで!」という大切なメッセージを伝えてくれています。意図的に作られたグラフや、都合よく切り取られたデータに惑わされないためには、少しだけ立ち止まって「これって本当かな?」と考えるクセをつけることが何より大切です。
アメリカのニュースのように、統計の信頼性が揺らぐような出来事は、私たちの社会の土台を揺るがす、とても深刻な問題です。
でも、統計は決して私たちの「敵」ではありません。正しく付き合う方法さえ知れば、世の中の動きを正確に理解し、自分の暮らしや将来を考える上で、これ以上ないほど頼りになる「味方」になってくれます。
明日からニュースを見るとき、広告のグラフを目にするとき、ぜひ今日お話しした3つのステップを思い出してみてくださいね。きっと、今まで見過ごしていた「おや?」という小さな気づきが、たくさん見つかるはずですよ。
<PR>データ分析や資料作成は、思考のスピードが命。処理の重いExcelファイルや、複数のウィンドウを開いた瞬間にPCが固まっていては、あなたの貴重な時間と集中力は奪われるばかりです。思考を止めないハイスペックPCや、作業効率を劇的に改善するデュアルモニターは、もはや贅沢品ではなく『ビジネス戦闘力を高めるための必需品』。最高のパフォーマンスを発揮するための環境投資を検討しませんか。