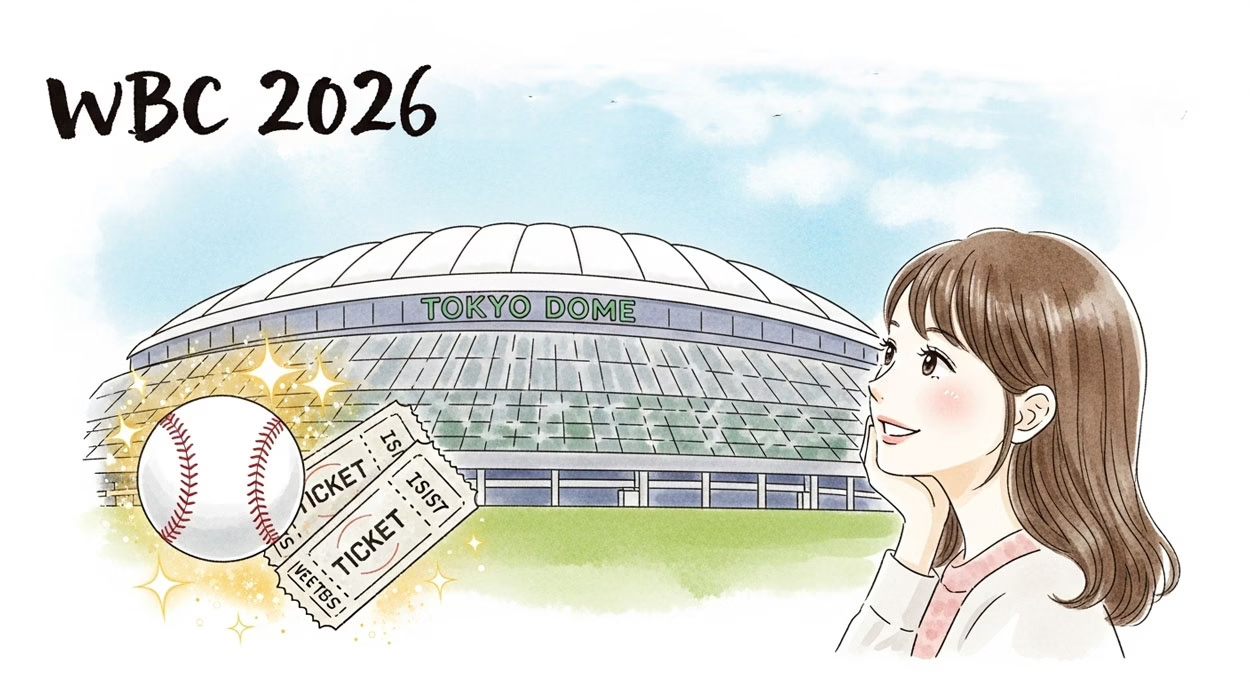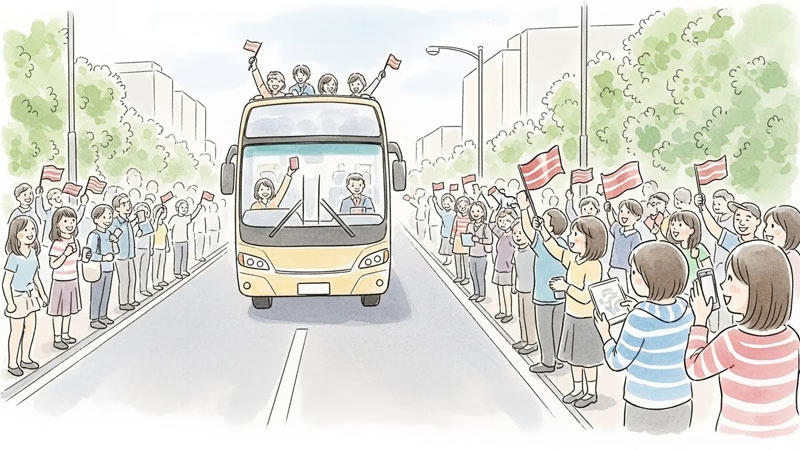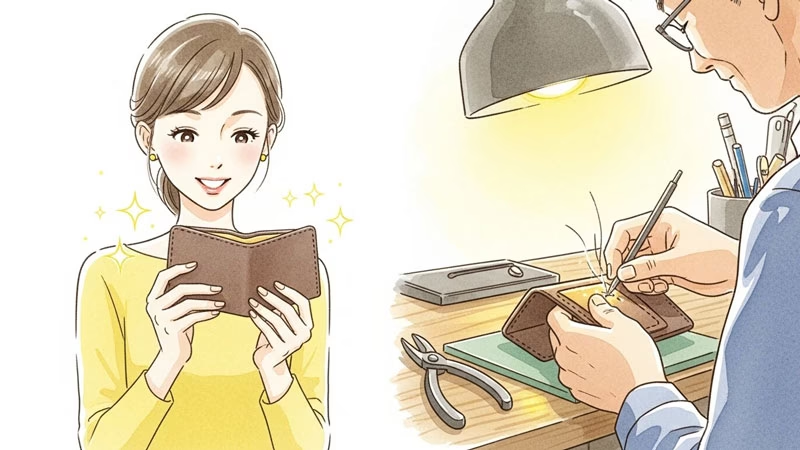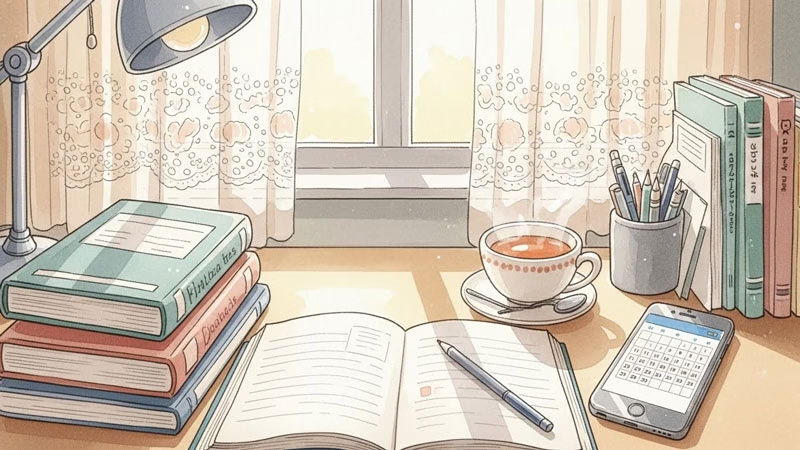2025年10月5日(日)朝刊春秋の要約と自民党総裁選・新総裁への期
はじめに:永井柳太郎が説く「政治家三原則」とは?
日本の政治の動きは、私たちの生活と切っても切り離せません。特に、トップリーダーが変わる「総裁選」は、国の未来を左右する大切なイベントです。
今回の自民党総裁選を受けて、日本経済新聞のコラム「春秋」では、戦前の政治家である永井柳太郎が説いた 「政治家三原則」 を引用し、選挙戦と新総裁の資質を考察しています。
日本経済新聞「春秋」からの引用
政治家に最も必要な素養は「信念、聡明(そうめい)、雄弁」の3つである――。名演説家として知られた戦前の政治家、永井柳太郎がそう説いている。まず不抜の信念。聡明は国民が要請することを読み取る力だ。そして自身の考えを世の中に正確に理解させる雄弁が欠かせない。
▼今回の自民党総裁選がこれらを満たすものだったかと問われれば、逡巡(しゅんじゅん)せざるをえない。意見が割れやすい論点を封印したり、穏当な主張にとどめたりと、信念に疑問符がつく場面が目立った。国民が求める将来を見据えた改革の議論も深まらぬまま。排外主義的に映る主張を重ねるなど、弁舌も小粒だったように感じる。
この記事では、この「政治家三原則」を手がかりに、今回の総裁選を振り返り、新総裁に就任した高市早苗さんのリーダーシップと、私たちの暮らしに関わる注目の発言について、女性の視点から掘り下げていきます。
I. 永井柳太郎の「信念、聡明、雄弁」を読み解く
永井柳太郎氏が提唱した三原則は、現代のリーダーシップにも通じる普遍的な価値を持っています。
1. 「不抜の信念」:ブレない軸を持つことの大切さ

信念とは、「何があっても曲げない、強い思い」です。
- 政治における意味:単なる人気取りや、その場の空気に流されることなく、「国や国民のために、自分はどうあるべきか」という揺るぎない志を持つことです。
- コラムの指摘:今回の総裁選では、候補者たちが意見の分かれる難しい論点(例:財政再建、社会保障改革など)を避け、当たり障りのない主張に留まったため、「本当に国を変える信念があるのか?」と疑問視されています。
信念があるからこそ、困難な改革にも踏み切ることができます。私たちも、自分の仕事や子育て、生き方において「これだけは譲れない」という信念を持つことは、芯のある人生を送る上で大切ですよね。
2. 「聡明(そうめい)」:国民の声を聴き、未来を見通す力
聡明とは、「賢く、物事の道理がよくわかること」です。単なる知識の多さではなく、国民が本当に何を求め、将来どのような社会が必要かを「読み取る力」です。
- 政治における意味:表面的なアンケート結果だけでなく、人々の不安や期待を深く理解し、未来を見据えた政策を作り出す知恵です。
- コラムの指摘:将来を見据えた、抜本的な改革についての議論が深まらなかったことは、この「聡明」さが不足していたと言えるかもしれません。
特に女性は、日々の生活の中で、子どもの教育、介護、家計のやりくりなど、様々な課題に直面しています。こうした 「現場の切実な声」 を、政治家が敏感に感じ取り、解決に導く「聡明」さが求められます。
3. 「雄弁」:考えを正確に伝え、共感を呼ぶ言葉の力
雄弁とは、「説得力があり、聞き手を惹きつける話し方」です。これは、ただ声が大きいとか、流暢に話すという意味ではありません。
- 政治における意味:自身の考えや政策の「真意」を、国民に正確に、そして心から理解してもらい、共感・協力してもらうための「伝える力」です。
- コラムの指摘:一部の主張が「排外主義的」に聞こえたり、議論が深まらなかったりしたことで、候補者の「弁舌が小粒だった」と評されています。
永井柳太郎は、「真意が理解されなければ、政治的理想は遂げられぬ」とも言っています。どんなに良い政策も、人々に伝わらなければ、絵に描いた餅になってしまいます。
II. 新総裁・高市早苗氏への期待と「ワークライフバランス」発言の真意

今回の総裁選の結果、自民党は初の女性トップとして高市早苗氏に再建を託しました。
1. 長年の努力が実った初の女性総裁
高市氏が総裁の座に就いたことは、女性の社会進出という点で大きな一歩です。
- コラムの視点:これまでは「お仲間が少ない」と言われることもあったようですが、党員票も議員票も幅広く集めたのは、地道な努力の積み重ねの結果だと評価されています。
- 目標とする姿:英国のマーガレット・サッチャー元首相を目標としてきた高市氏。その強い信念と実行力に、期待が集まります。サッチャー氏は、鉄鋼王国の女性首相として、厳しい改革を断行したことで知られています。
女性がトップリーダーになることは、私たち女性が社会で活躍する上で大きな励みになりますね。
2. 懸念された「ワークライフバランスを捨てる」発言の真意
コラムでは、高市氏が演説で述べた「ワークライフバランスを捨てる」という言葉について、「強い言葉は誤解にもつながる」と懸念を示しています。
| 発言の概要 | コラムの指摘・懸念 |
| 「ワークライフバランスを捨てる」 | 高揚感から出た言葉かもしれないが、強い言葉は誤解を招く。 |
| 懸念される誤解 | 「女性のキャリアのためには、家庭や私生活を犠牲にすべき」というメッセージと受け取られかねない。 |
この発言は、多くの働く女性、特に子育てや介護と仕事の両立に奮闘している女性にとって、非常にセンシティブな問題です。
💡 発言の「真意」を推測する
おそらくこの言葉の裏には、次のような意図があったと考えられます。
- 国家の危機感:今の日本が直面している経済的、社会的な問題を解決するためには、リーダーや政府が文字通り「寝食を忘れる」ほどの覚悟と情熱を持って、仕事に打ち込むべきだ、という決意表明。
- 自己犠牲的な献身:自らのリーダーとしての姿勢を示し、「私が率先して全身全霊を捧げる」という熱意を伝えること。
しかし、言葉は受け取り手がすべてです。特に、 「ワークライフバランス」は、現代社会において「豊かで健康的な生活」 を送るための重要な概念であり、単なる「なまけ」を意味するものではありません。
- 女性の視点から:女性は仕事だけでなく、出産、育児、家事、介護といった、 「見えない労働」 も担っています。この発言が「女性にも男性並みの自己犠牲を求める」と受け取られてしまうと、新たな女性活躍の妨げになりかねません。
3. これからのリーダーに求められる「丁寧な雄弁」
高市氏には、これからは一党のリーダーとして、「言葉が国民に直行する」立場であることを深く認識し、その 「信念」を「丁寧な雄弁」 によって伝えていくことが求められます。
- 誤解を招く強い言葉の回避:高揚感からであっても、感情的な言葉ではなく、理性と論理に基づいた説明が必要です。
- 言葉の「言い換え」の重要性:「ワークライフバランスを捨てる」ではなく、「難局打開のため、全精力を傾けて仕事に邁進する覚悟」のように、誤解の余地がない平易な言葉に言い換える努力が大切です。
- 国民を「まとめる」力:多様な価値観を持つ国民に対して、高市氏の描く未来図を正確に伝え、共感を呼び、皆を同じ方向に向かせる力が、今後の政権運営の鍵となります。
III. 読者にとって有益な視点:私たちが政治に求めること

今回の総裁選の動きや新総裁の発言から、私たち有権者が政治家に対して何を期待し、どう向き合うべきかを考えましょう。
1. 「封印された論点」を掘り起こす必要性
総裁選で十分に議論されなかった 「意見が割れやすい論点」 こそ、私たちの未来に関わる重要な問題です。
| 封印されがちな論点 | 私たちへの影響(女性目線) |
| 財政再建 | 子どもたちの世代に重い借金を残すことになる。将来の増税や社会保障費の削減に直結。 |
| 社会保障改革 | 介護や年金制度の持続可能性。特に女性は、自身の老後の不安や、家族の介護負担に直面することが多い。 |
| 少子化対策の抜本策 | 仕事と育児を両立できる環境の整備。働き方改革の具体策。 |
私たちは、政治家がこれらの論点を避けているとき、「なぜ議論しないのか?」と積極的に問いかける 「聡明な有権者」 であるべきです。
2. 「丁寧な雄弁」を促すための私たちの役割
政治家の「雄弁」は、 「聞き手」 である私たちの存在によって磨かれます。
- 一方的な情報で判断しない:高市氏の「ワークライフバランス」発言のように、強い言葉はキャッチーですが、私たちはその背景や真意を深く読み取ろうとする姿勢が大切です。
- 質問する姿勢:ニュースやSNSで流れる情報に「なぜそうなるのか?」「本当の狙いは何か?」と疑問を持ち、情報の裏付けを取ることで、より正確な理解に努めましょう。
- 政策を「自分の言葉」で考える:政治の言葉を難しく感じるときは、「それは自分の仕事や家族にどう影響するだろう?」と言い換えて考えてみましょう。
政治とは、一部の政治家だけの問題ではなく、私たち一人ひとりの日々の選択の積み重ねでできています。
まとめ:新時代に求められる真のリーダーシップ
永井柳太郎の説いた 「信念、聡明、雄弁」 の三原則は、現代においてもリーダーに欠かせない資質です。
新しい女性リーダーが誕生した今、私たちは彼女に、不抜の信念と国民の要請を読み取る聡明さを期待するとともに、 誤解を生まない「丁寧な雄弁」 で、日本の未来を語り続けてほしいと願っています。
私たちもまた、政治の動きに無関心にならず、聡明な視点でリーダーの言葉を吟味し、より良い社会の実現に向けて声を上げていきましょう。