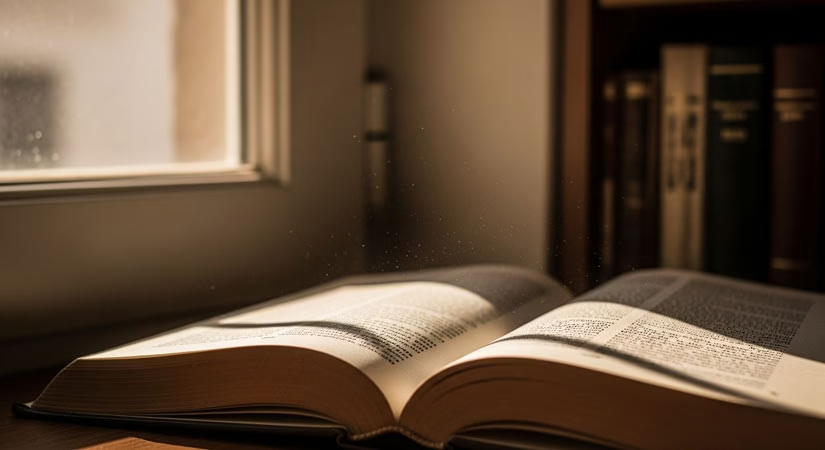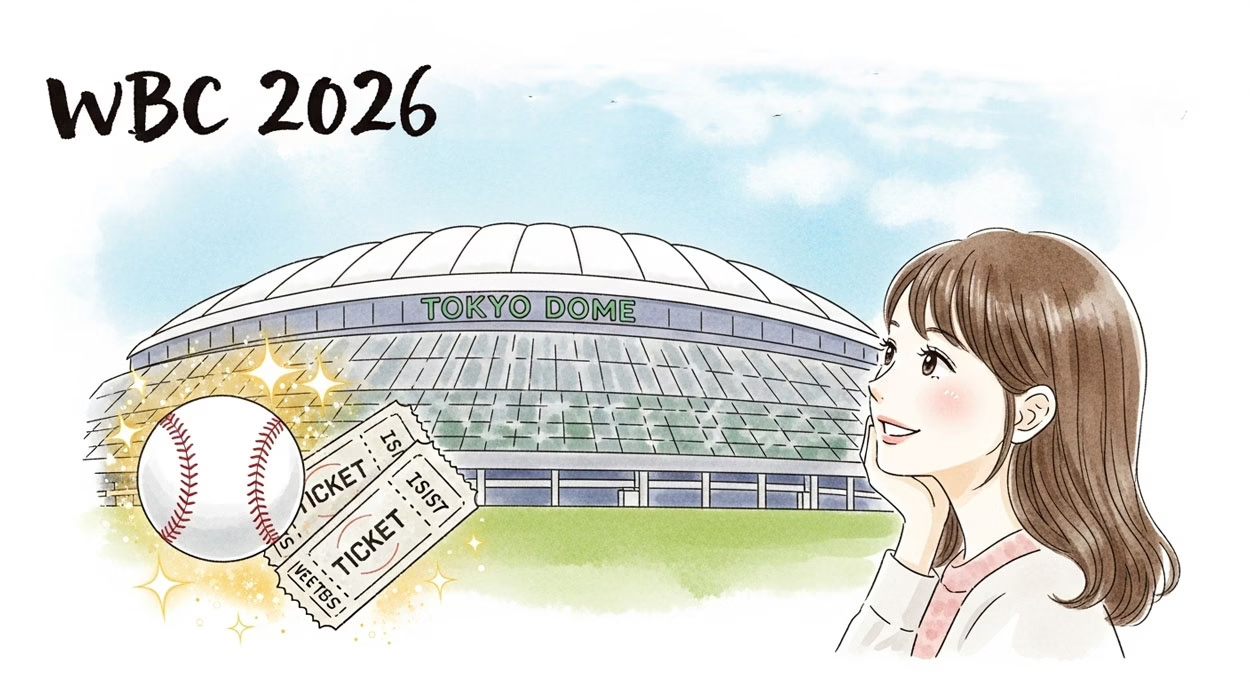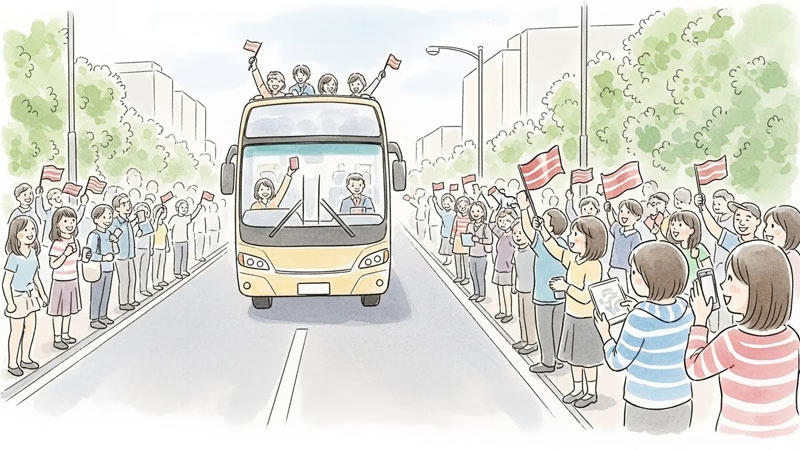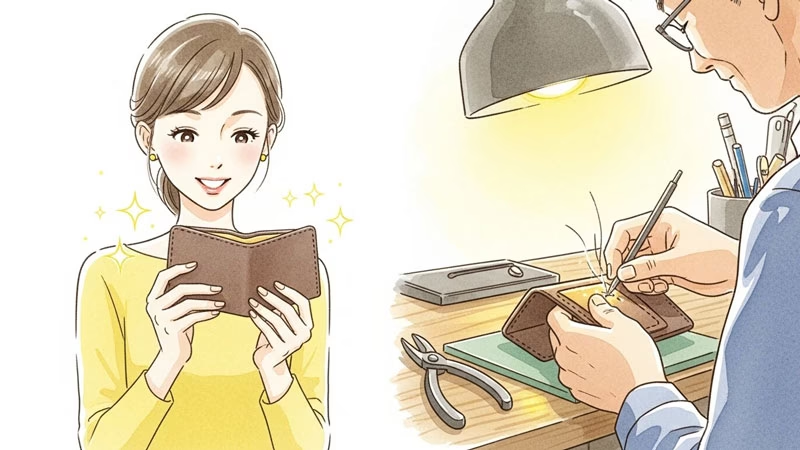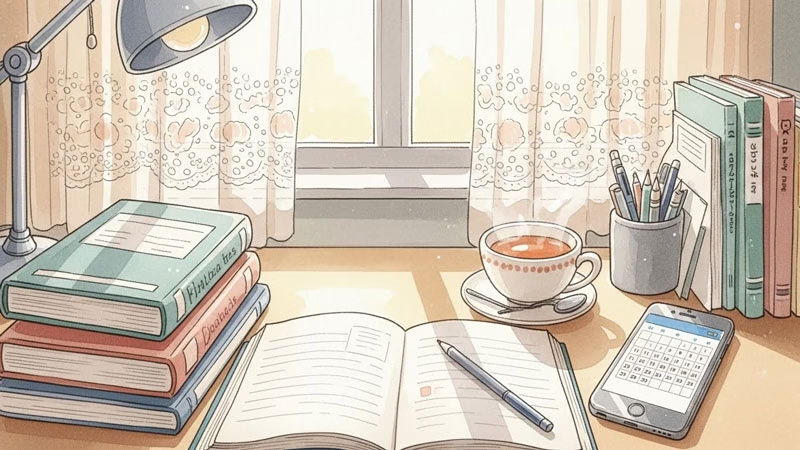日本経済新聞 2025年8月6日(水)の要約と未来への責任
作家・大田洋子氏が広島での被爆体験を記した『屍(しかばね)の街』。コラムは、戦後も続く放射線への不安を「新しい苦しみ」と表現し、作家としての責任感から惨禍を書き残した彼女の姿を紹介。GHQの言論統制や文壇からの非難など、作品が辿った困難な道にも触れつつ、体験者が減る今、残された言葉を未来へどう繋ぐか、その「バトン」は私たちにあると問いかけています。
「戦争が終わっても、まだ戦争のために人が死んでいく。それが不思議なんだ」
この言葉に、あなたは何を感じるでしょうか。
これは、80年近く前に書かれた小説の一節です。書いたのは、作家・大田洋子(おおた ようこ)。彼女は、広島で原子爆弾の投下を体験した一人でした。
毎年夏になると、私たちは戦争や平和について、改めて考える機会を持ちます。けれど、それは遠い過去の出来事で、どこか自分とは切り離された物語のように感じてしまう…。そんな方も、きっと少なくないはずです。
この記事では、今改めて注目されている大田洋子の小説『屍の街』を道しるべに、一緒に考えていきたいと思います。
- 作家・大田洋子ってどんな人? なぜ彼女は、言葉にするのもつらい体験を、書き残そうと決めたのでしょうか。
- 『屍の街』はどんな物語? 投下直後の惨状だけでなく、彼女が「新しい苦しみ」と呼んだ、終わらない不安の正体とは?
- なぜ作品はすぐ世に出なかったの? GHQによる規制や、心ない声との闘い。
- 私たちにできることは? 体験の記憶を直接聞くことが難しくなる時代に、大切なバトンをどう受け取り、未来へつなげていけるのでしょうか。
この記事を読み終える頃には、歴史の一ページが、あなたの心にそっと寄り添う「自分ごと」の物語として感じられるかもしれません。どうぞ、最後までお付き合いくださいね。
大田洋子ってどんな人? – ペンに込めた静かなる使命感

「いつかは書かなくてはならない。これを見た作家の責任だもの」
変わり果てた故郷の街で、彼女はそう心に誓いました。大田洋子がなぜ、これほどまでに強い使命感を抱くに至ったのか、その人生を少しだけご紹介します。
被爆した「作家」としての責任
大田洋子は、1903年、広島市に生まれました。原子爆弾が投下された1945年の時点で、すでに何冊も本を出版している、プロの小説家でした。戦争が激しくなり、東京から故郷の広島へ疎開していたまさにその時、彼女は被爆します。
目の前に広がる、筆舌に尽くしがたい光景。
言葉を失うほどの現実の中で、彼女は一人の人間として、そして何よりも「作家」として、「この事実を書き残さなければならない」という強い想いに駆られます。
それは、単に出来事を記録するというだけではありません。
声を発することもできずに亡くなった人々の無念、生き残った人々の静かな、しかし終わることのない苦しみ。そのすべてを言葉の力で伝えなければ、という切実な覚悟でした。
記憶が薄れてしまわないうちに、と手元にある限られた紙に、見たこと、感じたことを必死に書きつけたといいます。その切迫した思いの中から生まれたメモが、のちに『屍の街』という作品として形になるのです。
女性作家として歩んだ道
今でこそ、女性作家の活躍は当たり前の光景ですが、彼女が生きた時代は、まだ社会全体が男性中心に動いていました。
女性が社会問題について鋭く意見を述べたり、強い言葉で何かを訴えたりすることには、見えない壁が存在した時代です。特に、戦争や原爆という重いテーマについては、なおさらだったでしょう。日経新聞のコラムが指摘するように、「女性による怒りや抗議を嫌う」という風潮の中での執筆活動は、決して平坦なものではありませんでした。
それでも、彼女はペンを置かなかった。自分が体験した真実と、そこから湧き上がる想いを、ありのままに紡いでいく。その静かで揺るぎない意志が、彼女の作品に特別な力を与えているのかもしれません。
『屍の街』ってどんな物語? – 「終わらない不安」を描いた記録
『屍の街』は、投下直後の衝撃的な一日を描くだけでなく、その後の人々の心に深く根差した、静かな苦しみをも描き出した作品です。

あらすじと作品が描くもの
物語は、「死は私にもいつくるか知れない」という、静かな独白から始まります。
1945年8月6日。一瞬の閃光が、主人公である作家の日常をすべて奪い去ります。彼女は奇跡的に助かりますが、家族を失い、自らも傷を負いながら、見慣れたはずの街の、信じがたい光景の中を歩き続けます。
しかし、本当の苦しみは、その後も静かに、そして長く続きました。大田洋子は、それを「新しい苦しみ」と表現しています。
- 見えない脅威との闘い: 秋になり、少し落ち着いたかのように見えても、元気だった人が突然原因不明の病で倒れていく。
- 日常にひそむ不安: 自分の髪をそっと引っ張っては、抜け毛の数を数える。手足に、死の前兆と言われた紫の斑点が浮かんでいないか、絶えず確認してしまう。
- 消えない心の痛み: 助けを求める声にこたえられなかったという罪悪感。なぜ自分だけが生き残ってしまったのかという問い。
これが、彼女が描いた「新しい苦しみ」の正体です。
目に見える傷だけでなく、いつ自分の命が奪われるか分からないという、心の奥底に広がる「終わりの見えない不安」。戦争が終わっても、生き残った人々の心の中では、静かな闘いが続いていたのです。
今も響く、作中の言葉たち
『屍の街』には、時代を超えて私たちの心に響く言葉があります。
「戦争がすんでもまだ戦争のために現にこうやって死んで行く。そいつが不思議なんだ」
この言葉が持つ意味は、80年近く経った今も、決して色褪せません。世界を見渡せば、戦闘が終わった後も、心と体に深い傷を負い、苦しみ続ける人々がいます。この言葉は、武力衝突がもたらす悲しみが、いかに長く、そして理不尽であるかを私たちに伝えます。
「死は私にもいつくるか知れない」
これは、特別な体験をした人だけの言葉ではないのかもしれません。私たちの穏やかな日常も、実はとても繊細なバランスの上に成り立っている。この一文は、今ここにいること、今日という一日を大切に生きることの意味を、改めて問いかけてくるようです。
なぜすぐに出版されなかったの? – GHQの「プレスコード」

これほどまでに重要な記録である『屍の街』ですが、執筆後すぐに出版されたわけではありませんでした。その背景には、戦後日本の特殊な状況がありました。
| 時系列 | 出来事 | 内容 |
| 1945年8月 | 終戦 | 日本はポツダム宣言を受諾し、降伏。 |
| 1945年9月 | GHQによる占領開始 | アメリカを中心とする連合国軍総司令部(GHQ)が日本の統治を開始。 |
| 1945年9月19日 | プレスコード発令 | 新聞や出版など、あらゆるメディアに対する表現の指針(事実上の規制)が示される。 |
| ~1952年4月 | サンフランシスコ平和条約発効 | 日本が主権を回復するまで、プレスコードの影響は続く。 |
GHQが出した「プレスコード」は、報道や出版の内容に一定の制限をかけるものでした。特に、原子爆弾がもたらした被害の詳細な描写については、非常に慎重な扱いが求められました。
なぜ、原爆に関する情報が規制されたのか。
その一つには、原爆投下という行為がもたらした結果の深刻さが世界に広まることで、アメリカへの批判が高まることを避けたい、という政治的な配慮があったと考えられています。
そのため、『屍の街』のように、体験者が自身の目で見たありのままを記録した作品は、厳しい検閲の対象となり、すぐには人々の目に触れることが許されませんでした。表現が再び自由を取り戻すまで、約7年もの時間が必要だったのです。
「原爆を売り物にするな」 – 彼女を苦しめた心ない声
占領が終わり、ようやく作品が世に出た後も、大田洋子を待っていたのは穏やかな日々ではありませんでした。今度は、同時代の人々から、心ない言葉が投げつけられることになります。
時代の空気と文壇での孤立
戦後の日本は、「復興」を合言葉に、誰もが前を向いて歩もうと必死でした。
貧しい暮らしから抜け出し、新しい国を築いていく。そんな明るい未来を目指す空気の中で、過去のつらい記憶を繰り返し語ることは、一部で敬遠される風潮さえありました。
「もう終わったことなのに」
「いつまでも暗い話はやめて、未来のことを考えよう」
さらに、彼女が身を置いていた文壇(作家や評論家たちの世界)からも、「終わった原爆を売り物にする」という、あまりにも辛辣な批判が浴びせられました。
命がけの体験の記録が、なぜ「売り物」という言葉に変わってしまうのか。
それは、あまりに重いその事実を正面から受け止めることへの、人々の無意識の戸惑いや抵抗だったのかもしれません。また、女性である彼女が、社会にとって語りにくいテーマを追求し続けることへの反発も、少なからずあったでしょう。
それでも書き続けた理由
想像してみてください。
自らのすべてを懸けて書き上げた記録を、「商売道具」だと非難されるつらさを。
それでも、大田洋子は書くことをやめませんでした。
なぜなら、彼女にとって書くことは、お金や名声のためではなかったからです。それは、あの日の光景の中で出会った人々への祈りであり、生き残った者としての「責任」を果たすための、ただ一つの方法でした。
どんなに孤立し、批判されようとも、彼女には伝えなければならない真実がありました。その静かで強い信念こそが、彼女を生涯にわたって支え続けたのです。彼女の作品は、「原爆文学」というジャンルが確立されていく上で、なくてはならない大切な礎となりました。
バトンは私たちの手に – 未来へ記憶をつなぐためにできること

2025年。被爆者の平均年齢は85歳を大きく超えました。
あの日の広島や長崎で何があったのかを、ご自身の体験として語れる方は、本当に少なくなっています。
これは、私たちが歴史の大きな節目に立っていることを意味します。
体験者から直接、その声を聞く時代が終わりを迎え、残された言葉や資料を通して、私たちがその記憶を「継承」していかなければならない時代が、本格的に始まったのです。
日経新聞のコラムが「バトンは今を生きる私たちの手にある」と結んでいるように、その責任は、この記事を読んでいるあなたや、私の手の中にそっと託されています。
では、私たちには何ができるのでしょうか?
難しく考える必要はありません。今日からでも始められる、3つの小さなアクションをご紹介しますね。
私たちにできる3つのアクション
アクション1:【読む・知る】 まずは、そっと触れてみる
「継承」の第一歩は、何よりも「知る」ことから。
大田洋子の『屍の街』は、岩波文庫から出版されており、本屋さんや図書館で手に取ることができます。まずは、この一冊のページをめくってみることから、始めてみてはいかがでしょうか。
もちろん、活字が苦手なら、映画やマンガ、ドキュメンタリー番組でも大丈夫。大切なのは、自分に合った方法で、過去の出来事に少しだけ心を寄せてみることです。
[表] おすすめの関連作品リスト
| ジャンル | 作品名 | 作者・監督 | 特徴 |
| 小説 | 『屍の街』 | 大田洋子 | 被爆後の「終わらない不安」を女性作家の繊細な視点で描く。 |
| 小説 | 『夏の花』 | 原民喜 | 静かで詩的な文章の中に、あの日の記憶が静かに息づいている。 |
| 小説 | 『黒い雨』 | 井伏鱒二 | 被爆した女性のその後の人生を通して、社会の偏見なども描く。 |
| 詩集 | 『原爆詩集』 | 峠三吉 | 「ちちをかえせ ははをかえせ」の詩が有名。魂からの言葉。 |
| マンガ | 『はだしのゲン』 | 中沢啓治 | 作者自身の体験をもとにした、世代を超えて読み継がれる名作。 |
| 映画 | 『この世界の片隅に』 | 片渕須直 | 戦時下の暮らしを丁寧に描き、日常の尊さと、それが失われる様を描く。 |
| 資料館 | 広島平和記念資料館、長崎原爆資料館 | – | 遺品や写真から直接学ぶ。オンラインで展示の一部を見ることも可能。 |
アクション2:【考える・対話する】 自分の言葉で、感じたことを話してみる
作品に触れて心が動いたら、ぜひその気持ちを誰かと共有してみてください。
家族や友人、パートナーに。「こんな本を読んだんだけどね」と話すだけで、それは記憶をつなぐ、とても素敵な「継承」の一歩になります。
もし話す相手がいなければ、ノートやSNSに感想を書き留めてみるのもいいですね。大切なのは、ただ情報を受け取るだけでなく、自分自身の言葉で、感じたことを表現してみることです。
- もし、自分が当時の大田洋子だったら、何を感じただろう?
- 作中の「不思議なんだ」という言葉を、今の自分はどう受け止めるかな?
- 毎日当たり前に過ごしているこの時間は、本当はどれだけ奇跡的なんだろう?
こうした問いを自分に投げかけ、ゆっくり考えてみることが、遠い日の記憶を、自分の心の一部にしていくプロセスになります。
アクション3:【伝える・行動する】 小さな一歩を、未来のために
最後のステップは、ささやかな行動です。
あなたが作品から感じたこと、考えたことを、あなたの言葉で誰かに「伝える」こと。それが、次の人へとバトンをつなぐ、最も確かな方法だからです。
- SNSで、読んだ本の感想に「#大田洋子」「#屍の街」「#平和について考える」などの言葉を添えて投稿してみる。
- 近くの図書館で、平和に関するコーナーがないか、少し覗いてみる。
- 子どもや年下のきょうだいに、分かりやすい言葉で、学んだことを優しく話してあげる。
一つひとつは、本当に小さなことかもしれません。
でも、その小さなさざ波がたくさん集まれば、きっと社会の空気を変える力になります。大田洋子が命を懸けて残した言葉のバトンを、しっかりと握りしめる人が一人でも増えること。それが、彼女の切なる願いにこたえる、一番の方法なのだと思います。
まとめ – あの日の痛みを、二度と繰り返さないために

この記事では、作家・大田洋子の生き方と、彼女の代表作『屍の街』を通して、体験の記憶を継承していくことの大切さについて、一緒に考えてきました。
彼女が描いたのは、一瞬の閃光がもたらした破壊の光景だけではありませんでした。
生き残った人々の心を、生涯にわたって静かに苛み続けた、目に見えない脅威への終わらない不安」と、深い心の痛みです。
彼女が貫いた「作家の責任」という言葉は、80年近い時を経て、「今を生きる私たちの責任」という言葉として、私たち一人ひとりの心に響きます。
大田洋子の言葉は、今も私たちに静かに問いかけています。
「あなたはこの事実を知り、これからどう生きていきますか?」と。
その問いに、誠実にこたえていくこと。
『屍の街』を手に取り、遠い日に想いを馳せる。そして、そこで感じたことを自分の言葉で誰かに伝える。
その小さな営みの積み重ねこそが、あの日のような深い悲しみを、二度とこの世界に生まないための、最も確かな一歩となるはずです。