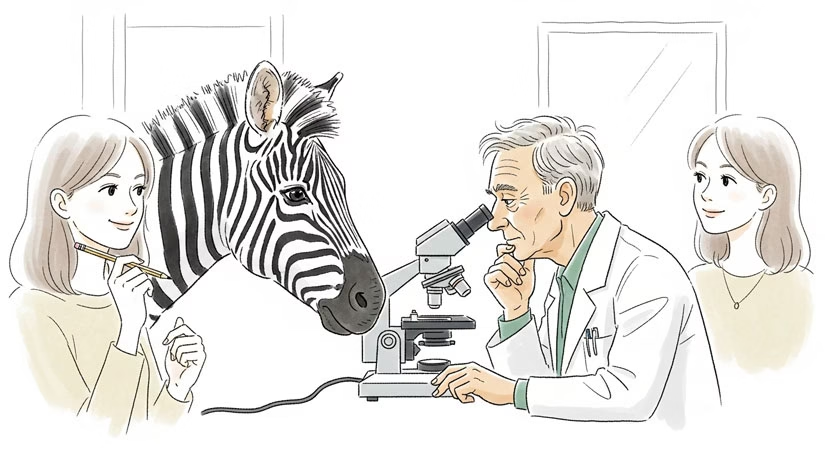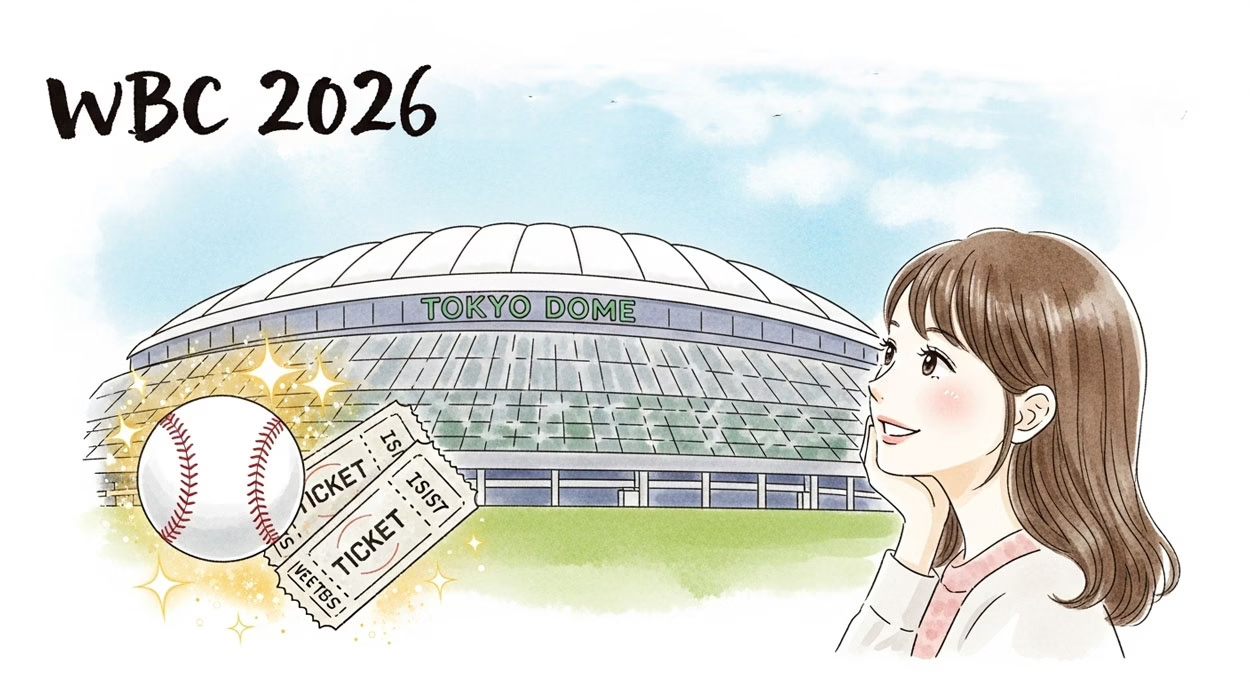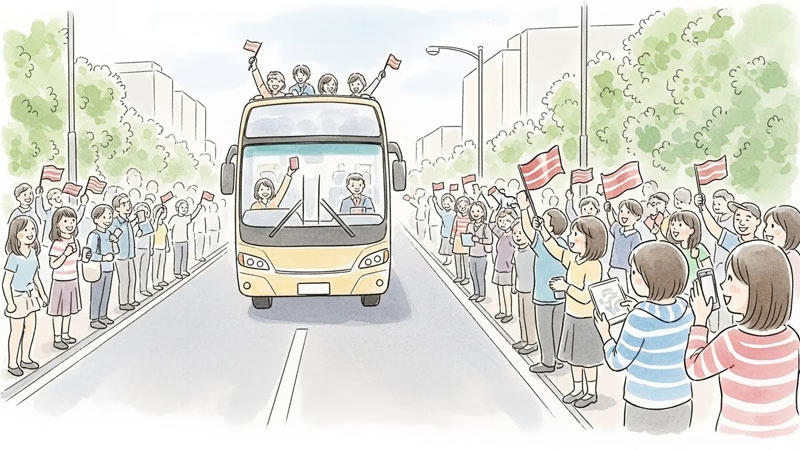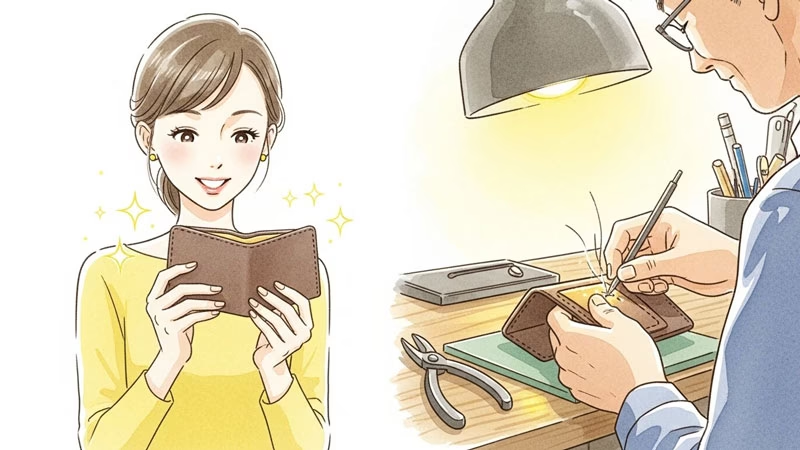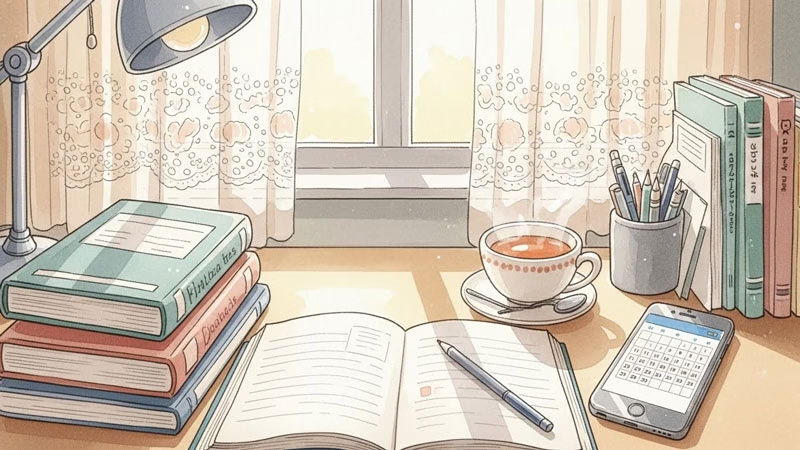日本経済新聞 今日の日付(2025年10月8日水曜日)朝刊春秋の要約と「常識に挑んだ研究者たち」
「シマウマはなぜシマシマなの? 子供だけでなく生物学者を悩ませてきた問題だ。米国の研究チームの説によれば、病気を媒介する吸血性のハエを遠ざけるため。実験してみたところ、しま模様で目がくらんだハエは、シマウマの実体が見えにくくなることが分かった。」
「▼世の中の目が向いていなかったことで、核心に近づけた――。ノーベル生理学・医学賞の受賞が決まった大阪大学の坂口志文さんは、ながらく研究が評価されず苦労した。発見した「制御性T細胞」が「抑制性T細胞(サプレッサーT細胞)」と同一視されたためだ。免疫反応を抑える作用においては共通点のある細胞だ。」
🦓シマウマの縞模様の秘密:なぜ彼らは「しましま」を選んだの?
シマウマの縞模様は「カモフラージュ」だけじゃなかった!
子供の頃、「シマウマの縞模様は何のため?」という疑問を持ったことはありませんか?長い間、この縞模様は周囲の景色に溶け込むためのカモフラージュや、群れの中で敵の目をくらませる錯視効果だと考えられてきました。
しかし、最近の興味深い研究から、別の、もっと切実な理由が浮かび上がってきています。
最新の研究が解き明かす「縞模様」の真実:吸血性ハエ対策🪰
日本経済新聞のコラムでも紹介されている通り、米国の研究チームは、シマウマの縞模様が病気を媒介する吸血性のハエ(特にツェツェバエなど)を遠ざけるためではないかという説を提唱し、実験でその効果を裏付けました。
| 縞模様の効果(研究チームの説) | 説明 |
| ハエの「目くらまし」 | 縞模様は光の偏光を乱し、ハエが着地しようとする際に目がくらむような効果を生み出すと考えられています。ハエが動物の実体や輪郭を正確に捉えられなくなり、着地成功率が大幅に低下するのです。 |
| 病気からの保護 | ツェツェバエのようなハエは、アフリカ睡眠病などの深刻な病気を媒介します。縞模様でハエの吸血を防ぐことは、シマウマの生存戦略として非常に重要だと言えます。 |
つまり、シマウマにとって、この縞模様は「天然の虫除け」のような役割を果たしている、というわけですね!
他の動物との比較でわかる縞模様の重要性
縞模様を持つ動物は他にもいますが、シマウマの縞は特にコントラストがはっきりしています。
牛や馬など、体毛が単色の動物と比べると、縞模様はハエにとって「着地しにくい」表面に見えることがわかっています。これは、私たちが熱いフライパンに触れようとしたときに反射的に避けるように、ハエも無意識に着地をためらう、というイメージかもしれません。
🔬ノーベル賞学者・坂口志文氏の研究と「制御性T細胞」って何?
「制御性T細胞」発見の道のりとノーベル賞受賞
ノーベル生理学・医学賞を受賞された坂口志文さんの研究は、長年、世間の評価が得られず苦難の道を歩みました。コラムにもあるように、彼の発見した「制御性T細胞」は、以前から存在するとされていた「抑制性T細胞(サプレッサーT細胞)」と同一視され、その研究自体が「うさんくさい」と疑われる時期があったからです。
そもそも「免疫」と「制御性T細胞」ってどういう関係?
私たちの体にある免疫システムは、病原菌やウイルスといった「外敵」と戦うための、いわば「防衛軍」です。
しかし、この防衛軍が暴走して、自分の体の一部(細胞や組織)を「外敵」と間違えて攻撃してしまうことがあります。これが「自己免疫疾患」と呼ばれる病気です(例:関節リウマチ、I型糖尿病など)。
| 免疫システムの役割 | 担当する細胞の例 |
| 攻撃役(アクセル) | ヘルパーT細胞、キラーT細胞など |
| ブレーキ役(制御) | 制御性T細胞(Treg・ティーレグ) |
坂口さんが発見した制御性T細胞(Treg・ティーレグ)は、この免疫システムにおける「ブレーキ役」です。
「戦うべきではない相手(=自分の体の細胞)への攻撃を止めなさい」と指示を出し、免疫反応が過剰になるのを抑えて、暴走を防ぐ重要な働きをしています。
制御性T細胞の存在が明らかになったことで、自己免疫疾患やアレルギー、臓器移植後の拒絶反応など、様々な病気の治療法開発に大きな光が当たるようになりました。
幻とされた「サプレッサーT細胞」との違い
坂口さんの苦労の種となったのが、1970年代に注目された「抑制性T細胞(サプレッサーT細胞)」でした。
| 細胞の種類 | 共通点 | 違い(坂口氏の研究の功績) |
| 抑制性T細胞 | 免疫反応を抑える作用がある(とされていた) | 遺伝子レベルで裏付けが見つからず、ブームが去ってしまった。存在自体が疑問視されていた。 |
| 制御性T細胞 | 免疫反応を抑える作用を持つ | 特定の遺伝子(FOXP3など)を持つこと、そしてその役割と仕組みが明確に証明され、免疫学に確固たる居場所を築いた。 |
坂口さんは、科学的に厳密なデータと、細胞が持つ固有の「目印(マーカー)」を見つけることで、「抑制性T細胞」とは異なる「制御性T細胞」の独自性を証明しました。
これにより、かつては「うさんくさい」と見向きもされなかった研究が、世界中の医学界を塗り替える大発見となったのです。
💡世間の評価がなくても貫き通した「けがの功名」と研究者の資質
「誰も見ていない」からこそ得られた研究の独占
コラムには、坂口さんが長年注目されなかったことについて「逆に研究を独占できたので『けがの功名』」と語るエピソードが紹介されています。
この言葉は、私たちにも大切な教訓を与えてくれます。
- 世間のトレンドに流されない強さ: 研究の世界では、注目されている分野に多くの資金や人材が集中します。しかし、坂口さんはブームが去り、誰も見向きもしなくなった分野を、自身の信念に基づいてひたすら掘り下げました。
- 「独占」のメリット: 誰も競合相手がいなかったため、彼は時間をかけて、じっくりと、「誰にも邪魔されずに」研究を深めることができました。これが、後の決定的な発見につながったのです。
一見不利に見える状況も、見方を変えれば大きなアドバンテージになる。これは、私たちの日々の仕事や生活にも通じる考え方ではないでしょうか。
苦難を乗り越えるための「活路」と「一つのこと」への集中力
研究が認められず、論文投稿を拒否されるという苦しい時期も、坂口さんは「活路は米国にあった」と、海外の環境でチャンスを掴みました。
| 苦難を乗り越えた要因 | 具体的な行動・考え方 |
| 環境を変える勇気 | 日本で評価されなくても、海外でユニークさを認めてくれる場所を探し、飛び込んだ。 |
| 結果で示す情熱 | かつてサプレッサーを批判した学会誌の編集長さえも、出された結果によって認めざるを得ない状況にした。理論ではなく、確かなデータが人々の心を動かした。 |
| 座右の銘「一つ一つ」 | 華々しい成果の裏には、地道で孤独な実験の積み重ねがあります。「一つ一つ」という言葉には、目の前の課題を確実にクリアしていく、研究者としての揺るぎない誠実さと集中力が凝縮されています。 |
シマウマの縞模様の解明も、制御性T細胞の発見も、「なぜ?」という素朴な疑問や、「常識」とされてきたことへの違和感を、地道な努力で追い続けた結果です。
私たちが何か新しいことに挑戦するときも、周囲の意見に惑わされず、自分の「探求心」と「一つ一つ」着実に進める力を信じることが大切だと、このコラムから学ぶことができますね。